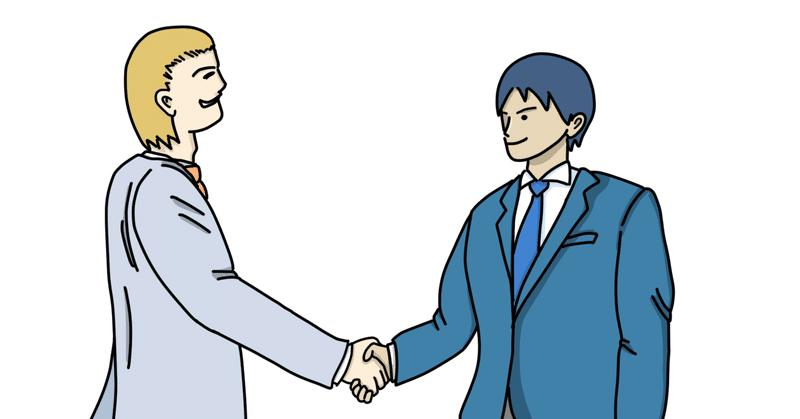
取締役②ー選任
会社法で学んだことをまとめます。
選任手続
取締役は、原則として、株主総会で選任します(会社法329条)。
(例外として、取締役・監査役の選解任についての種類株式(いわゆる「選解任種類株式」)を発行している会社では、取締役の選任・解任は、種類株主総会で選任することになります。)
そして、株主総会の決議は、普通決議となります(会社法309条1項)。
これは、例えば選任決議を特別決議(会社法309条2項)にすると、株主の意思は反映されやすくなりますが、選任に必要な数の賛成を得なければならないハードルがあがり、その結果、取締役を選任できなくなる可能性があるからです。
ただし、この普通決議が、ちょっと変わった普通決議なんです。
定款規定による定足数の引下げは、株主の議決権の総数の3分の1を限度とされています(会社法341条)。
普通決議には、①定足数(議決権の過半数を有する株主が出席)と、②決議要件(出席株主の議決権の過半数)があり、①定足数について、定款で「議決権を行使できる株主の議決権の過半数」という要件を「議決権を行使できる株主の議決権の3分の1」までしか引き下げることはできず、定款で定足数の要件を完全に排除することはできません。
(⇔ 原則的な普通決議であれば、①定足数を定款で排除可能)
これは、会社の役員を選解任する重要性から、できるだけ多くの株主の意思を反映させるためです。
累積投票制度
取締役の選任手続きには、累積投票制度という特殊な手続があります。
2人以上の取締役を同じ株主総会で選任する場合、通常は、1人ずつ選任が行われます。
しかし、この方法では、例えば、発行済株式総数100に対して60株の多数派株主と、40株の少数派株主がいた場合、多数派がすべての取締役ポストを決定することができます。
そこで、少数派の意思を反映させる方法として累積投票制度があります。
累積投票制度では、以下のようなルールで実施されます(会社法342条3項、4項)。
2人以上の取締役の選任決議を一括して行います。
株主は、1株につき選任すべき取締役の数と同数の議決権が与えられる。
株主は、この議決権数を1人の取締役への投票に使ってもOK。
もちろん、複数の取締役に振り分けてもOKです。
投票の結果、得票数の多い者から取締役に選任されます。
例えば、
発行済株式総数100株の株式会社において、多数派株主が60株、少数派株主が40株を有しているときに、取締役候補者A・B・Cから2名を選ぶ場合
この場合、累積投票制度のもとでは、
まず、取締役2人の選任なので、議決権数は以下のようになります。
多数派株主が、60株×2=120議決権
少数派株主が、40株×2=80議決権
そして、一括投票で、どのように議決権を振り分けてもいいので、
少数派株主が、Cに集中して票を入れることで、多数派株主がAに60議決権、Bに60議決権を投票しても、80議決権を得た候補者Cが当選することになります。
累積投票制度は、取締役の選任にしか使えない
これは、もともと、経営者の選任に少数派株主の意見を反映させたいという制度であるためです。
累積投票制度は、実務で行われているのか?
実は、累積投票制度は、ほとんど行われていません。
累積投票制度は定款によって排除することができるとされており(会社法342条1項)、ほとんどの会社で排除しています。
会社法が定款で累積投票制度を排除することを認めているのは、累積投票制度は手続きが煩雑であることと、そもそも株主間で露骨に対立すると会社経営がうまくいかなくなる可能性があるからです。
就任
株主総会で選ばれたとしても、まだ取締役にはなりません。
取締役に選ばれた人が、取締役への就任を承認しなければ、取締役とはならないのです。
これは、取締役になると様々な義務を負うこととなるところ、選ばれたというだけで、一方的に義務を負わせられるのは酷だからです。
そのため、「自分がやるよ」と言わない限りは、取締役にならないのです。
参考文献
・高橋美加ほか『会社法〔第3版〕』P172-174
・伊藤靖史ほか『会社法〔第5版〕』
・川井信之『会社法入門』P111
・根本正次『リアル実況中継 司法書士 合格ゾーンテキスト 6 会社法・商法〔第3版〕』P219-221
・松本雅典『司法書士試験 リアリスティック6 会社法・商法・商業登記法I〔第2版〕』P336-338
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
