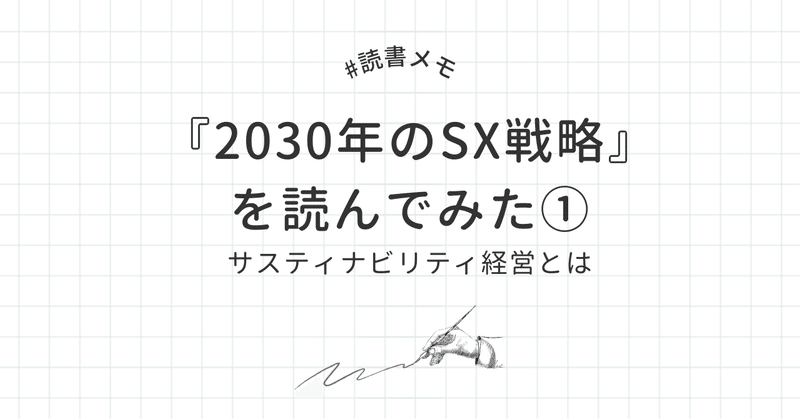
サステナビリティトランスフォーメンションとは。 #読書メモ
非営利法人や知り合いの他の会社のお手伝いをしたり、修士論文を執筆しているゆうゆです(広告代理店を休職中 (´・ω・`))。
今回、PwCの坂野俊哉さん、磯貝友紀さん著、日経BPから2022年出版の『2030年のSX戦略 課題解決と利益を両立させる次世代サステナビリティ経営の要諦』が非常によいので、わたしの読書メモを公開します。
本書の第1章は前置きになるので飛ばしています。
この記事は、第2章、第3章の読書メモです。まだ第4章以降は読んでない…。
notionにメモしたものをコピペしているだけなので崩れている箇所あります🙇♀️
※「語録」は恥ずかしながらわたしが読めなかった漢字や、本書で出てきたけれども意味を説明できない言葉をメモしています。
下記のようなモヤモヤをこの本を読むと言語化できます🙌
「サスティナブル」に興味のある就活生にもおすすめです。
「サスティナブルっていいよね!
経営に「サスティナブル」って必須だ!
日本を、世界に、ビジネスを通してより良くしていきたい!
具体的にどうやって?どの企業だって何かしら日本を良くしたいって思っているはず…。うーん、でも何か違うなっていうのもあって…。」
第2章 サステナビリティ経営についての疑問に答えます
☆4つの環境課題と3つの社会課題

トレードオフ志向。サステナブルとビジベスを両立できないからトレードオン志向へ
成長とは何か?人々から「幸せ」を奪ってきたのでは?
年収650〜800万円、幸福度と収入の相関ある。800万以上は相関がない
ある程度の物質的な成長、のうえに精神的な幸せは成り立つ。
☆資本主義とは「富を生み出す仕組み」=「無限成長」、「財産の私有」が内包
必然的に起こること
🌞ウェルビーングの向上<余暇時間
☔️無限の成長、プラネタリーバウンダリー。リスクをとるものにより大きな分前=格差の拡大
└21世紀の資本、トマ・ピケティは資本主義の格差の拡大について言及
☆ステイクホルダー
①経営者
②短期投資家:スピードをあげるようにいう
③規制:短期的利益の追求に規制
④長期投資家:親亀、子亀、孫亀の構造に気づいている。持続可能かつ長期的に儲かり続けるビジネスに投資したい
ex. 2016、米:超裕福層、年金基金
⑤年金保有者:年金基金を通して知らない間に株主になっている
年金ファンド
⑥マルチステイクホルダー:NGO、一般消費者
SNSでの発信、不買運動
☆ポスト資本主義
①資本主義の枠内で適切な成長への移行は可能
岩井克人
環境負荷の低い経済成長、技術革新と法の整備で資源の消費を最大限に引き締めた場合でも17%は伸びる
②「①」は幻想であり、まったく別の仕組みが必要
斎藤幸平:生産手段の私有化をやめ、人々が自発的に選択していく共同体社会が必要
☆サーキュラーエコノミー
2060年 世界の人口 2011年比1.5倍、1人当たりの収入2.7倍、1日1人当たりの資源利用33kg→45kg、資源需要790億トンから2倍
サーキュラーエコノミーへの関心
物質的消費の減少とサーキュラーエコノミーの新たな経済効果のどちらが大きいのか
親亀の限界を考慮すると長期的にはサーキュラーエコノミーの方が上回る
脱炭素で2030年までに世界で600万人が雇用を失う
ネイチャーエコノミー 3.95億人の雇用創出効果がある
☆事業ポートフォリオ
業績を落とさずに事業ポートフォリオを入れ替えるには?
外部不経済を見える化。大きなものから転換。
親亀、子亀をどれだけ傷つけているか?
ネガティブインパクトを最小化し、ポジティブインパクトに変えていくこと
☆サステナ経営での儲け
①外部不経済を防ぐためにかかるコスト=投資
②外部不経済を防ぐことで得られるメリット
数値化によって、数字でビジネスに取り組む効果、価値、投資利益率がいえる
インパクトパス→過去から得られた相関関係→市場予測データ→実数入れて推定値を算出
→ROIC(投下資本利益率)に組み込む→非財務要素を含む付加価値を設定→投資決定に活かせる
①と②の差が儲け
☆ サステナ経営しているよ、の企業
選好プレミアム:その会社の商品を選ぶ、相関
価格プレミアム:高くても買う 相関
拡散プレミアム:人に勧めたい 相関
語録
巧拙 こうせつ:上手(じょうず)と下手(へた)
性急:せっかち
プラネタリーバウンダリー:地球の限界
外部不経済:企業の経済活動は、地球、環境、社会になんらかの形で負荷を与えるが、そのことは財務には影響しないこと
イネーブラー:目的達成の手段
御者(ぎょしゃ、馭者)と:**馬などの使役動物を動力とする馬車やキャリッジなどを乗り物の専用座席から操作する作業者(運転手)**である
リニアエコノミー(直線型経済):自然から取り出す→加工→使用→廃棄
サーキュラーエコノミー(循環型経済):インプット(新たな資源の採取)もアウトプット(廃棄)もゼロにする
ジャストトランジションメカニズム:欧州委員会が2020年に発足させた。地球温暖化への対策を行う中で平等かつ公正な方法で脱炭素社会への移行を目指す概念
Moteur à combustion interne (内燃機関):燃料の燃焼が機関の内部で行われる熱機関の総称。これに対し,機関外で燃料を燃焼させる蒸気タービン,スターリングエンジンなどは外燃機関
ネイチャー・エコノミー(自然と共存する経済)
アグリゲーター(集約する):分散型電源等の電気を集めて需要家に供給を行う「特定卸供給事業者」や「小売電気事業者」
ブラックロック:界最大の資産運用会社となり、年金受給者から新興財閥、政府系ファンドまで、あらゆる投資家の資金を運用
環境損益分析:E P&L(Environmental Profit and Loss Account) 、ケリンググループ
バリューチェーン:****事業活動を「価値連鎖」として捉え、付加価値を分析。****企業における各事業活動を価値創造のための一連の流れ
どこでなんの活動が利益をもたらしているのかがわかる
https://www.persol-group.co.jp/service/business/article/321/
インパクトパス(PwC用語):入り口であるインプット(6つの資本(注)の投入)と出口であるアウトカム(6つの資本への影響)をつなぐ経路 https://diamond.jp/articles/-/330208?page=3
ROIC投下資本利益率(Return On Invested Capital):調達したお金を使って効率的に利益をあげられたかを測る指標
非財務情報:定性的な情報
経営戦略・経営課題
ESGやCSRに関する取り組み、活動状況
経営者が認識しているリスクやガバナンス体制に関する情報
サステナビリティの取り組み
第3章 未来を考える枠組み
未来のシナリオ
原因となる変数
①規則・ソフトロー
②人々の価値観
③テクノロジー
①規則・ソフトロー
2024:01:13.pdf
<問題提議フェーズ>
↓
↓
<ソフトロー化フェーズ>
1. 小さく始める。リーディング企業が主体となって小さなグループを形成
2. 低いハードルで参加企業を増やす
3. 規模拡大とともに締め付け強化。たとえば「除名」。自主的からソフトローへ
4. 自主的イニシアチブ乱立から統合へ
ex. PRI 責任投資原則
6. 新たなソフトロー基準の可能性
ex. トゥループライス
企業は問題提議化フェーズから議論に参加し、自主ガイダンスの作成から関与していくことが必要
↓
↓
<規制化フェーズ>
・中国は、IT分野のみではなくサスティナビリティ分野も成長分野に位置付けている。
ex. 中国タクソノミー
・日本政府は立ち位置を十分に決められていないよう。
②人々の価値観
「環境に負のインパクトを及ぼす自分の行動に対して罪悪感を覚える」
→若い世代ほど意識が高くなる
ベビーブーマー40%、x世代53%、ミレニアル世代62%、Z世代67%
カナダ社会調査機関グローブスキャン、対象27カ国約1,000人ずつ、合計27,000人ほど。2020年実施
世界ではミレニアル世代以降、サステナに関する意識は大きく変化しているが、日本では1世代遅れている(PwC調査)
サステナ意識の高さは欧州だけではない
東南アジア、インド、アフリカ、など途上国諸国でも非常に高い
日本の方が低く途上国の方が高いことも。
ローカル・ノームで論争が起きる時は、ハイパー・ノーム(SDGsなど)に解決をもとめることが多い
未来を予想する際の注意点
自分の経験に縛られず、未来の世代の価値観はどう変化するのか
日本だけ見て判断しない
ローカル・ノームとハイパー・ノームの視点で長期的に選択される規範は何か
世代間、地域間で考え方の振り子は異なる。最終的にどこへ向かうのか?
③テクノロジー
実用化の目処がつき5~10年後に実用可能なテック
ex. 電気自動車
突如生まれる破壊的テック
SXのグランドストラテジー
環境・社会価値を創出しながら成長を最大化しリスクを最小化
=利益を最大化せ、機会損失を最小化すること
成長=利益=売上拡大機会の獲得+既存コストの削減
リスク=機会損失=売り上げ減少リスク+コスト増加リスク
<短期>
①サステナビリティ・ブランド型(トップライン向上)
②顕在化しつつあるトレードオン市場追及型(トップライン向上)
環境・社会的価値そのものを販売。再エネ投資
③利益率改善型(オペレーションの改善によるコスト減)
効率化、シェアリング、コストシェア、ビジネスモデルの転換、技術革新などにより、利益率改善と環境負荷低減を両立。環境・社会価値を意識しない市場にも訴求できる
④顕在化リスクへの対応型(リスク対応)
⑤規制やソフトローにコストをかけて対応
<長期>
⑥未来のトレードオン市場創造型(トップライン向上)
フードシステムの崩壊、未来の環境問題を先取り。予見される社会課題を解決するために、新たな環境・社会価値の創造や市場形成に取り組む。投資が必要
⑦未来のオペレーション改善志向型(オペレーションの改善によるコスト減)
環境・社会価値創出に必要なコストを削減するために必要なことを積極的に進める。インフラ整備、ルールメイキング。投資が必要
⑧潜在リスクへの積極対応型(リスク対応)
まだ顕在化していない未来の機会損失リスクに対して、積極的に対応する
長期:長期の視点で効果を出すために、今やらなくてはならない
すべてを同時に行う必要がある
口先だけのパーパスは「長期的視点」が欠如している
サスティナビリティはコストである?
この考えを乗り越えるための3つのステップ
気づいていない財務インパクトを投資判断に組み込む
インパクトパスを明らかにすることで、長期的ではあるが利益ができることがわかる
経済合理性のある事業の利益をさらに拡大できないか検討
環境・社会価値創出と利益、機会損失の関係性をインパクトパスを利用して明らかにしても、「経済合理性がない」事業は残る
インパクトパスを描くことで、気づかなかった財務インパクトに気づく。どんなアクションが必要か考える
7つの視点でビジネスモデルを革新
「2」をしても、まだ投資額を回収できそうにない場合は、ビジネスモデルを変えるなどさらなる工夫が求められる
売上に関して
①サステナビリティを付加価値にして、単価、シェアを上げる
②サステナ価値そのもの(ゴミの削減量、健康価値)を販売し、シェア拡大
コストに関して
③オペ改善によりコスト削減
④ビジネスモデル改革によりコスト削減
⑤技術革新によりコスト削減
⑥コストをステークホルダーとシェア
⑦コストは長期で回収すると腹を括る
語録
リーディング企業:一定の業界で主導的地位にある企業
PRI 責任投資原則(Principles for Responsible Investment):投資に環境、社会、ガバナンスの視点を組み入れるなどの、機関投資家の投資原則のこと。機関投資家の投資に向けた意思決定プロセスや株式の保有方針の決定に、投資先企業の財務状況に加え、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance:企業統治)のESG要素を反映させるための考え方を示す原則。』
TCFD Task Force on Climate Related Financial Disclosures (気候関連財務情報開示タスクフォース):各企業の気候変動への取り組みを具体的に開示することを推奨する、国際的な組織のこと
TCFD 自然関連財務情報開示タスクフォース
タスクフォース:組織内部で緊急性の高い問題の解決や企画の開発などを行うために一時的に構成された組織のこと
トゥループライス:外部不経済を取り入れた本当の価格を計算し、消費者に示す
インベストメント・チェーン:資金を提供する投資家と、資金を調達する企業が、共通の価値観に基づいて中長期的な価値向上を目的として協働することで、社会全体の富を増やすことができる、という考え方
タクソノミー(taxonomy)」:分類」を意味する英語です。元々は生物を分類することを目的とした生物学の一分野を表す用語として用いられています。こうした物や概念の分類を体系化する考え方を応用し、「持続可能性に貢献する経済活動」を分類・列挙したものが金融におけるタクソノミーです。
EUタクソノミー:EUによってつくられた、何がサステナブルであるかを明確化するためのタクソノミー(分類)参考
何をもってグリーンであるのか
中国タクソノミー
ローカル・ノーム:特定の地域でのみ通用する論理規範
ハイパー・ノーム:ローカル・ノームを超えた普遍的論理規範
リジェネラティブ農業(regenerative agriculture):土壌を修復し、自然環境を回復する農業
コーポレート・ベンチャー・キャピタル:事業会社が自己資金でファンドを組成し、主に未上場の新興企業(ベンチャー企業)に出資や支援を行う活動組織のこと
トップライン:損益計算書の一番上(トップ)の項目である売上高(営業収益)のこと。
風が吹けば桶屋が儲かる:思いもよらぬところで影響が出てくることのたとえ
レジリエンス:「回復力」「弾性(しなやかさ)」
読んだ本はこちらです。
気になる方はぜひ手に取ってみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
