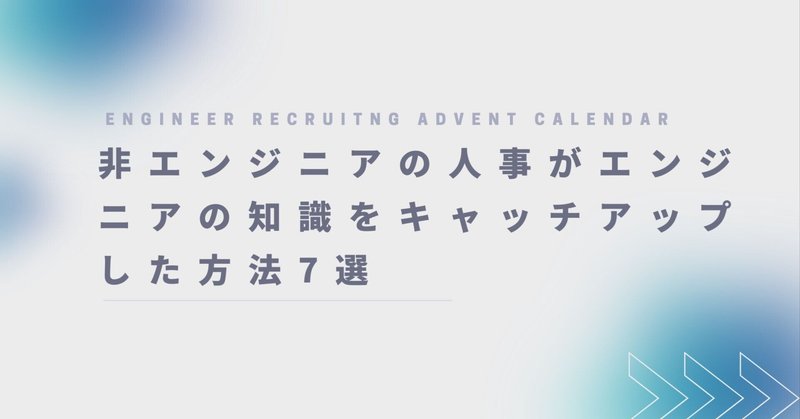
非エンジニアの人事がエンジニアの知識をキャッチアップした方法7選
ストックマークHR高橋と申します!
現在ストックマークにて、エンジニア、デザイナー、PMの採用や会社全体の組織開発を担当しています!
私はBizサイドのキャリアが長く、エンジニアの経験はありません。 (※上智大学在籍時代にインド出身の先生のJavaの授業を受けて、難しすぎて挫折しました。)
しかし、エンジニア採用においては一定の成果を出すことができたと思っています。
そこで今回は「非エンジニアの人事がエンジニア採用を成功させるために」というテーマで、同じく悩むHRの方に記事を書きました!
前提情報:ストックマークのエンジニア採用について
記事の前提となる情報として2つご紹介します
2023年度 エンジニア採用実績
社内の情報も含まれるため、ざっくりしていて申し訳ないですが、簡単にご紹介します
・プロダクトエンジニアにて年間で214名応募の獲得、うち6名が入社決定
・機械学習エンジニア2名、MLOps1名など機械学習系人材の採用に成功
・20名規模のEM経験者や一人目のDevRel人材などの採用に成功
採用計画もほぼ計画通りであり、良い成果が残せたと思っています。
ストックマークのエンジニア採用体制
以下のような体制で運用しています。
スカウトは人事、面接は現場のように分かれているというよりは、各々の得意分野を活かして分担するようにしています。現場の方がエンジニアとしての知見を持っているため、人事としては採用のプロとして伴走する形にしています。

前述の採用実績についてもEMやチームリーダーなどの現場メンバーのお陰で実現できた結果ではありますが、本記事としては人事の目線で書いていきます。
人事が知っておくべきエンジニアの知識とは?
「HRがどこまでエンジニアの知識を持っておくべきか」という問については、以下の2つを意識していました。自社の採用体制に依存するので一概には言えませんが、任されたことをしっかり完遂するための知識という基準で必要な情報を取得するようにしました。
自社の採用要件にフィットするエンジニアのレジュメがスカウト媒体で見極められる状態
人事面談でエンジニア候補者との会話が成立して、自社をアトラクトできる状態
非エンジニアの人事がエンジニア採用を成功させるために何をしたか?
主に私が行っていたのは以下の内容です。
1. 最低限の用語を理解するために基礎知識を書籍や記事で身につける
まずは最低限の用語がわからないと話にならないので、書籍やWebの記事を読み漁ることにしました。言語やフレームワーク、システム構造、職種名の意味など、前提の知識を身につけました。
特に参考になったのは以下です。
書籍:作るもの・作る人・作り方から学ぶ 採用・人事担当者のためのITエンジニアリングの基本がわかる本
書籍:ITエンジニア採用とマネジメントのすべて 「採用・定着・活躍」のポイントと内製化への道筋が1冊でわかる
メディア:Forkwell Press
弊社もお世話になっているForkwell。
特に、調査系のレポートがめっちゃ参考になります。
2. 先輩スタートアップでエンジニア採用をやっている人にインタビューさせてもらう
事業会社でエンジニア採用を実践するのが初めてだったので、色々と不安がありました。書籍ではわからない生の声を知りたいと思い、先輩スタートアップでエンジニア採用をやっている方にインタビューすることにしました。当時はカジュアル面談のプラットフォーム Pitta(旧Meety)を主に使ってインタビューさせてもらいました。
人事としてエンジニア採用にどうやって知識を身につけたのか、どう向き合っているのか、他社の事例をお伺いすることで解像度がかなり高まりました。
当時お話お伺いしたランサーズの二橋さん、インタースペースの関さん、サイバーエージェントの大沢さんなど非常にお世話になりました。ありがとうございました。
私もPittaやっているので、良かったらお願いします!
3. エンジニア関連の副業をする
私の場合は副業として、プログラミングスクールで営業として働くようになりました。未経験の方にエンジニアリングを身につけられるようにするスクールだったので、私自身もエンジニアの知識を身につけることができました。
また幸い副業しているメンバーにも教材を公開してくださったので、基本的な知識を書籍や動画で学ぶことができました。
4. 人事が手を動かしてスカウトしながら、面談所感を現場とすり合わせる
私が入社する頃は現場のエンジニアがスカウトを担当していました。人事はディレクションがメインになるので、どうしてもスカウト対象者の肌感が掴みにくく、基準が揃わないことがありました。
そこで私の方でスカウト業務を請け負う体制に変更しました。毎日スカウト媒体を見ながら、カスタマイズしたスカウト文章を送り、面談は現場にお願いしていました。面談や面接のフィードバックをもらいつつ、週次の定例で所感を伺いながら、少しずつすり合わせていくことで、大分目線が揃うようになりました。
スカウト業務という実務で学ぶことで、吸収する知識の質も高く、スピード感を持って目線合わせができました。現場にスカウト業務をお願いしている人事は、一度は自分でやってみることをオススメします。
5. 面談/面接動画をめちゃくちゃ観る
ストックマークでは、候補者に注釈を入れた上で面談/面接動画を録画するようにします(もちろん録画を希望されない方は録画しません。)エンジニア採用に携わった頃は、とにかく暇さえあれば録画を観るようにしたり、作業しながら流し聞きしたりしていました。
どんなエンジニアが市場にいるのか、何に悩んで転職活動をしているのか、現場がどう自社をアトラクトしているのか、面談/面接動画を観ることで、生の声をキャッチアップすることができました。
6. Slackやエンジニアが作成した社内ドキュメントを見る
ストックマークではオープンカルチャーを標榜しており、他部署のSlackやNotionの議事録を見ることができます。自社のエンジニア組織の理解を深めるために、エンジニアチームのSlackにはなるべく入るようにしています。またエンジニアメンバーのtimesチャンネルも複数あるため、入るようにしており、普段どういった情報をキャッチアップしているのか情報を取得するようにしています。
またNotionの議事録を見ながら、定例の議論や重要プロジェクトの変遷を追うようにしており、組織の状態を把握して、採用に活かすようにしています。
7.採用以外で社内外のエンジニアと話す機会を増やす
採用で得られる情報は限定的です。そのため採用以外でも社内外のエンジニアとコミュニケーションを取る機会を作るようにしていました。
特に最近入社したメンバーと会話しながら「ストックマークと他社の違いはどうか」「入社後のギャップはあったか」「今のプロダクト開発における課題は何か」など生の声を聞くことで多面的にエンジニア組織についての理解を深めるようにしています。
また知り合いのエンジニアとも話すことで、より深く理解するようにしています。
まとめ
今回は非エンジニアの人事がエンジニア採用を成功させるためにというテーマでした!
キャッチアップはしてきたつもりですが、日々共に採用に向き合ってくださる現場の皆さんのお陰で採用が加速できていると思います!少しでも参考になっていたら幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
