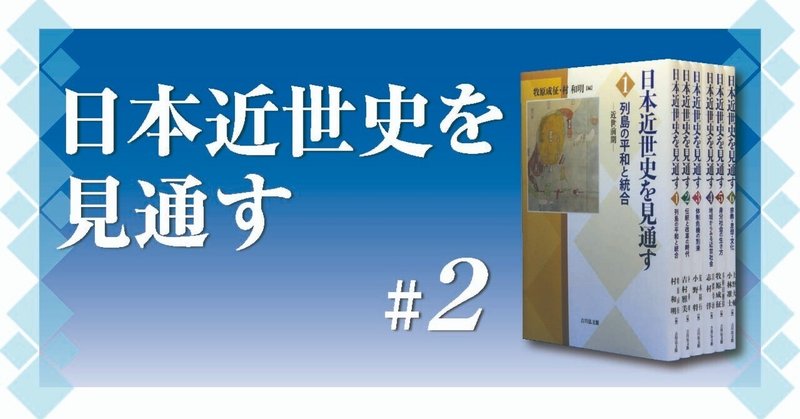
近世前期の政治とは何か? 牧原成征
『日本近世史を見通す1列島の平和と統合』では、信長・秀吉から四代将軍徳川家綱の時代までを、政治と対外関係を中心に描いているが、論者によって政治・民政についての考えにズレがあることに気づいた。そもそも近世前期の政治とは何なのだろうか。新しい時代が形づくられる当該期、それは必ずしも自明ではない。
参考になるのは大名評判記と総称される一群の書物である。正保元年(一六四四)前後に成立した『堪忍記』、一六六〇年前後の『武家諫忍記』、延宝三年(一六七五)の『武家勧懲記』、元禄三年(一六九〇)の『土芥寇讎記』がある(若尾政希氏による)。いずれも著者は特定されていない。
最初の『堪忍記』は、牢人・渡り者が仕官すべき大名を探すための就職マニュアルとされ、知行からの収入(年貢率)、江戸詰めの手当、家中の風儀、渡り者が望む家かどうかなどを簡略に記す。『武家諫忍記』以降もその項目を引き継ぐが、記述が丁寧になる。萩藩毛利家の記事を例にみてみよう(『土芥寇讎記』によるが、前二書もそれほど異ならない)。
まず「本知は三六万九千石余りだが、新地開き・諸運上・課役などをあわせて四五万石余りとなる」という。こうした記述は基本的にすべての大名にある。「新地開き」については「新地開くこと甚だ多し」と記される藩もあり、一七世紀に全国的に新田開発が盛行したことを示す。また「諸運上」には「山海の諸運上」、湊・津の運上などが含まれる。
次に萩藩は「米よく生ず。払いもおおかた也」、つまり米の生産が盛んで、年貢米換金の条件もまずまずだという。藩の所在地や経済条件によって、年貢米が換金しやすいかどうか大きな差があった。『土芥寇讎記』で他藩の例をみておこう。
福井藩では「以前は敦賀へ出し、あるいは大津にて払い、運送等の費えが多く収納が不足した。近年大坂へ廻船の便を得て払いがよくなったと聞く」と記される。弘前藩にも同様の記述がある。逆に小浜藩では「越前の敦賀津は、往古より船着きとして繁昌し諸運上が多かった。しかし近年北国筋は摂州大坂へ廻船の便を得て過半の荷物を大坂へ出すので、今は少々衰微して運上が少ない」とされる。盛岡藩でも「近年江戸へ廻船して払うので、運送の弊を引いても徳分があると聞く」とある。「近年」云々の記述はいずれも『土芥寇讎記』で初出である。一七世紀後半における西廻り・東廻り海運の整備が、藩の経済条件を変えたのである。
続いて年貢収納について、萩藩では「石高に対して五割から七割、均すと六割であり、家中へ地方で知行を給しているが、家臣の取り分は四割と定められており、新参者へは蔵米で石高の四割を支給している」という。地方知行ではあるが、藩が一律四割に家臣の収納額を限定・保証し、超過分は藩が蔵入として収納していた。このような藩がすでに多数派になっていた。
江戸へ参勤した家臣には、何人扶持という形で手当てが支給され、また摸合もあるという。模合は、家臣から金銭や米を取り立てて江戸詰のものへ援助する仕組みを指す。江戸詰の場合、三〇〇石以上は馬を持つとされており、本来の武士の地位を象徴する騎馬の出で立ちが、特に江戸での勤番に際して必要とされたことも興味深い。さらに「国役は少ない」と記される。これは『堪忍記』にも頻出するが、家臣が負担する知行役を指す。この負担の大小も、藩士の待遇に大きく関わった。

家中の風儀も記すが、萩藩は「家の子」が多いので法度が厳しくないという。譜代の家来が多い外様大名家では番役などの負担が少なかったことが、法度(統制)が厳しくないとされる所以であろうか。米沢藩では「国侍は無公儀に見えるが、江戸詰の輩は公儀なれていて見苦しくない」という。これは『土芥寇讎記』の記述で、以前の評判記にはないが、家中が江戸での幕府向きの儀礼に慣れているかどうかも、大名の評判を左右した。
他藩では統治の善悪と民間の貧富を記すことが多い。津藩では「地方知行の領主が百姓を厳しく貪り奪うので民間が大いに難儀した。藩主がこれを聞いて、公儀をはばかり、また百姓の辛苦を憐れんで、近年、地方知行を取り上げ、蔵米で四ツ成にして渡すことにした。誠に慈悲な仕置である」と記される。蔵米知行・均し免への移行は、公儀を意識しつつ給人の恣意を限定して百姓の成り立ちを図る、領主層全体の利害に基づくものだった。
萩藩に戻ると、商人らから買掛り(借金)を多くしているが滅多に支払わない、とも述べている。これは江戸の町での萩藩邸の評判であろう。この部分は『土芥寇讎記』で初出であり、同様の記事は会津藩・出石藩にもある。江戸幕府は金銭貸借の訴訟を受理して裁許したが、それは公儀の民間に対する恩恵であって、当該期には江戸で、寛文二年(一六六二)・貞享二年(一六八五)・元禄十五年(一七〇二)と、そうした受理や裁許を停止する相対済まし令を出した。金銭貸借が盛んになって幕臣・武家の窮乏も進んだために間接的に彼らを保護し、商人の債権を保護しない措置をとった。各藩はいやおうなく三都での経済活動に巻き込まれ、それへの対処が幕藩ともに大きな課題となっていた。
さて、『武家諫忍記』以降になると、以上のほか、藩主が、文武両道を修めているか、才知発明か、仁愛に深いか、女色・男色に耽るかなどを詳しく記す。さらにそうした見方を編者が検証し、古典的な書物を引用しつつ、当主が「主将の器」であるかどうかを述べている。武も軽視されていないが、学問が重視されている。変化はそれだけではない。平戸藩を例にみてみよう。
『武家勧懲記』では、藩主松浦鎮信について「武法を好み、行跡勇智発明にして善悪を弁え……誉れある者をは禄を以て招かれる」と述べる。『土芥寇讎記』では、子の藩主松浦任について「文武共に好み」としつつほぼ同様に記すが、父鎮信については「器量(ここでは容姿)を好む」として「男好きで、歩行侍に臂を張らせ、中間・小者は墨髭を作らせ手を振らせて悦び、相撲取を多く召し抱え慰みとしてきた。老中や出頭人へ諂う様子はみっともない、と世の中では誹りがあった。任はそうではなく、ほどよい「公儀ぶり」だ」とされている。鎮信の評価が反転している。
大和郡山藩主本多忠平も、家士に男を選んで器量を優先して召し抱えるので、由緒正しく芸能(学問などの能力)ある者でも無男であれば採用しない。身長が高く髭があり眼をいからし傲慢で憎らしそうな男を採用する。これを世間では武士の吟味(選考)ではないと批判しているという。
富山藩主前田利秀も、かつて侍の器量を好み氏先祖の吟味をせず、身長が高ければ高給で召し抱えた。ゆえに船頭・馬方・中間・小者に至るまで、身長の高い者は足を洗って侍となり奇妙な名目で奉公した。世間が批判したので、近年は男好きを止め実目(実直)になったという(『土芥寇讎記』)。武士・家臣に対する価値観が大きく変わったのである。
一七世紀半ばから後半にかけて、全国市場の確立と藩財政の窮乏、給人の恣意限定による蔵米知行と均し免への転換、江戸・中央での公儀勤めと藩の信用維持といった様々な課題が生起した。それらに向き合うなかで、大名たちにも、単に軍団を率いるというより、学問を取り入れて「正しき御政道」を行うことが求められる時代がやってきたのである。
(まきはら しげゆき・東京大学大学院人文社会系研究科教授)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
