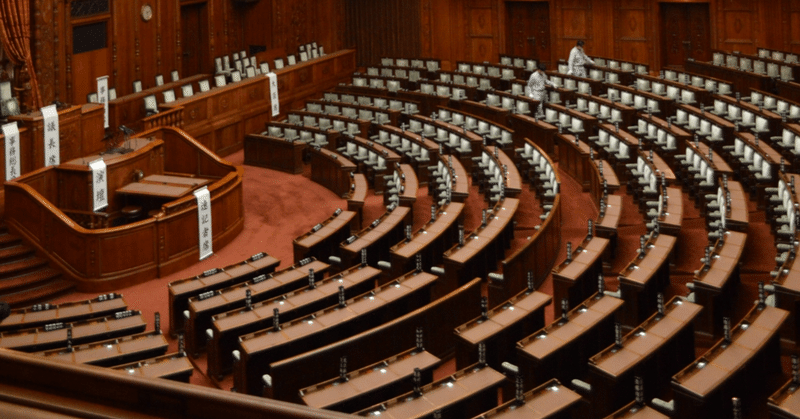
第74回:骨太の方針のポイントと、そのタイムライン、キーマンを学ぶ
1.はじめに
骨太の方針(正式名称は「経済財政運営と改革の基本方針」と言います)が6月16日に閣議決定されました。すべての閣僚合意によって決定される政府最高レベルの意思決定である閣議決定によるものなので、骨太の方針はいわば、政府が国民に対して行う約束のようなものと考えてもらえればよいでしょう。
各府省は閣議決定の内容に拘束されるので、骨太の方針に記載された政策は、その実行に強いプレッシャーがかかります。書き込まれた内容の実現可能性は限りなく高いともいえるので、骨太の方針が確定する直前まで様々なステークホルダーが骨太の方針に何とか希望する文言を盛り込んでもらおうと、奔走しています。
それほど影響力のある政府方針である骨太の方針の策定プロセスやその記載に影響を与える人々が誰なのかを認識しておくことは、進めたい政策を実現するためにとても重要です。
骨太の方針を理解することは政策実現の基本のキといえます。今回の記事では今回の骨太の方針のサマリーに加えて、決定までのタイムライン、関係者の動きなどを解説します。
政策を変えようといろいろ努力しているけど、結果に結びつかない。もしそんな悩みがあるなら、今回の骨太の方針の記事を読んでみてください。今まで見過ごしていた政策へのアプローチのチャンスを正確に意識することができるはずです。
骨太の方針を理解して、今後1年間の大きな政策の動きを理解するとともに、骨太の方針ができるまでの大きな枠組みを知ってもらい、明日からの社会変革に生かしていただければと思います。
2.骨太の方針とは
骨太の方針とは、経済財政諮問会議での議論をベースに作成される閣議決定文書です。その後の政府の政策の方針や予算配分の方針について記載しているもので、政府の閣議決定モノとしては最も重要なものの一つと言えます。
骨太の方針を議論する経済財政諮問会議は、内閣府に設置され、
①内閣総理大臣の諮問(意見を求めること)に応じ
②経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項について調査審議し
③内閣総理大臣に意見を述べること
をその職務としています。(内閣府設置法第19条)
ちょっと、難しいかもしれませんが、要は、経済財政諮問会議は、法律上は単に調査し、意見を述べるだけで、政策を決定することはできないこととされています。
しかし、実態上は経済財政諮問会議の議論を踏まえて骨太の方針は作成され、最終的に閣議決定されます。そのため、経済財政諮問会議は、実質的に政策を決定する重要な場になっていると言ってよいと思います。
3.骨太の方針の読み方
骨太の方針の章立てとしては、例年おおむね以下のような形となっています。
■第1章
第2章以降の経済財政政策につながる現状の日本経済・世界経済の分析を行います。
■第2章・第3章
新規に開始したり、更に力を入れたりする経済政策(霞が関用語では「充実ダマ」と呼ばれます。)について言及します。第1章で言及した政府の方向性を詳細化し、個別政策を列挙。「年末までに、検討し、結論を得る」といったような記載を盛り込み、期限を切ることもあります。近年こちらの記載は成長戦略(新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画)と重なることが多くなっています。
■第4章
財政政策(霞が関用語では「財政再建ダマ」と呼ばれます。)について記載します。第2章。第3章が政策を充実させるための記載だとすると、第4章は既存の政策を改革すること(支出を減らすこと)に主眼を置いたものが多いです。ざっくりとしたイメージでいうと、児童手当の拡充のような財政支出等によりサービスを拡充するような内容は第2章(内政がメイン)・第3章(外政がメイン)に入り、社会保障の持続可能性のための負担導入等、予算の効率的な使い方に重点を置くものが第4章に入るというイメージです。
ここまでで、骨太の方針の政府内での位置づけや、文書の構成などご理解いただけたと思います。ここからは、今回の骨太の方針のポイントについて解説するとともに、骨太の方針の策定プロセスを紐解きながら、骨太の方針への政策の記載を目指す皆さんがどのように動いていけばよいかを解説していきます。
(執筆:西川貴清、監修:千正康裕)
講演、コンサルティング、研修のご依頼などはこちら
‐©千正組:購読いただいたご本人が私的に利用する以外の理由による複製・転用を禁じます‐
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
