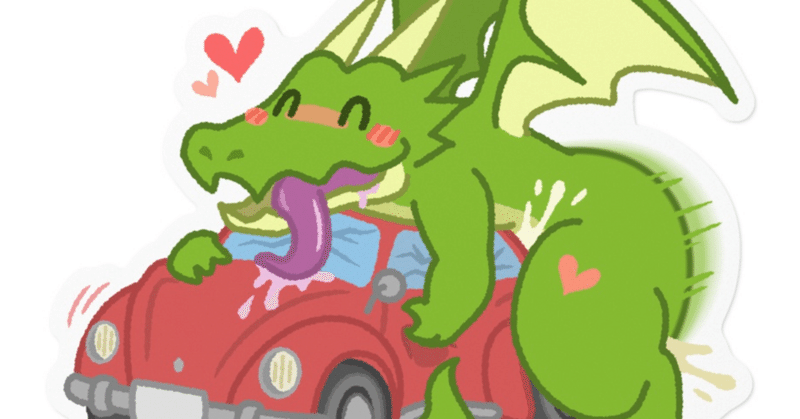
我々のペニスは道徳的に勃起する
悲しい現実だが、人間には「差別する本能」が存在する。
たとえ同じ罪を犯したとしても、ある属性だけが重罪に問われ、ある属性は免責される。そうした差別は古今東西枚挙に暇がない。現代日本における「司法の女割」はその典型例のひとつだろう。殺人や詐欺などの重犯罪を犯しても女性であれば起訴すらされないのは日常茶飯事だ。殺人罪における女性加害者の執行猶予率は40%。不起訴とされたケースなどを含めればどれほどの「女割」があるか想像すら難しい。
そうした「差別」はなぜ生じるのか。近年根強く囁かれているのが外見的魅力に根差す格差、いわゆる「かわいそうランキング」の存在だ。
提唱者の御田寺圭は、「本能的ともいえる人間の自然な感情」によって多くの差別が生まれていると主張する。おじさんはキモい、若い女はかわいい。黒くて大きな犬はキモい、猫はかわいい。何を見て「かわいい」「かわいそう」と感じるかは生得的な本能に左右され、であるからこそ女性や猫のような「かわいそうランキング」が高い属性はひたすらに庇護されそうでない属性は差別される。御田寺の主張をざっくりとまとめるとこうした話になる。
確かに説得的な仮説である。特に現代日本においては「かわいい」ことが一種の免罪特権のように語られることが多い。「美少女無罪」だの「かわいくてごめん」だのと言った妄言が垂れ流されるソドムとゴモラの都市に住んでいると、人間はアダムとイヴの時代からこうした感性を有していたのではないか───と考えてしまうのは無理もない。実際のところ筆者も一時期まではこの仮説に一定の妥当性を感じていた。
しかし最早ライフワークと化した感のあるジェンダー史にまつわる調査を続けている中で、少しずつこの仮説に対する疑問が膨れ上がってきた。
なんと言ってもまず、「かわいそうランキング」上位者と呼ばれる者たちの中に、外見的にキモい人々が相当に混ざっているのである。

上は2015年NY州のゲイ・プライドパレードの参加者だが、お世辞にも外見的に麗しい・かわいいとは言えないだろう。そもそも「かわいそうランキング」上位者の中には障害者、肥満者、トランスジェンダーなど一般的に容姿的魅力に恵まれているとは言い難い属性もかなり含まれており、彼・彼女らに対する特権的優遇が"本能的"な感情に根差しているとする仮説は全くもって説得力に欠けている。
唯一の例外は女性に対する優遇感情だろうが、これでさえも歴史上の女性の扱いを鑑みると疑問符がつく。そもそも「女性」という存在は人類史のほとんどの時期において「穢れ」「不浄」「罪に近い」「外面如菩薩、内心如夜叉」などと散々「キモい存在」として扱われていたのだ。現在でも南アジアなどでは女性に寺院への立ち入りを禁じる地域も多く、日本でさえ「女人禁制」を維持する聖域や聖地は少数ながら未だ残っている。「人間は本能的にかわいい存在を優遇する生き物であり、女性はかわいいので優遇される」という仮説ではこうした事例を説明できそうにない。
それではなぜ、現代日本においては「かわいい」とされる属性に対する優遇と、「キモい」とされる属性に対する差別がまかり通っているのだろう。
あくまで仮説だが、そもそもの論理が逆なのではないかと筆者は考えている。つまり魅力的であることが善と結びついているのではなく、善であることが魅力と結びついているのではないか。「かわいい=善」ではなく、「善=かわいい」こそが人間の本能により近いように筆者には感じられるのだ。
本稿ではホモ・サピエンスの「差別する本能」について、古今東西の事例を惹きながら一考察を提示することを試みる。
「おじさん=キモい」という図式はいつ始まったか
「かわいそうランキング」の仮説に基づくと、「女性=かわいい」「おじさん=キモい」という構図は人間の本能的な部分に根差しており、後天的には変更できないとされている。
つまり「おじさん=キモい」という図式は人類普遍の法則ということになるのだが、これはつい一昔前の大衆文化などを概観してさえかなり怪しげなところがある。というのは1970年代ごろまで、子供向けTV番組でさえヒーローと言えば「おじさん」というのがひとつの定式だったのだ。
初代「ウルトラマン」(1966)の主人公ハヤタ隊員は25歳の国際公務員、初代「仮面ライダー」(1973)の主人公本郷猛も24歳の研究者である。「月光仮面」(1958)に至ってはテーマソングで「月光仮面のおじさんは♪」と歌われるほどのまごうことなき「おじさん」であり、少年少女のヒーロー・ヒロインが本格化するのは相当後になってのことである。
1960年代の漫画文化といえば劇画ブームだが、ここでもやはりスーパースターは「おじさん」である。「ゴルゴ13」(1968-)や「ルパン三世」(1967-)を想像すればわかりやすいだろう。表紙グラビアでさえ飾るのは「おじさん」であり、野球選手や相撲取りなどが巨躯や胸毛を見せつけ多くの少年たちを魅了していたことが「サンデー」や「マガジン」の表紙からも伺える。(余談だが、そうした時代にあってさえフェティッシュな少年少女を描き続けたからこそ手塚治虫はオタクの始祖として名を残したのである)

今では信じられないが、1970年代ごろまで成人男性の胸毛はセクシーさの記号でさえあった。長嶋茂雄や加山雄三の胸毛は雑誌で特集までされており、頭髪用の育毛剤を胸元に振りかける少年まで当時はいたというから驚きだ。
こうした傾向は日本のみならず米国でも同様だったようだ。70年代のハリウッド・アクションの金字塔「ダーティ・ハリー」(1971)も主演のイーストウッドは当時41歳。娯楽の王道だった西部劇も出てくるのはおじさんばかりで、「荒野の七人」(1960)の主演ユル・ブリンナーは当時40歳。「明日に向って撃て!」(1969)の主演ポール・ニューマンも当時44歳である。
つまり1970年代ごろまで「おじさん=キモい」という図式はほぼ存在しなかった。それどころか「おじさん=カッコいい」という図式すら存在しており、だからこそ少年が胸毛を伸ばそうと躍起になったり、"シブく"見られるよう吸えもしない煙草を吸ったりとして「背伸び」繰り返していたのである。昨今のティーンエイジャーは「背伸び」(=大人の真似)をすっかりしなくなったが、その一因のひとつは「おじさん」に対する社会的評価がかつての時代と大きく変化しているからだろう。
それではなぜ、2024年現在「おじさん=キモい」という図式はここまで自明のものとして扱われるようになったのだろうか。筆者の答えは
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

