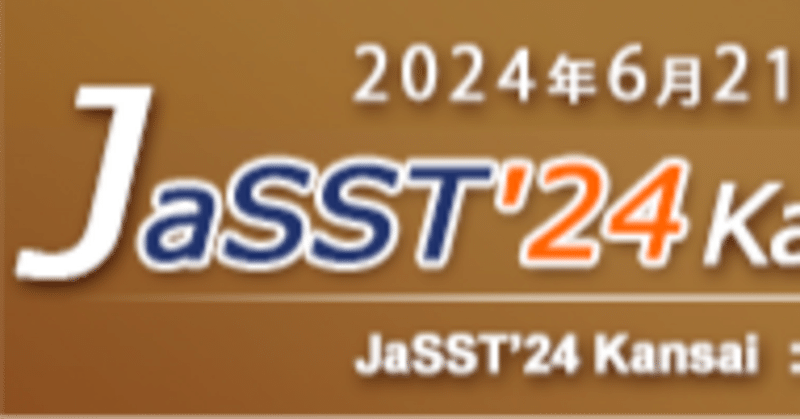
「QAはどう生きるか~テストと品質保証の枠を越えて」 JaSST'24 Kansaiのテーマに関する考察
はじめに
6/21(金) 伊丹にてJaSST’24 Kansaiが開催されます。
開催に先立ちまして、JaSST’24 Kansaiのテーマについて考え、記載します。
本記事は「JaSST’24Kansaiに参加する人を増やしたい」という意図で執筆しています。
ですので、この記事を読む方はできる限り最大限の努力をして、関西まで足を運び、JaSST’24 Kansaiに参加してください。
本記事は自分がとりうる限りの第三者的な視点でJaSST’24kansaiのテーマについて考察したものです。
講演者様の発表に対するコミットメントではないのでご注意ください。
JaSSTという場について
JaSSTとはソフトウェアテストのシンポジウムです。
ソフトウェアテストに関することを中心に、様々なことを学び、ディスカッションして、同じ問題意識を持った仲間と交流することができます。
もし、ソフトウェアテストに関連する業務で悩みや迷いがあれば、ぜひ参加してみるのがいいと思います。
JaSST'24 Kansaiについて
JaSSTは日本各地で行われますが、JaSST’24 Kansaiは関西で行われるJaSSTです。
今回のJaSST’24 Kansaiでは「QAはどう生きるか~テストと品質保証の枠を越えて」というテーマです。
実行委員長の堀川さんの挨拶を引用しながら、JaSST’24 Kansaiに参加する意味と意義について考えていきましょう。
QAエンジニアという呼称
この数年、以前からもあった"QAエンジニア"という呼称が一般的になってきたように感じています。
しかし実際のところ、その役割や職務内容についての議論は活発ではなく、理解が広がっているとは言えないでしょう。
QAエンジニアという呼称について、内容の議論がきちんとされていない現実があるとのことです。
QAエンジニアという呼称は一般的になる以前から存在しているらしいです。
“理解が広がる”とあるので、QAエンジニアについてコンセンサスがある程度存在するのでしょうか。
QAエンジニアという名前で呼ばれていても、その職務は従来のテスターのそれと大差ない、という話も伝え聞くところです。
”QAエンジニアと従来のテスターは本来違う”と読み取れます。
QAエンジニアはどうあるべきかがこの文章では論じられてはいませんが、「以前からもあったQAエンジニア」は「従来のテスター」とは違うのでしょうか?
その点は実行委員長挨拶で述べられることを期待します。
「QAエンジニア」や「テスター」という言葉に違和感を抱いている人はこの違和感をきちんと伝わるように言語化して、参加する人にぶつけるといいでしょう。
テストエンジニアやテスター、品質保証の役割が過去とどう変わったのか、何が同じで何が異なるのか。
「ただ名前が変わっただけ」の一過性のトレンドだと短絡的な結論で終わらせず、議論を深めていきましょう。
これらのロールには歴史的経緯があり、過去、現在、未来と繋がっていくものと理解しました。
過去から現在へ、どのように繋がっているのかは、興味深いところです。
また、前述では「理解が広がっているとは言えない」ともあったので、過去のQAエンジニアの定義は尊重すべきというスタンスが暗に示されているように思えました。
一人目のQAという存在
このテーマを踏まえ、講演は"一人目のQA"としてQAチームの立ち上げに貢献された方々を中心に予定しています。
今回は”一人目のQA”という方に登壇していただきます。
良く一人目QAと呼ばれたりしますが、一人目QAの方は「QAエンジニア」というロールについて、特に考え抜いた方々だと考えます。
一般的に「2人目以降のQA」というのは組織によって要請されたJob Descriptionを元に、ミッションや仕事を与えられ給料を得る、という働き方をしていると思います。
一方で”一人目”となるQAは、開発者からビジネスサイドまで、様々な期待値を調整して考え抜く、そして自ら「QAとは何か」を体現し、2人目以降に繋げていく、まさにQAというロールのパイオニアと呼べるような方だと思います。
そういった方が「組織の中で「QA」というポジション、ロール、活動を定義付けていく中で何を考えてきたか」ということは、一人目QA以外の人にとっても有益な洞察を得られるはずです。
「QAはどう生きるか~テストと品質保証の枠を越えて」というテーマについて
「QAはどう生きるのか」というテーマには、「QAの生き方は様々あり得る」というニュアンスを含んでいるように感じました。
上記で示したような「一人目のQA」以外にも様々な生き方は存在しており、そういった方々が今回の登壇者のお話しを聞いてどう思われるのか、大変気になります。
そういった様々な語り部のお話は情報交換会で話せることになると期待しています。
「テストと品質保証の枠を越えて」というのは大変示唆的です。
QAが生きる場所は「テスト」や「品質保証」あるいはその片方の中だけで止まっていてはいけないのでしょうか?
どうあるのがよりGoodな生き方なのでしょうか?
それは講演の中で知るかもしれませんし、自分自身で答えを見つけるものかもしれません。
QAとして生きることについて
「生きる」という言葉を使ったことも考える余地があるように感じました。
「働く」ではダメなのでしょうか?
「生きる」とは単なる仕事としてのQAを意味していないように思えました。
「生きる」とは目の前の仕事をすることだけでなく、自分の人生の一部として「QA」というものがあり、意味付けを行うものだと思えました。
「QAとして生きる」ことには我々の人生にどういった意味があるのでしょうか?
それもJaSST’24 Kansaiで得られることの一つかもしれません。
Smalltalk「QAの死」
「生きる」ことについて考える際、「死」ということを意識せざるを得ませんでした。
QAの死とはどのようなものなのでしょうか?QAはいつ死ぬのでしょうか?
それはいつか明かされるでしょう。
おわりに
そういや、今回は「生きる」ことがテーマですが、JaSST’21 Kansaiでは「テストエンジニアのサバイバル術~After DXの世界に生き残るには」でした。
中の人はだいぶサバンナの中で生存本能駆り立てられてるんですかね。
ここまで読んだ人はぜひ「JaSST’24 Kansai」に足を運んでください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
