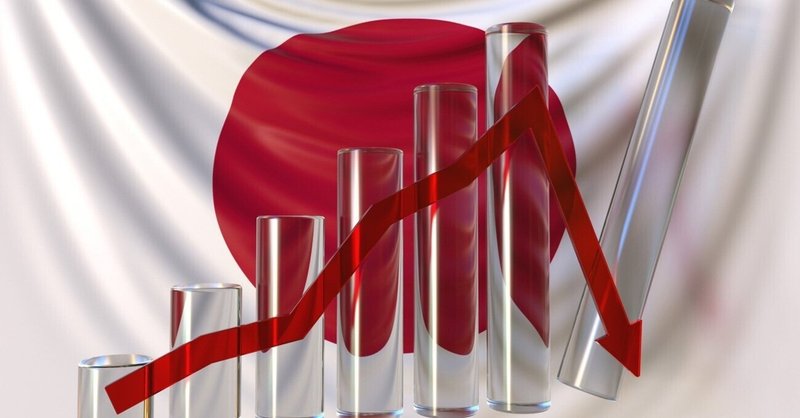
貧乏国ニッポン ~ますます転落する国でどう生きるか~②
前回の続きになります。
「安さ」だけではない、日本の転落
日本の国際的な地位は急激に低下
残念ながら日本の国際的な地位は急激に低下しています。ただ、この事実も日本国民に全体的に知れ渡っているとは言えません。メディアが非常に保守的であり、日本が置かれている厳しい立場よりもむしろ日本にとって良いニュースや耳障りのいい出来事ばかり垂れ流していることも主要な原因だと個人的には思っています。
では、どのような点で日本は衰退していると言えるのでしょうか。まずは私の専門分野である教育から見ていきます。
日本からノーベル賞受賞者は出なくなる
日本と言えばこれまでに毎年のようにノーベル賞受賞者を出してきたイメージがあります(特にノーベル化学賞)。
日本の競争力、国力が落ちているのは、1990年代後半あたりからのイノベーションが停滞し、卓越した製品やサービスを開発できなかったことが原因だとされています。特にIT革命に乗り遅れたことは致命的でした。各国の基礎的な国力や競争力は、研究開発の活発さとほぼ比例しますが、その研究開発の状況は発表される論文の数を見るとよくわかります。
引用回数がトップ10%に入る論文の中身を見てみると、これまではアメリカがダントツにトップでしたが、2000年代に入ってから中国が驚異的な勢いで論文数を伸ばし、現在はアメリカと匹敵するまでになっています。ドイツや韓国なども中国ほどでないにしてもかなり論文数を伸ばしていますが、日本はむしろマイナスになっており、このままだと韓国にも抜かれる可能性が高いそうです。
日本が近年ノーベル賞受賞者を多く輩出したという事実は、過去30年くらいの研究成果であって、上記の論文の状況を考えると、日本からは今後ノーベル賞受賞者は非常に出にくいのが現実のようです。
では、なぜ論文が少ないのかというと、研究に必要な予算が削られているからです。私は何度もこのnoteで日本は先進国の中で最も教育にお金をかけない国だと書いていきましたが、それがまわりまわって国力の低下につながっているということです。
「日本は暮らしやすい国」は過去の話
さて、みなさんは日本は最も訪問したい国ランキングで何位だと思いますでしょうか。実は日本は全体のランキングで堂々の1位になっています。
日本の経済的衰退に伴って、世界の人々が続々と日本に観光に訪れるようになったのは皮肉な話ですが、今日本は世界中の人々を魅了する観光立国への道を歩んでいます。ちなみに、先日アメリカから成田空港に帰ってきましたが、そこで圧倒的な数の外国人観光客を目のあたりにし、ポストコロナのインバウンドを肌で感じました。
一方で、「訪れたい」ではなく「住みたい」という見地で見ると日本はどうでしょうか。

なんと32位。治安に大きな問題があるメキシコや南アフリカよりも低いなんて・・・。
ちなみにこのランキングには2つの特徴があります。
スイス、シンガポールなどは、極めて賃金が高く、完璧なビジネス環境が整備されていることが順位に大きく貢献しています。一方、カナダ、スペイン、ニュージーランドなどは、ワークライフバランスの点数が高く、仕事だけではない充実した生活が送れるという点が評価されています。
日本のランキングが著しく低いのは、何かが大きく足を引っ張っているわけではなく、全ての項目において評価が低いことが原因です。「賃金」「ワークライフバランス」「子供の教育環境」などは最下位です。泣けますね。
日本は、人材供給源と想定している国よりも魅力のない場所となっており、このままでは、外国人労働者すら来てくれなくなるかもしれません。それどころか、むしろ我々が海外に出稼ぎに行かなければいけないという時代はすぐそこに来ています。
なぜここまで安くなってしまったのか
ここまで日本が「安い国」になっているという事実を書いてきましたが、その最大の原因は日本企業の競争力が下がり、経済成長ができていないことになります。
世界と比較してみると、日本の状況がいかに特殊かということがよくわかります。例えば、アメリカ、ドイツと日本を比べると下記のような感じになります。
年収400万円だった「日本君」は20年度の年収も400万円でした。一方、「ドイツ君」は400万円だった年収が20年後640万円になり、「アメリカ君」に関しては400万円だった年収がなんと倍の800万円になっていました。もっともアメリカの物価は1.5倍に上がっていますので、アメリカ君の支出もその分増えているのですが、それ以上に年収の上がり幅が大きいので、アメリカ君の生活水準は大きく向上したことになります。一方日本君は年収も物価も変わっていないので、生活水準も何も変わっていません。
我々は「変わっていない」ことに問題を感じないかもしれませんが、外国を見てみればこの「変わっていない」ことが大きな問題なのです。
日本の強みをどう生かすべきか?
これまで割と絶望的な内容を書いてきましたが、それではこれからの日本はどこへ向かえばよいのでしょうか。
まずは日本経済の仕組みを見ていきます。
日本はもともとモノ作りの国であり、輸出産業が経済を支えていると考える人が多いのですが、それは過去の話で、現在は消費と投資で経済を動かす国となっており、今後はこの強みを生かすように政策を変えていく必要があります。
まず、消費という点においては、国内市場を改めて見つめる必要があります。確かに我が国の人口は減少の一途をたどっており、消費の絶対値も低下することが予想されます。ただ、それでも一定以上の生活水準を保ち、同じ言語を話す1億人の単一消費市場が存在しているということは、世界を見渡してもそう多くはありません。輸出やインバウンドに頼ることなく、国内の消費市場をもっと活性化していくことは必要不可欠です。
サラリーマン社長を一掃すべき
日本では不景気が長く続いているせいもあり、多くの企業経営者たちは先行きを不安視して、現状維持を優先してしまう傾向にあるようですが、これは世界的には珍しいことです。
大手コンサルのPWCが行った調査によると、日本の経営者の中で「自社の成長について自信がある」と回答したのは全体の11%足らずで、主要国の中では最も低い数字だったそうです。企業のトップたちがこのように自信を失っているようでは、日本の経済が成長するわけもなく、まずは彼らがもっと挑戦できるような土壌を整える必要があると考えます。
また、下のグラフはユニコーン企業(「評価額が10億ドルを超える、設立10年以内の未上場のベンチャー企業」)の推移を表したものですが、アメリカや中国とは比べるべくもありませんが、韓国やインドネシアにさえ完敗しています。

これはIT革命に乗り遅れたことや、そもそも日本には起業家が育ちにくい土壌があるためだと個人的には考えます。これは教育の力で変えることができると私は思っており、プログラミングをはじめとしたテクノロジーの活用を本気で学校教育に取り組む必要があり、同時に中等教育の中でアントレプレナーシップ(起業家精神)を教える必要があると思っています。
現在の日本経済が抱える本質的な問題は、市場メカニズムに沿って自ら新陳代謝するという企業活動が阻害されており、それに伴って消費者の行動も抑制されていることです。最終的にこの状況を打破できるのは政府ではなく、企業の経営者であり、私たち消費者です。
あえて政策という点に絞るのであれば、有能な人材をトップに据えるためのメカニズムを強化する施策が重要です。そして消費者向けには、個人消費の拡大を阻んでいる将来不安を一掃するための施策が必要です。例えば、それは年金制度や子育て支援の充実化だったりしますが、なかなか難しいのも事実です。我々は国だけに頼らず、自分たちでしっかりと自分たちの生活を豊かにできるように、主体的に経済活動に取り組む必要があるのではないでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。
