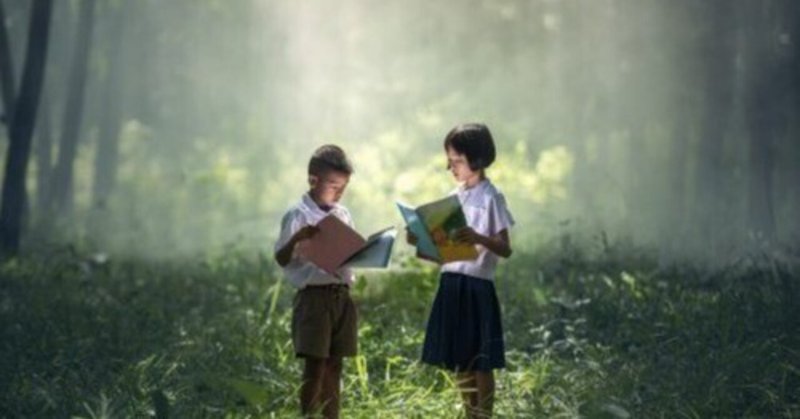
勉強するのは何のため?
何年か前に読んだ本ですが、Kindle Unlimitedのリストに入っていたので、久しぶりに読み返してみました。ちなみに作者の苫野さんは教育哲学者で、これまでに何冊か著書を読みました。私の好きな教育者の一人です。
タイトルの「勉強するのは何のため?」という疑問は誰でも一度は思ったことがあるのではないでしょうか。
特に日本では「勉強」=「試験勉強」/「受験勉強」というようにイメージされ、いやな思いしか残っていない人が多いと思います。ゆえにこのような疑問を抱く人は多いのではないかと推察します。もちろん私もそのうちの一人でした。
「一般化のワナ」と「問い方のマジック」
一般化のワナ
標題の質問の答えを探していく前に、「一般化のワナ」と「問い方のマジック」という2つの考え方を理解しておく必要があります。
「一般化のワナ」に関しては、人はとかく物事を一般化しがちです。特に教育に関しては、誰もが教育を受けた経験があるので、自分の経験から一般化してしまいがちです。
例えば、「学校の先生と塾の先生、どっちがいい?」なんて質問はどうでしょうか。
言うまでもなく、この質問には個人の経験と思いが反映され、人によって答えがだいぶ変わってきます。もし「学校の先生かな?塾の先生かな?」と迷ってしまったなら、それは「一般化のワナ」にはまっていることを示しています。
学校の先生と塾の先生は「教える」ことを生業にしているのは一緒ですが、そもそもその目的が異なっており、比較できるものではありません。また、もし塾の先生で教え方がうまい人がいたとしても、それはたまたまその人にとって教え方がうまかっただけで、他の生徒皆が同じように感じているとは限りません。さらに言えば、もしその塾の先生が教え方がうまかったとしても、その先生のことだけで塾の先生は教え方がみんなうまい、などと一般化することはできません。
こんな簡単なことでさえ、わかっていない人は多いと思います。子供だけでなく大人も含めてです。
問いのマジック
「なんで勉強なんかしなくちゃいけないんだろう?」
本書の主題となる質問ですが、これを次のような問い方に言い換えてみます。
「学校の勉強は、学校生活を送るうえで役に立つのか、それとも立たないか?」
ご覧の通り後者は二者択一の質問になっています。人間は不思議なもので、このような二者択一の質問になると、「どっちかの答えが合っている」という先入観に支配されます。「つまりどちらも合っていない(第3の選択肢が存在している)」、または「どちらの選択肢も間違っている」ということはなかなか頭に浮かばないのです。
他にも「子供はほめて伸ばすべきか、叱って伸ばすべきか」とか「幼いころから英語を勉強させた方がいいのか否か」とか、この手の質問に絶対的な答えなんかないのです。
まずスタートとしては、上記の「一般化のワナ」と「問いのマジック」を理解しておく必要があります。
なんで勉強しなくちゃいけないの?
もうここまでの流れでお気づきかと思いますが、この誰もが一度は抱いたことのある疑問に対して、絶対的な答えなど存在しません。
例えばこの質問の解として、「いい大学に入って、いい会社に入るため」とか「忍耐力や論理的思考力を鍛えるため」とかいろいろな答えが考えられますが、そんなものは人によって、または時と場合によって異なり、一般化などできるものではありません。
「生きる意味」に絶対的な正解なんてないのと同様に、「勉強はしなくちゃいけないのか否か」という問いも絶対的な正解など存在しないのです。
大切なことは絶対的な正解ではなく、自分にとっての「正解」を見つけること。これはかの有名な哲学者ニーチェの教えでもあるのです。「勉強する意味」についても、自分なりの意味と理由を探していくことが本来我々に求められるあり方なのです。
私なりの「勉強する意味」
では、一教育者として、そして一人の親として、私は勉強する意味をどう捉えているか。実は先日娘と「なぜ英語を勉強するのか」という話をしたばかりなのですが、娘には「自由になるため」だと伝えました。
英語の勉強をするのは決して受験のためでも、検定のためではない。そんなものは一つの物差しであり、通過点でしかなく、英語は自分の人生を自由にするための武器でしかないと話しました。折角の一度しかない人生の中で、果てしなく広い世界に飛び出ずに日本の中だけに留まることの意味を考えてほしかったのです。英語ができれば、もしこの国に心底嫌気がさしたときに脱出もできますし、自分の可能性を無限に広げることができます。(もちろん英語ができるだけでは何の意味もなく、人としての価値を高めることがそれ以上に重要なのは言うまでありません)
奇しくも、著者の苫野さんは本書で、勉強する意味に絶対的な正解なんてないという前提に立ちながらも、誰にも共通する勉強の意味は「自由になるため」だと言っています。彼が言う『自由』とは、「生きたいように生きられる」ということで、その自由を獲得するためには何ならかの「力」が必要です。極端な話、読み書きができなければ生活もままなりませんし、スポーツ選手や医者になるためにはそのための「力」が必要で、世界で活躍するビジネスマンになるためには英語だけなく、教養も必要です。自分自身を自由にするために「力」をつけるための手段が勉強だということです。
なんで学校に行かなきゃいけないの?
なんで勉強を強制させられるの?
この問いに対する「正論」は以下のようになります。
社会にとって必要だから
いつか必要になるから
前者については、例えば多くの高校生が「なんで微分積分なんか習わなくちゃいけないんだ!」と怒りを覚えているかと思いますが(私がそうでした笑)、実際に微積がなければ科学技術文明は全く成り立ちません。橋を架けることも、人工衛星を打ち上げることもできないのです。つまり、誰かが微積をマスターしてくれないと私たちの社会は成り立たないのです。
後者は、「自分はずっと日本で暮らすから英語なんて必要ない」と言っている人が、就職した後に海外とやり取りをしなくてはいけなくなる可能性も十分あります。(自分の友人でもそんな人はたくさんいます)だから今のうちにやれと。
ただ、これらの解答は的を得てはいるものの、子供たちがすとんと腹落ちして勉強するようになるかというとそんなことはないでしょう。実際に試験勉強や受験勉強で覚えたことなど、試験が終われば一瞬で忘れてしまい、社会に出てから使うこともほぼないからです。
しかし、学校で学んだことが社会に出てまるまる役立つわけではありませんが、社会で必要な知識の大半を学校で学んでいるという大切な事実を忘れてはいけません。これは勉強だけの話ではなく、人と人とのかかわり方やコミュニケーションの取り方など、学校は「社会勉強」の場でもあるのです。
学力とは
これもこれまでにnoteで何度も書いてきた内容になりますが、学力とは試験の点数や偏差値などの目に見える数字だけではありません。日本ではとかくそれらの「認知能力」を学力として捉えがちですが、それだけではこれからの時代を生き抜いていくことはできません。(その証左として、現在の日本の悲惨な姿があるのです)
苫野さんは学力とは「学ぶ力」であると定義しています。
社会に出れば、多くの場合知らないことだらけです。ましてや今は「VUCAの時代」と言われるほどに複雑で解なき問いがあふれる時代であり、その中で生きていくためには、様々なことを自ら学んでいかなければなりません。
自分の直面した問題をどう解決できるかを考え、そのために必要なことを「学ぶ力」。それが学力の本質なのです。
そうなると、学校での勉強は本来どうあるべきかという問いに行き着きます。細かい知識ばかりを覚えさせるのではなく、自ら「学ぶ力」を育むようなものにしていく必要があります。その手法として「探求型」「プロジェクト型」の学習が現在日本の多くの学校でも取り入れられています。
余談ですが、私が勤める学校では創設以来上記の探求型学習やPBLを取り入れており、グローバル教育やICT教育なども相まって、「教育先進校」とされています。生徒たちの多くは学校の枠にはまらずに、学内外で様々な活躍をしています。これまでの日本の教育は教師が主体になっていましたが、これからの時代の教育は主導権を生徒に渡し、生徒中心主義で進める必要があります。生徒が自らの学びを探求し、自律的に学習をするようになれば、「勉強するのは何のため」や「なんで学校に行かなくちゃいけないの」という疑問は、生徒たち自ら答えを持つのではないかと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
