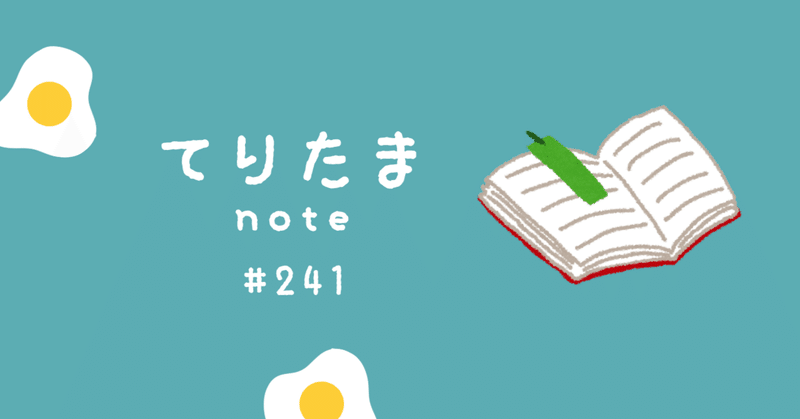
公認会計士35年目にして本を書くチャンス到来!【てりたま、本を書く❶】
私、実は本を書いております。どんな本をどんな経緯で書くことになったのか、お話しします。
監査法人で30年強、うち17年をパートナーとして勤めた「てりたま」です。
このnoteを開いていただき、ありがとうございます。
秘密でも何でもなく、お会いした方にはお話ししてきたのですが、出版のお話をいただき、本を書いています。
監査法人にいたときに、大勢いる共著者の一人になったことはあるのですが、単著ははじめて。
会計士界隈、経理界隈には本を出しておられる方がたくさんいらっしゃいますので、今さら感がありますが、私にとっては一大事です。
まだまだ執筆途中ですが、何回かに分けて経過をご報告していきます。
本を書くことに興味のある方には、役に立つかもしれません。
中央経済社から声をかけていただく
子どものころから本は大好きでした。
母は、外出時に黙らせるために本を買い与えたと言っていました。その動機はともかく、今では感謝しています。
本はずっと「読むもの」で、自分が書くイメージはありませんでした。
公認会計士になり、周囲に本を執筆した人が当たり前にいる環境に身を置くことに。出版というものを身近には感じたものの、自分で積極的に手を上げなかったこともあり、結局ほんの一部分を手伝う以上の機会はなかったのです。
それが、監査法人退職後、半年ほどして、出版社から声をかけていただくことになります。しかも、中央経済社さん。
声をかけていただいたから、よいしょするわけではないのですが、同社の数多くの専門書に学び、助けられてきましたので、私にとって目もくらむような存在です。
退職してからTwitter(現・X)やこのnoteでの発信をはじめましたが、当時のフォロワーさんの数はTwitterが2千人ほど、noteは500人ほどでした。私としては出来すぎで、当時からお付き合いいただいている方々には大感謝なのですが、数ある発信者の中で目立つ存在ではありません。
声をかけていただいた理由をお聞きしたところ、noteを読んでおもしろいと感じていたとのこと。
週3回、雨の日も風の日も書き続けたかいがありました。
本のテーマは…
ここで、問題がありました。
長年、監査法人では会計、内部統制、ガバナンスなどに関わってきたわけですが、私が一番こだわってきたのは監査です。
ところが、会計の本であれば企業の経理の方にもお読みいただけますが、監査の本を読むのはほぼ監査人に限定されるため、対象となる読者がかなり少なくなります。
中央経済社の編集者Sさんには、とはいえ最近は監査の本でも販売好調なものがあり、挑戦してみてもよいかもしれない、とおっしゃっていただきました。
さて、監査の何を書くか。
私の中にあったのは、次のような断片的なイメージです。
(会計士に限らないですが)日本の20代、30代の人たちを応援したい
コロナで本格的にはじまったリモート勤務では、若いスタッフのOJTが難しくなっている
そもそも「監査マニュアル」に書いてあることだけでは監査はできない
S編集者とブレーンストーミングした結果、若手監査スタッフ向けの本にしよう、ということになりました。
盛り込む内容についても、アイデアが出てきました。例えば……
監査に対する基本姿勢
クライアントとの向き合い方
監査チーム内のコミュニケーション
会計士の働き方やキャリア形成
若手スタッフに対して、監査現場や移動途中、食事などの機会に話すような内容をイメージしました。
これらの話題は頭の中にごちゃごちゃとあり、スタッフの状況やタイミングに応じて話すネタを見つけていました。これを掘り出して、まとまった形にするのは難航しそうです。
さて、どうなることやら……
おわりに
これから不定期で進捗をご報告します。
次回は、執筆にあたり、どんな苦労があったかをお話ししたいと思います。
まだまだ過去形ではなく、現在進行形です。
このnoteを書くことでつかの間の現実逃避ができましたので、また本に戻ります。では🫡
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
この投稿へのご意見を下のコメント欄またはX/Twitter(@teritamadozo)でいただけると幸いです。
これからもおつきあいのほど、よろしくお願いいたします。
てりたま

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
