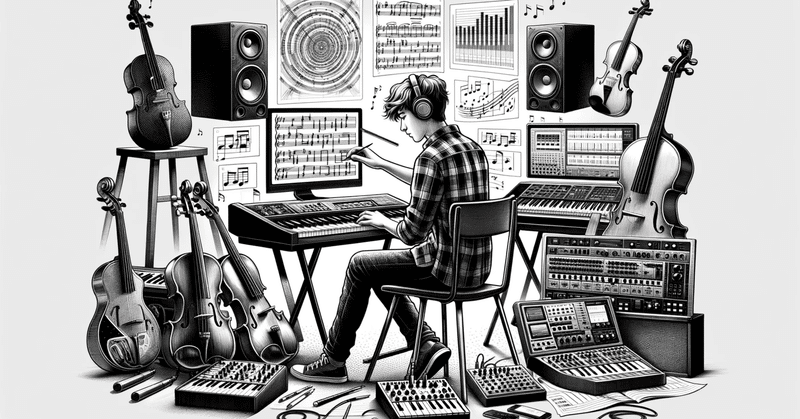
ネガティブハーモニー:音楽理論の冒険
ジェイコブコリアーの響きを聴いていると、
たまに独特な響きがするなぁと
ちょっとだけ普通の和声から逸脱しているような響きがしていたり、微分音みたいな調に転調したりとか、解説とかもしているので面白いのだけど
その中の一つにネガティブハーモニーという作曲アプローチがあって、ちょっと調べてみたけど、簡単な解説だと解釈がいろいろあるっぽくて、
tatmos流に判断してノート書いてみようと思う。
ので、なにが正しいとかは、ここで当てにしないて、
各自判断していただけるとありがたい。
おそらく厳密なルールはなくて、考え方だけ拾ってもらえれば幸い。
ネガティブハーモニー
ちゃんと調べていないけど、Webとかで見つかる情報から
おそらく、音を置き換えて、新しい響きを得る手法で、
でも、12音技法とか音列とかのような調性から外れたものではなくて、
調性音に近いけど、調性から外れすぎないという
五度圏のサークルを利用して、
調の重心となる音を境界とし、反転した音を選んで楽しむような
音が発生する装置のようです。
五度圏サークル

手書きなのでざっくりだけど、
この図を見ながら、暗号解読みたいに音を選んでいく
調性がCメジャーのキーであれば、
その主音Cと属音Gとの間に線を引く
(ここでは赤い線)
これで、置き換えルールは完了
まずは、変換元となる
普通のコード進行を作ってみて、
その構成音を、この赤い線の反対側にある音に置き換えて
再構築する。
例えば、こんな感じのハノンの練習とかにありそうな2-5-1のような進行を考えてみる

最初の和音はレファラドの Dm7の構成
ベースの音から処理していくと
D-7/Fの第一転回形なので F
ベースの流れとしては、F G C
と変化する
対応するネガティブハーモニー用の音は
D C C

最期の音は主和音なので、ネガティブじゃなくてオリジナルのCの和音で終わるようにしている。
ここの上3声もそれぞれ当てはめて埋めていく

のだけど
ここは気持ちよさそうな音の流れになるようにちょっと配置は転換してしまってもよいかなと
もともと和声的なら、和声的に自然な流れに改変してしまうとか

ネガティブハーモニーのルールで対象の音を拾っていくだけだと、なんとなく同主マイナー調から借りてきている感じ、ちょっとベースの音の進行が不思議なくらい
導音のはずのBの音もフラットしているので、教会旋法っぽい雰囲気だし、
ベースの音は属音との入れ替えなので、共通音を先行している感じ。
調性として安定している弱い進行のようなイメージ。
やわらかく終止したい時とかに使えそう。
和声だと、C-Fm-Cみたいなのに近い響き。Bbまででてくるので、スケールが変わった感じがするけど、五度圏ではそんなに遠くない音だから響きも濁らない。下属調の五度(よどごど)みたいな。
これでも、普通の音楽との橋渡し(共通理解からのすこし逸脱)としては落としどころなのかもしれないけど
五度圏の近接の調の音が入ってくることで、調性から少し離れているところを通っている感じ。転調まではしていないけど、一時的にふわっとするのは楽しい。
帰り道を別の道を通っていった感じ
とジェイコブコリアーさんも言ってたような、
実は道はいろいろあると教えてくれている。
そういう音を曲に合わせて選ぶのだと。
面白い音を求めてちょっとだけ遠回り
五度圏の近くの音を拾ってくるのが、素直だと、基準の帰り道だけど、
ちょっとだけ遠くを拾ってくると、もっと面白い音になりそう。
この考え方を拡張して、
音を選ぶルールをもっと考えてみる
ここからは置き換え実験、マニアックな世界かもしれない。
ネガティブとして対象となる音の選び方を少し外したら、
(道を少し外れたら)
もっと、調性から外れているけど、規則性の感じられる音が選ばれるような気がする。
例えば
音を元の調の重心(主音と属音)を中心にして、
まずネガティブハーモニーの音を選び、さらに
5度シフト・4度シフトして置き換える
F G C
のベースの音を
D C Cにして
調の中心からさらに遠い
A F C
と変換する

これは、ちょっと遠すぎて濁ってしまうか
ベースだけ元に戻して 合わせてみる

ちょっと、内声とベースが同じような動きになってしまっているけど、
普通には思いつかない不思議な積み重ねかたの響き
そういえば印象派
印象派の音の響きで、5度とか4度とか上とか下に音を重ねたりして、新しい音を探すみたいな探求があったけど
五度圏の旅をしているのかな
本来のあるべき場所の音をトランスフォームして
みたいなシンプルな変換でも
面白い音(目新しい音?人によっては懐かしい音?)になりそうだなと。
AIのジェネラティブについて思う
脱線話
さいころを振って音をランダムに選ぶのとは違う
AIとかも、何かバリエーションを出させようと、ちょっとルールを揺すると、本来の近い音から、距離のそれほど離れていないものを選んで、出してくるみたいな、そういうところに、時々目新しさとかを感じたりするのかもしれない。
ただ、その機械的な選択自体は、AIらしさとか、学習の偏りに見えてしまうかもしれないし、面白さも一時的なものなのかもしれない。
でも、それっていうのも、何かヒットして、普遍的に文化になってしまったら、ジャンルやスタイルになっていくのだろうか・・・
音楽や楽器の歴史は最新技術と共にあるから、
どうなっていくのかなぁと思いつつ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
