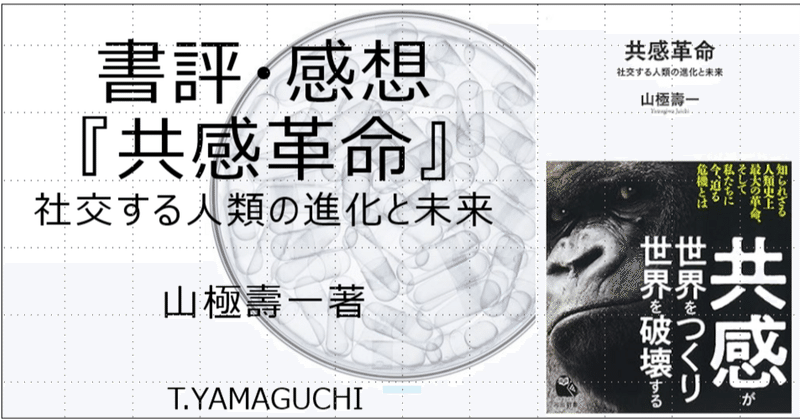
書評・感想『共感革命』 社交する人類の進化と未来 山極壽一著感想と個人的な評価
個人的な評価:★★★★☆(星3.5~4.0)
この本の基本的なメッセージである「共感革命」については、文字通り“共感”するし、その通りだと感じている。
しかし、後述するように、トータルで見るとやや違和感がある本であった。
そのため、本書に関しては、星は「3.5~4.0」という評価とした。
1. 本書の感想
本書については、序章~第二章までが「共感革命」の話の中心であり、ここまでを読めば、その最も重要な点を理解できる。
共感によって進化した人類は、今、共感によって滅ぼうとしている。
今までの定説では、人類の繁栄は約7万年前の言葉の獲得がその大きな起点だったとされている。
言葉の獲得によって「認知革命」が起きたというのだ。
これに対して著者は「認知革命」の前に、もっと大きな革命があったのではないか、と考えている。それが「共感革命」である。
私は、この考え方には大いに賛成である。
そして、この考え方・説がこの本のメイントピックであることも間違いないだろう。
本書では、この考え方以外にも、様々な話が展開されている。
しかし、とりあえずこの話を押さえておけば、まずは十分なのかな、という印象である。
2.「共感革命」とは何か
著者は、「共感革命」を主張する理由として、まず、次のように述べている。
『サピエンス全史』で知られる歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリは、ホモ・サピエンスが言葉を獲得し、意思伝達能力が向上したことを「認知革命」と呼び、種の飛躍的拡大の最初の一歩として考えた。
(中略)
もし七万年前に言葉が登場したという説が正しければ、人類はチンパンジーとの共通祖先から分かれた7百万年の中でわずか1パーセントの期間しか言葉を喋っていないことになる。その点を踏まえれば、まず身体があり、次に共感という土台があったうえで言葉が登場したと考えるほうが自然だろう
(中略)
人間の脳は200万年前に大きくなり始め、ホモ・サピエンスが登場する前に、すでに現在の大きさになっていた。つまり、言葉が脳を大きくしたわけではなく、むしろ先に脳が大きくなり、その結果として、言葉が出てきたと考えられるのだ。
著者の主張を言い換えると、次のようになるだろう。
人類は、言葉を喋るようになる前に、非常に長い期間、ここで言えば、「7百万年マイナス7万年」という期間に渡って、言葉をしゃべらない時代があった。
その時代に、人類が何らかの進化を遂げていないとすれば、チンパンジーと人類との差は、もっと小さかったのではないか。つまり、言葉を話すようになる前に、「共感」という土台があって、それが人間とチンパンジーの差を拡げる要因となったのだ。
人間の脳は、言葉を話し始めるようになる7万年前よりも、ずっと古い200万年前に脳が大きくなり始めていた。つまり、言葉を話すことで脳が大きくなったのではなく、脳が大きくなった結果として、言葉を話すようになったのである。
これは、まさしくそのご指摘の通りだと思われる。
人類とチンパンジーとの差を大きく広げたその要因こそが、「共感革命」である、という著者の主張に私も「共感」する。
この後、様々な話が展開されるが、この話がこの本の主張の根幹であり、結論としてこの点だけ押さえておけば、それで十分かな、と思えてしまう。
3.言葉を獲得していない時期に重要であったもの
著者は、次のように指摘している
人間の共感能力は、直立二足歩行を始めたことによって高まった。
直立二足歩行によって、人類は発声を自由に行えるようになった。しかし、発声ができるだけではだめで、その後に認知能力が加わらないと言葉はしゃべれないので、すぐに言葉がしゃべれたわけではないだろう、と著者はいう。
そこで出てくるのが、「音楽」や「踊り」である。
言葉を獲得していない時期に、重層構造の社会を可能にしたのが、音楽的なコミュニケーションだった。
(中略)
言葉という、音声と意味が合体されたコミュニケーションが出てこなくても、身体を共鳴させたり、他者と声を出し合って、合唱したりすることもできる。
そうすれば、集団の一体感が強まり、信頼しあえる仲間の規模は大きくなり、大型肉食獣にも打ち勝てる。
つまり、二足歩行を始めたことで、自由な発生ができるようになり、それによって「音楽」と、さらには「踊り」を獲得した。
それによって、仲間同士の共感性を高められるようになり、集団の規模を大きくすることができ、大型の肉食獣にも打ち勝てるようになって、人類は生き残っていった、というのが著者の主張なのである。
4.言葉の持つ暴力性
人類は、共感革命で得たもの、具体的に言えば、音楽的なコミュニケーションによって基礎づけられた共感力によって、仲間同士の絆を高めてきた。しかし、その後に得た言葉によって逆に攻撃性を高めてしまった、と筆者は言う。
しかし、言葉は人間の持つ攻撃性を高めてしまった。
社会の共感力を維持するには、それぞれが身体を共鳴させて心を一つにし、絆を強める必要がある。それが途絶えたり、マンネリ化したりすれば、仲間を思いやる気持ちが低下してしまう。そんなとき、共感力を高めるために共通の敵が作られる。みんなの目が敵に注がれ、一斉に団結して排除しようとすることで、仲間意識が高まるのだ。そんなときに多用されるのが、音楽に歌詞を付けて合唱することである。
音楽は、共感力を高めるが、それに言葉が加わることで、目的意識が付与されて強化されることで、逆に攻撃性が高まる、と著者はいう。
これまでの戦争を振り返っても、必ずといっていいほど軍歌がつくられ、合唱されてきたのはそのためだ
言葉による認知革命の重要性が指摘される一方で、著者による「言葉の攻撃性」の指摘は傾聴に値する。
現代のような社会へと加速させたのは言葉だが、そもそもの起源をたどれば、言葉のない社会があり、それでも人間社会の基本的な機能は十分に成立していたことは覚えておくべきだろう。
この言葉に、「共感革命」という著者の主張の根幹が存在している、と私は感じている。
5.その他のいくつかのポイント
(1)未来が過去に奪われ始めている
AIは情報がなければ動けない。答えを出すときは、必ず過去の情報を分析して未来を予想する。それはつまり過去に縛られているということだ。AIはゼロから一を生み出せないから、過去の出来事が未来をつくることになる。その未来のスケジュールに従って人間が動くのであれば、私たちはもう自律的に未来を描けなくなるだろう。
AIに関するこの指摘には、「なるほど」と思わされた。
「AIの裏をかいて、過去を捉えなおす必要がある。過去を振り返り、かつての誤ったポイントで別の判断をしていたらどんな現在が見えるのか、そしてその現在の彼方にある、まだ起こっていない未来を新たに創造していく必要がある。
まさしく、著者のおっしゃる通りである。
(2)「遊び」について
人間の遊びに関して、フランスの社会学者ロジェ・カイヨワの考察を著者が紹介しているが、これが興味深い。
遊びは、競争(アゴン)、偶然(アレア)、模擬(ミミクリ)、眩暈(イリンクス)という4つのカテゴリーに分けられ、そのどれもが時空間的な虚構の中で制定されたルールに基づき実施される。
(中略)
これらの遊びは他の動物にもあるのだが、偶然的な遊びは人間にしか見られない。人間以外の動物は、自分の意思でコントロールできない偶然性では遊ばないのだ。
この指摘の重要性は何なのかというと、「偶然性を伴う遊び」というものには、「未来を想像しながら偶然に賭ける」という人間独特の意識と認知が必要である、という点である.
さらに著者は、「遊びは緊張状態では起きない」と指摘している。
これを言い換えると、「遊びは生活の中で安心して余裕がある際に、はじめてできるもの」ということになる。
まあ、当たり前かもしれないが、面白い指摘であると思った。
6.本書の課題
既述の通り、本書の中心的なコンセプトである「共感革命」については、私自身も強く共感している。
しかしながら、本書については、以下の点で課題を感じている。
第一に、例えば「認知革命」などについて、何が学界等で通説とされていること、あるいは最新の学説・研究成果等であって、それに対して著者の考えがどの部分なのかが、今一つ判然としない書き方をしている点である。
言い換えると、本来であれば以下のような書き方がなされるべきなのに、それがきちんとできていないという印象が私にはある。
学界の通説では、以下のように言われている。また、最新の研究成果から、次のようなことがわかっている。
学界での通説や最新の研究成果を踏まえて、あるいは、それにも拘わらず、著者としてはこう考えている。
上記「2」の考え方の理由は、次の通りである。
本書を読む者である私の立場からすると、まずは「1」をきちんと知っておきたい。
それに対して、著者の主張・考えである「2」については、丁寧に傾聴したい。そして、その根拠(=「3」)についても理解をしたい。なぜならば、著者の考え方に賛同するかどうかは、「3」次第だからである。
第二に、「共感革命」という本書の主要コンセプトについては、本書の2章くらいまでを読めば、ほぼ内容を理解できるようになっているが、その後の各章については、それなりに面白い点もあるが、「共感革命」との関連性が見えにくくなっている点である。
まあ、紙数を稼ぐために仕方なかったのかもしれないが、結局何を言いたかったのかが、本書全体としてはわかりにくくなっているように思える。
最後に、感想のまとめとしては、もう少し論理的にわかりやすく、体系立った本にしてほしかった、ということになるだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
