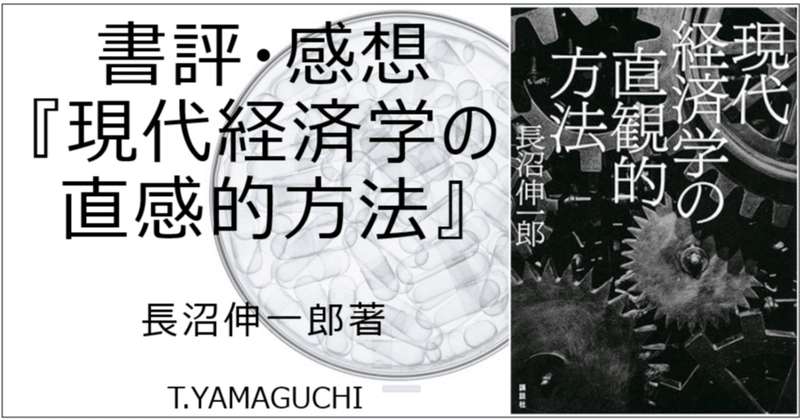
書評・感想『現代経済学の直感的方法』 長沼伸一郎著 感想と個人的な評価
個人的な評価:★★★★☆(星4.0)
少し古い本であるが、かなりの良著であると言ってよい。
その一方で、一部にこの著者の「独善的」とも言える解釈が混ざっているし、「もう少し深く考えるべきではないか」と思われる点もある。そのため、厳しくみて星を一つマイナスすることにした。
なお、最初に断っておくが、本書評は未完成の段階で公表することとしている。
そのため、随時更新し、過去の記載分に関しても修正を行っていく可能性があることについて、ご了解をいただきたい。
(現在は、第7章までとなっています)
【本書の総合的な評価・特筆すべき点】
本書については、「経済学者ではない人物が書いた経済学の本」ということが、最も特筆すべき点だと考える。
「なぜそれが特筆すべきことなのか」と言えば、「書かれている内容に関して、思想的なバイアスが比較的少ない」あるいは、「イデオロギーの影響をあまり受けていない」ということが言えるからである。
経済学、特にいわゆる「近代経済学」は、数学を盛んに活用することで知られている。そのため、自然科学のように、思想的なバイアスが少ない学問のように見えるかもしれない。
しかし、少し勉強すればわかることだが、経済学は実は思想的なバイアスの非常に大きい学問なのである。
それゆえに、経済学者が書いた経済学書は、何らかのイデオロギーに支配されており、思想的なバイアスを含んでいる可能性がある。
例えば、マルクス経済学はもちろん共産主義あるいは社会主義というイデオロギーの影響を受けていると考えられる。
近代経済学に関しても、最近では主流派経済学と言われる“新古典派経済学”は、アメリカなどでは、保守派のイデオロギーを強く受けている。
その一方で、“ケインズ経済学”は、アメリカではリベラル派の思想的影響を受けていると言ってよい。
それに対して、この本の著者であり長沼伸一郎氏は、物理学者であって経済学者ではない。そのため、上記に書いたようなイデオロギーや思想的なバイアスからは比較的フリーに議論を展開している。その点が特筆すべき要素であると考えている。
【本書評における私のスタンス】
経済学者ではない著者が書いた経済学書ということで、随所に説明の工夫がみられる一方で、逆にわかりにくいところや説明不足があると考えている。
そこで、単なる書評や感想で終わらせずに、私なりに説明の追加をしたり、著者のコメントに対する補足を追加したりして、掘り下げていく努力をしていきたい。
第1章 資本主義はなぜ止まれないのか
1.資本主義の中枢部を解剖する
この章、というかこの小節は、タイトルとしては大きなテーマとなっているが、書かれている内容はシンプルである。
その内容は、本文に太字で書かれている部分に集約されていると言ってよい。
最初は「資本主義の本質」に関するコメントである。
成長を続けなければならないというのは、資本主義というシステムが必然的に持たざるを得ない一つの宿命だからである。
著者は、その理由として「『金利』というものがあるから」と言っている。
これを言い換えて、意図するところを説明すると、次のようになる。
生産されたものが全て消費される、ということが続けば、経済は単純に再生産を繰り返して、成長することはない。
しかし、実際には「貯蓄」、すなわち「生産されたものを全て消費せず、一部を蓄える」という行為が存在している。すると、その分は生産した側に戻ってこないので、そのままではむしろ縮小生産になってしまう。
これに対して、「貯蓄されたものを使わせてもらって、新たな生産を行う」という行為が行われる。これが「設備投資」である。
「貯蓄されたものを使わせてもらう」ので、それを使用させてもらうことに対して「報酬」を支払わねばならない。これが「金利」に相当するものである。
設備投資を行う者は、支払うべき「金利」以上の価値を生み出さないと、金利を支払うことができない。そのため、資本主義は常に拡大に向けて進んでいくことになる。
以上については、第2節でより詳しく説明していく。
この小節では、筆者はさらに以下のように指摘している。
中世の世界においては、人々は金・マネーというものを、一種の核燃料のようなものだと感じていたようである
この点について、筆者は(太字ではないが)以下のように指摘している。
どういうことかと言うと、中世においては、カトリックにせよイスラムにせよ、原則として利息というものを禁止していた。というより、貯蓄という行為そのものをあまり望ましいことだと考えてはいなかったのである。
これは、なかなか面白い指摘だと言えよう。
既述の通り、「貯蓄」というものは、資本主義を停滞させる一方で、それを拡大させるための起爆剤ともなる、という両面を持った存在である。
こうした、いわば「2つの顔」「諸刃の剣」でもある貯蓄に関する中世の考え方に関して、筆者は太字で次のように指摘している。
中世の文明は大変な労力を払って資本主義の成長をむしろ意識的に抑制しており、またその際に用いられた手段は極めて巧妙なものであった。
さて、以上の説明であるが、私自身はこの説明は、基本的な考え方は正しいと言えるが、やや正確性を欠いている、と考えている。
なれはなぜか、ということを説明するために、ご紹介したい話がある。
下記は、『マンキュー入門経済学』から引用して私が作成した図である。下線は私が引いたものである。

原著では「この図は、経済の構造を図式的に表したものである。」とされている。
私は、この図を理解することが、著者の主張を正しく理解することにつながると思うので、本書からはやや脱線することになるが、ご紹介をさせていただきたい。
この図式は、次のような構造を示している。
経済社会における“プレーヤー”を「家計」と「企業」の2つに分けて考える。(つまり、ここでは「政府」を想定していない)
「家計」は「企業」に対して生産要素(土地・資本・労働)を提供し、「企業」は提供された生産要素を使って財やサービスを生産し、「家計」に供給する。
「家計」は「生産要素」を提供して得られた所得を使って、「企業」が生産し、供給した財・サービスを購入する。
ここで重要なことは、以下の点である。
1.「企業」は「家計」から生産要素である土地・資本・労働の提供を受け、それに対して賃貸料(あるいは「土地代」)・金利・賃金を支払う。従って、生産された財やサービスを提供して、それらを上回る利益を獲得しなければ「企業」としての活動が成り立たない。
つまり、「企業」は「金利」だけではなく、賃金・賃貸料等を含めた「生産要素を家計から調達することに伴うコスト」を越えるように経済活動を行わねばならない。
このうち、賃金については経済学のモデルには含まれているが、土地(※)に対する賃借料は含まれていない。つまり、土地はモデルから抜け落ちてしまっている。
この点に関する言及が抜けていることが、「やや正確性を欠いている」とする理由の一つである。
(※)この場合の「土地」とは、土地だけでなく、水・空気・光・熱などの天然資源全般を指すものと考える。
ちなみに、「金利だけではなく、賃金・賃貸料等を含めた“生産要素”を家計から調達することに伴うコスト」は、「資本コスト」に近い概念である。
資本コストとは、「企業が事業を行うために調達した“資本”にかかるコストのこと」だが、ここで言う“資本”には借入金だけではなく、幅広く世間一般から調達したものが含まれる。
2.こうした資金循環のサイクルは、「企業が生産要素を使って“何らかの活動”を行ったことにより、金利・賃金・賃借料等のコストの合計を上回る“価値”が生み出される」というように考えることができる。
これが広い意味での「付加価値」に相当する。(※)
つまり、「企業」は経済社会において、新たな価値を生み出す主体として大変重要な地位を占めているのである。
(※)本来の意味での付加価値は、売上高から原材料(ここでは、「資本」に含まれている)を差し引いたものに近い概念である。つまり、金利や賃借料は本来は付加価値に含まれるものである。
3.筆者は金利の存在の重要性を指摘した。しかしより正確に言えば、企業は資本コストを上回る(付加)価値を創造することが社会的に求められている。資本コストの中で、金利は重要な要素ではあるが、それだけが企業にとってのコストではない。
企業は金利を含めた資本コストを常に上回るように活動することが、社会的に要求されており、資本主義が常に拡大をしなければならなくなる理由の一つでもある、と言うことがより正確な表現であると考えられる。
2.「経済社会の鉄条網」と資本主義の恐ろしく不安定なメカニズム
この小節では、資本主義経済がどのような仕組みで回っているのか、ということについて、筆者独自の図解も用いながら、説明が行われている。
その説明のコアは「貯蓄と投資が均衡する、ということの意味」である。
その意味を、ここで詳細に説明するのは、説明が二重になるのでやめておくが、別の角度から、経済社会に対する経済学の標準的な理解を示しておきたい。
その代わりに、ここでは本書によって説明されていることの理解を助けるため、古典派の考え方による経済社会の理解を簡単に説明したい。
できるだけ言葉で説明するが、一部簡単な数学(関数)を使用することについて、ご了解いただきたい。
最初に、経済学においては、以下の各要素がどのように決まってくるか、ということが重要であり、各派によって理解が分かれている点でもある。
(1) 実質国民所得(≒GDP)
(2) 雇用量
(3)実質賃金
(4) 実質利子率(≒金利)
(5) 物価水準
ここで「実質」とあるのは、物価水準の変化による増加・減少分を調整した後のデータを使用する、という意味であるが、少し煩わしいので以下ではこれを省略して表記することとする。
いずれも、非常に重要な経済指標であり、この5つの要素がどのように決まっていくのか、ということは、いつの時代であっても常に話題になると言ってよいものである。
さて、古典派経済学では、上記の4つの要素を決定するため、経済社会を次の4つの市場に分けて考える
① 生産物市場
② 労働市場
③ 債券市場
④ 金融市場(あるいは貨幣市場)
(1)の国民所得(Y)は、①生産物市場において、雇用量(N)によって決定されると考える。(この点に関する想定は、ケインズ経済学なども同じである)
つまり、国民所得(≒GDP)は雇用量の関数としてあらわすことができる。
Y=f(N)
さっそく数式が出てきてしまって恐縮だが、これは次のように理解していただけるとありがたい。
雇用量(N)が決まると、自動的に国民所得が決まる、という関係になっている。
一方、(2)の(実質)賃金(W)は、②労働市場においてによって、労働需要(Nd)と労働供給(Ns)が一致するように調整されて決定される、と考える。
つまり、Nd=Nsとなる雇用量(N‘)によって、国民所得(Y’)が決まってくる、ということになる。
Nd(W)=Ns(W)→ N‘が決定
① ここからN‘(労働需給が一致する雇用量)が決定する。
② N‘から国民所得の水準Y’が決定される。
ここまでの関係を図示すると以下のようになる。

なお、念のために申し添えれば、労働市場に関する理解については、ケインズ経済学などでは大きく異なる。(ここでは説明は割愛する)
さて、問題は最後に残った貯蓄と投資をめぐる市場である。
この点に関して、古典派経済学がどのように想定しているのか、ということを理解しておくことが、本書の著者の考え方を理解するうえで特に重要となる。
最初に本書にも出てくるが、生産物市場で「企業」によって生産されたもの(=国民所得(Y)に等しい)は、「家計」によって購入されるわけだが、その際に以下のような等式が成り立つと考える。
消費(C)+貯蓄(S)=消費(C)+投資(I)(=国民所得(Y))
ちなみに、左辺が供給側で、右辺が需要側である。
この時に、消費(C)を両辺から差し引くことができるので、
貯蓄(S)=投資(I)
という等式が成り立つ。
本書においては、この等式の考え方について、筆者考案の図を交えながら丁寧な説明がなされている。
古典派経済学では、SとIに関して、利子率(i)による調整が行われ、この2つが均衡する、という想定になっている。
S(i,y)=I(i,y)
なお、(i,y)となっているのは、貯蓄(S)、投資(I)は金利だけではなく、国民所得(Y)の関数でもある、ということを意味している。

さて、長くなってしまったが、ここまでが本小節を理解するための前置きとなる。
資本主義の問題点として、前小節において著者から以下の点が指摘されていた。(一部繰り返しとなるが、再掲する)
「貯蓄」が存在することによって、資本主義では経済が縮小均衡に導かれてしまう可能性がある。
上記に対して、(設備)投資が行われることによって、経済は縮小均衡を免れることができる。
(設備)投資を行う者は、支払うべき「金利」以上の価値を生み出さないと、金利を支払うことができない。そのため資本主義は、常に拡大に向けて進んでいく運命にある。
上記の3つの点を古典派経済学では、「S(i,y)=I(i,y)」という等式を通じて理解している、ということになる。
ここで、「S(i,y)=I(i,y)」という等式から、以下の2つの点が自然に理解できる。
貯蓄(S)と投資(I)とは、金利(i)を通じて均衡するように調整され、経済社会は均衡に導かれる
投資(I)は、貯蓄(S)に対して金利(i)を支払うことでその資金を活用する。つまり、投資を行う者は、支払うべき金利以上の価値を生み出さないと、金利を支払うことができない。
ここで、「2」の点が、著者が直接的に指摘している内容を表している。言い換えると、こうした関係が成り立っていることを理解していないと、著者の主張を理解できない(あるいは、理解できないかもしれない)。
そしてさらに、「1」の点について深く考察することが必要なのである。
つまり、等式が文字通り示している「投資(I)と貯蓄(S)は金利(i)を通じて均衡する」ということに加えて「投資(I)の意味するもの」について、さらに注意が払う必要がある、ということである。
それにしてもあらためて感じるのは、貯蓄という日常的な行為と投資という途方もない行為との感覚的なギャップである。もともと資本主義というものが本質的にカンフル剤の連続的な投与によってのみ維持されるようなとんでもないメカニズムであるということ、そして貯蓄という行為が経済社会に貧血か超高血圧かの二者択一を強いる、これもまたとんでもない代物である
ここで、筆者の言う「カンフル剤の連続的な投与」とは、もちろん「投資」のことである。投資が連続的に投与されることが、なぜ「カンフル剤」なのか。まずはこの点を明確にしておく必要がある。
投資には、ほかの消費(C)、貯蓄(S)と比較して、以下のような特徴がある。
投資(I)は、企業が設備投資を行うイメージであるが、設備投資が行われれば、中長期的に生産能力が向上する。もともと、生産されたものが全て消費(C)されず、その一部が貯蓄(S)されるものを、投資(I)によって“埋める”ことになるのだが、生産能力が向上すれば、生産されたものと消費(I)とのギャップが拡大する可能性がある。
投資(I)は企業によって決定されるものであり、その決定に関して金利(i)が大きく影響するのは事実である。しかし、「企業による(付加)価値創造」の本質を考えれば、金利(i)だけでその水準が決定する、という考え方には無理がある。
著者の言っている「投資とは、カンフル剤のようなもの」というニュアンスは、上記の2つの要素が含まれていると考えられる。
そして、私は特に「2」の重要性について指摘をしておきたい。

この図は、前節で説明した経済社会における資金循環を示した図である。
「企業」は、「家計」から提供された生産要素(土地、資本、労働)を使って財やサービスを生産し、「家計」に供給する、という役割を負っている。
そして、「生産要素を使って“何らかの活動”を行ったことにより、金利・賃金・賃借料等のコストの合計を上回る“価値”が生み出す」ことが企業の役割とされる。
一般的な経済モデルの中では、生産される財・サービスは1つしか想定されていない。そのため、企業が設備投資をしたとしても、同じ財やサービスの生産量が増えるだけのことである。そうであれば、新たな需要を創造し、経済を拡大させる効果は限定的なものにしかならない。
しかし、実際の経済においては、企業は新たな財=新製品や新しいサービスを開発・創造することで、新たな価値を生み出すことが求められている。
そうした新製品や新サービスを生み出し、生産して販売する場合、企業は金利(i)だけをみて意思決定をするわけではないのである。そこには、必ずしも合理的なものだけではない判断や、企業家の「勘」のようなものも働いているのである。
ケインズ経済学の創始者であるケインズは、企業におけるこうした考え方・傾向を「アニマル・スピリット」と呼んだ。ちなみに日本語では「血気」「野心的意欲」「動物的な衝動」などと訳されることがある。
経産省のホームページ(同ホームページでは「アニマルスピリッツ」と呼んでいる)では、以下のように説明されている。
アニマルスピリッツという言葉は、経済学者ケインズが使用した言葉で、一般的には(企業家の)野心的な意欲などと訳されており、不確実な状況下を切り抜ける企業の経済活動の原動力になるものとして注目されています。
つまり、古典派経済学が想定するように、金利(i)によって貯蓄(S)は図にあるような右肩上がりの関数を描くことが想定できるとしても、投資(I)は金利だけできれいな右肩下がりの関数となるとは限らない。つまり、「金利によって貯蓄と投資とが均衡するように調整される」とは限らない、ということになるのである。
これが、経済社会において不均衡が起きる一つの原因であり、「不況」「インフレ」「デフレ」「バブルの発生」といった現象が発生する大きな原因となるものなのである。
重要な補足:貯蓄と貨幣に関する重要な視点
先ほど「古典派経済学が想定するように、金利(i)によって貯蓄(S)は図にあるような右肩上がりの関数を描くことが想定できるとしても」と書いた。

しかし、古典派経済学が想定している上記の点に関しても実は大きな課題が存在している。ここで関係してくるのが、「貨幣」の存在である。
どういうことかというと、貯蓄を貨幣によって保有する、という考え方を是認するかどうか、ということが、一つの重要なポイントとなるからである。
古典派経済学では、貨幣に対して次のような考え方が存在している。
「貨幣は「ベール」または幕のようなものであり、実体経済(つまり、生産、消費、労働供給など)には基本的に影響を及ぼさない」
これは、「貨幣ベール観」とも呼ばれ、現在の主流派経済学である新古典派経済学にも通じる重要な考え方である。
古典派、あるいは新古典派では、貨幣を貨幣のままで保持する、ということは基本的には想定されていない。なぜかと言えば、貨幣を保有していてもそこから何の利益も得られないからである。
同派の経済学者は、貨幣が利用される理由については、基本的に下記のような考え方を持っている。
貨幣は「商品」を購入する際の「支払い手段」として使えるから需要されているのです。支払い手段として使えるということは、支払い手段というサービスを私たちに提供してくれているということです。(以下では支払い手段というサービスを「決済サービス」とよぶことにします)。(中略)
決済サービスに魅力があり、だから私たちは貨幣を需要します。
つまり、貨幣を持つ理由はあくまで「決済サービスの魅力」に基づくものであり、それ自体を保有することには、基本的に何の魅力もない(はずである)ということを主張している。
しかし、現実には貨幣を資産として持つことに対する需要が存在している。
その代表的な考え方の一つが、ケインズ経済学における「流動性選好説」である。
貨幣より高い収益を生む資産の存在にもかかわらず資産としての貨幣に対する需要が存在するという考え方が,貨幣的なもの,すなわち流動性の高いものを選好するという意味で流動性選好と呼ばれる。
ここで「流動性」とは、「他のものとの交換のしやすさ」を意味する。
流動性選好説では、貨幣はその流動性の高さ、つまり「何とでも交換ができる」という性質から、それ自体は何も収益を生まなくても、人々が保有することを欲する、と考える。
この考え方に立つ場合は、金利が高くなってくれば、人々は貨幣を保有するためのコストが高くなるため、貨幣を持つ需要は低下するはずである。
しかし実際には、貨幣は「何とでも交換できる」というその性質から、人々はそれ自体を蓄財の対象として欲するようになる、ということがより重要性を持つようになるのである。
やや余談になるが、私はテレビ東京の『何でも鑑定団』という番組をよく視聴する。
その番組を見ていると、骨とう品等を買い集める人が多く出てくるので、いつも感心してしまう。そして特に驚きを持って見ているのは、それらの人々の多くが、「骨とう品を買い集めるということ」自体に執着、あるいは満足しているように見えることである。
つまり、購入した骨とう品を鑑賞して楽しむ、という行為をせず、部屋の隅や倉庫などに購入したままの形でしまいこんでいる、という人が多く見受けられるのである。
それらの人々は、それらの骨とう品等の価値が値上がりすることを期待して持っている、というよりも、「骨とう品を持っている」ということ自体に価値を見出しているように、私には見える。
言い換えれば、ただ単に所有欲を満たすために、骨とう品等を買う人がかなりの数存在しているのである。
貨幣を保有することの価値は、もしかするとこのような「骨とう品を持ちたい」という欲望に似ているように見える。
つまり、「貨幣の『何にでも変えられる』という性質」に魅せられて、それ自体を保有することに魅力を感じる人が、少なからずというよりも、非常に多く存在する。それが貨幣に対する需要の、かなりの部分を占めている可能性があるのである。
この話をすると、知識のある方は「流動性の罠(わな)」の話をしているのだな、と思われるであろう。
流動性の罠とは、次のように説明されている。
金融緩和で金利が一定の水準よりも低下し、伝統的な金融政策の効果が失われること。通常、金融緩和による金利低下は消費や設備投資を促進させます。しかし、利子率がゼロ%近くまで低下すると、消費や投資よりも貨幣保有が選好されるようになるため、利下げによる景気刺激策は無効になるとされています。
上記の引用にもあるように、「流動性の罠」とは、金利(i)が低下したために、投資などにお金を回すことをやめて、貨幣を保有する傾向が生まれることを意味している。
しかし、私がここで強調したいのは、金利水準の高さの如何に拘わらず、人には貨幣を保有するという高い意欲が存在している、という点である。
重要なメッセージ:投資と貯蓄は“事前的”には均衡しない
さて、説明が長くなったが、「貨幣自体を保有したいという(強い)需要」を認めると、投資(I)に関してだけでなく、貯蓄(S)に関しても問題が起きてくる。

すでに説明した通り、企業による設備投資に関しては、“アニマル・スピリット”などの不確実性をもたらすような要素が存在しており、必ずしも金利(i)だけを見て合理的な意思決定がなされるわけではない。
それに加えて、貯蓄に関して人々が「金利(i)の水準に拘わらず、貨幣を保有したいとする強い動機」の存在を認めるとすれば、金利(i)が貯蓄(S)と投資(I)を均衡するように調整する、という古典派経済学の想定は成り立つことが難しい、ということになる。
ちなみに、本書の中で「投資と貯蓄が一致する」と言う話が出てくる。
これは、「貯蓄と投資は事後的には一致する」ということで理解されており、「事前的」には上記のような理由で「一致する」、あるいは「均衡する」とは限らない。いや、むしろ一致あるいは均衡しない、と想定する方が普通である。
この点に関して誤解が無いようにすることが重要である。
なお、「事前的に」「事後的に」という言葉は、なかなか分かりにくい概念であって、経済学を学ぶ者にとっては、頭を悩まされる問題である。
ここで、「事前的に」という言葉を理解するためには、「事後的に」という言葉を先に理解する方が望ましい。
「貯蓄(S)と投資(I)とが事後的に一致する」(※)というのは、国民所得(Y)の計算上(あるいは「分類上」)そのように処理される、ということである。言い換えると、「貯蓄(S)と投資(I)とは、それが一致するように国民所得(Y)の計算上処理される」ということなのである。
(※)貯蓄(S)と投資(I)が事後的にでも一致するのは、輸出入が無い場合においてである。輸出入がある場合には、貯蓄と投資の差額は経常収支の黒字または赤字によって補填される形になっている。
3.文明社会はいかにしてそれを選択してきたのか
【金利が容認されるに至った文化的背景】
この小節では「金利」に関する歴史的な経緯が語られている。
前の小節において、「金利」の重要性について説明があった(その点に関する私なりのコメントも付けさせていただいた)ので、この小節があると言ってよい。
それ以上のコメントは省略する。
【資本主義の必要性の「3要素」】
この段落での筆者の指摘に関しては、比較的重要性が低いと考えているので、コメントは省略する。
ただし、日本の資本主義を駆動する精神とは「心配」である、という著者の指摘は、非常に鋭いものがあり、傾聴に値すると考えている。
【資本主義は最終的な勝者か】
この段落に関しては、本書の中で太字になっている以下の2つのコメントにやはり注目をしたい。
資本主義とは、その外見とは裏腹に、実は最も原始的な社会経済システムなのであり、それ以上壊れようがないからこそ生き残ってきたのではないだろうか
資本主義は際限なく拡大を続けて死ぬまで走り続けなければならないという、異常な性質を根本に抱えたシステムであることに変わりはない
冒頭の【本書の総合的な評価・特筆すべき点】に記載した通り、本書は「経済学者ではない人物が書いた経済学の本」という点が最も特筆すべき点の一つであると、私は考えている。
その理由については、やはり既述の通りであるが、「『書かれている内容に関して、思想的なバイアスが比較的少ない』あるいは、『イデオロギーの影響をあまり受けていない』ということが言えるから」である。
現在、経済学の“主流派”と言われている新古典派経済学は、基本的に資本主義を支える市場経済システムの安定性を重視している。
それに対して、ケインズ経済学を支持する経済学者は、資本主義とそれを支える市場経済の不安定性や不均衡の発生を強く意識していると言ってよい。
そのため、経済学者が経済学の書物を書く場合は、上記のいずれの立場に立つかによって、その思想的背景、あるいはイデオロギーにどうしても支配されざるを得なくなる、という問題点が見え隠れする。
それに対して、本書の著者が、そうした思想的バイアスや、イデオロギーなどから離れた立場から、資本主義の性質をどう見たのか、ということは、より客観的な立場からの指摘として、とても大事であると、私は考えている。
特に、「資本主義とは際限なく拡大を続けて…」という指摘については、今までいずれの学派からもあまり聞こえてこなかった主張では無いか、という印象を私は受けており(もちろん、私の不勉強も十分にあり得ます)、やはりとても傾聴に値するものだと考えている。
第2章 農業経済はなぜ敗退するのか
ペティ・クラークの法則
この章では、農業の抱えている根本的な課題について考えている。
最初に話題になっているのは、「ペティ・クラークの法則」である。
ペティ・クラークの法則
C.G.クラークは,産業を三つの種類に区別して,それぞれ第1次,第2次,第3次産業と名づけた。第1次産業は農業,林業,水産業などから成り,経済発展に伴いその比率は低下し,製造工業を中心とする第2次産業の比率が高まるという現象がみられる。さらに主として商業,サービス業から構成される第3次産業の比率の上昇もみられる。このような傾向をふつう〈ペティの法則〉と呼ぶ。もともとはW.ペティが《政治算術》の中で主張したことであって,〈農業よりも工業のほうが利益が大きく,さらに進んで商業のほうが利益が大きい〉という文章に基づいてクラークが名づけたものである。そのため,ときとしては〈クラークの法則〉〈ペティ=クラークの法則〉と呼ばれることもある。
農業製品あるいは農産物製品について、考えておくべきは次の2点である
1.農業製品の需要に関する“価格弾力性”の小ささ(※)
2.農業製品の供給に関する特性
(※)価格弾力性については、「大きい・小さい」とする場合と、「高い・低い」とする場合が存在しているが、ここでは「大きい・小さい」を使用することとした。
第一に、「農業製品の需要に関する“価格弾力性”の小ささ」という点について考えてみる。
価格弾力性とは、「価格の変化(=価格の上下)によって、ある製品の需要や供給が変化する度合いを示す」ものである。
「価格弾力性が大きい」場合には、価格が上下すると、それに伴って需要や供給が大きく変化する。
それに対して、「価格弾力性が小さい」場合には、価格が上下しても、需要や供給はあまり変化しない。

「需要の価格弾力性が小さい」と需要曲線は垂直に近くなる
農産物の場合は、次の理由によって、「需要の価格弾力性が小さい」ことが知られている。その理由は以下の2点による。
もともと比較的価格が安い製品が多いうえに、製品の価格の変動が大きい。製品によっては簡単に2倍・3倍に価格が跳ね上がるものも存在する。(逆もある)
農産物は価格の高い・低いに拘わらず、需要は常に一定程度存在している。(例を挙げれば、「鍋物には白菜」「とんかつの付け合わせにはキャベツの千切り」など、必須の取り合わせがあるなど)
農産物は生鮮品なので、「安い時に購入しておいて、高くなったら在庫を使う」といった工夫をすることが難しい
さらに、農産物の「供給面」に関しては、以下のような特徴が存在している。
農産物は季節性が高いものが多く、供給者も「小口分散」しているケースが多い。
各生産者が、製品を市場に供給する時期はあらかじめ決まっている場合が多く、市況に応じて生産調整をすることが難しい。
このため、供給曲線は、「製品の価格によらず、時期に応じて一定」となることが多いのである。
以上のことを図示すると、次のようになる。

そのため、農産物は豊作の年には価格が大きく下落し、場合によっては「作ったものをそのまま廃棄する」ということが起きる一方で、不作の年には価格が大きく上昇し、一部の農家に大きな恩恵をもたらすこともあるのである。
(かつて、「白菜御殿」と呼ばれたくらい、白菜農家が大儲けをしたこともあった)

本書においては、農業と工業の対立に関して、以下のような太字のコメントがなされているが、その背景には上記のような事情があることを理解しておくことがよいと思われる。
農業と商工業の対決においては、農業の側がほとんど伸びない需要と中途半端な速度で伸ばせる供給という、最悪のコンビネーションから成り立っているのに対し、商工業の側は、供給の伸びの速度が速すぎるという不利を抱えながらも、ゴムのように伸縮自在な需要がその不利をカバーしている。
徳川政権のジレンマ
この章では、徳川政権に関する指摘が個人的には大変興味深かった。
次のような視点は、私には無かったからである。
農業文明が商業文明の上に体ごと覆いかぶさってねじ伏せようとしたという、世界史の中でもちょっと稀な実例ではなかったかと思われるからである。
徳川政権は文明全体をそれとは逆の、機動性が発揮されにくい状況に閉じ込めることを考えた。
江戸時代は本書でも指摘している通り、「米穀経済」であった。
では、経済面で見た時、徳川体制の最大の特徴が何だったかというと、それはこの体制が米穀経済、すなわち米というものを建前上、主力貨幣として扱い、金銀を代用貨幣の地位に置いていたという点にある。
上記の視点に立って徳川体制を見る時、私が注目したのは、八代将軍徳川吉宗が行った「享保の改革」である。言うまでもなく、徳川時代の三大改革(享保、寛政、天保の各改革)の中で最初に行われたものである。
享保の改革で行われた施策のうち、注目すべきは以下の3つ制度である。
1.質素倹約
2.新田開発:米の生産量の増強
3.上げ米の制度:大名が参勤交代で江戸にいる期間を1年から半年に短縮するかわりに、1万石につき100石の米を幕府におさめることを義務づけた。
「1.質素倹約」については、商業経済をできるだけ押さえつけることで、米価を維持しようとするという考え方である。
農産物である米の需要が大きく伸びることは無いため、商業経済が活性化すると、米の価格が相対的に低下する、ということを理解したうえでの施策であると考えられる。
それに対して「2.新田開発」と「3.上げ米の制度」は、「米の生産量を増やして、最終的には幕府の財政を改革しよう」という考え方である。
しかし、すでに述べたように、農産物である米には「需要の価格弾力性が小さい」などの“宿命”が存在している。
そのため、もしも幕府の収入を増やしたいのであれば、むしろ米の生産量を減らした方がよかったかもしれない、ということになると考えられる。
新田開発を行い、幕府に対する米の提供を増やせば、一時的には幕府の財政状況は改善するかもしれないが、長期的にはむしろ米価の低下要因になった可能性がある。
享保の改革は、一時的には成功したと言われるが、その後の寛政・天保の改革については、あまり成果が出なかったと言われている。
その理由について、本書の指摘によって、ようやく理解できるようになった、という気がしている。
それにしても、「なぜ質素倹約を国民に強いることが改革になるのか」という点について、私自身はよく理解ができていなかった。表面的な理解というのは、恐ろしいものである。
第3章 インフレとデフレのメカニズム
貨幣の中立性
本書が書かれた時代は、2018年~2020年頃ではないかと推察されるが、その時期はコロナ禍の前ではあったが、まだまだデフレが深刻な時代であった。
それに対してこの「書評・感想」を書いているのは2024年の初頭であって、日本経済におけるインフレ基調が本格化している真っただ中にいる。
そうした時代の比較も背景として、本書の指摘を読むことは、いろいろと意義深いものを感じる。
本章に関連する議論の一部を、すでに前章までに論じているので、重複は避けたい。
今まで、古典派経済学のモデルにおいては、経済社会を次の4つの市場に分けて考える、という説明をしてきた。
1.生産物市場
2.労働市場
3.債券市場
4.金融市場(あるいは貨幣市場)
この中で、「1.生産物市場」「2.労働市場」「3.債券市場」については、図解も含めて説明をしてきたので、説明は割愛する。
しかしながら、「4.金融市場」の説明が行われていない。
古典派経済学の貨幣に対する考え方は、本書にもあるように「貨幣の中立性」、あるいは「貨幣ベール観」という言葉で説明される。
私も第1章の書評・感想において、以下のように説明した。
古典派経済学では、貨幣に対して次のような考え方が存在している。
「貨幣は「ベール」または幕のようなものであり、実体経済(つまり、生産、消費、労働供給など)には基本的に影響を及ぼさない」
これは、「貨幣ベール観」とも呼ばれ、現在の主流派経済学である新古典派経済学にも通じる重要な考え方である。
ここで、貨幣市場における国民所得(Y)と物価水準(P)との関係をグラフの形で示すと、下図のようになる。

せっかくグラフまで作成して説明したが、ここで重要なのはグラフよりも次の式である。
P=M/kY
この式は、(名目)貨幣供給量(M)を2倍にすれば、物価水準Pが2倍に、同じく1/2にすれば、物価水準も1/2という関係になっていることである。
さらに言えば、分母の国民所得(Y)は毎年一定程度成長により数値が大きくなっていくので、分子である(名目)貨幣供給量についても、経済成長に合わせて一定程度増加させていく方が望ましい、ということになる。これが本書にも説明されている「フリードマンのk%ルール」に相当するものである。
さらにこれも、すでに取り上げたことであるが、古典派、あるいは新古典派では「貨幣の魅力は決済サービスにある」と考える。
下記は、一部はすでに紹介したものだが、新しい引用部分と合わせて再掲する。太字が新しい引用部分である。
決済サービスに魅力があり、だから私たちは貨幣を需要します。
この考え方に立つと、例えば貨幣の供給量を2倍にすると、決裁サービスの供給もそれに比例して2倍になります。供給が2倍なので、決裁サービスの魅力はその分、低下します。これは、貨幣の魅力の低下に他ならないので、物価は上昇します。
この決済サービスという考え方は、本書で言うところの「貨幣のラベル」と同じことを意味している。
つまり貨幣というものは、単に現実の経済社会で取り引きされる様々な物に貼り付けられた、一種のラベルのようなものに過ぎないのではないかということである。
つまり、「貨幣は商品にラベルを付けて、取引をしやすくするだけのもの」という考え方、ということである。
これに対して、ケインズ派では、既に紹介したように、貨幣の需要は決済サービスだけではなく、貨幣の流動性=「他のものとの交換のしやすさ」にもあると考える。これが「流動性選好」である。
この2つの考え方の違いは、2020年頃まで日本の悩ませてきた「デフレ」と、それに対する対策として行われてきた金融緩和政策・アベノミクスの関係を見るとき、なかなかアベノミクスが成功しなかった原因を考えるうえで、好対照の考え方を取ることになる。

2024年にこのブログを書いている段階で言えば、この「対立している」2つの考え方には、それぞれ合致する点があると言える。
「価格を引き上げることができない」という企業が減り、各企業が価格を引き上げるようになった。
その一方で、金融緩和をずっと続けているにもかかわらず、物価は大きくは上がっていない。
インフレで誰が得をするか
この章の問題点の一つは、この小節での説明にある。
この小節では、著者は以下のように説明している。
インフレ環境のもとでは一般的に、
・資産家階層(最も金持ち・その資産で生活=機動性鈍い)は損をする
・企業家階層(2番目に金持ち・借金多し=機動性高い)は得をする
・労働者階層(最も貧乏=機動性鈍い)は損をする
筆者がこの小節で言いたいことのコアは、次の内容である。
すなわちインフレのもとでは「機動性の高い人々」が得をして「動きの鈍い人々」が損をするということである。
この表現が実に巧みなので、思わず引き込まれてしまう。
しかし、著者が書いていることを良く読んでみると、もしかすると少なからず誤解をしている可能性があることに気が付く。
どういうことかと言うと、資産家がなぜインフレで損をするのか、ということについて、著者は以下のように書いている。
一方これとはちょうど逆に、金を貸す側の資産家(あるいは投資家)たちの立場からすると、これ(筆者注:インフレが起きること)は自分たちの財産がまるで空気中に蒸発していくようなもので、インフレは彼らにとって刑罰に等しい。
この引用を読む限り、著者は「インフレが起きると資産家は損をする」と単純にというか、素朴に考えているようである。しかし、以下の理由により、それは正確な表現ではない。
インフレによって債権者が損をして、債務者が得をする、と一般に言われているのは、インフレが起きると債権の価値が目減りするため、債権者が損をすると考えているからである。
金利とインフレには、一般に以下の関係が成り立っていると言われている。
実質金利(r)=名目金利(i)-期待インフレ率(π)
つまり、名目金利(i)から、期待インフレ率(π)、すなわち人々のインフレ予想を差し引いたものが、実質金利(r)となる。
このため、名目金利がもしも一定であれば、インフレによって期待インフレ率が増大するので、実質金利が低下し、債権者は損をすることになる。
しかし、実際にはインフレが起きると程なくして名目金利(i)が上昇し、実質金利(r)の水準も上昇するのが一般的である。そのため、一時的には金利低下によって損をすることがあっても、新しい融資を行う際には引き上げられた金利によって対応することができるので、損失は生じない。
つまり、固定金利で長期間の融資をしていたりしない限り、債権者に大きな損失は生じないのである。
従って、著者が言うように「インフレによって資産家階層が損をする」ということは、短期的あるいは一時的には言えることであっても、長期的には当てはまらない。
確かに、インフレが起きてから金利が上昇するまで時間が掛かったり、政府が意図的に金利を低めに誘導し、実質金利が低く抑えられたりすることはあり得ることである。その場合には、債権者が不利になり、債務者に有利となる。
しかし、総合的に見れば、誤解を生みかねない表現であることは間違いないだろう。
第4条 貿易はなぜ拡大するのか
1.貿易のメカニズム
この章では、貿易そのものの意義が論じられている。その問題について述べる前に、「国際収支」という観点から、貿易の意義について論じておきたいと考える。
[国際資金循環という観点で見た貿易の意義]

ただし、貿易の存在は想定していない
まず、「政府と貿易の存在が無い場合」で考える。
この場合は、すでに説明したように、需要側は消費(C)と投資(I)に、供給側は消費(C)と貯蓄(S)に分類される。
次に、「貿易が無い場合」で考える。この場合は「政府」が表に出てくる。
{政府支出(G)-税収(T)}は国の財政収支となる。
政府は、国民や企業から税金を徴収し、税収(T)を得る。政府支出(G)は「需要」として計上されるが、家計と企業からは税金が徴収されているので、その分は需要側から差し引く必要がある。
そのため、左辺、すなわち需要側に政府支出(G)-税収(T)が加えられる。

最後に、貿易も加えてみると、上図のようになる。輸出(E)が需要側に、輸入(M)が供給側に加わることになる。
輸出は海外からの自国製品に対する需要であり、輸入は海外からの製品の供給にあたるものとなる。
ここで、両辺を整理したのが、下記の式となる
貯蓄(S)-投資(I)= {政府支出(G)-税収(T)}+{輸出(E)-輸入(M)}
政府支出が税収を上回る場合には、財政赤字が、その逆では財政黒字が生じる。
{輸出(E)-輸入(M)}は経常収支に該当する。輸出が輸入を下回れば経常赤字となり、その逆では経常黒字となる。
ちなみにインバウンド消費などは、輸出に該当する。海外の人々の日本の製品やサービスに対する需要に該当するからである。
本ブログを書いている2024年の初頭では、日本の場合、財政収支は赤字となっており、経常収支は黒字である。(ちなみに、貿易収支は赤字となっているが、インバウンド消費などで埋め合わされ、経常収支としては黒字になっている)
これはつまり、国内の貯蓄超過、すなわち投資が貯蓄に及ばない状況にあるものを、政府の財政赤字と経常収支の黒字で補っている、という構造を示しているのである。
このように、貿易を「国際収支」という観点から見た場合には、国内における需要と供給のアンバランスを、政府の財政支出と合わせて調整しているとする観点が非常に重要となっている。
[貿易の意義]
この章で特に重要な著者のメッセージは、第1小節の最後の方に記載されている、以下の太字を含む著者の言葉であると言ってよい。
自由貿易とは要するに「一番最初に二階に上がった者がはしごを引き上げてしまう制度である。
どういう意味かと言うと、それは産業競争力においてトップにある国が、後続の国々の追いつく望みを失わせるための仕掛けに他ならないというのである。
この議論を考える際に、留意しておくべき経済理論が一つある。それは、「比較優位理論」と呼ばれる理論である
自由貿易において各経済主体が(複数あり得る自身の優位分野の中から)自身の最も優位な分野(より機会費用の少ない、自身の利益・収益性を最大化できる財の生産)に特化・集中することで、それぞれの労働生産性が増大され、互いにより高品質の財やサービスと高い利益・収益を享受・獲得できるようになることを説明する概念である。
一読をすると、「なるほど」と思われるかもしれないが、この話は実は先ほどの著者のメッセージと大きく関連しているのである。比較優位理論に従うと、次のような結論が導かれる。
この理論に従うと、現在工業化が進み、工業技術に関して先行している国は、工業製品に特化・集中する一方、農業生産が多い国は農産品に特化し・集中した方がよい、という結論が得られる。
工業国は工業に注力し、農業国は農業生産に特化・集中することで、全世界的に労働生産性が向上し、全世界が利益を得られる、という「国際的な分業体制」の妥当性を、この理論が支持する。
しかし、それは同時に、著者が主張するように、最初に工業化を進めた国が、工業製品に関して優位になり、輸出ができるようになる一方で、工業化に遅れた国は農業生産物の輸出を続けるしかない、という帰結がもたらされる。
農業生産物には、第2章で著者が指摘したような課題が存在しており、農産物の輸出だけで国を豊かにすることは容易ではない。
こうしたことが、自由貿易というものについて、「一番最初に二階に上がった者がはしごを引き上げてしまう制度」と言っているのだと考えられる。
2.貿易の歴史
自由貿易に関しては、基本的には工業化されたいわゆる「先進国」が利益を受ける可能性が高い、ということについては、今まで説明してきた通りである。
しかし、著者も本書で言っている通り、そうした流れに逆行するような動きが全世界で起きつつある。
考えてみれば、自由貿易を推進することで、最も大きなメリットを受ける国は、やはりアメリカであろう。そのアメリカがTPPからの脱退など、自由貿易から脱退するなど、自由貿易の推進から撤退する動きを強めているのは、非常に不可解でもある。
これについて、本書で著者は次のように言っている。
確かにいままではそうしたグローバル化が進行して、一時は一つの極に達していたが、今後それは揺り戻しの時期を迎えることになるかもしれない。現在すでにそのような傾向があちこちで見られており、トランプ政権の登場などはさしずめその代表である。
さらに、比較優位理論によれば、自分たちに比較優位がない製品、日本で言えば各種の農産品などは自分たちで生産するよりも、輸入したほうがよい、ということになるが、「経済安全保障」の観点から、そういった視点も見直しを必要とされている。
貿易は、国際的な資金循環という観点から見れば、国内における需給ギャップを調整する役割も有しており、たいへん価値が高いものであることは間違いない。それにも拘わらず、著者の言う通り、いろいろな意味で見直しが必要な状況にあると言えるのだろう。
第5章 ケインズ経済学とは何だったのか
最初に記載した通り、私がこの本を評価していることの一つは、「経済学者ではない人物が書いた経済学の本」ということにある。
私自身も経済学者ではないが、経済学についてはケインズ派の立場に強いシンパシーを持っている。この章のタイトルはケインズ経済学とは「何だった」のかであるが、「何だった」と“過去形”になっていることにも、実は違和感がある。ケインズ経済学は、現在も有効な学問だと思っているからだ。
しかし、ここでは本書の内容を尊重して、意見を述べていきたい。
最初に、著者が本書で図を使って説明しているものについて、古典派のフレームワークを使って別の角度から説明してみる。

上図で、企業による労働需要(Ndf)と家計からの労働供給(NS)が、Wfで均衡しており、その時には国民所得(Y)はYfとなって、完全雇用の雇用量Nfが実現している、とする。
ところが、何らかの理由によって企業による労働需要が(Ndf)からNd‘に低下したとする。
ここで、何らかの理由とは、企業が生産に対して悲観的になるような理由、例えば、典型的には「パンデミックの発生」などが考えられる。
これが、本書で言うところの「動いている途中に何らかの理由でポリタンクから燃料がこぼれて一時的にタンクが空になってしまった」というような状況に該当する。
この時には、労働供給曲線がシフト(この図では下方にシフト)するので、(実質)賃金が低下(Wf→W‘)し、雇用量も低下する(Nf→N’)ことになる。
すると、雇用量が減少するために、国民所得も減少(Yf→Y‘)してしまう。
雇用量が減少して、国民所得も減少する、というのはGDPがマイナス成長となり、失業が発生することを意味する。失業が発生するのは、雇用量N‘が、完全雇用量であるNfを下回るからである。
GDPが減少して、失業が発生するというのは、まさしく経済が不況に陥っていることを意味する。
しかし、古典派が想定している上図の状況は、労働市場においても需給が一致しており、不均衡は生じないことになっている。つまり、不均衡はどこにも生じていないことになっているのだ。そのため、この状況は不況で失業が生じている状況であっても、その状態で「低位安定」してしまっているのだ。
この状態が筆者の言う「消費と企業活動の水準が非常に低い状態に設定されてしまえば、恒久的にその水準に留まり続けるという現象が生じるのである」ということに該当していると想定される。

上図は、既存の図とはX軸とY軸が逆になっているのでご注意いただきたい。
繰り返しになるが、もう一度改めて説明すると、労働供給がNdf→Nd‘となったことで、(実質)賃金が低下(Wf→W’)し、労働供給も減少して、その結果雇用量が減少(Nf→N‘)し、完全雇用需要量を下回った。
この時、ケインズ経済学では、「非自発的な失業が生じている」と考える。
それに対して、(新)古典派では、次のように考えるのだ。
「賃金が低下したので、労働供給量を減らした。」
つまり、労働者は賃金水準に応じて主体的に労働供給量を増減させているのであり、それによって失業が生じたとしても、それは労働者側の主体的な選択の結果だ、と考えるのである。
つまり、ケインズ派が考えるような「非自発的な失業」というものは存在せず、「自発的な失業」の一種であると考えるのである。
そのため、政府などが介入して調整などを行う必要はなく、「神の手」による調整結果に任せればよい、という考え方に立つのである。
実際には、経済社会が不況になり、失業が発生すれば、それは大きな社会問題となる。
ケインズ派はそうした社会問題を解決するために、公共事業などの政府支出を積極的に行って、失業対策をすべきであると主張する。
しかし、古典派、あるいはそれが“進歩”した形である「新古典派」の経済学では、政府支出を増やして、一時的には経済を動かすことができても、それは結局長続きしない、と考える。あくまで、経済社会は「神の手」に委ねるべきである、というのが新古典派の主張なのである。
乗数効果のメカニズム
ここでは、ケインズ理論に関して有名な「乗数理論」について、著者独特の方法で説明を行っている。
政府の支出を増やすことで、需要をその分増やすことができる。そうすると、その分家計は所得を増やすことができるので、その一部を家計はまた消費に回すから、さらにその分消費が増える、それはさらに・・・
というのが、乗数理論の基本的なロジックとなる。
つまり、政府が1単位の資金を経済社会に投入することで、その何倍もの経済効果をもたらす(本書の例では、10倍となっている)というのである。
この乗数理論について、著者は次のように“太字”で言っている。
ケインズ経済学を理解する重要な柱であり、これがケインズ学派によってはじめて理論的に明らかにされた時には、当時の多くの経済学者に大きな衝撃を与えた。
この理論に従って、ケインズ経済学では、「穴を掘ってただ埋める、というような“無意味な”事業に対してであっても、政府支出をすることで経済効果がある」と言われてきた。
乗数理論は、一回聞くと「なるほどそうか」と思う一方で、「そんなに都合の良いというか、魔法のようなことが本当にできるのか?」という印象を持つ方も多いだろう。
実際問題として、この理論にはケインズ派の経済学者からも批判が出ている。ここで詳述することは避けるが、その批判によれば、やはり「穴を掘ってただ埋める」というような無意味な事業の場合には、その効果が何倍にもなる、ということは無いと考えられる。
ケインズ経済学の泣き所
ケインズ経済学について、本書で著者は次のように“太字”で言っている。
「財政赤字という毒は一時的に良薬となる」という認識を受け入れるか否かが、ケインズ経済学そのものを受け入れるか否かの分岐点となったと言える。
この点について、間違いとは言えないが、正確な評価ではない、というのが私の主張である。
私の意見としては、ケインズ派としては、財政赤字の問題は手段であって目的ではない、というのがその主張の根幹だ、ということである。
その意味では、この言葉よりも著者の別の太字の言葉を重視するべきだと考える。
貯蓄行為そのものがまるで豊かな社会の成人病か何かのように有効需要の足を引っ張っていることになり、それゆえ豊かになった社会はこの貯蓄という贅肉を何とか燃焼させねばならない宿命を負うことになるわけである。
今まで説明をしてきたように、資本主義、特に市場経済に基づく資本主義においては、需給の不均衡が恒常的に発生することが避けられない、ということがケインズ派の主張のコアだと私は考える。その原因となるのが、著者の指摘するように「貯蓄行為」なのである。
第6章 貨幣はなぜ増殖するのか
この章で注目したいのは、「貨幣の類型」に対する筆者の考え方と、そこから導かれる「貨幣の磁化」と「信用創造」についてである。
「貨幣の類型」→「貨幣の磁化」→「信用創造」・・・貨幣の増殖
ということになる。
この中でまず注意すべき点は、「貨幣の類型」に対する筆者の考え方は、経済学において語られる『貨幣論』とは、かなり趣を異にしている、ということである。
以下、最初に「貨幣の類型」について、経済学における貨幣論との関係も含めて、レビューをしていきたい。
増殖してきた貨幣
まず、筆者は貨幣が増殖した理由として、以下のように指摘している。
貨幣の「自己増殖」という観点から見てみると、やはり貴金属から紙切れに変化した時が、最も大きな質的変化であった。金や銀というものは、単に見た目の美しさや鉱物的特性ゆえに貨幣としての資格を得たわけではない。むしろその本質は、希少性が十分に保証されていて人間が勝手に増やせないことにあり、それこそが貴金属が貨幣たり得た理由である。
実は、かつて貴金属が貨幣として使用された、ということについて、次のような指摘がある。
古今東西、多くの人は、金銀がおカネとして使われるのは、それが多くの人が欲しがる貴重なモノ、多くの人が手に入れたがる価値の高い商品だからと説明してきました。この説明は「貨幣商品説」とか、「貨幣物品説」とか呼ばれます。
実は、この貨幣商品説とは、いままで説明してきた古典派の「貨幣ベール観」のベースとなる考え方なのである。貨幣ベール観とは、「貨幣は「ベール」または幕のようなものであり、実体経済(つまり、生産、消費、労働供給など)には基本的に影響を及ぼさない」とする貨幣に対する考え方である。
この貨幣商品説について、ご紹介した岩井克人教授は次のように述べている。
かつては、貨幣商品説は多くの経済学者に信じられてきました。だが、これはまったくの間違い。トンデモ説です。もちろん、今では、頑迷固陋な保守主義者やマルクス経済学者以外には、支持する人はいません。
貨幣商品説を否定する“代表的なもの”が、紙幣である。紙幣は単なる紙に過ぎないのだから、貨幣商品説は成り立たない。
本書では、そうした議論には踏み込まず、貨幣商品説の原型ともいえる話から、いきなり紙幣に話が飛ぶ。
そこで出てくるのが、「イングランドの紙幣とモンゴルの紙幣」の話である。
イングランドの紙幣とモンゴルの紙幣
この2つの紙幣について、著者が指摘している点をまとめると、次のようになる。
1.イングランド型紙幣
金細工師たちが発行していた預かり証書が銀行券代わりに流通していた。
それに対して、国王がイングランド銀行の母体に対して銀行券の発行を認めて、やがて一本化されていく、という過程を経て成立した。
つまり、民間で大量に発生していたものを国家が整理統合したのにすぎない。
2.モンゴル型紙幣
フビライが導入して誕生したもの。
イングランド型と違って、元帝国の治安が最も安定していた時期に、その整備された行政機構の力によって、国家の意思として上から流通させていった。
紙幣の導入に当たって、元帝国の政府当局は、一応は銀の裏付けを保証することでその流通を図ってはいたが、それは十分なものではではなかった。むしろ貨幣に本当に意味で価値を付与していたのは、フビライの軍隊の存在であった。
元帝国が消滅するや否や、その紙幣はただの紙切れとなり、次の明朝では消滅して次代に後継者を生み出すことなく、紙幣そのものがしばらく歴史から姿を消してしまった。
つまり、著者によれば、「イングランド型紙幣」はもともと国家が上からの命令で流通させたものではなく、民間で流通していた通貨を国家が統合して成立したものであり、それに対して「モンゴル型紙幣」は上からの力で紙幣が流通することになったもの、ということになる。
ちなみに、筆者は「フビライの軍隊の存在が貨幣に価値を付与した」と言っているが、この点に関しては、私は極めて疑わしいと思っている。
軍隊が軍票のような形で資金を民間から調達するケースはあるが、その軍票が貨幣として流通するかどうかは、軍隊の力だけで決まるものではないからだ。
紙幣の信用の源泉に関する筆者の説は、貨幣論の立場からすると、かなり疑わしいと考えられるが、ここではこれ以上踏み込むことはしない。
さて、ここで注目したいのが、第二の貨幣に関する説である「貨幣法制説」である。
おカネがおカネとして価値を持つことの理由を、モノとしての価値ではなく、国家の権力や大様の権威や共同体の取り決めなどに見出そうとしたのが、「貨幣法制説」あるいは「貨幣法定説」です。国家や王様や長老が法律や命令や口伝えで貨幣として使えと定めたから、おカネはおカネとして流通するという説です。今日では、貨幣商品説に代わって、この貨幣法制説が経済学者の間での通説になっています。
つまり、モンゴル型貨幣は、元帝国が命令して流通させた貨幣なので、「貨幣法制説」が見事に当てはまるように見える。
しかし、貨幣法制説については、岩井克人氏が以下のように痛切に批判をしている。
しかしながら、いくら通説であろうとも、『貨幣論』から見れば、貨幣法制説も正しくありません。
岩井氏は、オーストリアのマリア・テレジア銀貨が国境を越えてヨーロッパ全土で流通し、さらにはエチオピアでも使用されていたことを紹介し、貨幣法制説が間違いであると主張している。
さらに、本書で書かれたイギリス型紙幣の例でも、最終的にはイングランド銀行が母体となって発行されることになるが、それまでの間は国家や法律などとは関係なく紙幣は流通していたのである。これはまさしく、貨幣法制説を否定するものに見える。
本書では、貨幣の本質に迫る、ということよりも貨幣が増殖する過程に重点が置かれている。
著者は「貨幣を磁化する」という言葉で表現している。
磁化される貨幣
「貨幣が磁化される」ということについて、著者は以下のように説明をしている。
貨幣が価値を帯びる過程というものは、磁石がそばにある鉄を磁化させてしまう現象にやや似たところがある。単なる紙切れでも、それが常に金の地金の隣に置かれて、それとの交換を約束されていると、時が経つうちにちょうど鉄片が磁化されるように、それ自体が価値を帯び始めてしまうのである。
これが、イングランド型紙幣が誕生していく過程で生じたことである、というのが筆者の見立てである。
では、モンゴル型ではどうだったかと言うと、すでに説明したように「フビライの軍隊の存在」が価値を付けたのだ、というのが筆者の主張である。
イングランドの紙幣が永久磁石でゆっくり磁化されたのだとすれば、モンゴルの紙幣はちょうどフビライの軍隊という電磁石によって急速に磁化された紙幣であったと言えるだろう。
こうした筆者の考え方は、「貨幣商品説」や「貨幣法制説」に近い考えだということができるだろう。
つまり、貨幣が流通するためには、金や銀などの価値の裏付けが必要であった、というのは「貨幣商品説」であり、フビライの軍隊の軍事力が背景にあったというのは、「貨幣法制説」に近い考え方である。
しかし、これらの考え方にはすでに紹介したように、岩井教授の指摘する問題点がある、ということを指摘しておきたい。
なぜ社会は貨幣の増殖を容認したのか
本章における著者の見解について、「貨幣の類型」と「貨幣の磁化」を中心にして、「貨幣論」との関係から少し丁寧に見てきた。
著者の論法は、既述の通り、以下の通りであり、その次は信用創造へと続く。
「貨幣の類型」→「貨幣の磁化」→「信用創造」・・・貨幣の増殖
これ以上の検討は長くなってしまうので、「信用創造」についての解説は割愛とさせていただき、筆者の指摘のコアについて考える。
筆者の指摘のコア・すなわち最も注目すべき点は、この小節・「なぜ社会は貨幣の増殖を容認したのか」にあると考える
筆者は以下のように指摘している。
「絶対的健全経済」、すなわち経済社会が恐ろしく堅実な人々だけで構成されており、危ない借金などは一切行わず、手元にある現金以上の消費を絶対に行わないという常識で社会全体が貫かれているとしたなら、そこでは経済の拡大などということはあり得ないのである。
既に筆者が指摘している通り、誰かが自分自身の見込みを信じて、銀行から資金を借りて、新たな設備投資を行う、というリスクの大きな行動に出ることによって、経済拡大の最初のキッカケが作られ、消費と生産の拡大が行われることになる。
経済社会というものが規模の変動を伴うものである限り、こうした銀行の「又貸し」と貨幣増殖という不健全な行為は、経済社会のかなり根源的な部分に根差したものであることがわかるだろう。
[私の本小節のまとめ]
以上、この小節について、かなりのエネルギーを費やして説明を行ってきたが、その意義について次のようにまとめたい。
著者の「貨幣の類型」に関する議論は、「貨幣論」と比較するとかなり疑わしい点があり、すべてをそのまま受け入れることは難しい。
「貨幣の磁化」の議論についても、疑わしい点があることは否めない。
しかしながら、最終的な事象である「貨幣の増殖」に関する著者の“見立て”は、資本主義の持つ不安定性・不確実性を見事に指摘したものであり、傾聴に値する。
第7章 ドルはなぜ国際経済に君臨したのか
この章は、前章に引き続き、貨幣に関する議論となる。そしてその議論は第8章の仮想通貨に関する議論に続くことになる。
1.ドルから見た国際通貨
まず、基軸通貨としての米ドルについて、著者は次のように言っている。
実際に第二次世界大戦後の国際経済を見た時、そこに「世界通貨」というものがあったとすれば、ドルだけがそう呼ぶに値するものだった。つまり第二次大戦前まではドルというものは、単なる米国という国の中だけで使われる国内通貨=ローカル・カレンシーに過ぎなかったのだが、大戦後の世界ではそれは米国内だけではなく、世界全体で使われる唯一の基軸通貨=キー・カレンシーだったのである。
米ドルが「基軸通貨」となったことの意味としては、以下のように説明されている。
各国が外国と貿易を行う場合、たとえ米国を相手としない場合―例えば日本とタイの間での貿易の場合などーでも、その取引の決済は円やバーツではなくドルで行うということである。
ここでキーとなるコンセプトの第一が、「貨幣の類型」と「貨幣の磁化」であり、特に「貨幣の磁化」が重要である。
(1)貨幣の類型
筆者は、「当初は『イングランド型紙幣』として始まった」とする。
国債社会の第三国同士の取り引きにおいて、ドルが用いられるようになったのは、要するにドルが金との引換え証だったからに他ならず、ドルが米国という強い国の通貨だったことはむしろ二義的な問題だった。
(2)貨幣の磁化
筆者は、モンゴル型紙幣がフビライの軍隊に支えられていたように、米ドルはアメリカの軍事力と核兵器に支えられたと主張する。
現代のドルは「核兵器という電磁石によって磁化された特権的な世界通貨」なのであり、第二次世界大戦後の国際経済の中で、最初はイングランド型の国際通貨として出発したドルは、いつの間にやらこの種のモンゴル型の国際通貨に変貌を遂げてしまっていたのである。
これらの主張について、私は次のように考える。
1.米ドルが基軸通貨として使われるようになったキッカケとして、米ドルに金との交換の裏付けがあったからだ、とする筆者の主張は信ぴょう性が高いと考える。
2.ちなみに、生成AIの一つである“Gemini”に、米ドルが基軸通貨となった理由について質問したところ、以下の3つを理由として挙げてきた。
(1) アメリカの経済規模と金融市場の大きさ
(2) 米ドルに金との交換の裏付けがあったこと(金ドル本位制)
(3) アメリカとOPECとの石油取引おいて米ドルを使用する合意が行われたこと
著者が挙げている理由はこの中の2番目に該当する訳であり、その点からも著者の主張の信ぴょう性は裏付けられるであろう。
3.これに対して、米ドルと金との交換が保証されなくなった後について、著者が「アメリカの軍事力と核兵器である」と主張している点については、極めて疑わしいと言わざるを得ない。
そのような理由が、基軸通貨に関して該当するというのは、一種の「筆者の妄想」ではないかと考えられる。
4.やはり、生成AIのGeminiに「アメリカドルが金ドル本位制終了後も基軸通貨として使用されている理由」について質問したところ、以下の回答が戻ってきた。
(1) アメリカの経済規模と金融市場の大きさ
(2) 石油取引おいて米ドルを使用されていること
(3) 信頼性と安定性
上記の3つのうち、1番目と2番目は既に挙げられている理由であるが、重要なのは3番目である。
ドルは、長年にわたって国際通貨として広く使用されてきた歴史があり、その信頼性と安定性が高い評価を受けています。世界経済の不確実性が高まる中、投資家は安全な資産としてドルを求める傾向があります。
なお、基軸通貨としての米ドルについて、『貨幣論』の岩井教授は次のように述べている。
基軸通貨は何らかのビッグバンがなければ生まれない。米経済は19世紀後半から最強だったが、基軸通貨国は長らく英国だった。第2次大戦という大きなショックが、ようやくドルを基軸通貨に押し上げたのだ。その後、米経済のシェアは落ち、ベトナム戦争のとき、米政府は基軸通貨の座から降りようとしたこともある。ところが貨幣の自己循環論法が働き、米以外の国はドルを基軸通貨として使い続けた。ドル危機が繰り返し叫ばれても、いまだに基軸通貨のままだ
岩井教授が「貨幣の自己循環論」と言っているのは、「貨幣は貨幣であるから、貨幣である」(岩井克人「欲望の貨幣論」を語る(丸山俊一/NHK「欲望の資本主義」制作班より)という理屈なのだが、ここではこれ以上深入りはしない。
岩井氏の説明をより分かりやすく言えば、「すべての貨幣には信用が含まれる」(『政府債務』森田長太郎著より)ということだと考えられる。
そしてその“信用”の裏付けが、生成AIの言う「(米ドルのもつ) 信頼性と安定性」であると考えるべきなのであろう。
広い意味では「軍事力と核兵器」も含まれると考えるべきかもしれないが、決してそれだけではない、と考えるべきだと思われる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
