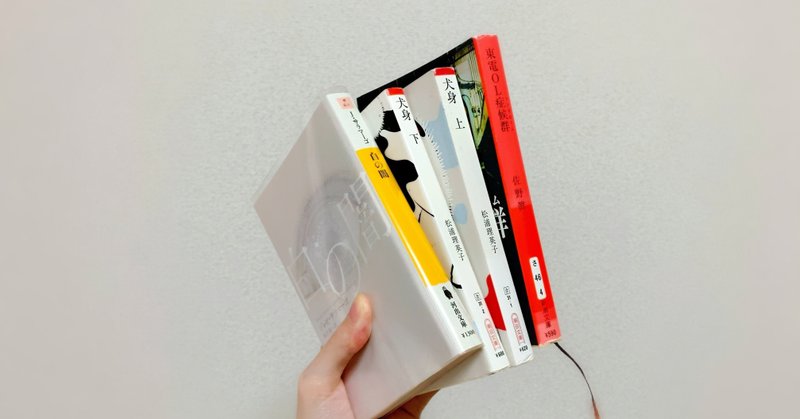
ステイホームGW読書 まとめ
ほとんど部屋から一歩も出ずに過ごしたゴールデンウィーク2020、部屋の片隅に積み上がった未読本タワーからの厳正なるチョイスの結果読み終えた4冊を記録します。各書店が休業するなか、日頃から積読本を溜め込んでおくと部屋に居ながらにして選ぶ楽しみが残されていてたまにはいいことがあるものだと思いました。なお買った本はちゃんと読んだ方がいいです。
白の闇 / ジョゼ・サラマーゴ
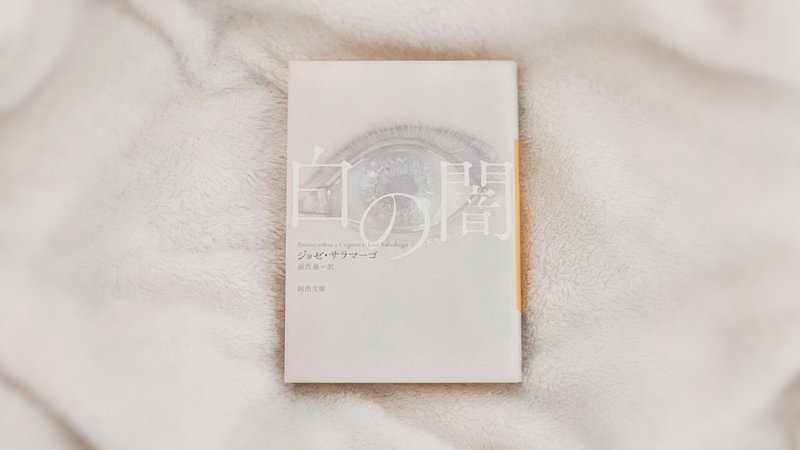
突然世界が真っ白になるという原因不明の失明症が爆発的に広まり、失明した人々の混乱や隔離された患者たちがむき出しにする人間存在の愚かさ醜さ、地に堕ちていく人間の尊厳が克明かつ容赦無く描き出されています。
まさに現在、未曾有の感染症対策でステイホームを要請されている中で読むにはふさわしい本かなと思い始めに手に取りました。
読む前は勝手にアルベール・カミュ『ペスト』のように、病原菌がペストとはっきりしている感染症に対し人はどう立ち向かうか、いわば人間vs病の構図の小説かと思っていましたが、本作における失明症の原因は結局のところわかりません。問題は原因ではなく、いきなり究極の理不尽に突き落とされた人間たちがどのように考え、行動し、生き延びていくのかということであり、もっとも重要な主題は「人間の尊厳の在処」です。そういう意味では本作はフィクションではありますが、『ペスト』よりもアウシュヴィッツ絶滅収容所での体験記であるヴィクトール・フランクル『夜と霧』、プリーモ・レーヴィ『これが人間か』の系譜に近い本であるような気がします。また、物語後半はかつてCAPCOMに一攫千金をもたらした伝説のサバイバルホラーゲーム「バイオハザードⅡ」を思わせる描写です。バイオハザードシリーズもウィルスに感染した人間たちが強制的に人間性を剥奪されゾンビに身を落とし、街ひとつを破滅させる(そして熟練のゲーマーたちに虫のように殺されていくか弾が勿体無いのでガン無視される)という設定なので、近いものがあります。実際読んでいて、目が見えなくなるだけで人間もゾンビもそう変わらんことになるんやな…という陰鬱な感想を持ちました。大事なことなのでもう一度書きますが、この本の主題は「人間の尊厳の在処」です。
『白の闇』
著:ジョゼ・サラマーゴ / 訳:雨沢泰
河出書房新社 2020年
犬身(上・下) / 松浦理英子

人間よりも犬が好きで、「種同一性障害」という言葉まで生み出し自分は犬になりたい、犬と飼い主の関係性に自分を置きたいと切望する主人公が実際に犬になり、陶芸家である女性の飼い犬として彼女と生活を共にする物語です。
私にとっては久しぶりの松浦理英子作品です。数年前の帰省しなかったゴールデンウィークに『葬儀の日』『セバスチャン』『ナチュラル・ウーマン』を立て続けに読み、松浦氏の鮮烈な思想、暴力的なまでに激しい感情の発露、文章のエッジの鋭さに読書後はくたくたしばらく動きたくない、という体験をしましたが、前述三作は1980年代に発表された初期作であるのに対しこちらは2000年代の作品で、少し(?)間があいています。
どうしても初期三作と比べてしまいますが、こちらはかなり読みやすかったです。犬目線だと感情の発露もシンプルになるのでしょうか。主人公を犬に変えた正体不明のバーテンダー、朱尾とのやり取りが随所に挟まれるのですが、これがうまく読者にとって「休憩」の役割を果たしているように感じました。朱尾は何を考えているのかわからないキャラクターではありますが、主人公のリクエストをだいたい叶えてくれたり、悪い方向に持って行こうとはしないので彼が登場すると少しほっとしてしまいます。
本作で少し驚いたのは、主人公が飼い犬として「嫁いだ」先の陶芸家の女性、玉石梓の家族関係がかなり露悪的に書かれている点です。梓本人は控えめで心優しく、飼い犬に対しても惜しみない愛情を持って世話をする女性であるのですが、彼女以外の玉石家は最悪です。それぞれをぶん殴りに行きたいほどに最悪です。しかし物語もまた、その最悪な玉石家に対しかなり派手な展開を仕掛けます。この展開の派手さにも驚きました。正直、おそらく松浦氏の得意とする「他者との名付けられない関係性」の行方をじっくり追いかけるというよりも、玉石家の込み入りようと展開の派手さに目を取られたまま読み終えてしまったような感じです。
あと解説がなぜか死ぬほどつまらなく感じて途中で読むのをやめました。
『犬身』(上・下)
著:松浦理英子
朝日新聞出版 2010年
東電OL症候群 / 佐野眞一
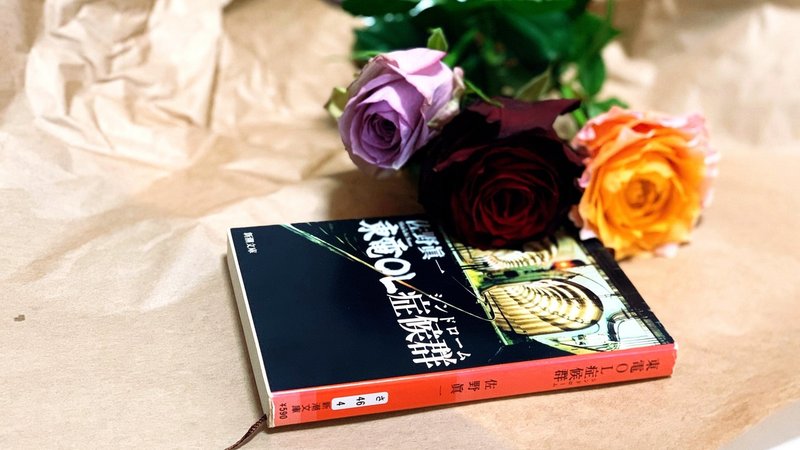
この本は自分で選んで買ったものではなく、東京は池袋にある古書店、コ本やさんの「古書パック」で購入した選書の中の一冊でした。(現在はSOLD OUT状態です)
くたくたになって帰ってきたらコ本やさん(@honkbooks)から選書パックが届いていた📚「ノンフィクション」「フェミニズム」ていうちょっと安直すぎたかな…というリクエストでもザ・斜め上の選書が来た 一周回ってわたしのこと知ってるんですか?と思えてくるチョイス…死に山気になりすぎるやん…🏔 pic.twitter.com/jvnUa3I1Po
— 𝐬𝐥𝐨𝐰 (@__slowlikehoney) April 6, 2020
帯からして、「これは確かに自分では買わんな…」と思った本だったのですが、ここまで小説つづきで読んでくると一旦学術書かドキュメンタリー本が読みたくなり、なんとなく手に取ってページをめくり始めると止まらなくなり、気づいたら一日で読み終えてしまいました。
本書は1997年に発生した東京電力女性社員の殺害事件とそれを巡り、どう考えても冤罪としか考えられないネパール人容疑者の一審無罪からの二審逆転無期懲役判決、前作『東電OL殺人事件』に寄せられた女性読者からの予想外の反応の多さと実際に著者に手紙を寄せた女性たちとの対談、そして容疑者の逆転有罪に関わった裁判官の児童売春という不祥事までもを丁寧に追いかけます。(タイトルでは「東電OL」となっていますがOLと書くと良くも悪くも若くて一般職の女性をイメージされそうで、女性社員と書きました。被害者の女性は総合職で、東電企画部門でかなり上の役職に就いていたからです)
コ本やさんの古書パックを購入したとき、「フェミニズム」と「ノンフィクション」という二つのキーワードで選書していただいたのですが、ぱっと見これはノンフィクション枠で選ばれたのかな? と読むまでは思っていましたが、実際読んでみると本書は「ノンフィクション」「フェミニズム」両方を含有した内容でした。決定的証拠がないままに有罪をゴリ押す検察、ことを急くように無期懲役判決を下した司法の杜撰さ、そこに横たわる日本・ネパール間の力関係、アジア系外国人への明らかな差別、という日本の警察・司法の闇という視点からも書かれていますが、同時に、女性が大企業の総合職として働くことの(2020年現在よりもはるかに高く大きく立ちはだかっていたであろう)厳しさ、社内の出世競争に破れるという現実に直面した一人の女性が「崩壊」していく様も克明に書かれており、多くの女性読者が共鳴したのもこの部分であったからです。被害者女性は定時で東電を退社してから毎晩渋谷で4人の客を取って売春行為を行い、終電で帰宅して翌朝はまた東電へ出社する、というかなり極端で自己破壊的日々を送っており、その果てに事件が起きましたが、これは彼女の「生きづらさ」を象徴する行為であり、女性読者が共鳴するのも大なり小なりこの「生きづらさ」を共有しているからだろうと著者は考察しています。本書は前作を受けての事の経過と事件を巡る周辺的エピソードでまとめられており被害者女性の行動、内面の掘り下げはおそらく前作で詳細になされているのでボリューム感としてはそれほどでもなかったのですが、どうにも気になるので前作もメルカリあたりで購入しようと思います。
タイトル『東電OL症候群』は、殺害された東電社員に感化された人たち(帯がまさにそうだったので…)のことを指しているのかと思っていましたが、実際のところこの病に最も深く冒されているのは著者自身ではないでしょうか。この取材量と考察の展開の仕方には何か病的なものを感じます。
それにしても、本書が発刊された2001年から2020年現在の間に東京電力という社名にも全く異なる印象がついてしまったことは皮肉です。
『東電OL症候群』
著:佐野眞一
新潮社 2003年
4/30〜5/5の間に読んだ量にしては多いのか少ないのか、映画もB'zのLIVE-GYM(YouTube無料公開中)も観ていたので自分としてはまあまあかなと思っているところですが、昼寝の時間をもっと削ればあと1冊くらいは読めた気がして本当に眠気を飛ばす薬が欲しい(それはすなわちドラッg...)
ゴールデンウィークなどの大型連休は基本的に帰省するようにしていますが、帰省すると毎日のように出かけたり人と会ったりして基本的に一人の時間ゼロなので、数年に一度は帰らない連休があってもいいのかもしれないなと思います。早く日々が収束することを祈りつつ。
読んでくださってありがとうございます。いただいたお気持ちは生きるための材料に充てて大事に使います。
