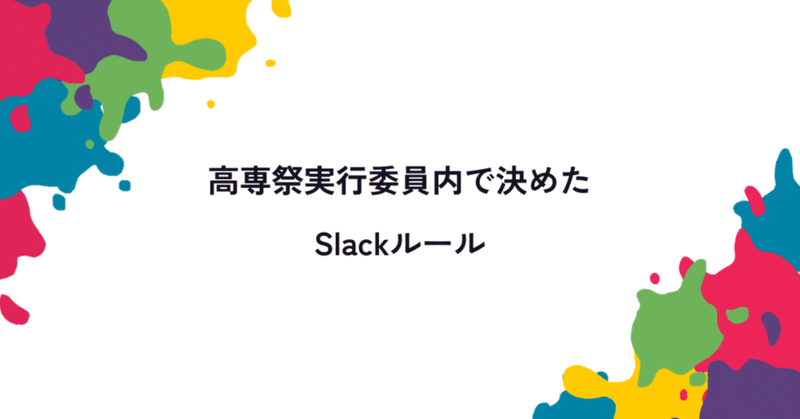
高専祭実行委員内で決めたSlackルール
こんにちは。この記事では高専祭実行委員の連絡手段としてSlackを導入し、どのようなルールを定めて運用していったのかを書いていこうと思います。
この方法が正解ということではなく、「僕はこんなふうにしました。振り返ってみると〇〇でした。」のような書き口でこの記事を書いていこうと思います。参考になれば幸いです。
前提条件
どういうふうに導入を進めたかを書いていく前に、実行委員の規模感やどれくらいの期間をかけて準備を進めていくのか等を簡単に書かせていただきます。
そもそも高専祭とは
はじめに「高専祭って?」となる方もいらっしゃるかと思うので簡単に説明します。想像つくと思いますが、いわゆる学園祭です。僕の通う高専では毎年10月終わり~11月初め頃の土日に開催されます。その準備は例年4月頃から始まり、今年はその連絡手段としてSlackを導入しました。

実行委員の連絡手段としてSlackを導入したのが初めてかというとそうではありません。過去にも導入していた年はあったらしいのですが、その次の年にはLINEで連絡するように戻ったりしていたみたいです。
実行委員の規模感
今年の話にはなりますが、全体として60名ほどが参加していました。学年や学科もバラバラで初めて会う子も多くいました。
僕は情報系ですが、生物・化学を専攻する学生や、機械や電気を専攻する学生などそれぞれのバックグラウンドは大きく異なる学生が集まっていました。
情報系の学生は何らかの形(インターン, チーム開発など)でSlackを使ったことがあるという子が多かったんですが、他の学科の子は初めてSlackを使うという子がほとんどでした。
前提条件はここまでにしておいて、導入時に工夫したことやどんなルールを定めて運用していったのかを書いていこうと思います。
導入時に工夫したこと
僕の話にはなってしまうんですが、ただやれと言われてもそれをやる理由や使う理由がわからないとあまりやる気が起こりません。逆に「こういう理由があって今これをやってる」というのが分かれば納得して使うことができます。
こういった理由から「なぜSlackを導入したのか」ということをはっきり伝えるようにしました。Slackを使う理由として以下の2点をメンバーに説明しました。
チャンネルという概念が存在すること
スレッドという概念が存在すること
それぞれをどう説明したかを基本的にはメンバーに説明した通りに書いていこうと思います。
チャンネルという概念
高専祭にはそれぞれの部門があって(例: 美術, 大工, 会計など)、もしそれぞれの内容を話せるチャットがなくて全体の全員参加のチャットだけだと、内容がごちゃごちゃになってしまいます。
これをLINEのグループで管理しようとすると、たくさんのグループが必要で、それぞれのグループに入る必要があります。また、話したくてそのグループに入ったのに自分が入る以前のトークは見ることができません。
Slackではワークスペース (2022年度高専祭実行委員) に入っておけばチャンネルと呼ばれるグループチャットに自由に出入りでき、過去のトークも閲覧することができます。
ほとんどそのままコピーしてきたんですが、チャンネルという概念を伝えるのにこのように説明しました。過去LINEでやり取りしていた年もあるみたいで、それを引き合いに出してSlackのメリットを伝えようとしたのを覚えています。
スレッドという概念
例えば複数人に同じことを聞くときや、深い議論をするときに便利なのがスレッドです。
例えば「各自の出席番号と名前を教えてください!」のようなメッセージがあったときに、スレッドがないとそれぞれ全員が「{出席番号} {名前}です」みたいなことを書いていく必要があるので、トークがかなり流れてしまいます。
スレッドがあることで、トーク自体は流さずに、その投稿に対してリプライをすることができます。
これはそのままコピーしてきました。実際に出席番号と名前が必要なシーンがあり、それを引き合いに出して説明しました。
導入時はこのようにSlackを使う理由を説明することを心掛けました。この説明の効果がどの程度あったかは不明ですが、高専祭終了後に「実行委員の連絡ツールとしてSlackは適切だと思いますか?」という質問に100%で適切だと思うと回答してくれていました。
しかしこのSlackを使う理由の共有が高専祭の準備が始まる1番最初にできたわけではなく、遅くなってしまったことを後悔しています…
次は定めたルールについて書いていこうと思います!
定めたルール [初期設定編]
初期設定時に「この設定しておいて〜」と伝えたのは基本的には1点だけで、表示名を ローマ字 + あだ名 に変更するということだけでした。
その時も「なぜ表示名を変更するのか?」というところで疑問にさせたくなかったので、以下のように理由をつけて伝えるようにしました。
ローマ字にしてもらう理由はメンションしやすいからです。あとあだ名をつけたのは、より話しかけやすくなるかなと思ったからです!
あだ名も表示名に含むようにしたのは、話したことのないメンバーが多く、最初のコミュニケーションのきっかけを作るのが難しいというところを問題点に感じていて、直接的な解決になるかはわからなかったけど「こうやって呼んでほしい!」っていうのを表現しておくことでコミュニケーションのハードルを下げようと思ったからです。
今思えばこの内容もそのまま共有すればよかったなと思っています。
定めたルール [運用時編]
運用時 (使っていく上で) のルールとしては4つほど定めました。
どんどんメンションを使おう!
DMは極力使わない
深い議論をするならスレッドを使おう!
どんどんリアクションをつけよう!
どんどんメンションを使おう!
みんなに聞きたいときだったり、この人に聞きたい!みたいなのをはっきりさせるためにもメンションは積極的に活用するといいです!
高専祭実行委員メンバー全員に聞きたいときは、#random で話してくれるとうれしいです!
このように伝えました。メンションするハードルをなるべく下げたいと思い、ルールとして定めました。
また、メンションしなかったことによる連絡漏れが怖かったという理由もあります。
DMは極力使わない
理由としては、その後議論が発展して他の人を巻き込んでいくようになったときに、元々2人でしていた議論が公になっていないので、また共有する必要が出てくるからです。
なので、#random や それぞれの部門のチャンネルでメンションつけてもらって話してくれると嬉しいです!
深い議論をするならスレッドを使おう!
議論が長くなったりしそうだったら、スレッドを使うといいかもしれません!
トークが流れてしまうといったこともさけることができるので、スレッドは積極的に活用してください!
どんどんリアクションをつけよう!
リアクションを積極的につけることで、Slackのコミュニケーションも活発になるので積極的につけてくれるとうれしいです!
上記4つのルールを定めて約半年間Slackを運用してきました!
結果としては上記4つのルールはみんながそれぞれ守って使っていくことができたんじゃないかなと思っています!1つのメッセージにたくさんのリアクションが付くこともあって、盛り上げながらコミュニケーションをとっていくことができたと感じています。
今思えば「雑な共有だなあ」と思うところもあり、もう少しちゃんとできたような気もしますが、一旦おいておいてこのように運用してましたっていうことでまとめておきます。
最後に・感想
IT系の企業からもこういったガイドラインは出てはいますが、「Slackを使ったことがない人に向けて」というのは僕も経験がなくとても難しいながらも色々なことを考えて楽しかったな〜と思いました。
Slackを初めて使うメンバーでも、ここで書いた内容 + Slackの基本的な使い方 (メッセージ送信の仕方、スレッドの作り方、リアクションの付け方など) を書いたドキュメントを共有して、説明会を行ったことでほぼ全員使い方がわかるという状況に持っていけたのは非常によかったと思っています。
この記事ではSlackを使う上でのルールというところにスポットを当てましたが、高専祭実行委員のマネジメントというところでも記事を書こうと思っているので興味があれば是非読んでくださると幸いです。
学生を統括する方だったりそういった方のお役に少しでも立てれば嬉しく思います。拙い文章でしたが最後まで読んでいただきありがとうございました。何かあれば Twitter の DM等で連絡ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
