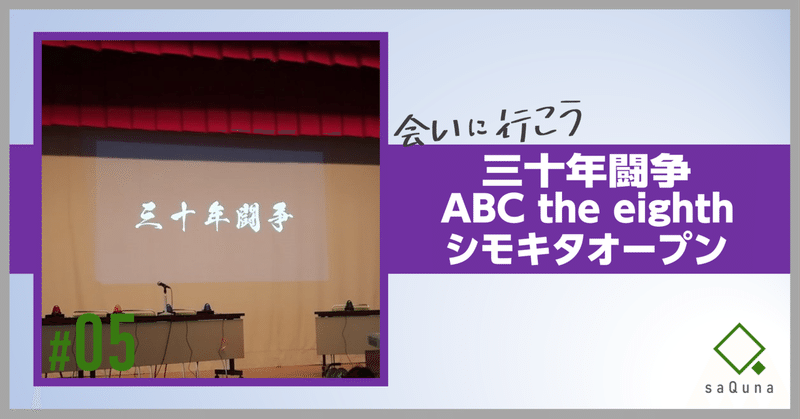
自分のあと5年、スタッフの「広さ」、雰囲気づくり【会いに行こう#05】
「競技クイズとデザイン」という記事を書きました。
そして自分自身もいろんな大会/イベントの実例へ会いに行こうと行動している最中です。「つくる(≒アウトプット)」を繰り返してきた自分が、よりよい実例をインプットするI/Oの記事シリーズ。
今回は3本立てでお送りします。「リプライのツリーは3つまで」というこだわりがあり(3つまでなら"さらに表示"が出ないから)、それに習って140文字×3段落へ収められるように書きました。
三十年闘争
個人イベントの命名はいつも迷うものです。ある意味で枷を自ら取り付け、それに違わないイベントの用意へ向かう第一歩、それが命名だと思います(自分は"色・カラー"というキーワードを通年で使うよう設定したらだいぶやりやすくなりました)。で、この大会は「三十年闘争」といいます。
実際に行くと血生臭い展開はとうぜんなく、しかし熱量はバッチリの戦いが展開されました。主催者の考える「短文」の発露の連続。そのなかに、感心してしまう新事実や共感を引き起こされる記述が盛り込まれていて、たいへん楽しめました。
ところでこの「三十年闘争」というタイトルには、「30歳の区切りとして、ここ5年ぼんやりと考えていた課題へ挑戦しよう」という思いが込められています。私は現在25歳、同人クイズ文化に触れてからもうすぐ丸10年。自分自身のこれからとは……そう考えたくなるイベントでした。
ABC the eighth
「社会人による基本問題実力No.1決定戦」の8回目。学生対象「abc」のスピンオフ。初めて参加しました。これは自分自身が、「abc the20th」「21st」のスタッフを担当した経験からいろいろと考えたいことがあったからかもしれない。
勝負の内容としては、その「21st」を戦ったいわゆるラストイヤー上がりがすさまじい。なんで正解できるんだ、と同人クイズの門をたたいたばかりのひとみたいな感想が出続けていました(ぼくはプレイヤーとしては実際それくらいの修練度に近いが)。
非常に印象的だったのはスタッフの「広さ」。abcとは逆に学生が運営する大会ですが、性別や活動エリアなどの属性がかなり多様に見えました。複数人で集まったうえで「基本」を標榜するならまずはここからだろう、と個人的に考えている部分でしたが、かなり納得度が高かったと思います。
シモキタオープン
さいきん数ヶ月だけ東京にいましたが、目星をつけていたスポットのひとつにここが挙げられます。毎月平日夜、下北沢で開かれるクイズ大会。上京後さっそくエントリーし、12月・1月の2大会に参加しました。
予選で短期決戦の機会が3度設けられ、どこかで勝ち抜けると準決勝、決勝…という形態です。何度も早押しボタンに触れられるルールと問題のジャンルの幅広さ、それに耐える個々の問題の面白さ、軽妙な司会が魅力に感じました。芸能ジャンルは特に押していて楽しい(自分が得意という自覚があるだけ?)。
「ワンドリンク制なので手元にお酒やソフドリがある」「参加者が近い場所に自由に座っている」などの特徴から、よくある同人クイズイベントとは違う雰囲気が漂っており、自分はそれがとても好きです。学生のそれとは異なりがちな"社会人のクイズの在り方"を、ひとつ示していただけました。
ありがとうございました。
まだまだ会いに行ったクイズはたくさんあるので、いろいろ書いていきますね。
saQuna/さくな
Web/SNSの統轄責任者として「abc/EQIDEN」2022年・2023年大会に参画。その他の担当クイズ大会に「"ONLY MY QUIZ" new generations(メインスタッフ)」「mono-series'19(問題チーフ)」「abc-west 3rd(デザイン・得点表示・広報)」「saQunaたんたるひまたんダイキリクイズ(共催)」など。2023年6月には個人大会「IRODORI ONSTAGE」を開催。
立命館大学クイズソサエティーを経て現在は社会人。
頂戴したサポートは、よりよい作品づくりに活用させていただきます。よろしくお願いします!
