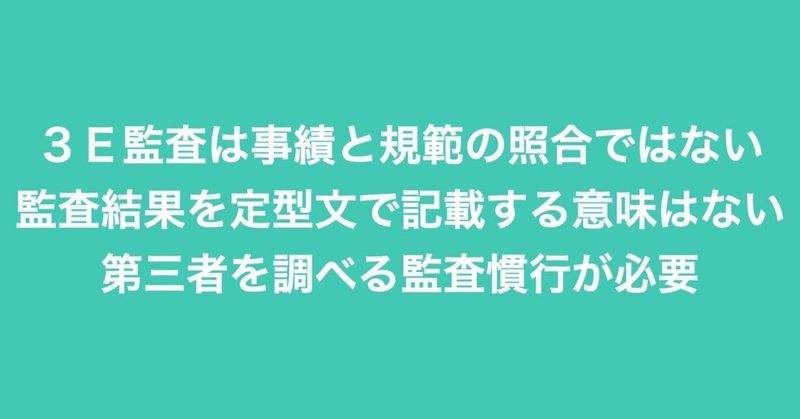
3E監査の難しさを監査基準で知る
この記事は、3E監査をどうすればできるのか分からない方や、監査報告に監査の結果をどう記載すれば良いか分からない方に向けて書かれています。
<総務省の監査基準案における3E監査>
監査制度の充実を柱の一つとする平成29年地方自治法改正の眼目の一つは、監査基準の作成と遵守を監査委員に義務付ける監査基準制度の創設でした。改正法施行(令和2年4月)の1年前(平成31年3月29日)に総務省は自治行政局長名で「監査基準(案)」(以下「監査基準案」といいます)と「実施要領」を通知しました。その監査基準案では、第2条で「監査等の範囲及び目的」について定めていますが、その第1項第1号で財務監査の目的を、第2項で行政監査の目的を、それぞれ次のように定めています。
第1号 財務監査
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること
第2号 行政監査
事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること
つまり、『法令に適合し、正確であるか』と、『最少の経費で最大の効果を挙げるようにしているか』と、『組織及び運営の合理化に努めているか』の3点をそれぞれの目的と定めています。
このうち最初の、『法令に適合し、正確であるか』監査するということは、財務監査については、監査客体を財務の執行事績と経営の管理事績とし、これに対して合規性と正確性の観点から点検することを表現しています。一方、二つ目の「ようにし」と三つ目の「努めている」で締めくくられている目的は、監査対象組織の意思を監査客体として点検するような表現となっています。この違いについて、総務省は、監査基準案と併せて通知した実施要領で次のように説明しています。
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 199 条第3項において、監査委員は、財務監査及び行政監査を行うに当たっては事務の執行及び経営に係る事業の管理が同法第2条第 14 項及び第 15 項の規定の趣旨に則ってなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならないと規定されている。このことから、監査基準(案)第2条第1項第1号及び第2号においても、同様に規定したところであり、 事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的(より少ない費用で実施すること)、 効率的(同じ費用でより大きな成果を得ること、あるいは費用との対比で最大限の成果を得ること)かつ効果的(所期の目的を達成していること、また、効果を挙げていること)に行われているかについて監査することが求められる。(第2条第1項 関係)
この説明により、総務省監査基準案が二点目と三点目の目的として定めているものが、地方自治法第199条第3項の規定に基づくものだと総務省が理解していることが分かります。同項が引用している地方自治法第199条第2条第14項及び第15項の規定は次のようなものです。
第14項 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
第15項 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
これで分かるように、監査基準(案)がいう「ようにし」と「努める」は地方自治法第2条の文言を使用しているのです。
念の為、付言しておくと、読者の中には、「最少の経費で最大の効果」が経済性・効率性を意味することは理解できても、「組織及び運営の合理化」がどうして効率性・有効性を意味しているかが理解できないかもしれません。これを理解するためには、行政組織を含む組織というものが一定の目的のために統制された人的資源であるということ、また、行政運営が、組織目的のために行政組織によって行われる公的資源(人的資源を含む。)の運用を意味していることを理解しなければなりません。その理解の上に立てば、それらの「合理化」が、行政目的のために運用される公的資源が、人的資源も含め、よりスリムなものにし、より目的を達するように運用されること、すなわち、より効率的に、より効果的にすることを意味していることが理解できるはずです。
<3E監査はどうして難しいのか>
話を元に戻すと、「ようにし」、「努める」のように監査対象組織の意思を問題視するということは、3E監査が難しいことを意味しています。通常の監査は、例えば一連の執行事績を逐次、規則や前例などの規範と照合して点検して行いますが、3E監査は規範と照合するだけではできないのです。ただし、照合して可能なこともあります。例えば、契約事務については競争契約の方が経済性を確保できますので、競争契約を原則とするという財務規範が確立されています(地方自治法第234条第2項)。このような、経済性を確保するための財務規範に基づいて執行事績を点検すれば、経済性の観点からの監査と言えなくもありません。ただ、財務規範と執行事績との照合だけで成立していることに着目すれば、合規性の観点からの監査と理解すべきです。
3E監査は、財務規範と執行事績との照合だけではできない監査です。上記の総務省実施要領で説明しているように、3E監査とは、経済性(より少ない費用で実施する)、効率性(同じ費用でより大きな成果を得る、あるいは費用との対比で最大限の成果を得る)及び有効性(所期の目的を達成している、また、効果を挙げている)の観点から点検する監査を言いますが、一部が財務規範に具体化されている経済性と異なり、効率性と有効性については、こうした方が良いという形での規範の整備は困難です(だからこそ、多額の費用を伴う公共事業について評価制度が整備されているわけです)。
例えば、過去の執行事績について、別のやり方で執行すればより効率的だったという形での認定を試みようとしたとします。しかし、そのような立論は結果論になりやすく、結果論では修復や将来の改善を図ること、つまり実効ある監査は困難です。客観的に実効ある監査をするのであれば、現状こうなっているが、このように取り組めば、もっと公的資源を活用できるはずという立論を採らざるを得ません。つまり、出発点を過去の執行事績に置くのではなく、公的資源の実状に置かざるを得ないのです。その公的資源をもっと活用できる方途を提供することが3E監査の基本です。ちなみに、実効ある監査とは、地方自治法が監査基準を「法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(‥)の適切かつ有効な実施を図るための基準」という表現から採っています。
3E監査の難しさは出発点が公的資源の実状であるということに起因します。財務監査を行なう場合、監査対象組織における既往の執行事績から抽出したものを点検する、ということになりますから、公的資源の実状にはなかなか気が回りません。例えば、次は3E監査の事例ですが、これに即してみていきましょう。
プール及びスプリンクラー用に敷設された水道についての経済的な執行に関する件
使用実績がほとんどない水道について、基本料金を支払っているものがあった。
当校は、旧横浜市立日向山小学校の施設、設備を使用しており、校舎等で使用する一般用の水道管とは別に、プール及びスプリンクラー用として水道管(メーター口径 50mm、以下、「プール用水道」という。)が敷設され、プール用水道料の基本料金を隔月で 22,524 円支払っている。
プール用水道の用途のうち、プールについては、水深が浅く支援学校(高等部単独校)としての利用が困難なことから使用しておらず、また、スプリンクラーについても、校庭には飛散しにくい砂が使われていることもあり使用実績はなかった。そのため、平成 25 年4月の開校以来、使用実績は、プール清掃時の4m³のみとなっていた。
水道の使用については、一旦中止の電話連絡をすることで基本料金を支払う必要はなくなり、追加的な経費を掛けることなく電話連絡で簡単に再開することができる。
したがって、有効利用の観点から、プール及びスプリンクラーの利用計画について改めて判断を行い、当面の利用予定がないのであれば、一旦使用中止手続を行い、プールの利用計画が明確になった段階で、改めて使用再開の手続を取ることにより、経済的な執行となるよう改善する必要がある。
この事案は、水道料金支払の事務が法令に適合し、正確に行われているかを点検しているだけでは、発掘しにくい事案と言えるでしょう。毎月の支払額を比較してみるか、使われる実績がないとの説明を聞き出すかしないと監査人としては把握しづらい問題です。また、教務サイドで利用するかしないかの意思決定を行わない限り、会計事務サイドとしては請求されている限り支払わざるを得ないわけですから、既往の支払が間違っていたという認定もできません。つまり、『3Eを向上させる余地があるから、アクションを起こすように』というのが、指摘の趣旨と言えるでしょう。アクションと言っても、最初に起こすのは教務サイドで、これは財務監査の範疇を超えています。このことは、いわゆる定期監査・定例監査(地方自治法第199条第4項の規定に基づいて実施する周期的財務監査)において行政監査を行うことにしておくことが必要であることも示しています。
付言すると、この指摘からは、次のことも理解できます。そもそも、『改善の余地あり』と認定するためには、「一旦中止の電話連絡をすることで基本料金を支払う必要はなくなり、追加的な経費を掛けることなく電話連絡で簡単に再開することができる。」という知見が必要であるということです。法令に適合して正確な財務事務を執行する上では、そのような知見は必要ありません。しかし、3Eを改善するアクションを起こすためには、そのような執行上は必要でない知見が必要とされることもあります。必要とされない場合は、競争契約とすべきという指摘のように、合規性の観点からの指摘に吸収されるはずです。このことから、さらに、次のようなことも言えるはずです。それは、合規性と正確性の観点からの監査は、執行した記録(帳簿と根拠資料)と被監査組織からの説明聴取だけで行うことも可能ですが、『こうすべきだった』と立論しない純粋な3E監査は第三者(上の事例では水道局)の情報収集が必要不可欠ということです。逆に言うと、そのような知見がないからこそ、活用の余地がある公的資源が放置されていたのかもしれません。
一方、合規性と正確性の観点からの監査でも、時には、金融機関の残高証明など第三者の情報を収集することが必要になることもあり、それが不正経理の抑止と摘出を可能にします。
したがって、3E監査に取り組むことで、第三者の情報収集を監査慣行とすることができますが、ひいては、それが不正経理の抑止と摘出を可能にすることにもなります。これこそ、監査委員に3E監査が求められる所以でもあります。
<総務省監査基準案は監査報告に何を記載させるのか>
話をもとにもどすと、総務省の監査基準案が、財務監査の目的として3E監査も規定していることは、前記のとおりですが、次に、監査報告にどのように記載することにしているかをみていきます。総務省監査基準案は第15条で「監査等の結果に関する報告等への記載事項」を定めています。その第1項では、監査等の結果に関する報告等に記載する事項を列記しており、その中の「監査等の結果」において記載することを第2項から第4項までで規定しています。第4項は「是正又は改善が必要である事項」を監査結果としてどう記載するかを規定しているものですが、第2項と第3項では、監査結果によって、第2項の規定に基づく記載か、第3項の規定に基づく記載か、のいずれかを監査の結果として記載することを規定しています。これを財務監査についてみると次のとおりです。
第2項 前項第六号の監査等の結果には、次の各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められる場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
一 財務監査 前項第一号から第五号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること
‥
第3項 第一項第六号の監査等の結果には、前項各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められない場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
つまり、「監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること」が重要な点において認められる場合にはその旨を、重要な点において認められない場合にはその旨を監査の結果として記載すると定めているのです。
まず、最初に浮かぶ疑問は、「重要な点」とは何か、ということでしょう。これが分からないと監査報告をどう記載すれば良いか分かりません。結論から言うと、これは監査報告を受け取る議会や首長等に対するメッセージなのです。例えば、財務諸表監査の監査基準では「監査人は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会 計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況 を全ての重要な点において適正に表示していると認められると判断したときは、 その旨の意見(‥)を表明しなければ ならない。」という定めがあります。これにより表明される無限定適正意見の意味は、『瑣末なところでは適正に表示していないところもあるかもしれませんが、全体としては信じて良いですよ』というメッセージです。総務省監査基準案も同様で、『‥ことが重要な点において認められる』(第2項の規定に基づく記載)とは、議会や首長等に対して、『想定の範囲内の異状はあり得ますが、全体として特段の問題はありませんから、特に何もする必要はありません』というメッセージを伝えようとするものです。一方、経理紊乱などで統制を立て直す必要がある場合は、『‥ことが重要な点において認められない』旨のメッセージを発することになります。
総務省監査基準案に基づいて監査報告を作成する場合には上記を踏まえる必要がありますが、これを理解している監査委員は少数派です。このため、多くの監査委員が監査報告の記載について総務省監査基準案を採用していながら、「重要な点において」の記載がないなど監査基準に準拠していないのが実状です。
また、不特定多数を相手に誤解が生じないよう定型文で記載する必要がある財務諸表監査と異なり、議会や首長など普段から付き合いのある特定の者に対して監査報告を提出する監査委員の場合は、言いたいことがある場合には、定型文で伝えるより自由記述で伝える方がメッセージが的確に伝わりますし、その方が合理的だと考える監査委員もいます。このためか、少なくない監査委員が、自ら作成する監査基準に上記第15条第2項及び第3項に相当する規定を盛り込んでいません。具体的には、都道府県では、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、山口県の14都府県、政令指定都市では、札幌市、京都市、堺市、神戸市の4市、中核市では、八戸市、宇都宮市、川越市、八尾市、吹田市、尼崎市、奈良市の7市です。
<総務省監査基準案のとおりに作成していない監査委員>
では、総務省監査基準案の第15条第2項及び第3項に相当する規定を盛り込んで監査基準を作成している多数派の監査委員がどのような監査報告を作成しているかをみていきます。
まず、監査結果記載について、自らが作成した監査基準を一顧だにせずに、従前と同様の記載を継続している二流の監査委員も存在しますが、監査基準の存在は意識しているものの、3E部分の記載について放棄している監査委員が存在しています。監査報告の記載について総務省監査基準案を採用している佐世保市監査委員は監査結果を次のように記載しています。
上記、記載のとおり監査した限りにおいて、収入事務につき、別記のとおり改善を要する事項が見受けられた。その事項を除き、重要な点において、監査の対象となった事務は法令に適合し、正確に行われていた。
なお、軽易な事項については記述を省略した。
佐世保市監査委員のこの記載は、佐世保市監査委員監査基準が求めている3Eの記載はありませんが、3E監査を行うに至っていないことを示している点では、真摯で誠実な監査報告と言えます。同様な監査委員として、監査結果を「前記のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が次の事項を除き法令に適合し、正確に行われていると認められた。」と記載している船橋市監査委員もいます。
これらと対照的に、3E監査結果を記載している監査委員も存在します。鳥取市監査委員が6年1月19日に公表した監査報告書の「第6 監査の結果」の冒頭は次のように記載されています。
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね適正に処理されていると認められた。また、最少の経費で最大の効果及び、組織及び運営の合理化においても、特段不合理なものは確認されなかった。
改善を要する事項(指摘事項)は後述のとおりであり、必要な措置を講じられることを求めるものである。
なお、事務処理上の軽易な過誤等については、注意事項として文書により、またはその都度、関係者に対し指示・注意を行った。
引用文の第1段落の前段で、合規性及び正確性の観点からは問題がなかったことを「おおむね適正に処理されている」と表現する一方、後段では、3Eの観点からも問題がなかったことを「特段不合理なものは確認されなかった」と説明しています。合規性は執行事績と規範との照合であり、正確性は執行事績と執行記録との照合ですから、問題がなかったことを「適正に処理されていた」と表現することは可能です。後段の表現は、3Eの観点が、公的資源の実状にもっと経済的・効率的・効果的に改善する余地はないかという観点であることを踏まえれば、公的資源の実状を点検して、その活用度を改善する余地はなかったことを「特段不合理なものは確認されなかった」と表現していると理解できます。つまり、公的資源の実状を点検して、そこに大きな活用の余地がなければ、「最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めている」と認定できるわけです。
ただし、上記の監査報告の記載が監査基準に従っているかというと微妙です。なぜなら、鳥取市監査基準は、総務省案と同様に、「監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること」が「重要な点において」「認められる場合にはその旨」を監査の結果として記載することを求めています。したがって、上記第1段落は、次のように記載することが監査基準に従った記載になります。
『財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね適正に処理されており、重要な点において法令に適合し、正確に行われていると認められる。また、経済性・効率性。有効性においても、特段不合理なものは確認されず、重要な点において、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認められる。』
もちろん、監査基準に従って監査報告を作成している監査委員も存在します。滋賀県監査委員が令和5年12月1日付けで公表した監査報告は、「5 監査結果」の冒頭を次のように記載しています。
1から4までの記載事項のとおり監査した限り、重要な点において、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めていることが認められた。
なお、一部において次のとおり是正または改善すべき事項が認められたので指摘する。
<まとめ>
以上述べてきたことをまとめておきます。
総務省監査基準案は、地方自治法の規定を踏まえて、①被監査組織の3E意思を点検すること、②定型文でその存否を報告すること、を監査委員に求めている。
3E意思を点検する3E監査は、公的資源に活用度向上の余地がないかを点検する監査であり、執行事績と規範とに乖離がないかを点検する監査とは異質である。このため、3E監査に取り組んでいない監査委員も存在し、それを監査報告で表現している監査委員も存在する
3E監査には財務以外を監査することも不可欠であり、4項監査で2項監査も行えるようにしておく必要がある。
監査基準案が提案している、監査結果を定型文で報告する規定は、その意義が乏しく、提案を却下している監査委員も少なからず存在している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
