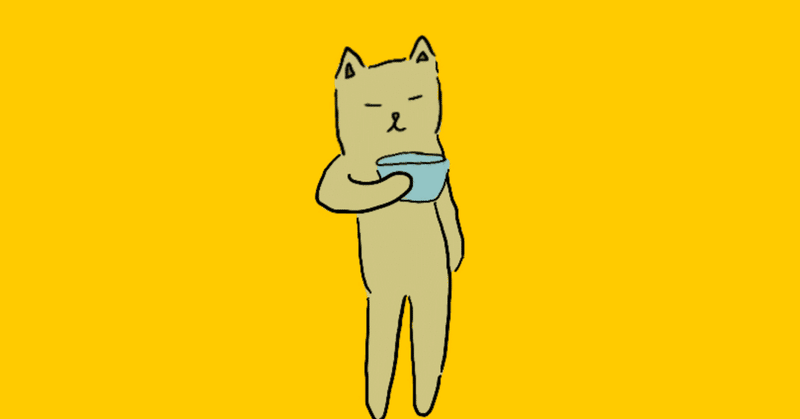
2016年か17年だったと思う。マレーシアに住んでいた私は、夜になると窓を閉めてエアコンに切り替えた。
寝巻にしているTシャツで、ベッドに横になり、パソコンを置くとYoutubeをスクロールした。
それまでにも、いくつかスタンダップコメディーを見ていたから、きっとおすすめに上がっていたのだと思う。
インド系らしい、パーカーを着た男性がマイクの前に立っている動画が出てきた。名前を聞いたこともなく、まったく知らない人だったから、特に期待もなかった。
Hari Kondabolu。
5分ほどのクリップを見る。
私は、ひっくり返るほど、衝撃を受けた。
初めてこんなものをみた。
彼は、人種差別をスタンダップのネタとして扱いながら、差別「する」ものを笑う作品を作っていた。ひっくり返しだった。
天才だ、と思った。
ーーー
私は、スタンダップコメディ全体に詳しいわけではなく、以下は、私の個人的な感想である
ーーー
それまでにも、人種差別を扱うスタンダップコメディをみたことはあった。それらの多くは、ステレオタイプに依拠した笑いだった。
すべてそうだったかは分からないけれど、十年以上前は、このタイプが多かったのではと思う。
〇〇人ってこうだよね、というもの。言葉を真似してみたり、動きを真似したり。他者からみた「〇〇人」という像を、コメディアンが表現する。
ーーー
その日本人版ー日本人って〇〇だよね、をみたことがある。
設定としている聴衆は、非日本人だろうから、私に響かないのは当然だろうけれど、面白くなさは、それによるのではない。
このタイプの笑いは、笑われる対象が、〇〇人であろうが、ある種の集団であろうが同じことで、「自分たちと違う」誰かを仕立て上げることによって成り立つ。
コメディアンと聴衆(マジョリティーを想定している)は、一体感を持った「私たち」となり、特権的にナラティブを握る。
異なる文化や習慣をもっている「他者」が笑われる対象だ。
「他者」の言葉や行動に違和をおぼえるのは、相手側の文化を知らないことによるのだが、それは無視される。
「他者」を知ろうとしない時、それを理解できない自分の無知によるものとは認めない。その齟齬を、相手に押し付け、相手が「変」だと笑うのだ。
〇〇人はこうだ、〇〇という集団はこうだ、という笑いは、対象を「他者化」し、自分を「標準」とする傲慢さをさらけ出す。
ーーー
このような笑いが終わりを迎えつつあるのは、「ポリティカリーコレクトが強すぎるから」ではないだろう。
「多様性といわれ、自由なことが言えなくなってなんでも批判される」ということではなくて、構造が見えた人にとっては、そんな笑いが「面白くない」ということと思う。
構造を見抜くのは、まずは笑われる側だろうが、その波は広がっていく。
私の知る範囲でも、スタンダップコメディーにおいても、英語のイントネーションを強調して、移民や外国人を笑ったり、特定のグループはなんとかだ、みたいな笑いは、すたれていってると思う。
面白いものがポリティカリーコレクトや「言葉狩り」によって規制されていった、のではなく、昔は面白いと思われていたものが、今となっては「面白くない」のだ。
王様が裸だということが分かった時、その王様の指の先に、誰かを笑う気がするだろうか?
倫理や道徳の問題ではなく、王様の知性の限界を感じないだろうか?
もう、その王様についていきたくないと、思わないだろうか。
ーーー
さて、ハリ・コンダバルに戻る。彼の両親は、インドからアメリカに移民としてやってきた。ハリ自身は、NYのブロンクス生まれ、ブロンクス育ちで、多様な文化が当たり前の環境で育ったという。
ハリの笑いに衝撃をうけたのは、彼が、どちらを笑う対象にしたか、ということに気づいたからだ。
私はそれまで、それほど鮮やかに「差別をする人」を笑ったスタンダップコメディーをみたことがなかった。
ーーー
しばらくの間、彼の名前を検索し、たくさんの動画を見た。それからSpotifyで彼のスタンダップコメディのアルバムをみつけ狂喜した。
一年ほど、毎日のように聴いていた。車にのるとき、眠る前、ご飯を食べながら。
他の人はそうでないみたいだから、私の変なところなんだろうけれど、同じ喜びに執着する。
食べ物、飲み物もそうで、同じ店に行って同じものを注文し続けるし、音楽も同じものを1年とか聴き続ける。
1年もすると、ハリのアルバムは、内容をおぼえるどころか、次に何を言うか、観客がどう笑うかまで、全部、先に分かっていた。
私は、毎回同じところで笑う。
毎回、すごいなあと思った。
尊敬と憧れの気持ちが胸にあふれた。
批評性、知性。
ーーー
彼のアルバム「Mainstream American Comic」と「Waiting for 2042」が大好きだ。
それらは、もうSpotifyでは聴けないけれど、この記事を書くにあたり探したら、「All Lives DON'T Matter」の動画があった。「Black Lives Matter」のムーブメントの頃の話だ。
もちろん、アルバム全部がいいけれど、これだけでも雰囲気が分かるかな。
「抽象概念のメリッサ」という架空の存在までつくり、ラストのカタルシスに持って行くのは、天才の技と思う。
※ もう一人、同じころに大好きになったスタンダップコメディアンにAamer Rahmanがいる。彼のことは、別の機会に書くかもしれない。
私は、そのあと、Ronny Chieng, Jimmy O. Yang, Ali Wong など、アメリカで活躍するやはりアジア系のすばらしいコメディアンたちを知るようになる。
この話は、また書こうと思う。
いつもありがとうございます。いま、クンダリーニヨガのトライアルを無料でお受けしているのでよかったらご検討ください。
