
山下 大祐 超望遠ズームM.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 ISで撮る鉄道写真
望遠レンズをよく使う鉄道撮影に、さらに変化を与えてくれるのが超望遠の世界。望遠と超望遠の明確な境界はないが、35mm判換算400mm程度以上のレンズは、たいてい超望遠レンズと呼ばれる。このほどOM SYSTEMに加わったM.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 ISは、35mm判換算300-1200mm。超望遠域が格段に広いことがわかるだろう。テレ端の600mmはOM SYSTEM最長の焦点距離だ。
この個性が立ったレンズを鉄道撮影で使うと、どんな変化をもたらしてくれるのか。ワクワクしてロケに出た。
迫力!超望遠の世界。咄嗟の構図変更にも対応

600mm(35mm版換算1,200mm)
全長約400メートルの16両編成がぎゅっと圧縮される換算1200mm画角。開放絞りF6.3は、この画角クラスでは相当明るく、フェンス越しでも影響が少ない。
京都で訪れたのは東海道新幹線を上から撮ることができる跨線橋だ。ここは京都駅を発車した上り新幹線が、下り坂でぐんぐん加速していくところを正面がちに撮ることができる。関西出身の私も高校生の時からよく知っている撮影地である。
奥のカーブまでの距離は600メートルほど。非常に遠い距離からの撮影となるため、電化設備などの障害物が手前に写ってくるのをカメラ位置を少しずつ変えて一番良い位置を見つけるのがポイント。フェンス越しでの撮影なので、フェンスは大きくぼかして目立たせないようにしたい。そのためにもレンズ前端をフェンスに極力近づける必要がある。今回のレンズは手持ちで狙いを定めてこれらの吟味ができセッティングが早かった。また開放絞りがF5.0-6.3と、この画角では口径が大きく、フェンスぼかしに一役買っている。

548mm(35mm版換算1,098mm)
粘っていると狙い通り上下の列車がすれ違う瞬間が。咄嗟に横位置、そしてズームで画角調整。ズレたピントはAF任せでOKだった。こういう向かってくる列車に対しては、カメラ・レンズともOM SYSTEMのAFに抜け目はない。
この撮影地のハイライトは2本の列車がすれ違う瞬間だろう。時間に正確な新幹線とはいえ、やはり先述したように障害物も多いため、こちら向きの新幹線の先頭部がクリアに見えるところですれ違ってくれることはそう多くない。その瞬間が来た時に確実に撮るために、縦横や画角の想定はしておこう。AFは被写体認識「鉄道」にして大きめのターゲットにしておくと安心だ。
想定したカットが撮れたので、ちょっとエッジが効いたものも撮りたくなった。経験上、想定したカットよりこういう時に撮った写真の方がのちに作品となることが多い。そうして撮ったのが以下の写真。

229mm(35mm版換算458mm)
暗闇からぬっと出てきた新幹線の顔を、黒バックにしてしっとりとした白のトーンで表現した。
京都駅のほうに向けていたレンズを反対のトンネル出口に向けて、逆方向の列車を撮ってみた。トンネル出口という条件とその日の天候もあって、ローキーに撮ると車体の白だけに露出が残って印象的に見えたのだ。他に情報を入れないために、顔を縦に切ってでも画角を広げすぎないようにした。微妙な画角調整はズームレンズであるがゆえの特権だ。

1,200mm(35mm版換算2,400mm)
テレコンバーターMC-20をつけた換算2400mmの画角。アーチ橋の中を通るモノレールを500メートル離れた駅から撮影した。肉眼では見逃してしまうほど小さくしか見えない出来事が、目の前に展開された。
空気感を伝える描写力。柔らかいボケ

637mm(35mm版換算1,274mm)
凍えた朝の大地を陽の温もりが溶かしていく。そこに国鉄型の気動車が現れた。M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 ISは超望遠域のズームレンズでありながら、柔らかい逆光に包まれた現場の温もりさえも、そのまま写真にし伝えることができた

636mm(35mm版換算1,272mm)
少し引きつけてから縦位置に変更。コントラストの低い逆光線の遠景も自然な濃淡で描写できた。
兵庫県の北条鉄道には、国鉄が製造した車両がJR時代を経たあとここにやってきて活躍している。国鉄車両の普遍的なデザインを保っており、鉄道ファンに愛され続ける車両だ。さぁ超望遠でその表情を捉えてみたい。日の出前、ちょうど良い直線が見つかったので、ススキの茂みの配置と線路の角度が良くなるようにカメラをセット。背景を限定するため600mm以上欲しいということになり、MC-14を入れて少し焦点距離を伸ばした。光が奥までまわった頃、排煙をたなびかせて坂を登ってきた国鉄型車両。奥から手前まで、要所要所で構図を変えてシャッターを切った。その間、カメラのAF制御にきちんと追従したレンズ。撮れた!という実感に満たされた。

342mm(35mm版換算684mm)
上の写真と同じように、逆光に包まれたコントラストの低い条件でも被写体を検出してAF撮影できた例。高輝度の部分が画面に入っていても、目立つようなハレーションはなくうまく抑え込んでいる。
隅々まで解像感ある光学性能

200mm(35mm版換算400mm)
鉄橋の直線を基調にした構図。歪みの少なさが応えてくれた。また解像感も期待以上で、鉄橋のリベットの凹凸まで確認できる。遠景のロングショットにも安心できる解像性能だ。
写真の解像度はレンズの性能に依存するところが大きい。いくらハイレゾショットなど高解像機能があるとはいっても、レンズの解像感が甘ければ元も子もない。そこで新レンズM.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3の解像力にも注目したいところ。山の上から海の一部を切り取って撮影した作例をみてほしい。四隅まで像が流れていないのも確認できるが、鉄橋の錆びつきやリベットまで、小さいところにしっかり情報が描写されている。白波の立体感も損なわれていない。
手持ちで撮影できることがOM SYSTEMの所以

358mm(35mm版換算716mm)
直進ズーム操作にも対応したグリップ感のあるレンズのため流し撮りも特に難しくない。作例はライブND(ND4)を併用した流し撮りである。レンズ内にも手ブレ補正機構のある“IS”レンズだが、カメラのS-ISモードを流す方向に応じて設定している。
ボディとのシンクロISの手ぶれ補正効果は、ワイド側で7段、テレ側で6段。通常はとても手持ち撮影などできない超望遠域だが、このレンズは例外。OM SYSTEMの機動力を損なうことなくバリバリ手持ちで使うことができる。ただ同じ撮影倍率だったとしても、望遠レンズと超望遠レンズとでは、やはり超望遠レンズのほうが被写体を捉える難易度は上がる。ファインダーを見る前に、被写体付近の目標となる背景なども確認しておくほうが良いだろう。
OM SYSTEMの多彩な機能に対応

600mm(35mm版換算1,200mm)
プロキャプチャー連写SH2も使用可能である。手持ち撮影ではファインダーを覗きながら構えることが多い。そんなときもプロキャプチャー機能はとても有効だ。
※SH2:AF追従連写、ブラックアウトフリー
深度合成をはじめ、OMの多彩な機能にも対応する。アップで撮影する機会が増える超望遠域だけに、プロキャプチャー連写などは使うことも多いだろう。PROレンズに使い慣れたユーザーでも使い勝手に差が出ないような仕様になっている。

840mm(35mm版換算1,680mm)
満月の月の出。一年前、ここに写っている駅から満月と列車を撮ったときに思いついたアングルだったが、同じ方角に月が昇ってくる一年後に撮ることができた。レンズの試用時期が重なったのは幸運だった
超望遠レンズは面白い。肉眼の視野の中で小さすぎて気に留めていなかった出来事にスポットライトを当ててくれるのだ。上の写真を撮った時も、道ゆく人は私がカメラを構えているのを見て何を撮っているのかと不思議そうにしていた。遥か遠くで月が出ていて駅と重なっている状況は、見ようと思えば見えたはずなのに、道ゆく人には小さくて見えなかったのである。圧縮効果とか遠近感の喪失とか言ったりもするが、レンズで被写体の位置関係が変わるわけではなく、あくまでそれは自分のポジショニングである。小さな出来事の発見を大切にしつつ、M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 ISの利便性と光学性能を活かせればまさに鬼に金棒。いつもの鉄道写真が大きく変化すること間違いなしである。
使用した機材
カメラ:OM-1 MarkⅡ
レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS
テレコバーター:MC-20、MC-14
筆者紹介
山下 大祐(ヤマシタ ダイスケ / Daisuke Yamashita )

1987年兵庫県出身 日本大学芸術学部写真学科卒業
幼い頃からの鉄道好きがきっかけで写真と出会い、今度は写真作品制作の舞台として鉄道と関わるようになる。幾何学的な工業製品あるいは交通秩序としての鉄道を通して、人や自然の存在を表現しようと制作活動を行なっている。
業務では、鉄道会社のライブラリ、車両カタログ、カレンダー、CM撮影などに携わるほか、鉄道誌、カメラ誌等で撮影・執筆を行う。
OM SYSTEMゼミ講師、日本鉄道写真作家協会(JRPS)会員
2018年 個展「SL保存場」富士フォトギャラリー銀座
2021年 個展「描く鉄道。」オリンパスギャラリー東京・南森町アートギャラリー
ウェブサイト:http://www.daisuke-yamashita.com
SNS: https://www.instagram.com/yamadai1987/
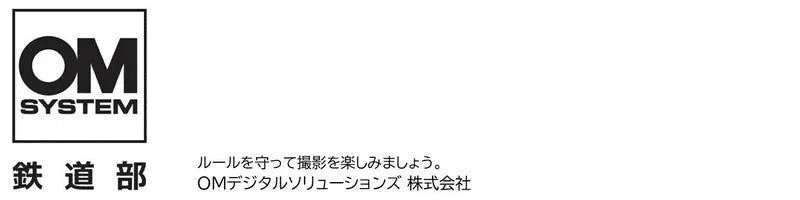
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
