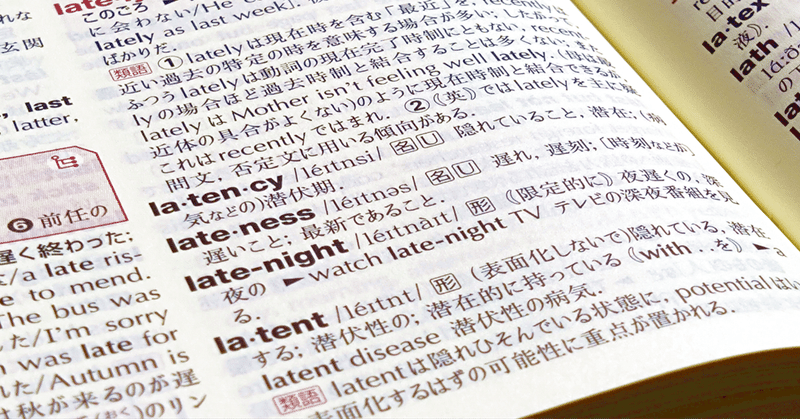
レイテンシーと「差延」について

「Dr.レイテンシー」というハンドルネームが登場したのは『燕石博物誌』でのことだ。メリーの思いつきで始まった、幻想の奇譚を扱う博物誌の執筆。その著者、蓮子とメリーというユニットのハンドルネームとして、蓮子が提案したものであるらしい。レイテンシー(latency)とは、
転送要求を出してから実際にデータが送られてくるまでに生じる、通信の遅延時間。
通信処理やデータ処理が実行されてから、実際に処理が反映・終了するまでの時間差のこと。IT・デジタルの世界では「遅延(時間)」を指すケースが一般的。
CPUなどがデータの要求をしてから、実際にデータが転送されるまでの時間。遅延時間。コンピューターシステムの性能指標の一。
など、一貫して通信におけるデータ転送の「遅延」を意味している。遅延という時間的なずれ、時間的差異である。ここではレイテンシーが意味する「遅延」と、それを取り巻く二通りの考察を描き出してみたい。
レイテンシーについて
ここで言葉遊びにも似た、ある一つのことを指摘しておきたい。それは「遅延」というのが本来的に「何に対して遅れているか」を指示していることだ。当然のことであるが、遅延という言葉を使うときに、人は「何に対して遅れているか」を明に暗に意識する。ある時間t₁に対してt₂が時間的に後である場合、t₁に対してt₂は「遅延している」し、t₁はt₂にとって「遅延の対象」である。t₁がなければしたがってt₂は「遅延している」とは言い難いし、t₂がなければそもそも「遅延するもの」がない。ここから、遅延という出来事が他の時間との関係によって成り立つのだということがわかる。遅延とは、その実相対的であること、相関の上でのみ成立するという条件を含み持つ。

これはちょうど「差異」についても同様だ。差異とはある根源的なところにある、物と別の物とのあいだに発生する「違い」のことをいう。犬と猫は違う、機械と生命は違う、囲碁と将棋は違う、携帯用ゲーム機と据え置き機は違う、宇佐見蓮子とマエリベリー・ハーンは違う……挙げればきりがない自由連想だが、「差異」とは無数の名辞に、さらに無限の関係を指摘することで生まれる、汲めども尽きぬ性質を持つ。
しかしわれわれの言語活動に「差異」だけが存在しているかと言われれば、それは違う。父方の祖母と母方の祖母を同じ祖母という括りに入れることがあれば、携帯用ゲーム機と据え置き機を同じゲーム機として扱うこともある。絵画と彫刻、音楽や演劇はまとめて芸術と呼ばれるし、クソガキだった頃の私、いくらかませた頃の私、今の私を「同じ私」として認識することもある。本来なら異なる点ばかりが目につくはずのこれらの「差異」に対して、人は同じさという観点から「同一性」という目印をつける。
「差異」と「同一性」はそれぞれ対照的な概念だ。差異のほうからすれば同一性による規定ほど粗雑で無根拠なものはなく、同一性のほうからすれば差異の体系はあまりにもとりとめがない。
宇佐見蓮子にとってのレイテンシー
遅延、そして差異と同一性の話はまた後で言及するとして、レイテンシーの議論に戻ろう。レイテンシーというネーミングについて、蓮子はこう言っている。
「量子の隙間に潜む世界を見る博士だもの。ぴったりじゃない。男女も判らない、西洋っぽくも東洋っぽくも感じるし」
レイテンシーがなぜ量子の隙間に潜む世界を見る博士にぴったりであるのか、蓮子の意図は知り得ないが、ちょうど「遅延」の考察を見て、それが常に二つのものの関係性でそうであったように、奇遇にも量子力学には「二つであること」という中心的で切り離せない性格がある。
・量子が持つ粒子と波の二重性、相反する二つの性質を持つ量子特有の現象。いわゆる重ね合わせの原理。光子や電子といった量子が、粒子であるとともに波であるという事実──ニールス・ボーアはこれを相補性と呼んでいる。
・また量子力学では状態を表すときに、すべての量子をセットで考える。そしてセットで表された状態が一般に複数、共存する。これをエンタングルメントと呼ぶ。「エンタングル」という語を初めて使ったのはアインシュタインの側についたシュレーディンガーであったようだ。
・さらにエンタングルメントの効果を利用して離れた場所に量子状態を転送する手段に量子テレポーテーションがある。これは一方の量子状態が判明すればセットの量子の状態が判明するという現象をテレポーテーションに例えたもので、テレポーテーションに有する時間は瞬時とされる。
いずれも量子力学を象徴する出来事であるが、これらがいずれも「二つであること」という事実を共有していることは、一つの事件とも表現できる。重ね合わせ──相補性、エンタングルメント、量子テレポーテーションはいずれも古典物理学の観点からは説明のしようがない、直感に反する結果を示している。
奇しくも、秘封倶楽部は絶えず、始終、止めどなく二人でなされる。「二人でいること」、あるいは「絶えず複数であること」は、二人にとっては、ただ二人であること以上に特別な意義を持っているに違いない(二人でない秘封倶楽部もあるようだが……)。
そして量子テレポーテーションにおいては、それに有する時間が一瞬であることから、量子情報の転送にわずかな「遅延」も含み持たないという事実がある。これは非常に興味深いことだ。このことを鑑みると、蓮子にとってレイテンシーというネーミングが一つの言葉遊び、いや、意図された皮肉であったことが明らかになる。量子テレポーテーションにおいては、量子間の遅延は存在しない。時間差は0であるからだ。レイテンシーは「遅延」を意味する。遅延は存在しない。ゆえにレイテンシーは存在しない。
「差延」について
レイテンシーというネーミング自体に、レイテンシーその人の虚構を暴く意図が暗に示唆されている。レイテンシーは存在しない。そのことがわかったところで、差異と同一性の話に戻ろう。

いわゆる犬と猫、機械と生命、囲碁と将棋、携帯用ゲーム機と据え置き機……これらの差異は、空間的差異として改めて問うことができる。差異とはすなわち別の空間にあるものとの差異であって、人は空間的に同じ位置にあるものを差別化しない。空間的に同じ場所にあり、空間的に同じ形相をしていた場合、それには同一性が見出され、それらは同一者として扱われる。
遅延がt₁とt₂の関係にあったように、差異とはある名辞と別の名辞の関係にある。逆に言えば、名辞が意味するところは別の名辞との差異が決定している。犬を定義するとき、最もわかりやすいのは「……ではない」という形での定義だ。犬は猫ではない、トンボではない、クジラではない、サルではない、シロクマではない、アザラシではない、シカではない……というように。定義するということは、固定化そのものを意味する。それは同一性への固定である。
さて、具体例を挙げながら迫っていこう。すなわち「差延」とは何であるか。「AはAである」あるいは「A=A」という命題は、そのまま任意の名辞AがAと同一であることを示している。当然、これはあたり前のことだ。しかしここで、フランスの哲学者ジャック・デリダは待ったをかける。これもあたり前のことであるが、「AはAである」と人が言うとき、前者のAと後者のAは同時的に発声されることはない。同じく、この命題を黒板に書いたときにしても、前者のAと後者のAは同時的に書かれない。これは然るに、前者のAと後者のAのあいだに存在する時間的差異、遅延であるが、デリダはこれを「差延」と呼ぶ。
なぜこんな些細なことに注目しなければならないのか。それは、前者のAと後者のAのあいだに発生する時間的差異は、そのまま空間的差異として展開されるからである。確かに、前者のAと後者のAが同時に発声されることがあれば、それは真に同一性そのものであったに違いない。なぜなら両者のあいだに発生する差異の関係などなかったのだから。厳密に自己同一的な現在は、そのまま時間の死を意味する。事実として、前者のAと後者のAは異なっているために、前者のAと後者のAのあいだに発生する差異は無視できない(ここでホーミーなら可能ではないかと考えた人は、発想はともかくとして、ぜひがんばってほしい)。
現在は、過去の痕跡と未来への移行の運動をはじめから内含するかぎりにおいてのみ、つまり時間的な差異化の運動、差延の運動の一契機であるかぎりでのみ、現在でありうる。ようするに差延とは、空間的差異であれ、時間的差異であれ、ともあれ差異を生み出しつづける運動なのである。デリダはこうした様相を「差異の戯れ」と表現するが、あらゆる同一性に則った決定や固定化も免れることのできない根源的な偶然性、予見不可能性、決定不可能性を表している。「差異の戯れ」とは、もろもろの抹消不可能かつ決定不可能な仕方で、つぎつぎに生まれつづける差異化の運動である。

差異化が行われると、具体的に何が起こるのか。差異化が行われると、まずあらゆる同一性が解体される。ここでは二通りだけ述べておくことにしたい。一つ目は──どうもイメージがつかなければそれでも構わない──人間の主体、「私」という人格の同一性の権威への異議申し立てである。「私」という象徴は、一つの固定化された対象であるが、それは幼少の頃の私、青年期の私、大人の私、今の私が、それぞれまったくの別物であるという事実を隠蔽しにかかる。「私」が通時的に同一性を保っているというのは、まったくの幻想でしかないことを差異化は暴き出す。
二つ目は、意味のイデア的同一性の解体である。これはそのまま、名辞が持つ同一性の解体を意味する。絶えず発生する差異化の運動によって、同一性のヘゲモニーはその効力を失う。時代とともに意味が変化した言葉は、数え上げれば枚挙にいとまがない。そして差異化=差延の運動に晒されているいまも、その影響を無視することはできず、常に移行の途上にある意味内容の上で、われわれは言語活動を敢行しなければならないというのが、言語の宿命なのである。
「差延」は、そのまま空間的差異と時間的差異を生み出す根源的な運動であり、諸差異の産出の運動を表す。あらゆる同一者は、他者との差異においてのみ、またそれ自身の反復においてのみ同一なものとして構成されるのであり、この差異、さらに差異化運動の反復、すなわち「差延」の運動に先立つあらゆる同一者は認められない。あらゆる同一者とそれに伴う同一性は、「差延」の一効果であり、「差延」のシステムのうちに書きこまれた一効果である。
いかなる同一者も現前しない、つまりその場に現れないのは、「差延」が他者(差異の対象)への関係を持ちこむことによって同一者の現前を無限に延期するからだ。こうした「差延」が持つ根源的性質は、そのまま根源の不在を意味している。なぜなら、そこにあれば、それは根源に同一者を想定することになり、それでは差異化の運動は発生しないどころか、時間的な死を意味し、すべてが時間的に静止した世界になるからだ。当然、そんなはずはないというのが正しい結論のはずで、現にわれわれの世界は、あらゆる意味の交換や移行が行われることのないような、静止した世界ではない。そのために、世界が動き出すための条件とは、そこに空虚を設置すること、そこに据えられた「差延」の肯定であるのだ。
レイテンシーと「差延」
「遅延」の話に戻りながら、レイテンシーが含み持つ「差延」という意味について考えてみよう。遅延とは、そのまま他との時間的差異を意味していた。
時間的差異は、そのまま空間的差異につながる。例えば、口で話された発話行為による言語は、話されると同時に消失する。それは瞬時に相手に伝達されるので、発言の意図や受け取った側の解釈のあいだに誤りが生じることは少なく、したがって差異は発生しにくい。しかし、黒板に書かれた文字による言語は、発話によるそれと異なり、書いた瞬間からいつまでも残り、のちには嘘として現れる。
書かれた文字。例えばある男は、近所のスーパーに買い出しに出掛ける意図を以てメモに「スーパーに買い出しにいってきます」と書いて机の上に添える。それを見た人は、彼がスーパーにまで出掛けたことを知るが、当の本人は、そこでスーパーが休業日だったという事実を知り、商店街のほうまで赴く。商店街で買い物を済ませると、偶然にも旧友と出会い、つい喫茶店で話し込んでしまう……。
この時点で書かれた文字と現実のあいだには大きな差異が発生している。時間は、駆動する差異産出の機械であるとともに、差延の運動そのものといえる。それはちょうど文字の記述による現実の根源的な偶然性、予見不可能性、決定不可能性を意味している。まさしく差異が「戯れ」るかのように、そこにはあらゆる流動性が含意されている。
「遅延」は時間的差異を発生させるが、それは偶然性、予見不可能性、決定不可能性そのものである。「遅延」とはすなわち「差延」であり、「差延」はそのまま時間的差異であれ空間的差異であれ、諸差異を生み出しつづけることで、一見素朴に認められるような同一者と同一性に対して反駁し、その根拠の軽薄さを事実としてつきつける。
「遅延」と「差延」は、いずれも差異を産出する運動であった。「遅延」は端に時間的差異のみを生み出すだけかと思われていたのが、ここにデリダの「差延」を導入することによって、対象となる差異の性質に、新たに空間的差異を加えることになった。
レイテンシーは、時間的差異としての「遅延」であるとともに、空間的差異も同時に生成する根源的運動としての「差延」であるといえる。レイテンシーは、量子の隙間に潜む世界を見る博士だ。現実とは異なるもの、メリーが垣間見た別世界は、蓮子によって「別のブレーンワールド」として指摘されている。
「妖怪はどこに消えたのかなぁ、と考えていたらね、見えて来たの。今も妖怪の棲む世界が」
「それってもしかして、別のブレーンワールド……」
「何それ」
「物理学者にしか見えない世界の一つよ」
ここで言及されているのは、超ひも理論による多元宇宙論であろうか。超ひも理論では、世界を九次元のものとして扱う。超ひも理論には五種類のバリエーションがあり、それぞれⅠ型、ⅡA型、ⅡB型と二種類のヘテロティック弦理論と呼ばれるが、さらにこれらを統一する企てとしてM理論がある。M理論は十次元の超重力理論をヒントに、世界を十次元(時空間で十一次元)のものとして扱う。超ひも理論では一次元の「ひも」だったものが、M理論においては一つ次元が追加されることによって二次元の「膜」になる。
超ひも理論では、三次元足す時間の四次元時空であるわれわれの世界を、ブレーンワールドと呼び、五次元目以降の次元をバルク空間と呼ぶ。この理屈であれば、バルク空間の中にわれわれと異なるブレーンワールドが存在していることは容易に想像できる。蓮子のいう「別のブレーンワールド」とは、そうした意図のもと言及されたものだろう。
さらに、多元宇宙論には超ひも理論に関連したものだけでなく、他にも様々なものが提唱されている。その一つにエヴェレットによる量子力学の多世界解釈を挙げることができるが、この立場は、宇宙や世界全体が瞬時に分岐すると主張する。別世界の存在を肯定するSFのような世界を必然なものとして捉えているようだ。
一見「差異」とは関係がなさそうな物理学の理論に対して、こういう表現が取れるのではないか、と思う。超ひも理論による多元宇宙論も、エヴェレットによる多世界解釈も、ほぼ無限に広がる別世界とその諸相を認める。それはちょうど、「差延」が言語にもたらす差異化の運動と結びつくようだ。デリダによる文学色の強い哲学と、理論付けられた物理学がその見解において一致しているなどと生意気なことをいうつもりはないが、やはり無視できるものとは思えない。
「差延」は、諸差異を産出する運動である。そして蓮子による別世界の示唆も、文脈上それと無関係ではいられない。レイテンシーは「遅延」であるとともに、差異の産出運動としての「差延」でもあり、最も力強い「差異の肯定」の体現者である。差異を肯定することはそのまま「他者」を肯定することにつながる。差異のあらわれとは他者のあらわれに他ならないからだ。
その上で、「別の世界」はそのまま他者そのもの、差異そのものを意味する。絶えず分裂する世界で、他者である別世界を肯定する、根源的に差異を肯定する運動。レイテンシーの意味に込められたのは、たんなる「遅延」であるはずがなく、「絶えず二人であること」だけでもなく、別世界の可能性の肯定であり、他者の肯定の原理、根源的な他者の肯定にこそある。
参考文献:
高橋哲哉『デリダ』(講談社学術文庫)
岡本裕一朗『フランス現代思想史』(中公新書)
千葉雅也『現代思想入門』(講談社現代新書)
松浦壮『量子とはなんだろう』(ブルーバックス)
和田純夫『量子力学の多世界解釈』(ブルーバックス)
大栗博司『大栗先生の超弦理論入門』(ブルーバックス)
『燕石博物誌』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
