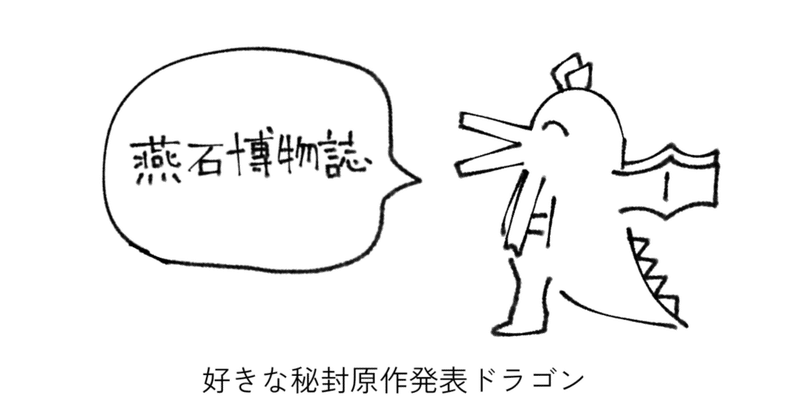
補論──(相対性)精神学についての試論
精神とは何か
『日本的霊性』において、鈴木大拙は「精神」という語について次のような指摘をしている。精神という語は、一般に心と同義とされるが、たびたび多義的な扱われ方もする。そのために、それが真に意味するところをめぐってわれわれは迷わされるかのようですらある。
精神は意志、注意力を意味する文脈で使われる。その一方で、「日本精神」とか「日本的精神」においては使われ方が異なっている。意志や注意力と「日本精神」「日本的精神」とが同じ「精神」によって結びつくはなんともおかしな話だ。なぜなら、意志や注意に「日本だの支那だのユダヤだのというのはない」のだから。
それでも、精神は一般に心を意味している。精神は、心、魂、物の中核ということであるが、しかし魂が必ずしも精神に相当しないこともある。心においても、それは同様だ。「武士の魂」と呼ぶとき、それは「武士の精神」とか「日本精神」という場合とではいささか意味が異なっている。この場合では、魂は具体性を帯びていて、それに比べて精神は抽象的であることに気づく。それは魂が訓読みで、音読みに由来する精神とは相容れぬことにあるのかもしれない。魂というと、何かしら玉のようなものがそこに転がっているように感じるが、精神においては実体を思い浮かべることができない。「時代の精神」ということがあるが、これが「時代の魂」だと然るような感じを与えない。
それに、精神を心と同一視して良いというわけでもないらしい。精神科学は必ずしも心理学を意味しはしないし、「立法の精神」はそのまま「立法の心」で済ますことはできない。この場合、精神には心とは別に、主張、条理、筋合いというものも含んでいることがわかる。
「日本精神」はまた倫理的な意味合いを持ちえる。日本精神というときの精神は理想を意味するが、理想はいつも道義的な根拠に依らなければならないからだ。
例えば人は、縁側で涼しげに鳴る風鈴を見て、ししおどしを見て、雄大に広がる枯山水を見て、その風流な光景に日本的な精神を感じる。また夏に回る扇風機、キンチョールを前に感じるのは、やや近代化されたにしても、日本的精神には違いない。この場合の精神は、倫理や理想とは異なって、風土や文化と言うことができる。
「精神的」などというときには、物質的なものと対照的な位置にあるものを指すことが多い。それは必ずしも宗教的なものとは限らないが、物質的なものとは対比して扱われる。それには心や魂、意識や自我、意志や注意力、理念や理想、風土や文化といったものを挙げることができる。
「精神家」といえば、それは形式ばらない人であったり、豊かな思慮深さを持つ、節操や気概に富む人を意味するだろう。ちょうど短絡的に「物質」を消費する人間とは裏腹に、何が重要であるかを真に理解している、そんな高尚な精神の持ち主を想像させる。
「精神史」であれば、文化史と同意義にとられる。人間が自然から離れて、あるいは自然の上に加える、また自然とともに織りなす人間的工作の全般を精神史の対象とする。思想史が、人の書き残した書物や活動についての研究であれば、精神史や文化史は範囲としてはより広大であると言える。
鈴木は、精神が持つ特徴を軒並み挙げた上で、それを貫く一つの本性を、次に引用する箇所で指摘している。
精神は、物質と相容れないことはもちろん、二分されたものの側面であると言うことができる。物質に対して優位にあることで、精神は自らを確立するのだと言える。物質的な特性と真っ向から張り合い、これを退けること、それが精神の条件であるのだ。物質と精神の両者を包むものがあるとすれば、それは自然である。物質と精神という二元的な枠組みがあったとして、それが二元的なものとして生起する、その根源にある一元的なものを、人は自然と呼ぶ。そうした限りにおいて、物質と精神という区分、あるいは精神そのものは、反自然的な生起物なのである。
つまるところ、精神が話されているところ、それは必ず物質と、何かの形態で、対抗の勢を示すようである。すなわち精神はいつも二元的思想をそのうちに包んで居るのである。物質と相剋的でないとすれば、物質に対して優位を占めるとか、優越感を持つとかいうことになるのである。精神は決してその中に物質を包むということはないのである。まして精神が物質、物質が精神だとかいうような思想は、精神の側からは決して言われぬのである。精神が物質と睨み合いをしない場合には、前者は必ず後者を足の下に踏みつけて居るのである。あるいは踏みつけてやろうという気合いを明白に面に現わして居るのである。二元的思想のないところには精神は居ないと謂ってよい。此処に精神という概念の特異性を見出すのである。
精神学の見取り図
「精神学」というフレーズは、われわれに何を想起させるだろうか。そこに含まれる精神という語から、「心理学」と結びつけるのが最も自然だろう。しかし、「精神学」がそのまま心理学の領野に収束するかと言われれば、それはことを定めるにはいささか性急であると言わざるを得ない。精神学をめぐる事態は、簡単ではないのだ。語に忠実にしたがうならば、最も近いのは「精神医学」であると言える。それに、先に紹介した、フロイトに端を発する「精神分析学」も、精神という語がそのままに含まれる点、無視することはできない。さらに、このように「精神──学」と表される領野となると、これらに加えて「精神病理学」も挙げることができる。それに対し、やや趣向を異にして「神経科学」や「脳科学」を考えることも可能だろう。この二つが検討するのは厳密には心でも精神でもなく脳であるが、心脳同一説に則って同じものとして図ることもできる。
また、心そして精神を対象とする領野には、これらとは別に「哲学」を挙げずにはいられない。先にいくつかの紹介を経たが、哲学に身を置きながら心を主題として論じる分野に「心の哲学」がある。近年は特に発展の目覚ましい認知科学の、脳としての心の解釈に対して、デイヴィッド・チャーマーズやジョン・R・サールといった哲学者は鋭い疑問を投げかけている。哲学では、人間が思考しうるものの次元を現象というが、一般に心や精神に並び立つこの領域を結びつけて、これを研究する分野として「現象学」を指摘することができるだろう。この運動の創始者エドムンド・フッサールや、弟子の関係にあったマルティン・ハイデガーなどによる現象学が著名であるが、精神学を考慮するにおいてこれを無視することはできない。
最後に、精神という語が独自に持ち得る意図を汲んで、精神を探求する学としての「神秘学」を挙げることもできる。ルドルフ・シュタイナーはこれについて神智学や人智学という名称も用いているが、これらも同様である。そして、一時は奇異の目で見られたこの思想にしても、いまや後期科学世紀での影響を無視して軽んじる輩もいないであろう。
このように、精神学をめぐる状況はきわめて入り組んでいると言わざるを得ない。さらに、精神学は、これらの領野をないがしろにして十分に語ることもできない。精神学は、これらの領野と、一見複雑なまでに錯綜した様相を呈する。それでいて、これらの領野とは明確に、おのれが棹さす潮流を異にするように、まったく別の思想的立場に自らを置いている。精神学では、これらの文脈とともに、これらの文脈にそって、絶えずこうした連関のもとで、思考を続けなければならない。
ここでは、先に言及した領野の中でも、主に心理学と精神医学に、次に哲学と精神分析学に言及しながら、これらとの関係のあいだで精神学の構築を図ることから出発する。またここでは、心と精神を、似て非なるものとして扱うつもりはない。同じものを指していると考えてもらって構わない。ここで描かれる精神学の肖像は、他の肖像との対比によって、ひときわわかりやすい形で理解されるだろう。
心理学の歴史
「心」──それは情動に生き、判断をくだし、自らを律し、そして成長する。日々をともに過ごすわれわれにとって、それは一つの親しみやすい対象でありながらも、同時にある種の不可解さを持ち合わせているかのようだ。人間の心とは何か、精神とは何か、あるいは人が考え、感じ、行動するとき、どのようなメカニズムに則って、それは起こるのか。心理学が主題とする「心」は、先に言ったメカニズムとしての心であると言うことができる。これは、哲学における心や、精神医学における心とは異なる。哲学や精神医学とは異なる主題のもとで、心理学における「心」は論じられる。また、神経科学・脳科学で検討される「脳」も、心と同値ではない。それに比べると、心理学の対象は、脳と社会のあいだに想定できると言える。そう考えると心理学が占める領域は想定よりも狭いように思えてくる。
哲学における心は、何か新しい理論を考えるために、その土台として整えるような対象であって、それがどう感じているかなど、そのメカニズム自体を問題にはしない。哲学における心とは、認識する主体である。それは正しい知識の獲得とか、あるべき認識の姿を検討する企てにすぎない。心理現象としての情動、発達の過程、錯視、心象などは、哲学としては意に介すことがない。認識、真理、知識の性質、起源、範囲といった知的活動の根拠付け、基礎付けこそ哲学が求める「心」であると言える。
精神医学における心は、治療の対象であって、心が平常時どうであるか、ということを主題にしない。精神医学の目的は、精神疾患に対して診断を下し、病気の内容を明らかにすることだ。そして、有効な手段を講ずる。具体的には、薬物療法や心理療法による治療が行われる。しかし最大の違いは、精神医学が目的とするのが患者の治療であるのに対して、心理学、とりわけ臨床心理学は患者の悩みや訴えに傾聴することを目的とする。
臨床心理学においては、「患者を治療する」という言い方をしない。カウンセリングを受けるのは「患者」ではなく「クライエント」であり、「治療」ではなく「援助」という言い方がなされる。臨床心理学が目的とするのは患者の治療ではなく、クライエントの援助であるのだ。臨床心理学で求められているのは、あくまで心理的問題を解決して、健康的な心理状態を取り戻すことではあるが、精神医学における「治療」とはまた異なったものだ。
心理学(サイコロジー、psychology)と精神医学(サイキアトリー、psychiatry)をそれぞれ分解すると、「psycho-logy」と「psyche-iatry」になるが、psychoとpsycheはいずれもプシュケー(psukhe、ギリシア語)を由来としている。そのために、日本における「心理─」と「精神─」の区別はどこから来たのかが問題として浮き彫りになる。原語においては区別されることのなかった心と精神は、どのようにして区別されることになったのか。
心理学の場合は維新前の一八二二年に刊行された「新修蘭日辞典」には「pneumatica」(現在のpneumatology、霊物学)の訳として「心学」という訳語が与えられていた。その後(七五年)には西周によってジョゼフ・ヘヴンという心理学者の著書「Mental Philosophy」に「心理学」という語を与えているが、ご覧のように、この時点で心理学はpsychologyを指しているわけではなかったようだ。psychologyに対しては西によって性理学という訳語が与えられている。訳語として「心理学」が定着したのは八七年ごろのようだ。
西洋の学問や思想を取り入れる風潮が進み、心理学については元良勇次郎がアメリカで学んだ心理学を日本に紹介している。九三年になると、元良によって「心理学、倫理学、論理学」と題された講座が行われるようになった。一九〇三年には日本初の心理学実験室が設立されているが、ヴントによる心理学実験室の設立が近代心理学の始まりだとすれば、このときに日本の心理学は始まったと言えるかもしれない。
カントショック
心理学以前の話をしよう。十七世紀にはデカルトが現れる。デカルトについては先に述べたので深入りはしないが、「我思う故に我あり」によって「私」を確立した裏で、人間の心理の説明を試みてもいる。心と身体の関係を考察し、前者は考えることにおいて存在するが空間的に場所を占めない「思惟」であり、後者の特徴は空間的に場所を占め実体として存在するが、考えることはない「延長」にあるとした。思惟と延長を二元論的に考えたように見えるが、脳内の松果体という器官において心身が交流・合一するとも主張していた(ただし松果体仮説については現在では否定されている)。デカルトの仮説は、心理学的な試みとしては先駆として評価することができる。
十七世紀末、イギリスのジョン・ロックはその著書の中で、人間の心は生まれつき白紙(タブラ・ラサ)だと考え、感覚器官を経て経験がそのノートに書き込むのだとした。「人間の本性とはなにか」という問いに対して理性を唱えたデカルトに対して、経験を唱えたのがロックといえる。人間は経験の塊であり、したがって経験したことのないものを描いたり、考えたり、所有することはできない。人間とは経験する主体なのであり、経験した内容を組み合わせることでコンセプトを作り出す。得た経験や、経験に着想したものは観念と呼ばれる。
ロックはさらに「精神的に狂った人たち」は複数の観念の結びつきが誤っている人たち、「知恵遅れの人たち」は複数の観念を結びつけることができない人たちだとした。つまり、経験主義的な立場から、正常な精神の働きと、異常な精神の働き、遅れた精神の働きを説明しようとしたのである。
一八世紀になると心理学という言葉で表される学問分野を統一的なものにしようという動きが現れた。デカルトやロックの他にはクリスティアン・ヴォルフやカール・フィリップ・モーリッツなどによって心理学の進展が図られている。ヴォルフによって刊行された『経験的心理学』などによって、「心理学」という語は馴染みあるものに進展した様子である。彼はアリストテレスの能力心理学の考え方を継承し、心的能力を上級と下級に分類したようだ。論理の形式や神の認識に関連するものが上級であり、五官を通じるために外界の影響を受ける感覚や記憶は下級であるとされた。モーリッツは『汝自身を知れ──経験心理の学』という雑誌を刊行し、心の性質だけでなく心の病や心の治癒などに関心をもつ人たちが学問的交流を行うようになっていったようだ。この雑誌に集められた一連の事実は、心の医学を確立するための観察や経験のデータであったらしく、経験心理とはすなわち経験を通して心の病にアプローチするという研究態度の表明であった。この雑誌は一七八三年から九三年まで年三回分冊が発刊されていたらしい。
このように、心理学の発展は順調かに見られたが、ドイツの哲学者イマヌエル・カントによって冷や水を浴びせられることになる。この哲学界のビッグネームとも言うべきカントだが、彼のいう科学の条件は二つある。一つ目は数式による表現が可能であること、二つ目は研究手法として実験が可能であることだ。当時は心を扱う実験方法も開発されず、また心を数式によって表す目処も立っているわけがなかった。ひどく複雑な心の領域で、普遍的な理論を企てることなど可能であるのか。カントが憂慮した点はそこにあったといえる。ビリヤードの玉は突かれればまっすぐに移動する。それは運動方程式という明快な手続きによって立証されるが、心理学が科学であるためには、心というブラックボックスを相手にそれが可能でなければならない。偶発性の塊である人間心理を、普遍的な原則や理論に収めきることなどできるのだろうか。
ヴントによる近代心理学の成立
魔女狩りが最盛期を迎え衰退に向かう一五世紀には、スペインに最初の精神病院が設立されたことからわかるように、狂人を病人として処遇しようという考えが現れ始める。 一八世紀までは、悪霊祓いという形で治療を行う祓魔師(エクソシスト)が活躍していた。祓魔術(エクソシスム)は、人間の精神の変調は悪魔によるものとし、教会が定める手順で悪魔祓いを行うものであるが、それ以後は衰退することになる。
カントショックの少し前には、祓魔術による治療に対してフランツ・アントン・メスメルが動物磁気説を唱え、宗教ではなく科学の力で精神病の治療を試みている。メスメルは人間を含む動物には動物磁気という磁気流体が存在し、その流れを変えることで心身の疾患・不調を治療できると考えた。こうした祓魔術に対するメスメルの姿勢は近代科学的態度の萌芽、とりわけ理性による啓蒙のはじまりとしてとらえることができるだろうが、メスメルの後にはカントによって心理学の死亡宣告がなされる。
カントの不可能宣言によって科学であることを否定された心理学であったが、それを乗り越えて科学化に挑んだのがヨハン・ヘルバルトである。彼はカントの後任として、哲学と教育学を教えていたが、ある表象と他の表象の関係を数式で表すことができる、など心理学にも関心を寄せていた。イギリスにおいても心理を科学的に扱う運動があったようだが、実際に心理学を科学の領域に近づけたのはドイツの生理学者たちの研究にあった。
エルンスト・ウェーバーは生理学や解剖学の研究を続けるなかで、感覚の問題に興味を持った。たとえば、重さの感覚である。彼は一九世紀前半に行った実験を通じて、オモリの重さの分別か絶対的な差ではなく、相対的なものであることを見出した。感覚においては、二つの絶対的な差が重要なのではなく、あくまでも相対的な比が問題だということである。
ウェーバーの発見した関係性についての原理を整理して発展させたのが一九世紀に活躍したグスタフ・フェヒナーである。フェヒナーはウェーバーの考えを「ΔI/I=K(Iは刺激の強度、Kは定数)」という形で定式化し、整理した。フェヒナーは物理学者であり、デカルト的な心身二元論を前提に物理量とその感覚の関係を理解しようとした。彼は、ウェーバーの研究成果を整理、発展させた。感覚をE、刺激をIで表し、定数をcとするとき、「E=klogI+c」で表せるとした。これはフェヒナーの法則と呼ばれる。感覚の大きさは刺激の強度の対数に比例して増加する、というわけだ。彼の体系は精神物理学と呼ばれる。
心理学の成立には、人間の心に関わる通念が宗教の影響を脱しつつ科学として独立した経緯を踏まえる上で、進化論の提唱者として名高いチャールズ・ダーウィンに言及せずして済ますことはできないだろう。その意味で、一九世紀中ごろ非常に重要な時期といえる。
ヴントによる心理学実験室の成立は、そうした背景を汲んだものだった。ある一つの学問がある時、ある場所に限定されて生まれるということはまずないが、それでも象徴的な出来事を挙げるとすれば、近代心理学の成立はヴントによってドイツ、ライプツィヒ大学に心理学実験室が設立されたことだろう。なお、実験室の設立とは端に建物や部屋として実験室を建設したというわけではない。心理学に実験という方法を取り入れることで新しい知識の産出が可能となり、その新しい知識を体系的に訓練することが可能になったという「システムの完成」こそが心理学実験室設立の意義なのである。ヴィルヘルム・ヴントによる心理学の研究対象は意識であった。どのようにすれば意識の実験研究は可能であるのか、かつてカントによって「心理学は科学になり得ない」と主張した理由の一つは、実験が困難であることにあったが、それを鑑みれば実験を手法として取り入れることは心理学の科学化に大きく寄与したと考えられる。
ヴントは従来の心理学の系譜をひく内観心理学に実験生理学の手法を取り入れた。音を聞いたときに働く意識の様子を研究するとき、音を出すことは「刺激提示」というが、その刺激提示を体系的に行うことで、内観という他者にはわからない意識の働きを捉えることができるとしたのが、ヴントの実験心理学の意義である。そして、実験研究を行うにつれて知識も備蓄され、『生理学的心理学要綱』は、第四版以後六部構成となりページ数も初版の三倍弱となった。
アメリカにおける心理学
イギリス人のエドワード・ティチナーは、ドイツに留学してヴントのもとで博士号を取得したあとにアメリカのコーネル大学で心理学実験室を開設した。彼は当時の心理学の主題である意識を単純な要素に分解すること、そしてその要素の連合法則を見出すことを重視しており、その心理学は構成心理学と呼ばれる。
アメリカ心理学の立役者はウィリアム・ジェームズである。彼もヴントと同じく医学を修めてから実験心理学に転身し、ハーバード大学で心理学実験室を設立した。彼の成果は『心理学原理』である。彼の心理学の特徴は心の機能(はたらき)を理解しようとしたところにあり、機能主義的心理学と呼ばれる。こうした考え方はアメリカで生まれた行動主義にも引き継がれる。ただし、ライプツィヒ大学の心理学実験室ほどには体系的なカリキュラム提供を行っておらず、研究者を育てる水準には達していなかったようだ。
ジェームズの業績のうち「悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しい」として知られる情動の末梢神経説は有名である。ただし、同時期にデンマークのランゲによっても同様の主張がなされたため「情動のジェームズ-ランゲ説」と呼ばれている。彼はまた、自己を純粋自己と経験自己に分けた理論でも有名である。前者は「I」であり、純粋自己たる「I」によって知られる自己の側面が経験的自己であり「me」である。「I」は主体としての自己、「me」は客体としての自己、として理解されている。ジェームズはこのほかにも習慣の重要性を説いたことでも有名であるが、その後は哲学に関心を移しプラグマティズムの提唱者として知られるようになる。
アメリカで臨床心理学の創設に大きく関わったのはライトナー・ウィトマーである。ペンシルベニア大学を卒業したウィトマーは中等学校の教師をしたあとで政治学の博士号を取得するために同大学の大学院に進学するが、そこで心理学者のキャテルに出会い、彼のもとで助手を務める傍ら専攻を実験心理学に変更した。その後のウィトマーはライプツィヒ大学に留学し、ヴント実験美学に関するテーマを与えられて上意下達的な雰囲気に辟易しながらも、博士号を取得することになる。同時期に留学していたティチナーとは懇意になり後々まで交流が続いたようだ。実験を終えてアメリカに帰国していたウィトマーはペンシルベニアで講師となり、実験心理学を中心とした研究と教育に邁進した。そこでは公立学校の教師向けに児童心理学のコースを開講する。一八九六年にはペンシルベニア大学に心理学クリニックが実質的に開設される。これは、心理学の訓練を受けた者が臨床的な問題に体系的に取り組んだという意味で臨床心理学の始まりとして理解することができるだろう。一九〇七年には学術誌『心理学クリニック』を創刊している。
日本における心理学
臨床心理学的な関心は江戸時代以前にも見られたが、学問として成熟するのは近代日本に心理学が導入されてから以降のことである。日本の心理学の歴史を紐解いていこう。学問としての心理学は、西洋の哲学から派生もしくは分岐していると見なせるが、心理思想ということについて言えば土着的な思想は確かにあるものの、学問としての心理学に関しては土着的な思想の影響はそれほど強くはない。
先にも触れた通り、学問としての心理学に初めて接した日本人の一人が西周である。彼は江戸末期に幕府の役人としてオランダに派遣され広く人文社会学を学んだ。明治維新後には明治政府の役人として、ヘヴンの著作を翻訳し、そのタイトルに「心理学」と名付けた。日本で最初の心理学の本であり、この本の影響で今も心理学という名称が扱われていると思われる。
明治時代になると、西洋の学問や思想を取り入れる風潮が進み、心理学については元良勇次郎がアメリカで学んだ心理学を日本に紹介し、自ら研究を重ねた。彼の関心は広く、「白内障者の視覚に関する実験」は、モリヌー問題を日本で初めて扱ったものである。また精神遅滞児の成績が悪いのは「注意ができない」ことに起因すると考え、「児童の注意力とその訓練についての実験」を行い注意の訓練法を提案した。ウィトマーのような臨床心理的関心が、ここには現れているといえる。元良は後進を数多く育てたが、その代表は松本亦太郎と福来友吉である。前者は知能とその測定、後者は催眠や変態(異常)心理学の研究によって日本の臨床心理学の発展に大きく寄与した。ただし福来は大きな問題を起こし、日本の臨床心理学発展に少なからぬマイナスの影響を与えることになる。
明治後期になると、欧米の影響で催眠術が流行した。中には催眠術を用いて詐欺まがい、犯罪まがいのことを行う人も出てきたので、その取り締まりが重要な社会問題になっていた。福来友吉は、東京帝国大学で催眠や変態心理学の研究を行っていた。変態はAbnormalの訳語であり、現在は異常と訳される。当時の日本では、このようないかがわしい催眠が流行しており、福来は心理学の専門家という立場から催眠の濫用を取り締まる側にとって有用な知識を提供した。もちろん、自身も催眠を習得しており、心理療法の領域にも足を踏み入れていた。福良に期待されていたのは変態心理学(臨床心理学)を研究し、その後進を育てこの領域を発展させることであった。しかし彼は、催眠の研究のさなかに、透視ができるという女性(御船千鶴子)を知り、その研究を始めてしまう。当然、多くの学者が参加した公開実験などを経て、透視の存在は否定されつつあったが、福良は透視だけでなく念写ができる女性を発見したとしてその研究に打ち込んだ。
心理学前史からヴントやアメリカを経て日本における心理学の勃興までを振り返ったが、ここで指摘しておくべきことは、戦前日本における心理学はアメリカ式心理学から多くを受け取ったということだ。ここが、主にドイツ経由で発展した日本の精神医学との違いである。
精神医学の歴史
精神医学に話を移そう。精神医学とは、ドイツの精神病医ヨハン・クリスチャン・ライルによって一八〇三年に生まれた造語である。精神はプシュケー(Psyche)、医学はイアトロス(Iatros)とそれぞれギリシャ語から取られており、合わせて精神医学(Psychiatrie、ドイツ語)というわけだ。「精神」は、一八八四年に公刊された明治一七年版の学術ターム訳語辞典『哲学字彙』には、ドイツ語の「geist」の訳語として登場している。
日本の精神医学は、意外なことに維新前からすでに仏教各派によって治療の試みがなされており、その方法は各派の疾病観・医療観によって異なっていた。では近代精神医学・西洋的な精神医学はどこから始まったのか。日本における近代精神医学の発祥は、心理学同様明治時代の勃興の中に見て取ることができる。明治新政府は一八八三年に医師国家試験制度を開始して医学教育の近代化に乗り出す。医学教育の現場においては、他の分野と同様に外国人教師が招聘され、一八七一年にはドイツからレオポルド・ミュラーとテオドール・ホフマンという軍医が招かれて当時の東京医学校で教育にあたることになった。ミュラーとホフマンが帰国すると、一八七六年には同じくドイツからエルヴィン・べルツが来朝して内科学の講義を行うようになる。
日本で初めての精神医学講義も、このベルツによってなされた。ベルツが教材としたのは、ヴィルヘルム・グリージンガーというドイツの精神科医による精神医学教科書であったとされる。一八八六年、「帝国大学令・中学校令」が出されると、帝国大学には医学部を設置することが義務付けられ、同時に精神医学を教授科目とすることも決定された。この法令によって当時唯一の帝国大学であった東京大学にも医学部が置かれ、「帝国大学医科大学」として、日本初の精神医学講座も開かれる。一八八六年には精神科講座(当時は「精神病学講座」)がドイツ留学から帰国した榊俶によって開講している。
帝国大学医学大学に初の精神医学講座が開かれ、ドイツ留学から帰国した榊が主としてクラフト=エビングの教科書をもとに講義を開始して以降、日本の精神医学はドイツのそれ一辺倒に偏移していくことになる。さらにエミール・クレペリンの真新しい教科書とその精神医学体系が、榊の弟子である呉秀三のドイツ留学からの帰国によってもたらされることになる。一九〇二年には京都に帝国大学が新設され、その後続々と設立される帝国大学あるいは医学専門学校に精神医学の講座が開講されると、その初代教授に就任したのは、ほとんどが呉の門下生であったといっても過言ではない。同時に、彼らの信奉した精神医学もまた呉の精神医学すなわちドイツ精神医学であったことはいうまでもない。こうして日本の精神医学はドイツ化、「ゲルマン化」されることになる。
精神医学の優生学
検証すべき重要な歴史的問題点についても触れることにしてみたい。それは、日本における優生学の言説である。近代日本における精神医学の側からの優生思想への言及も、興味深いことに、先に触れた日本で最初に精神医学を講じたドイツ人医師ベルツに発する。ベルツは当時、急速な欧米化に伴って民間に現れた「欧米人種との雑婚推奨論」(日本人は体格が欧米人に劣るため、積極的な欧米人との結婚を進める議論)に反対し、「日本人は欧米人に劣るところはないので、遺伝に注意して慎重に結婚相手を選択すれば、日本人同士の結婚で問題はない」と『日本人種改良論』の中で主張している。このベルツの言説が、その後どこまで日本人精神医学者に影響を与えたかは不明だが、少なくとも文献上でみる限り、明治・大正期を通じた精神医学からの優生学的分野への言及は、主として結婚問題に絞られていたようだ。
その後、日本人精神医学者による優生学への言及は、一九三〇年代に入るまで表立ってはなされなかったようであるが、一九三一年に日本軍が中国東北部に侵攻して中国との間に戦争状態が生まれると、優生学に関する論議も精神医学の内部でふたたび活発化する。特に、東京大学精神科教授の三宅鉱一は、一九三一年の「変質者問題座談会」において、精神病者の断種に対する積極的賛成論を述べ、のちの一九三九年には「精神病者一千万人断種論」ともいえる強硬な発言をして、自ら断種論者であることを公言した。三宅は、その前年に設置された厚生省予防局の「民族優生協議会」の主要メンバーであり、日本においてもドイツ同様に国立の優生学研究所を設置すべきことを説き、その結果、カイザー・ヴィルヘルム研究所にならった施設の建設計画がもちあがることになる(ただし、太平洋戦争のために計画のみに終わり、実現されることはなかった)。
精神医学と反精神医学
科学世紀においても、優生学は活発に議論されている印象を受ける。それは主として伝統的風土、文化に訴えかける方向にあり、国民的、民族的アイデンティティとして同一化しようとする傾向にあるが、相対性精神学もその流れと無関係ではないだろう。特に、精神医学の科学世紀的状況においては、近代主義的な傾向が強く見られる。近代という時代は理性に対する期待が強い時代だったが、その理性の信奉や啓蒙精神は、非理性的なものを排除するという悪い方向に導かれることも大いにあった。サナトリウムで行われる「療養という名の隔離治療」は、精神医学における権威的体制の象徴である(『伊弉諾物質』)。そこには医者と患者の関係が存在しており、「患者は医者によって治療されなければならない」という図式が存在している。それは一つの上下関係であるばかりか、権力の関係であり、露呈していない暴力の関係である。医者が言うことの聞かない患者を拘束し、暴力をふるうなど、ぞんざいに扱うといった事例もあるはずだ。理性的人間や啓蒙の精神を第一のものとする近代的な精神医学には、そうした状況に陥りかねない危惧が指摘される。
ここに、優生学や近代的精神医学の対極に位置するであろう立場を紹介してみたい。反精神医学である。精神科医ジャン・ウリや精神分析家フェリックス・ガタリによって一九五三年に創立されたラボルト精神病院は、通常の精神病院とはいささか異なる理念を宿している。端的にいえば、この病院の試みは、精神病は本質的に医学の外部にかかわる、という観点を原理にしている。精神医療は、決してただ医学によって確立された知識と技術を、病院で患者に提供するという活動に限定されてはならない。精神の病が発生することは、この社会の集団、家族、関係のあり方に、ひいては政治にも資本主義にも密接にかかわっている。病院もまた医者と患者、その他の成員がいっしょに形成するひとつの社会である以上、病院の外部の社会と病院の内部の社会を、どのように関係づけるかが重要的な問題になる。病院がそのような発想を持たず、閉じた場所である限り、病院自体も、外部の社会を模倣して、病を発生させ、悪化させる場所になりかねない。
患者が病院の外部でなぜ病み始めたのかと問うことと、病院という場所をどのように構成するか考えること、この二つは同時進行しなければならない。精神の病は、この社会の中の日常生活を構成する心理的、政治的、経済的、文化的要素の軋轢と密接に関係する。その意味で、精神の病とは、必ずそのような多様な要素のあいだの葛藤の表現であり、それに抵抗したり、それに抵抗したり、それから逃げて生きのびようとしたりする過程でもある。精神病院とは、その意味で、高度に社会学的、政治学的な場なのである。
だから精神病院を単に医学的な知識に基づく臨床や治療の場とみなすことは、あたりまえのようでも大きな問題をはらんでいる。精神病院をどのような関係の場として構成するか、ということは、逆に、正常とみなされる社会の中のあらゆる葛藤や抑圧を別のまなざしで見るための機会になるはずである。結局それは、この社会のあり方そのものを変える試みと切り離せない。
ウリもガタリも、単に新しい開放的な精神病院を作ろうとしていたのではなく、政治的社会的文脈の中に精神医療を問題として位置づけ、そのための一つの実験として、この病院を開設した。この実験を二人は「制度論的精神療法」と呼んでいる。それはまさに、医療の外部のさまざまな制度との関係で精神医療を捉え、精神医療と精神医学をひとつの制度として批判的に再構成する試みだったのだ。
制度論的精神療法の立場からすれば、精神病院とは精神の病を単に薬物によって治療したり、芸術療法などによって緩和したりするような場所では決してない。それは、私たちが社会と自己に対してしばしば固定させてしまう通念を揺さぶり、社会的関係のたえまない動きや変化と、治療の空間とを貫通させるような場である。
科学世紀における精神医学の実践状況は、反精神医学の観点からはあまりにも近代主義的だとして批判されるだろう。それは医者が患者を治療する場であり、患者を従属させる場であり、政治的社会的文脈を不当にも削いだ場であるのだ。そこでは「精神」がベルトコンベアの上に乗せられ、医師という権威によって診察され、病院という制度によって管理される。
心理学と精神医学
振り返って、心理学と精神医学の関係について考えよう。心理学は主に哲学から派生した学術分野であった。科学としての心理学は、ヴントの実験的手法によって構成する試みがなされ、アメリカではジェームズによって同じく実験的ではありながらも別様の心理学が生まれ、これが日本で受容されたというものだった。精神医学は明治期の近代化によって、榊や呉がグリージンガー、クラフト=エビング、クレペリンといったドイツ式精神医学を輸入した。また日本で初めて精神医学講義を開いたベルツによって優生学的な言説も取り入れられ、戦時は優生学的観点からの精神病者の「断種」をめぐって活発に議論された。
語源の話であれば、心理学(psychology)と精神医学(psychiatry)は、同じギリシャ語のプシュケー(psyche)に由来していた。日本における心理学は、西周のジョセフ・ヘブンの著書の訳語として一八七五年に与えられたものだった。対して精神医学(psychiatrie)は、ライルがギリシャ語の精神(psyche)と医学(iatlos)によって生み出した造語であることがわかった。
しかし、「精神」という語が明治期にドイツ語の「geist」に当てられた訳語であることもわかった。ここで気になるのは、「geist」が「psyche」に由来しているかということである。ここで「geist」が「psyche」に由来せず、異なる意味合いで用いられる語彙であったならば、はじめに立てた前提「心理学と精神医学における心と精神は同一のものを指している」に矛盾が生じてしまう。無論、それは大した問題ではない。外国語を厳密に翻訳することは、その構造上不可能であろう。
ここに問題になっているのは、相対性精神学における「精神」とは何か、であった。それは精神医学にならって「psyche」に依拠した、霊魂として精神、心としての精神、心理的な意識として精神と考えるのが一般的であろう。
精神についての学
しかしここで、鈴木大拙の指摘を振り返ってみたい。鈴木によれば、精神とは端に心や魂ではなく、実体を持たない、広範で抽象的な概念なのであった。それは個別の身体に宿る、個人に分割可能な内面性ではなく、非実体的で文化的な、風土や伝統を人間ごと貫く地平のイメージとして提示される。心や魂では回収されない多義性が、精神にはあるといえる。
では、ドイツ語の「Geist」はどうであるのか。英語の「mind」や「spirit」といった心や魂としての内面性に回収されない多義性が、「geist」にあるというのか。それが、あるのだ。それはある現代のドイツ人が書いた哲学の書物に、「geist」について、「geist」だけが持つ多義的な意味についての矜持が読み取れる。
それは現代という時代に活躍するドイツの哲学者、マルクス・ガブリエル(一九八〇─ )である。二〇一三年(邦訳二〇一八年)に発表された『なぜ「世界」は存在しないのか』は世界的なベストセラーとなり、その中で提示した「新しい実在論」は二一世紀の哲学として注目を浴びており、彼自身も「哲学界のロックスター」と呼ばれる。彼は『新実存主義』の中でこう語っている。
標準的な反唯物論的スタンスから距離を置くために、私が描写しようと思う現象を「精神(ガイスト)」という言葉で表すとしよう。(中略)英語には「精神」と厳密に等価な言葉はない。mind(心)もspirit(魂)もぴったり同じではない。私がドイツ語の言葉にこだわり、読者にそれを専門用語として受け取って欲しいとお願いするのも、それが理由だ。
最初の方はガブリエルの哲学の詳細に立ち入るつもりもないので無視するとして、ガブリエルは精神(geist)が英語における心(mind)や魂(spirit)と同じではないと述べている。ガブリエルの想定する「精神」が何であるかは知り得ないが、それでも「精神」が一般的な心や魂と異なるところのものであるということは、相対性精神学における「精神とは何か」を考えるうえで重要なヒントになる。ガブリエルは別の著作でこうも語っている。
文化という意味での他者の中に自分と同じ人間を認めるとき、私たちはその人の脳ではなく、文化という意味で自分自身を決定する能力としての精神を認識しているのです。ここで大切なのは、この能力があるか否かであり、したがって友愛の情を示すことができるか否かです。友愛の情を示すことは日本では至極もっともなことだとうかがっています。日本的なおもてなしと社会のコミュニケーションを、私は精神が体現されたものとして体験しました。ここで私が「精神」と呼んでいるものは、日本では至る所で見受けられます。それは形式の美であり、秩序のバランスを保つために他者が今何を望んでいるのかを予測することです。
そこでは「精神」が、個別的な心や魂ではなく、関係を貫く地平のイメージとして素描されている。それは分割可能であったり、実体的に想定できる個別的な内面性ではない。社会的なコミュニケーションは精神の体現であり、形式的な美だとして言及されている。
しかし、精神という語の、ドイツにおける特異な使われ方や意味付けは、何もガブリエルに始まったことではない。ドイツの哲学の伝統が、そこにははっきりと現れている。一九世紀ドイツで活躍したヘーゲルという哲学者は、世界をつらぬいて統一的にはたらき、万物の形成、結合、秩序付けをおこない、また人間の個別的精神の根拠をなすと考えられた原理を「世界精神」と呼んだ。一般的には、あらゆる存在を統一させる根源的な原理であるが、当然、精神は「geist」である。ここで指摘できるのは、一般的な心や霊ではなく、もっと壮大な何かしらを表すために「精神」という言葉が使われているということである。それは決して具体的な生起物なのではない。それは意志や理念という言葉の使い方に近い、抽象的で広範な意味を持つ語彙なのであり、実体的なものとして扱うことのできない対象である。
相対性精神学における精神学とはなにか、また精神とはなにかについても、一般的な意味で言うような、心や魂としての「精神」ではなく、次のような憶測も可能であるように思う。すなわち、精神学とは精神についての学であるということだ。精神学が扱うのは心や魂ではなく、文化や自然といった周辺をまるごと貫通する地平としての「精神」なのである。このような結論を、「相対性精神学のガイスト的解釈」と呼ぶことができるだろう。相対性精神学は精神についての学である、とは、他ならぬ精神の持つ多義性に由来する。偶然にも、明治期に導入されたのはドイツ式の精神医学であった。鈴木大拙による精神の多義性という指摘は、そのまま相対性精神学の解釈の多義性にもつながるように思える。それこそ、相対性精神学が、心理学でも、霊魂学、霊学でもない所以である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
