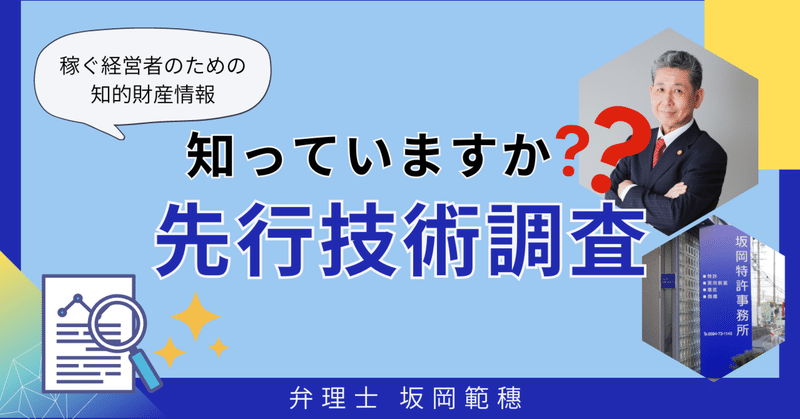
先行技術調査のやり方とは?
【稼ぐ経営者のための知的財産情報】
弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。
今回は、「先行技術調査」をお伝えします。
※出願等のお問い合わせはこちらから http://www.sakaoka.jp/contact
1.知財を活用して企業価値を上げる方法の概略
以前の記事「知財を活用して企業価値を上げる方法」では、具体的な方法として以下の7つを挙げてみました。
https://note.com/norio_sakaoka/n/nc45fe8bec77c
(1)課題探し
(2)従業員全体から課題を吸い上げる工夫
(3)効果の高い改善提案を選別
(4)先行技術調査
(5)抽出した先行技術文献を模倣する
(6)先行文献をさらに改良する
(7)特許出願の可否を検討する
今回は、上記のうち(4)先行技術調査について、さらに詳しく説明して参ります。
2.先行技術調査の必要性
そもそも、なぜ改善提案を実施するのに先行技術調査が必要なのでしょうか。
実は、殆どの改善提案には不要です。そのまま改善提案を実施してください。
しかし、その改善提案を対外的な商品やサービスに用いるときは、先行技術調査をする方がよいでしょう。
何故なら、その商品やサービスをリリースした途端に、他社の特許権侵害になってしまうおそれがあるからです。
もっといいますと、製造方法であっても先行技術調査をする方がよいです。
これは、コンプライアンス的にみて、他社の特許権を侵害していないことが求められるからです。
特に、大企業の下請けをされているところは注意が必要です。
さらに、対外的な商品やサービス、製造方法の両方に当てはまりますが、先行技術調査をすることで、抽出した先行文献の技術情報を入手できるという利点があります。
3.先行技術調査で注意すること
さて、それでは実際に先行技術調査をするのですが、大きな注意点があります。
それは、FI(ファイルインデックス)やFタームなどの特許分類記号を使って検索することです。
文字だけで検索するテキスト検索は、予備検索にしか使えません。
理由は、類義語に対応することが難しいからです。
例えば、「電気モーター」を検索しようとするとき、同じ意味の言葉として「モーター」「もーた」「モートル」「電動機」「電動器」などがあります。
実際の検索式では、「電気モーター」だけでなく他の言葉も複数加えて検索します。
そうすると、テキスト検索のみではどうしても漏れやノイズが多くなるのです。
私も予備検索ではテキスト検索を使用しますが、ヒット件数の半分くらいがノイズになることが少なくありません。
特許分類は、特許情報プラットフォームのパテントマップガイダンスに詳しく記載されています。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p1101
4.無料データベースか有料データベースか
次に、先行技術調査をするのに、無料データベースか有料データベースという話があります。
最初は、無料で使用できる特許情報プラットフォームでよいと思います。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
私も開業当時は無料データベースで検索していました。
それに、無料データベースも昔に比べたらずいぶんと使いやすくなり、機能も増えました。
とはいっても、頻繁に特許調査をされるなら、有料データベースでの調査をお勧めします。
お値打ちなものは月額1万円未満で契約することができます。
ここでも注意点ですが、有料データベースといっても全てが良いものではないということです。
私が過去に経験したことですが、使い物にならないものもありました。
参考までに、弊所では現在「日本パテントデータサービス」を利用させてもらっています。
最近ではAIを使った有料データベースもあるようです。
私見ですが、現時点ではあまり必要性を感じていないです。自分で行う調査で十分足りていることと、信頼するにはまだ不安があるからです。
もっとも、時間短縮を目的とすることや初心者向けには良いかも知れません。
例えば、プログラム系の特許調査だと、図面を見ただけは判断できないため、ある程度の文章を読まなくてはならず、時間がかかります。
また、初心者が最初につまずきやすいのが、特許分類の特定です。特許分類を間違えてしまえば、いくら検索してもヒットしません。
このようなときにAIがあると便利そうですね。
5.実際の調査
それでは、実際の調査はどうするのでしょうか。
基本的には、以下のようになります。
(1)テキスト検索を用いた予備検索
(2)予備検索で抽出した文献からおよその特許分類を推定する
(3)パテントマップガイダンスをみて検索対象の特許分類を決定する
(4)特許分類を基本にして検索式を作成する
(5)検索作業をする
詳しくは、弊所HPに記載しております。
よろしければご覧ください。
(有料級の記事ですよ!私が実際に指導するとお金がかかります 笑)
https://www.sakaoka.jp/category/1770793.html
この記事が御社の発展に寄与することを願っております。
坂岡特許事務所 弁理士 坂岡範穗(さかおかのりお)
※自社の技術の権利化をお考えの人のお問い合わせはこちらからhttp://www.sakaoka.jp/contact

ホームページ http://www.sakaoka.jp/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100065245853871
https://www.facebook.com/sakaoka.norio
Twitter https://twitter.com/sakaoka
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
