
避難の流れと判断の仕方
こんにちは、今回は「避難」に焦点を置き、
地震発生後の避難行動をお話ししたいと思います。
地震が発生し、強い揺れが私たちを襲います。
物が落下したり、棚が倒れたりするでしょう。
そうなった時に慌てず行動することで、身の安全を守ることができます。
机の下に潜って(外の場合は低い体勢をとる)手で頭を守ること。
揺れが収まったら、コンロの火を確認すること。
出口を確保すること。
備蓄用品があれば、持って非難すること。
こういった手順を行うことが
安全を守りながら行動することに繋がります。
(NG行動)
1.ライターなどで火をつけてはいけない
ガスに引火する場合があるから。

2.ブレーカーを上げて通電させない
火災の危険性があるから。

3.スイッチを押して電気をつけない
火災や爆発の危険性があるから。
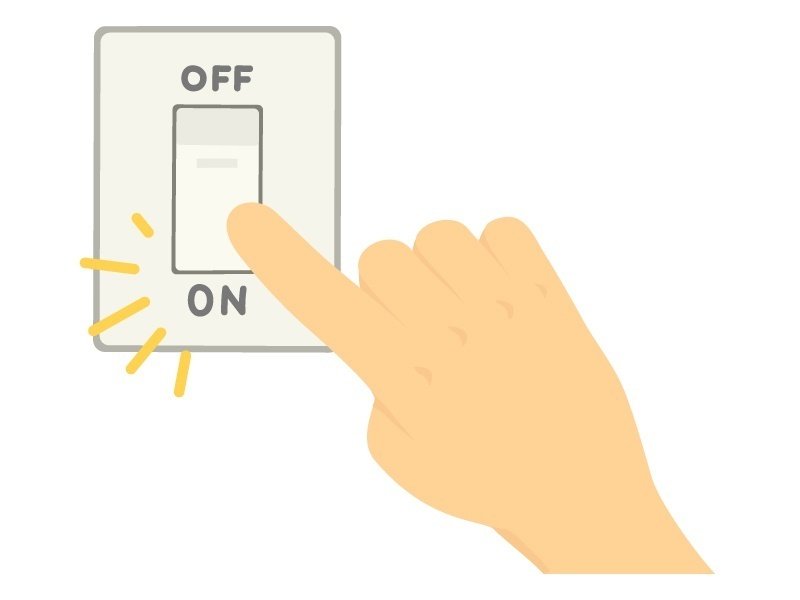
4.エレベーターは使わない
閉じ込められる危険性があるから。

5.電話の使用を控える
電話回線がパンクしてしまうから。
(家族に知らせる場合は、「171」にかける)
※「171」は、災害伝言ダイヤル

6.部屋の中を裸足で歩かない
ガラスの破片などが飛散しているので、ケガをする危険性があるから。

7.救出活動は一人では行わない
自分の身に危険が及べば、二次災害になるかもしれないから。
8.車は使用しない
緊急車両の妨げになるから。

では、
外に出てからどうすればよいのでしょうか?
(避難の流れ)
避難時の服装:ヘルメット(防災頭巾)、動きやすい服装、
履きなれた底の厚い靴、軍手
火災の危険がある場合:避難指示に従う
それ以外は、近所の公園、小学校、中学校などに向かう。


その場所が危険区域になった場合、別の公園や広場に移動する。
☟(危険性がなくなったら)
家に被害があるかを確認しに行く
被害がなければ、帰宅する。
被害があれば、避難所に避難をする。
という状態になります。
(避難の判断はどうすれば良いの?)
デマ情報が拡散し、多くの人が誤った情報を認識してしまう現状が
あります。
そういった誤った情報に振り回されないようにするためには、
ラジオや行政のサイト、消防署のサイトから正しい情報を得る必要が
あります。
スマホにラジオのアプリを入れておくと簡単に聴くことができます。

(最後に)
今回は、「避難の流れ」と「判断の仕方」についてお話ししました。
本日も読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
