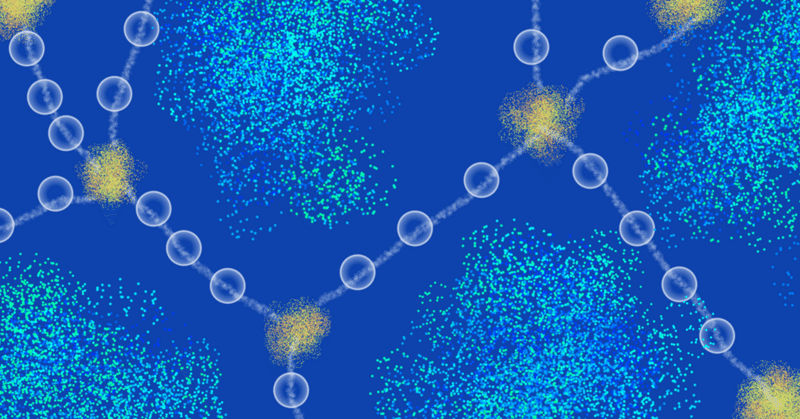
ネットワークをつくると強い 〜学校視察から考える〜
こんにちは、めぐみです。
前回、富山県の「フリースクールフレンズ」に視察に行かせていただいた記事を書きました。↓
前回の記事では、公民連携が進まない問題に焦点を絞ったのですが、高和さんを中心に、つい最近、公民連携が急速に進み始めました。
そこで今回は、フリースクールフレンズ代表の高和さんへのインタビューをもとに、高和さんがどのようにして公民連携に向けて動いていかれたかについて、私が理解した範囲でお伝えます。
増え続ける不登校
今全国的に、不登校児童の数が増えていることが問題になっています。
富山県も例外ではなく、2022年度の富山県内の不登校の小中学生は約2200人で過去最多でした。
不登校を取り巻く問題に対する早急な解決が望まれていましたが、不登校児童をケアする民間のフリースクールと、公的機関がうまく繋がっていないという問題がありました。
公立学校が合わない子の親に対し、その子が在籍する学校が、民間フリースクールを紹介するということがほとんど行われていなかったのです。
しかし、その状況に危機感を募らせた方がいたんです。
それが、私が視察に行かせていただいたフリースクールフレンズの代表、高和正純さんです。

高和さんの取り組み
高和さんは、フリースクールや放課後デイサービスなどを運営されている方で、長年子供たちの居場所づくりに取り組んでこられました。
しかし、子供の情報を一番多くもっているはずの公立学校から、親御さんに対してフリースクールへの紹介がないことや、フリースクール利用にあたっての補助金がないことに問題意識をもっておられました。
そこで県に話をしに行き、理解を求めました。
しかし、事はなかなか思うように進まなかったそうです。
そのため高和さんは、「富山県不登校を考えるネットワーク」という団体を作り、富山県内のフリースクールやオルタナティブスクールを洗い出したのだそうです。
すると、なんと60以上もの団体があることが分かりました。
思っていた以上に、公教育以外の場で、子供たちをサポートする機関がたくさんあったのです。
そして高和さんは、フリースクールやオルタナティブスクール、公的相談機関など公も民も混ぜこぜにして、地域別の一覧表を作り、パンフレットとしてまとめました。
それを県に持っていったのだそうです。
すると一気に風向きが変わり、話が進み始めたそうです。
今までは公的機関が民間のフリースクールを紹介することは無理だと言われていたのが、このパンフレットを教育委員会や学校に置いてもらえることになったそうです。
そしてついに、2024年2月に発表された新年度予算案で、富山県はフリースクールに通う子供がいる家庭に対し、月1.5万円を上限に半額を補助することを決めました。
このような補助金を設けているのは、全国でも東京都、長野県、富山県など、わずかな県にとどまります。
それくらい、この新たな決定は画期的なものです。
これは富山県内でも大きなニュースになりました。
問題は山積み、でも大きな一歩
しかし、まだまだ問題は山積みです。
フリースクールの数は足りていないし、通うための手段やお金の問題もあります。
不登校問題の解決に向けて、富山県は今まさに入り口に立ったところ、というのが現状なのかなと思います。
でも、予算案に補助金が盛り込まれたと言うのは、とても大きな一歩だろうと思います。
もしかしたら富山県が、不登校問題の解決に向けて、先頭を行く県になるのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
