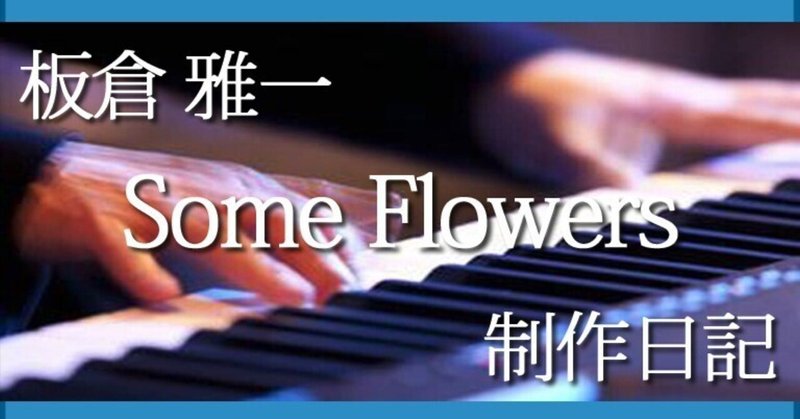
【Some Flowers制作日記 その21】
Chapter20 セルフライナーノーツ「Harbor lights」
6/24にぼくのアルバム「Some Flowers」が発売になりました。
すでにお聴きいただいている方もいらっしゃるかと思います。まだの方は聴いていただけたら嬉しいです。
セルフライナーノーツ的なもの第二弾は「Harbor lights」について。
2.Harbor lights
1987年に作った曲。浜田省吾作詞、板倉雅一作曲。
今から37年前の1986年9月から87年4月まで、浜田省吾さんの大規模なコンサートツアー「I’m a J.BOY」が行われた。
その大掛かりなツアーが終了して、1987年はツアーの無い年となった。
しかし「I’m a J.BOY」が終了すると、すぐに次のアルバムのレコーディングが控えていた。
今度のレコーディングは、1985年に発売されたクリスマスアルバムの続編にあたる、サマーリゾートアルバムの制作だった。
しかもなんと今回はバンドメンバーが曲を書いて、それに浜田さんが詞を書くという、画期的なアイデアの作品だった。
その話を聞いてから、バンドのメンバー達は意気揚々と各々作曲作業に入った。
早速ぼくも曲作りをスタートさせた。いつから作り始めたのかは定かでは無いが、ツアーが終わって間もなくだったか、ツアー中だったか、よくは覚えていない。
他のメンバーがどんな曲を書いてくるのかは皆目見当もつかなかったが、ぼくは最初からバラードナンバーを作ろうと決めていた。というのは、なんとなく他のメンバーはバラード曲は作らないだろうと踏んだから(笑)。
ま、それは冗談としても、その時のぼくはバラードのほうが作れるような気がしたのは確か。
その頃のぼくは、アメリカのAOR(アダルト・オリエンテッド・ロックとかアルバム・オリエンテッド・ロックの略)にハマっていて、ド定番のボビー・コールドウェルやボズ・スキャッグス、クリストファー・クロス等の、オシャレで洗練されたサウンドの虜になっていた。
で、それらの楽曲に必ずといっていいほど参加していたのが、後に押しも押されぬ大プロデューサーになる、キーボーディストのデヴィッド・フォスター。
自身でもギタリストのジェイ・グレイドンとAirplayというユニットを結成していて、その唯一発表されたAirplayのアルバムは、後にAORの教科書とも呼ばれるようになる名盤であった。
当時のぼくは、まるで熱に浮かされたかのように、デヴィッド・フォスターの作り出すサウンドに夢中になっていた。
ぼくがどれだけデヴィッド・フォスターに影響を受けたかは、浜田さんのアルバム「J.BOY」の中のサウンドにも顕著に現れている。
当時のデヴィッド・フォスターはバラードのキラーチューンもたくさん作曲していた(=アレンジ、プロデュースしていた)。
重度のデヴィッド・フォスター病に冒されていたぼくが、それに影響を受けないわけがなかった。
ぼくが作ろうと決めていたバラードナンバーも、自然とそんな曲調になるはずだった。
はずだったと書いたのは、そんなに事が上手くいくはずが無かったからである。
すっかりデヴィッド・フォスターが憑依していたぼくは、彼のような曲がすぐにでも書けるよう気分になっていた。
ある日、デヴィッド・フォスターのヴィデオ作品を観ていたら、彼が曲作りのために車(メルセデスか何か)を運転して、持参したハンディレコーダーを片手に、鼻歌のような曲を歌いながら、カナダのヴィクトリアの雄大な橋を渡っているシーンがとても格好良くて、ぼくはすぐに真似をしたくなった(笑)。
ぼくは曲作りのために車(メルセデスじゃなくて、フォルクスワーゲン・ゴルフ)を運転して、持参したハンディレコーダーを片手に、深夜の駒沢公園の周りをぐるぐると何周も周回した。当然そこには、ヴィクトリアの雄大な橋などあるはずもなかった。
結局何周したのだろう、夜が明けそうな時間になっても、ぼくは曲の欠片すら作ることが出来なかった。そのうちレコーダーの電池も空になっていた。
そんなアホみたいなことをやって分かったことは、やっぱりぼくにはデヴィッド・フォスターのような才能など、まるで無いと言うことだった。
「車を運転しながら鼻歌作曲作戦」をやむなく断念したぼくは、作曲のために自宅でピアノと対峙する時間が多くなった。それでもなかなか納得の行く曲は出来なかった。
何日かして、ようやくこれなら何とかいけそうな感じのメロディが出来た。
特に出だしのAメロの部分と、大サビの部分は自分でも良いメロディが書けた手応えを感じていた。
その出来た曲をさっそく浜田さんに聴いてもらった。
浜田さんの感想はこうだった。「すごく良い曲だと思うよ。ただサビのメロディが少し弱い気もする。もっとシンプルで大きなメロディにしてみてはどうだろうか」
浜田さんからのアドバイスを聴いて、ぼくは目からウロコと言うか、耳から鱗が落ちたような気分になった。
最初にぼくが作ったサビの箇所は、音符を詰め込みすぎていて、少し技巧に走り過ぎていた。
そしてあまり難しいことは考えずに、もっとシンプルで気持ちが高揚するようなメロディに書き換えた。
サビをシンプルにしたら、その後に転調を盛り込むアイデアも湧いてきた。そして後半で再度転調してゆくという展開も。
ぼくは自信作が出来た感触を手に、再度浜田さんに聴いてもらった。
すると今度は「良いよ、すごく良い!素晴らしい曲になったね」と言ってくれた。
すっかり気を良くしたぼくは、すぐに曲のアレンジも完成させた。
レコーディングは1987年の5月のゴールデンウィークに横須賀、観音崎のマリンスタジオで行った。演奏したのはドラムの高橋くん、ギターの町支さん、ベースの江澤くん、キーボードのぼくの四人。
偶然か運命か、このレコーディングの最中に、なんとデヴィッド・フォスターの来日公演が行われた。それもぼくの自宅からわずか歩いて5分ほどの距離の場所でだ。
ぼくは観音崎からデヴィッド・フォスターのコンサートを観に行った、というか自宅に帰った(笑)。
後日、中学の先輩でもあるギターの土方さんにもう一本のギターのダビングをしてもらった。
レコーディングでのコーラスは町支さん、江澤くん、ぼくの三人で担当した。
いけね、またも前置きが長くなりすぎた(笑)。
そんなぼくにとってエポックな作品となった「Harbor lights」をセルフカバーすることは、大きな挑戦でもあった。
なにせこの曲は本当に弾くのも歌うのも難しい。ましてやオジリジナルバージョンで歌っているのは、あの浜田省吾である。
まぁ、最初から浜田さんみたいに歌おうなどとは思ってもいなかったし、歌えるわけがない。
自分のスタイルで歌えればそれで良しと思って挑んだ。
今回のHarbor lightsのアレンジは、基本的にはオリジナルアレンジに沿ったものにした。
87年のアレンジではこれでもかというぐらいシンセサイザーを導入していたが、今回は必要最小限に留めた。87年当時はやはりシンセを入れることが普通だったというか、当たり前の時代だったのである。
2023年の今は、ハード(リアル楽器)としてのシンセはかなり少なくなっていて、主流はPCの中で立ち上げる「プラグインソフト」というものになっている。
プラグインソフト音源は、楽器やシンセサイザーの音をそのままパソコンで使えるようにソフトウェア化したもので、そのクオリティは本物と比べても分からないほど。
それで本物のシンセやピアノみたいに重くないのも素敵。というか重さはゼログラムである(笑)。
ぼくも今回のアルバムでは、このソフト音源を多用している。
曲のキーもオリジナルアレンジと同じにした。
ぼくはこう見えて結構高い声が出せる(笑)。今回のアルバムでも、ある曲では上はファルセットではなく地声でA(ラ)の音まで頑張った。
それでいて意外と下の低い声も出たりする。でも音域が広いのと歌のテクニックとはまた別物である。
そのあたりが実に難しくてもどかしい部分でもある。ボーカルに関しては一生の課題である。
今回はシンセベースも自分で弾いた。オリジナルバージョンでは、The Fuseの江澤くんが弾いている。
エレキギターもぼくが弾いている。もちろんピアノも。
一聴するとオリジナル版よりも地味に聴こえるかもしれないが、極力音を省いてスリム化した今回のバージョンも、ぼくはとても気に入っている。
続く。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
