
私(たち)が黛冬優子を愛するといって、それはいかにしてか?――愛の技法、またはFの肖像
――右側が堤で、その向こうに海の広がる道にぼくはいる。歩いている薄暗がりのなかを女のあとをつけている。追いついて、有無を言わさずセックスしなければならない。ぼくに対する一種の試験。ぼくに宿る欲望、ぼくがこの対象をそこに与えようと決意している欲望も混じっている。すなわち、だれとでもセックスできなくてはいけない。
(…)そんな配慮が問題となるのは客観性の場合だけであるが、一方、主観性にとっての最大の幸福――私にとってますます重要でありつづけるもの――は、まちがいだらけの恋文や、「綴字法の欠けた艶本」のなかにこそ在るのである。
序章:「書けない」という不能とその美徳ないし悪徳
ある任意のテクスト――あるいは、この世に存在するすべてのテクスト――は、あらかじめ避けがたい宿命をそのテクストが編まれるより前に持っている。すなわち、「すべてを書くことはできない」という、自明にして解決しようのない宿命である。このある種の「どうしようもなさ」から出発しないことには、私たちにはテクストを読むこともできない。「どうしようもなさ」からはじめることなく、簡便さと一通りの身ぎれいさを備えたテクストが様々なジャンルで、紙媒体の面倒なしにインターネットでいくらでも読めるこの現状は、何も神秘化やオカルティズムの無謬的な称揚に頼らずとも、少なくともこの文章の書き手であり、この文章を読もうとする読み手のような「時代遅れ」のオールドスタイラーにはいささか酷なものと成り果てている。懐古趣味をすべからく是とするわけではないが、あらゆるジャンルの興隆と衰退の新陳代謝の速度にあえて抗おうとするテクストの登場は、こういった時代だからこそ来たるべきものとして到来しなければならない。
私たちがこれから語ろうとするゲームのキャラクターは、固有名であることにもはや一切価値はない。それは黛冬優子だろうが、樋口円香だろうが、はたまた早瀬ユウカだろうが、聖園ミカだろうが、なんだってよいのだ。しかし、私たちは都度「担当」を交換しながら、今はあなただけなのだ、という張り裂けんばかりの慟哭を愛するキャラクターにぶつけていたのではなかったか。何も書けなくなる地平で、何も読めなくなる地平で、私たちはそのたびごとの永遠に身をやつすことによってしかこのゲームを闘う術を知らないのではなかったか。好きなキャラクターであればいくらでも語れると思い込んだ矢先から、語る主体はいつの間にかはじめから不可能な恋に浮かされるウェルテルとならざるを得ない。ある人格に対して責任を負うこととは、その人格のすべてを語ろうとすることではなく、描かれたことを追いながら輪郭を素描するまでにたどった軌跡を説得的な形で語ることである。そういった文章こそが、回り道であれ自分の好きなキャラクターに初めて愛していると伝えることができるのである。そして、キャラクターであれなんであれ、愛するものに愛していると叫ぶことが、ともすれば愛する対象を越えて美しく輝く可能性を秘めているということは、あらためて語るまでもないだろう。
シャニマスについて、私たちはどの程度「書く」ことに成功したと言うことができるだろうか?シャニマスというゲームは、キャラクターごとの差異をノベルゲーム的な方法で落としこむと同時に、連綿と続く「アイドルマスター」シリーズの末っ子としてゲーム内に秘められた同一性にタイトル全体が貫かれている。その差異と同一性を掬い取ることがシャニマスの醍醐味であると同時に、いわゆるオタクの間ではすっかり死語となった「萌え」もまた回避できない。それは美少女ソーシャルゲームが持つ最低限のコードであり、また単なるエクスキューズではなく「萌え」に本質が宿ることもある。こうして見ると、シャニマスのコミュはあたかも思弁的な「読み」の段階と、キャラ萌え的なオタクコンテンツの存立要件を「プレイヤーがオタクであること」によって外的に成立させようとする段階の二段階しか用意されていないように見える。
しかし、それでよいのだろうかという疑問もまた残る。いや、さらに言えば、シャニマスがゲームとして次のステージに進んでいる(音ゲーであるシャニソンのリリース)以上、コミュの持つ思弁的な性格さえも脱臭されて、もうキャラ萌えするだけがシャニマスの正しい消化方法なのかとすら思わざるを得ない。そんなことはない、とゲームのシャニマスに一定以上の情熱を注ぎこんできた私たちは叫ばなければならない。決定的に「担当」への愛が炸裂する瞬間を私たちは経験してきたはずである。何度も言葉にするのに挫折し、自らの不能を幾度も幾度も呪ったとしても、「このアイドルが、俺は/私は好きで好きでたまらないのだ」という瞬間を感じるのがやめられなくて、もしかしたらプレイヤーはゲームの外で何か自分の力ではどうにもならない出来事に打ちひしがれたとしても、シャニマスを開いたときの彼女らの笑顔にいつでも胸がいっぱいになってきたはずである。ただ、この感情を何か秩序立てて言葉にする努力を私たちはそのたびに怠ってきたということは無視されてはならない。コミュのモチーフを「謎解き」するのではなく、そのアイドルによって自分の中の何がすり替わったのか、欲望の真の座には何が来るべきなのかという問いに何度もプレイヤーが回帰しつつも、私たちはそのたびに問いを忘却してしまうことを忘却として記憶しなければ、コミュを読む意味はない。キャラクターがその生きざまの中で何を示そうとしたのかということすべてを掬い上げることはできないとしても、自らの愛それ一本でそのキャラクターしか持ちえない孤独と祝福をわが身のこととして引き受けなければならない。少なくとも、シャニマスはそもそもそういうゲームだったはずだ。そうでなければ、放クラの放つ生命の煌めきに、ノクチルの蒼い魂に、私たちが心打たれることもついぞなかっただろう。私たちがシャニマスに負うものとは、「読む」ことの不可能性を越えて「書く」ことをシナリオで語られなかった本質からテクスト上に掴み取る魂の賭けなのである。
この記事では黛冬優子というキャラクターを扱う。こう書いてしまえばいかにも無味乾燥だが、冬優子について語ることのできる語彙は(この文章の書き手が何よりも黛冬優子担当であることを考慮に入れるとしても)そんなに多くはない。では、何故今黛冬優子なのか。あるいは、私たちが冬優子について多くを書けないとしたら、それはいったいどういった理由なのか。
一つに、冬優子において記号的に用いられる「両面性」を解体しなければならないというモチベーションが書き手にはある。「ふゆ」と「冬優子」が果たして分裂であるのかという問いに対して、多くの書き手は無謬的にそれをやり過ごしてきた。当然、これは「読み」の問題であると同時に「書く」ことの問題も黛冬優子というキャラクターの中に繰り込まれている。安易な二項対立を避けるためにも(あるいは、最近の冬優子のテキストがその二項対立を解体しにかかっているのも)、冬優子の自我の問題を一元的な結論に還元するのではなく、美学と倫理の問題として私たちは冬優子の人格の問題を改めて考え直したい。そして何故「今」なのかという問いに関しては、先日実装されたpSSR【三文ノワール】の衝撃もさることながら、冬優子の物語としては【三文ノワール】のリリースで決着がついた(つまり、この後冬優子がどのような道を進むのかについてSTEPと合わせて然るべきところに収まった)と判断できる根拠がある程度出揃ったためとさしあたり回答しておきたい。しかし、私たちはそれでもなお冬優子について語ることは不可能であることを見ることになるだろう。
一つ目の問題提起と骨絡みになる二点目については、黛冬優子という人物の肖像を描くことが困難なのは本人の性質もさることながらとりわけこういった文体で書くことの限界に方法論的な意味で存しているからである。冬優子について論じようとした人々の多くは、シャニマスというタイトルが持つハイコンテクストな性質に内在的に冬優子を結び付け、プライドと両面性という側面から語るために片手落ちになるか、冬優子のテキストを書き手自身のナラティブに回収するかのどちらかになっている傾向が強く、主題的な方法で冬優子を論じようとする文章は(少なくとも今挙げたような「方法論的に無理がある」手法で論じられることが比較的少ないノクチルよりは)あまり見られない。冬優子への距離を見失う前に、私たちは「黛冬優子」を何らかの仕方で基礎づける必要がある。そして、それは読むことと同じくらい重要なことをうちに秘めている「書く」ことの技法がそのままキャラクターに対する愛の技法へと軌道を一にするものなのである。
道具立てが出揃いつつある。私たちはここで黛冬優子を論じるとともに、彼女の持つ悲劇的な宿命を「読む」のではなく成就不可能な思いのたけを引き受けて「書く」ことを選ぶということ。そして、読まれ、書かれたテクスト(テキスト)が読み手に与える永遠と宇宙に賭けること。ここから黛冬優子も、ストレイライトも、シャニマスも始まる。私たちがやろうとしていることは、何度も言うように失敗が前提されている。キャラクターへの愛を叫ぶことは、そのキャラクターを現実に掬い上げる手立てでもなんでもないからだ。しかし、その徹底した無産性からしか二次元キャラクターに対する行き場のない愛情は賦活され得ない。それは、「読む」ことを諦めるのではなく、「読めない」ことを引き受けてなお読むことを選び、そこからさらに進んで「書く」ことが誰にも届かない地平でなおも書くという傍目から見れば狂気の沙汰でしかないことを一篇のエクリチュールにまとめ上げる作業が、黛冬優子が知らないところで彼女を想いながら枕を濡らす名前も知らない哀れなオタクを存在論的に救済することもあるのだ。そういった、生まれつき「何か」であることを余儀なくされたソーシャルゲームの中のアイドルに「何者でもない」誰かが救われることは、私たちにとって何も救いはしないが美しいことではないだろうか。
私たちがこの記事で伝えたいこと、それは黛冬優子を愛する手立てを再度発明することによって、名も知らぬオタクが冬優子への愛を再発見し、そしてこのどうしようもない世界を一日でも多く生きてみようと前を向く契機をこの記事を読む人々に掴んでもらうことである。
第一章:弁証法は蒼穹へ上る――WING、GRAD、STEP
黛冬優子がいかに虚構内存在として定立しうるかという問いに答えてくれるシャニマス内のテキストは絞っていけばかなり単純な構造になる。冬優子の成長譚とは、彼女自身の弁に反して「これがふゆ」という自同性の宣言をある意味で諦めていく過程である。すなわち、自己破砕に始まり(WING)、自我を解体し(GRAD)、最終的に自らの対外的なアイデンティティを「ふゆ/冬優子」より大きな括りで彼女自身が捉えることによって過去のしがらみから自由になる(STEP)という一連の変奏されたビルドゥングスロマンと言うこともさしあたって可能であるだろう。それは冬優子自身が自らを許す過程であると同時に、アイドルになる前まではこだわっていたものを捨てる道のりでもある。冬優子がアイドルに求めていたものがSTEPが公開された今ようやく全貌を見せ、彼女が自らの自我の何にこだわっていたのか、そしてそれは果たして「立ち向かう」ことによって可能となるのか否かという問題に適切に回答が与えられつつある。この第一章では、黛冬優子の弁証法とでも言うべき彼女の精神の逍遥をいささか退屈になること込みで順序だてて解釈するに留めておこう。
冬優子は悲劇の人である。つまり、打ち倒されるべきヴィランがいて、ヴィランを討ち取ろうとして格闘するものの、派手に散って英雄的な死を遂げるヒーローである。喜劇が抽象的な力の戯れであるとするならば、悲劇は具象の関係が必然的に結び付けられ、特有の因果の中で予定調和する。冬優子が悲劇の人なのは、冬優子にとってのヴィランや英雄的な死といった諸々のモチーフが何か具体的な対象を指し示すわけではないのにそれと分かる形で存在していて、彼女にとって見えている結末が常にあらかじめ決まっているという形式が悲劇そのものだからである。それはWINGから【三文ノワール】まで同一の論理で貫かれている。しかし、単に冬優子を悲劇の人と定位するのでは、悲劇の持つドラマトゥルギーを縮減しかねない。これから私たちが閲する一連の共通コミュは、冬優子が自らの悲劇性を折り重ねるように反復しながら、成熟と共にしがみついていた自我を解体して「どうでもよくなる」までのプロセスを示している。自分の運命というものがどうでもよく感じられるようになったとき、その人は運命がどうでもよくなっているというよりは、守るべき自意識や自我を誰かに委ねたり、はたまた委ねる必要がないぐらいそれらが自らという人間を構築する上で不要と感じられる瞬間に直面して自意識や自我を捨てざるを得なかったりすることを運命のせいとしてすり替えている。冬優子はプロデューサーと、お互いが意図しない形でお互いの守るべきものを委ねあっている。そういった持ちつ持たれつの関係性を構築していく過程で、冬優子は明らかに「ふゆ/冬優子」の区別に関して明らかに(ある意味で、という留保は免れないが)「どうでもよく」なっている。そしてそれをどうでもよいものだとするとき、彼女は自分で自分のことを誰よりも許しているのである。
WING編、あるいはSTEP編で、冬優子はアイドルのことを「かわいくて、かっこよくて、キラキラしてて」、「ふゆとは正反対の女の子ばかり」とアイドルへの憧れを隠さない一方で自分を下げている。

冬優子がここで自分のことを下げている(ふゆとは正反対)のが果たして「冬優子」のボロを出さないかどうかの心配なのか、はたまた反語的な表現なのかどうかはこの時点で区別はつかない。結局、STEPを踏まえれば前者の心配込みでアイドルへの憧れが本気であることとクラスメイトから言われた「アイドルになれる」を「真に受けた」ことに対する自嘲と受け取れるが、WINGではそのような背景が描かれることはない。結局冬優子にとって初期衝動めいたものとはなんだったのだろうか?それはほぼ確実に、『ミラ☆ミラ』の中で出てくるようなアイドルに「変身」し、自らを偽るのでも粉飾するのでもなく、「ふゆ」としてステージで歌って踊ることに対する憧憬のイメージだった。そしてこの初期衝動に、ほかならぬ冬優子自身がこの後長らくの間がんじがらめになり、「黛冬優子とは誰なのか」という問いに対して「『これがふゆ』って胸を張れるようなアイドル」という貧相なトートロジーの中でしか息をすることができない自縄自縛の主体を冬優子自身が彼女の体に内面化することになる。

黛冬優子のある種の「正解」として多くの論者が設定する「これがふゆ」(あるいは、「これがストレイライト」と言うことも可能である)というトートロジーは、内実が貧相であるが故に読み手の感情を揺さぶらずにはおかない。何故ならば、アイドルが「私たちはアイドルです」と叫ぶとき、そこには外在性なき自同性の宣言があり、その宣言によってオタクたちは自分の見ている光景が一般的な倫理の埒外で特有の倫理の圏域を形成していることがほかならぬ自分の好きなアイドルによって証明されている実感を得るからだ。冬優子が泣きながら「もう一度、アイドル、やりたい」と言うシーンがこんなにも切実で、本当にいとおしいのは、黛冬優子というキャラクターに吹き込まれた魂がトートロジーとして貧相(つまり、充実した説話構造がない)であったとしても、であるがゆえに私たちの心を揺さぶってやまないのは、冬優子がアイドルとして生きる覚悟を、そして何個でも選び取りえるが、それゆえ一つしかない真理を私たちの前に開示するからである。開示されるべき真理の一端がWINGにおいてある程度見えてきたところで、GRADとSTEPが私たちに黛冬優子の何を教えるかをさらに深掘りしていこう。
GRADにおいて特に焦点が当たるのは、「ふゆ/冬優子」が果たして単なるウラオモテの関係性として捉えられるかという二元論に対して、WINGで開示された「冬優子」を織り込んだ「ふゆ」という真理による問題解決ではなく、「どちらも本当」という形で論理的には間違っている二者択一の破綻を冬優子自身が受け入れているというポイントである。GRAD優勝コミュのタイトルにある通り冬優子は「詐欺師」としてのロールを完璧にこなし、ファンを「騙す」ことで自分の破綻した二項対立を正当化することに成功している。基本的に対立する二項があった場合、どちらかは真でどちらかは偽ということになるが、冬優子の場合、それは当てはまらない。むしろ、それらが対立しているという前提がそもそも冬優子においては誤謬なのだ。「どちらも本当」であるという鎖の輪のような冬優子の人格を、私たちは再度(そして、何度でも)議論の俎上に上げなければならない。

二項対立という語を聞くと、私たちは極めて俗流の弁証法をあてがいたくなる。しかし、冬優子が自らの人格に折り合いをつける過程は、まさに弁証法的な回路を前提として、それを逸脱するような「あえて」の操作が行われているように見える。「どうしたって痛いし、どうしたって幸せで/そういう歩き方にするって決めたのはふゆだから」とこぼす冬優子は、彼女の中にある対立をプロデューサーとの対話の中で――それはあたかも「そうなるようになっていた」という前未来的な形で常に冬優子の口から語られるのだが――練り上げていったように見える。冬優子の中にある「ふゆ」と「冬優子」の「区別」は、ここに来て溶解する。お互いの中でお互いが溶け合い、「ふゆ」と「冬優子」はそれぞれがそれぞれを内包しあう。そして、その二つを制御する冬優子の中の超越的な自我は、その二つが溶け合いながらも別々のものとして働くことを妨げない。「痛い」ことと「幸せ」であることが奇妙にも両立するテキストでは、既に「ふゆ」と「冬優子」が単に双璧をなすものとして描かれていないことを意味する。そこにあるのは冬優子の中で起きる自我の変容であり、彼女が上に書いたような悲劇の人であると同時に弁証法の構築と逸脱をつねにすでにあらかじめ行っている宿命的な人物であることの証左なのである。
上で既に触れているが、STEP編で描かれる冬優子像は自らに折り合いをつけた冬優子が「どうでもいい」という形で成熟したことを描く一種のエピローグと呼んでも差し支えないだろう。STEPの脚本が秀逸なのは、WINGの「台本通りの茶番劇」で冬優子がカメラマンにこき下ろされて逆上するシーンがあえて語られていないことである。これにより、逆説的に冬優子の記憶をプレイヤーは追体験することになる。「台本通りの茶番劇」で見せる冬優子の逆上は多くのプレイヤーの度肝を抜いたことだろう。

STEPの結末では、冬優子とプロデューサーが初めて出会った街の一角で冬優子がテキスト上で今までのことを振り返っている。「あいつにダサいところもいっぱい見られた」と冬優子が言うときに、それでも私たちが冬優子のどこに惚れ込んでいるのかと言えば当然「ダサいところ」である。しかし、冬優子は逃げなかった。自分の「ダサいところ」に向き合い、ときにプロデューサーやストレイライトの面々と衝突し、そのたびに冬優子は剥きだしで彼ら彼女らに応えている。しかし、冬優子が他のアイドルに対して種差的なのは、その剥きだしぶりというよりも、激情と悲劇性があらわになった後で、それをいともたやすく放棄できるところである。それは、「ふゆ/冬優子」の二元論を独自の弁証法ですり抜ける軽やかさでもあるだろうし、単に成熟の問題に還元できない冬優子なりのロジックがあるのかもしれない。STEPの最後は、「案外、悪くないわよ/今のあんた」という台詞で幕が下りる。この「あんた」が「冬優子」であることは疑いようもないだろう。そして、冬優子が「『ふゆ』でなければならない」という呪縛から自分の力と判断で降りる瞬間は、途方もなく美しい。それは冬優子がアイドルとして以前に人間として彼女自身の尊厳を取り戻す手段であると同時に、彼女でしかありえないやり方でアイドルというゲームをサヴァイブする手立てだからだ。
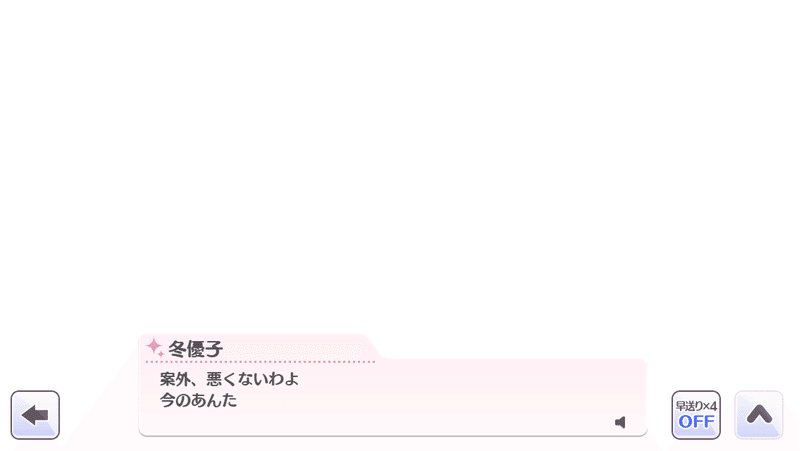
ここまで見てきた冬優子のWING、GRAD、STEPは、一貫したテーマのヴァリアントとして読むことができる。すなわち、自我や自意識といった自らを精神的に規定するものを破壊して再構築するのか、規定そのものの地盤をひっくり返すか、新しい規定に書き換えるか、という自己を巡る一連のプロセスである。しかし、こういった独自の論理系をまとめてみても、冬優子がアイドルたらんとする理由は全容が掴めたわけではない。強いて言えば、GRADの「ふゆ/冬優子」の「二枚舌」に対して自己肯定を高めることができた「詐欺師」としての成功が彼女におけるアイドルの基礎づけであると言うことはできそうだが、結論を性急に求めるのはやめておこう。私たちが最終的に目指すのは、「ふゆ」も「冬優子」もない地点からいかにして「黛冬優子」という女の子が持つ求心力と私たちが一方的に彼女に愛の叫びをぶつけるかどうかだからだ。もっと叫ばなくてはいけない。もっと吠えなければいけない。だが、私たちにはその叫びをできるだけ丹念に描く努力もまた課されているだろう。
次章への助走として、冬優子が「アイドル」にこだわる理由、あるいは「ふゆ/冬優子」でなければならないと考える根拠を雑駁ながら瞥見しておこう。冬優子において、「こうであらなければならない」という命法は倫理に基づいており、それは多くの場合(公式のテキストさえもが)「プライド」の問題にすり替わっている。冬優子に内在するものがプライドであったとしても、最終的な問題の帰着が単に自尊心のものとして一元的に回収されてしまうのはあまり喜ばしい事態ではない。と同時に、冬優子について何か言葉を紡ぐとき、プライドの問題を回避して語ることは非常に難しい。しかし、プライドに関する問いをいったん脇に置いて冬優子を見たとき、彼女の美と倫理を超越論的な問題であるとして問いを立てることも可能だろう。そしてそのような形で冬優子を捉え直せば、シャニマスのテキスト、あるいはシャニマスについて書かれたテクストを読む営みはその前より豊かになるだろう。次章で目指すのは、黛冬優子という女に存する美と倫理の問題を超越論的な主題のセリーとして描き直すことである。
第二章:アイドルにおける超越論的なものとは何か?――【starring F】、【幕間、沸々と高温】、『Run 4???』
既に腐臭を漂わせている「アイドル論」において、かつてオタクたちは好きなアイドルを好きなように用いてこのアイドルは「超越」そのものなのだ!と絶叫していた。当時高校生だった書き手は、Twitterで会ったオタクとオフ会でそのような話に熱を上げ、また翌日部活が終わった足でアイドル現場に向かった。確かに、宇野常寛や濱野智史が言うような幸福な時代というものがあったことを認めないわけには、私たちがここで主張するようなシャニマスについての批評すら可能ではなかっただろう。しかし、そういった幸福な時間には必ず終わりが来る。皆が「どうでもよく、なんでもいい」になり、交換可能な「推し」をとっかえひっかえしては卒業ライブで涙した次の週には別のアイドルの握手会に通い詰めている。そこに「超越」なるものは本当にあったのだろうか。地下アイドルのライブで大してビジュアルが優れているわけでもない女の子にハコがオタクですし詰めになって奇声を上げるあの光景を無謬的に称揚していいのか。あれから10年が経った今、シャニマスで決して私たちに干渉してこない二次元の女の子を見ながら、それでもシナリオや、ともすればホームユニットに編成した黛冬優子の立ち絵を見るだけでも涙が溢れそうなこの気持ちをどう説明すれば、私たちは自分と何の関係もない女の子のことを自分のことのように応援できる感性を正当化できるだろうか。アイドルを二次元だろうと三次元だろうと過剰に聖化することなく、しかしあらゆる規定的なものを越え出ると同時にあらゆる魂の運動を基礎づけることの可能性としてシャニマスを受け取ること。あるいは、ちゃぶ台をひっくり返すようだが、超越と内在のような二項ではなく、似ているようで違う道具立てとして超越論的なものの措定を冬優子の中に試みること。それがどんなに馬鹿馬鹿しいことであれ、一旦「真に受ける」ことぐらいしか、私たちがオタク的言説の中で生き残る術はないのである。
冬優子には所与を享楽する力能が最初から欠けている。それはWINGの逆上もそうだし、【starring F】で中学生以降「ふゆ」として振る舞うことを決めるに至った意志の流れも、冬優子は感性的なレベルで自らを世界が与える享楽から距離を取っている。所与を享楽するとは、与えられた世界に対して一般的な仕方で快を受け取ることである。例えば、なんとなく入った定食屋のカツカレーが美味しいとかでもいいし、愛する人とのセックスでもいいし、ともかくなんらかの外在性を伴う快楽的刺激を受け取って自らの感官を充実させるということである。冬優子にはそれができない。自らの内在性だけで世界が構築されており、外部から注入される快楽を受け取ることを拒否しているように見える。「ふゆ」をあらかじめ決壊する二項対立のどちらかとして設定せざるを得ないのは、所与を享楽できない不能を遍在する真理によって所与を受け取る主体の布置を攪乱する機能が「ふゆ」という主体のうちに存しているからである(「ごまかし」たり、「覆い隠」すのではないことに注意)。
ところが、その「享楽できない主体」の底が割れる瞬間が必ずやってくる。『Run 4???』で全力疾走してあさひを追い抜くあの一瞬を、『VS』で愛依の涙にどうしても自分も泣くのをこらえきれなかったあの一瞬を、冬優子は誰よりも待ち望んでいたのではなかったか。黛冬優子という「お仕着せ」の主体――それには「ふゆ」も「冬優子」も含まれる――をぶち割って、主体の組成が一気に組み替えられてしまうような裂けめとしての奇蹟が報われなければならないと本心から冬優子は望んでいたはずである。だからこそ、ともすれば安易にペルソナという捉え方をされかねない「ふゆ/冬優子」というそれ自体一種の擬制として自らに享楽を禁じるという形の生存戦略を選んだ結果が「ふゆ」であり「冬優子」なのである。そこでは打算もなく、裸形の魂が私を壊してくれと叫ぶ冬優子の悲痛なわななきを聞くことすらできるだろう。
第一章では、既に破綻した弁証法の理路に冬優子を乗せて単なる「二面性」ではない分裂の在り方を示したが、【starring F】は冬優子が今のスタンスを獲得するに至った経緯が直接的に語られる部分は少ないものの、はっきりと分かる形で(いささか図式的な整理という誹りは免れないものの)コミュの中に落とし込まれている。STEPや後述する【三文ノワール】でも共通していることだが、冬優子は自らの一筋縄ではいかない分裂の問題に対して「どうでもよい」(=アイドルの「ふゆ」とそうではない「冬優子」を使い分けることに関して何の葛藤もない)ことと考えている。そしてその鈍感さは冬優子が中学生以来向き合ってきた問題であり、GRADで言及がある通り「人から思われるより大変じゃない」という形で冬優子本人が自分を納得させている。

一方で、そういった「どうでもよさ」をある程度内面化することは冬優子にとってある種の防衛機制とも読み取れる。「傷ついてもいいから頑張る」ことは、あさひや愛依を引き合いに出されてそれでもなお自らの立ち位置とするべきパフォーマンスを言動と一致させる努力でもあるだろうし、「自分を傷つけてもいい」としてアイドルをやることには冬優子自身が明確にノーを突き付けている。ここで問題となるのが、プライドすなわち美と倫理の問題ではないという否定の命題である。
冬優子にとって、「アイドルをやる/である」ことは何を意味するのかというクエスチョンは一見答えることがたやすそうに見えて実のところ茫漠とした答えしか導き出せそうにない。しかし一つ言えるのは(そしてあさひや愛依と決定的に異なっているのは)、アイドルに必要な職能と黛冬優子を「ふゆ/冬優子」として成り立たしめる回路に冬優子自身が一定の相似を見出しているということである。それはつまり、やっていいことと悪いことという前提がまずあり、それを踏み抜く自我の超越論的な権能がどちらにも適用できて、そして善悪を踏み抜く瞬間に彼女はパブリックであれプライベートであれ快楽を得ているということである。しかしながら、彼女は滅多なことではその自分なりの倫理(超越論的な権能)と美(快楽)を発動することがないばかりか、むしろ自分からそれを発露するのは「はしたない」とすら思っている。そして私たちが何よりも黛冬優子に惹かれるのは、こういった理性と反理性のせめぎ合いが現実よりもリアルであるからではないだろうか。そして、【starring F】の最後で放たれる「ありがと、バーカ」という言葉に、道徳とは異なる彼女だけの倫理と、プロデューサーとの関係を慈しむ美的感性が集約されていると述べることすらできるかもしれない。
そういった意味で、トワイライトコレクションの【幕間、沸々と高温】で描かれる「ちゃんと怒りなさいよ、自分のために」と冬優子がプロデューサーに注意するシーンは、冬優子における価値判断をよく示す好例だろう。横暴なディレクターに対して怒りを隠すこともない冬優子にとっては、自分がどうでもいいと思っている(あるいは、気に入らない)相手に対しては守るべき道義もモラルもない。冬優子にとって大事なのは、善悪の彼岸にある超法規的な(何が善で何が悪かを決めるシステム)倫理が冬優子の意向にときに反してでも倫理の方が先に動くことや、自分にとって美しかったり気持ちよかったりすることであり、それは何にも優先される。

ところで、何故冬優子においてはことさら「二面性」と「プライド」が(偽の)問題として浮上しがちなのだろうか。二面性については、シナリオをよく読めば読むほど彼女の自我において主題的なのは「どちらかが裏」なのではなく「どちらも本当」であることが止揚されず解体へ向かう弁証法として表象されていることにすぐ気づくことができるが、プライドが偽の問題なのはシナリオ上ほぼ常にミスリードである。むしろ、シャニマス側がプレイヤーに要求している読みは偽の問題を正当化する読みであるとすら言えるかもしれない(それは冬優子の語りが「冬優子がそう言っているから」というだけでテキストの正当性を主張するだけのあまりにナイーヴな読みなのは言うまでもない)。しかし、それでもなお冬優子は美と倫理の人なのである。何故ここまでしてオーセンティックな「誤読」を批判し、冬優子を解釈するにあたって新しい軸を思考しなければならないかについて不十分ながらいくばくかの証言をしておくに留めておこう。
『Run 4???』は、「冬優子があさひにリレーで勝つ」という、ストレイライトの「誰にも負けない、互いに負けない」というテーマがこれ以上ないほどシンプルかつスマートにアレゴリーに移し替えられた筋立てである。白眉とも言えるクライマックスである第6話「run selfishly」で、冬優子は初めて直面する二者択一に迫られる。すなわち、台本の筋書きを書き換えてでもあさひと勝負できるなら「やってやる」のか否か。これに対し、冬優子は最初「それは愛依の役目だから」と言って断る。しかし、このシナリオの最大の美点は、冬優子がプライドではなく、あらかじめ踏み抜かれる美と倫理を前にしてたじろいでしまうそのためらいにこそある。つまり、「やっていいこと/ダメなこと」の向こう側に行くことの躊躇、そしてもし「ダメなこと」を選んだらアイドルとしての「黛冬優子」ではなくなってしまうのではないかという恐れである。好き勝手動くあさひのようにはなれないと思えばこそ、余計に愛依の役目をぶっちぎって「自分勝手」にあさひと戦うことは許されないことなのだ、と。そして冬優子は、「嫌なのよ/ちゃんと、仕事をしないのは……」と述べる。

そして、その踏み抜かれようとする美と倫理の前で立ち往生する冬優子の背中を押すのは、ほかならぬ愛依である。「冬優子ちゃん、ちゃんと仕事してるじゃん」「だから、自分勝手になっていいんだよ」と愛依は冬優子に言う。誰よりもその板を踏み抜きたかったのは冬優子だった。しかし、愛依がいなければ板に足をかけることすらできなかった。何故この冬優子と愛依のやり取りが掛け値なしに美しいのか?それは、ある主体がうちに秘めつつもかけがえのない第三者と共有している観念がその第三者によって行為となって具象化する事態がそもそも奇蹟だからである。冬優子は、誰によってでもなく自分で自分のことを肯定してきた。その意味では、彼女は誰よりも誇り高くストイックである。しかし、その誇りの奥に眠るやぶれかぶれで手のつけられない超越論的な倫理とすべてを台無しにすることの美しさを知っていればこそ、我慢した分だけその快楽は跳ね返ってくる。当然のことながら、『Run 4???』の幕切れは冬優子の中に眠る初期衝動的な美と倫理が、リレーという運動にオーヴァーラップして勝利を収めるという喜劇でしかあり得ない。このときばかりは冬優子は、悲劇の代理人であることをやめ、自らが喜劇の主役であることを勝ち誇って高笑いを上げる。喜びが、成就が、テキストの中に充満している。そしてテキストの中で、冬優子は誰のためでもなく、悲劇が喜劇へと転じる瞬間の幸福を味わうのである。
私たちはこの章で語るべきことをいくつか留保してしまっているようだ。例えば、冬優子の冬優子自身でさえ制御できない美と倫理が超越論的であることは分かったが、黛冬優子という存在そのものは超越論的なものなのだろうか。これに関しては、冬優子というパーソナリティ自体がメタ的に何らかの価値判断を行うわけではないという観点から冬優子を超越論的なものと呼ぶのはシニフィアンとシニフィエの関係がそもそも成立しないので超越論的ではない(というか、そもそも問いの立て方がおかしい)と言うのが適切だろう。本章でことさら問題として取り上げた美と倫理の問題が超越論的な(transzendental)ものとして浮上してくるのは、どちらも固有かつ普遍的な価値判断をメタ的に行うにあたって必然的に要請されるからである。つまり、冬優子の「これはいい」「これはダメ」という判断を成り立たしめているものこそが冬優子にとっての超越論的なものであり、冬優子が超越論的であるわけではない。他にも詳述しなければならない問いはあるが、さしあたって価値判断に関わる問題の水準がキャラクターに対するものかそうでないかで異なるということだけ確認しておきたい。
第三章では黛冬優子の始まりであり現時点での終着点(あるいは新たな始まり)である『Straylight.run()』と【三文ノワール】を主題に、冬優子が見ていた世界像を解釈の上で再構築することを試みる。とりわけ、【三文ノワール】で提示されるアイドル観や永遠の両義性、そして映画というモチーフがコミュの相互で呼応している様をどの程度的確かつ十分に記述できるか分からないものの、この文章でテーマとなる黛冬優子をいかに私たちは愛することができるかという問いに結び付けて描くことが当座の眼目となる。
第三章:ペシミズムに陥ることなく適切に世界に絶望すること――【三文ノワール】、『Straylight.run()』
とはいえ、やはり黛冬優子が黛冬優子であるのは、彼女が悲劇の人だから、という以外には特に抽象的な説得性を持たせるのに十分な他の形容が私たちには思いつかない。冬優子は、常に敗北することを選んでいる。それは、あさひや愛依であり、プロデューサーであり、カメラマンであり、またあるいは時間そのものであったりする。それぞれが冬優子を打ち倒そうとするヴィランに仕立て上げられるのは、言うまでもなく冬優子自身の手によってである。そして何にも救済されることなく彼女は闘いの中で息の根を止められ、見苦しく悶え、喘ぎの中に死ぬ。黛冬優子の葬礼で鳴り響くラッパは、彼女を讃えると同時に哄笑する。悲劇的であることの条件は、それ自体皮肉なことに悲劇がコミカルであらねばならないということである。冬優子はあるときはヒーローに、あるときはピエロになって、自らの不能力を嘲笑い、そして無念のうちに倒れるのだ。本論の終結部で見ることになる【三文ノワール】が何故冬優子のコミュの中でひときわ異彩を放つとともにシャニマスの神髄とでも言うべきシナリオの完成度を放つかについて、最終的な目的地点を【三文ノワール】からずらしつつ、しかし中心的な主題を見失わないように述べてみよう。
【三文ノワール】で反復されるテーマはひとことで言って「永遠は時間に内在するか否か」という問いである。しかし、このあまりにも素朴なクエスチョンを私たちは先の分析で解体する術を身につけたのだった。つまり、「これはありやなしや」という二者択一のどちらも選ばず、どちらも選ぶという技法を崩壊する弁証法から美味しいところだけ「パクって」思考パターンに組み込むことが、哲学書ならいざ知らずこのゲームに関しては「アリ」ということになっている。だが、扱っているテーマが相応に重厚なため、この技術を用いる際にはなおさらの用心が必要であることは言うに及ばないだろう。「永遠」と「時間」は、一見――それこそアンリ・ベルクソンのアの字も知らない人からすればごく素朴に――「時間」に対する状態の説明として「時間が永遠に感じられる」といった風で述べられるため、「永遠」という「時間」があると思っている人も少なくないことだろう。実際、【三文ノワール】で重要な役割を果たす映画監督が「未来の幽霊」という形で映画の中の俳優たちを表現している箇所は文字通り「永遠」=「時間」の一対一対応が成立しているように見受けられる。
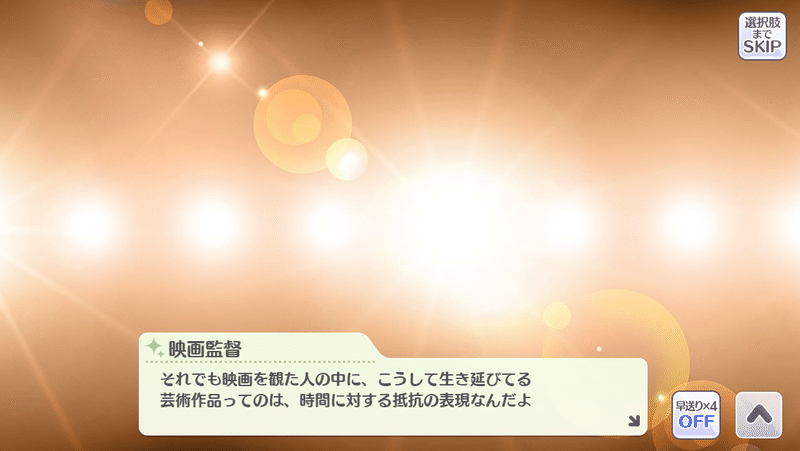
確かに、映画というメディアが資料的価値含め年月の経過からある程度自由であると言うことはできる。とりわけこの映画監督の文脈ではアイドルが消費の対象であることと対比されているため、「アイドル」=「一瞬」で「映画」=「永遠」という対照を読むことはアクロバットなしに可能である。であるならば――冬優子が選んだ道である「アイドルとして時間に抗う」とはどういうことなのか?

先程名前を挙げたフランスの哲学者、アンリ・ベルクソンはその最初のまとまった著作である『意識に直接与えられたものについての試論』(『時間と自由』)の中で「持続」という概念を発明している。ベルクソン的に言えば、時間には二つの相がある。量的時間と質的時間という区別を設け、前者は1秒、2秒……と数えられるものであり、後者はその時間の中に置かれた主体にとって感覚的に伸び縮みする時間(つまらない校長先生の話を聞く30分と、友人と楽しく話しているときの30分はベルクソン的には「質的に異なる」と言われる)。少し難しい文章になるが、『試論』から一節引いてみよう。
(…)そうなると、われわれは今度は感覚を空間のうちで展開するのだが、自己展開していく有機的組織や、相互に浸透し合う諸変容の代わりに、われわれは、同じひとつの感覚がいわば長く延長され、それ自身に無際限に併置されていくのを覚知する。真の持続、意識が知覚する持続はこうして、強度的と称される大きさのひとつに数えられることになろう。
要するにこういうことである。持続という形で主体に知覚される時間(質的時間)はそれが感じられるだけの段階の時点では「強度的と称される大きさ」として漠然と意識上に上るに過ぎず、「同じひとつの感覚」が「長く延長される」ことによって量的な(計測可能で有限な)時間からは免れる(このあと、「感覚を空間のうちで展開」=刺激が数値化される(量化される)ことが持続との対比で説明される)ということになり、持続が言語や数値によって置換不可能であるという旨のことがここでは主張されている。話を戻して、冬優子が「アイドルとして」追い求める「永遠」の時間性とは、ベルクソンの言う持続のようなものとして咀嚼することが可能であると多少の牽強付会を承知で断言してしまおう。つまり、永遠には二つの様態がある。一つは、時間の制約を受ける永遠(ベルクソン的に言うならば量的時間)。これは映画のフィルムが適切に保管されれば「100年後」も観ることができることが例として挙げられる。もう一つは、ステージ上で放つ一瞬の煌めきに宿る「永遠」(これは質的時間)。冬優子は、アイドルの矜持として、後者の永遠の中で生きることを選んだ。映画監督の言う永遠と、冬優子の言う永遠は本性から異なる。それは単に一瞬か無限に延びるかというだけでなく、それぞれをお互いに内包しようのない質的な差異が両者の「永遠」という語に含まれているということである。
【三文ノワール】は、今までの冬優子のどのpSSRにもない形で冬優子の世界に対する絶望を描いている。それは、量的な意味で永遠に生きることをスクリーン上で余儀なくされた「天才」である女優の黛冬優子のみが味わう絶望であり、あさひの「天才」とは異なった意味で「幽霊」になってしまった冬優子に課せられた呪いであるとも言える。コミュタイトルやそこここに散りばめられたともすればペダンティックな「シネフィル向け」の映画の元ネタは、引用されたほぼすべての映画が白黒映画で現在観ることができるということ、そして最後のゴダール『気狂いピエロ』(ランボー『地獄の一季節』)からの引用だけがこのカードの中で出てくる唯一のカラー映画であることは看過できない。冬優子が見たのは極彩色の黄昏であり、色づくことによってより鮮明となる世界の終わりのイメージである。
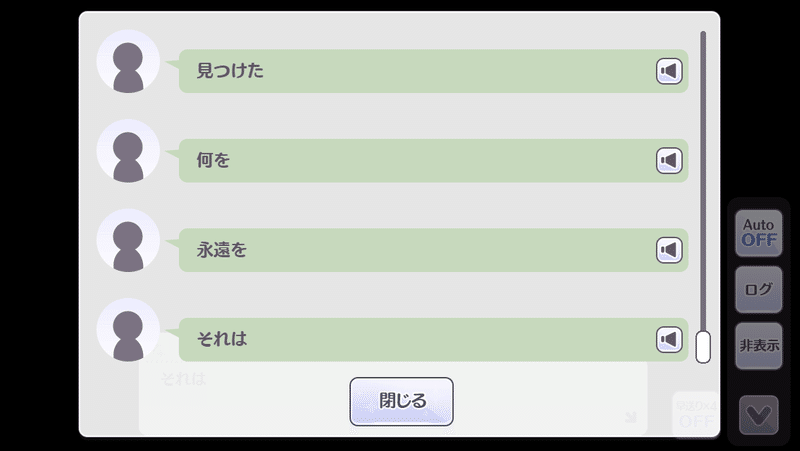
【三文ノワール】が傑出しているのは、永遠という時間のアスペクトを冬優子に固有なものとして冬優子の自体的な語りで留めることなく、映画という対照項を設定することにより冬優子にしか/でしか語られることがない(そして本質的なことが直接冬優子の口から語られるわけではない)特異な「永遠」の相を描き出したことであるとひとまずは言うことができるだろう。では、冬優子が陥っている真の絶望とは何か?「ユウコ」があくまで映画の中のストーリーテリングで時間的な永遠を選び取った結末を見て悲しげな表情を浮かべる冬優子にとって、世界がどう立ち現われてくれれば彼女の一人芝居である「悲劇」の幕を下ろすことができるのだろうか?
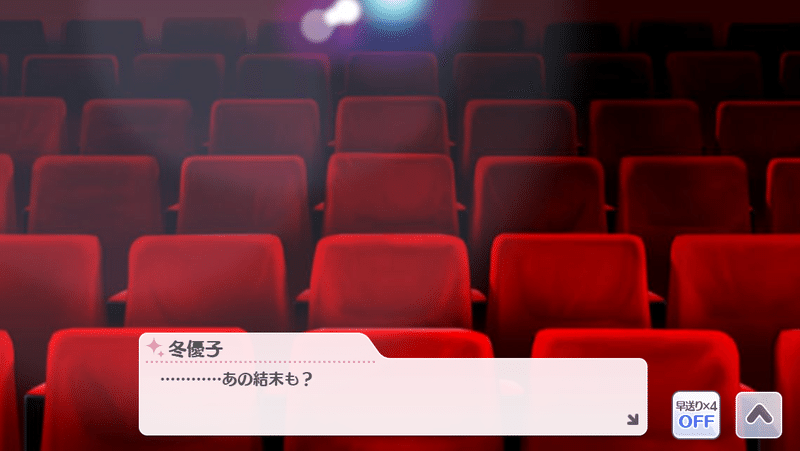
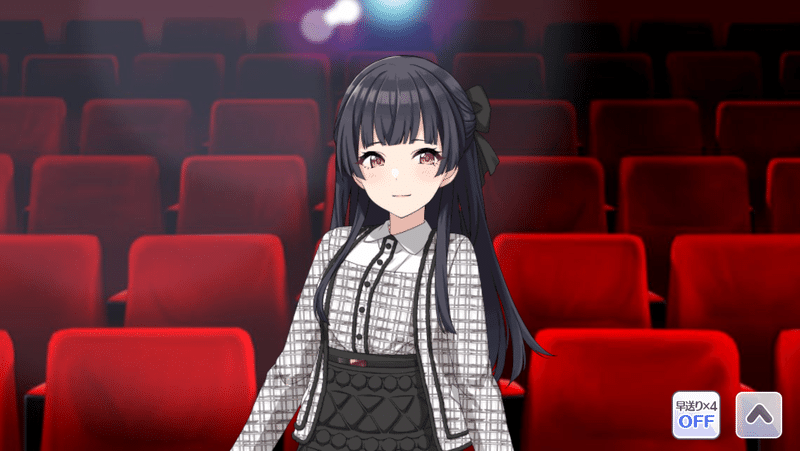
冬優子は、実のところ、ストレイライトが始まったときから世界を見限っている。自らの中にある自壊することが宿命づけられている弁証法も、かけがえのない誰かによって誰かを救い、自らを救う美と倫理も、彼女が一番それが何の役にも立たないことを知っている。どうすればこの世界に「目にもの見せて」やれるのか、痛快な「詐欺師」として世界を欺くことができるのか、冬優子だけがそれらの問いに一人で立ち向かい、そしてそのたびに彼女は巨大な不条理に打ち倒される。アイドルとして有限な生を特異な永遠として生きながらえることが、焼け石に水でしかない抵抗であると知りながら、彼女は世界の終わりにメガホンで絶望を絶叫する。『Straylight.run()』で理不尽な目にストレイライトが遭ったとき、誰よりも誰かのために苦い涙を流し、誰よりも怒り、自分の中にある美と倫理を蹂躙されたことを真っ当に告発しようとしたあの気高い黛冬優子を見て、彼女が何故悲劇的でないと言えるだろうか。「バカ正直が通用する」ような世の中でない「バカバカしい世界」を断罪する彼女のあまりの愚直さは、私たちに黛冬優子について語る言葉を失わせる。

冬優子は、バカ正直であることが報われないこの世界で、誰よりもバカ正直が報われることを望み、そしてこの世界がほんの少しでも良いものになればいいと誰よりも願っている。そして冬優子は、シャニマスというゲームの中で成長するにつれて、だんだんと「どうでもよく」なっていっている。それはSTEPでもそうだし、【三文ノワール】でもそうである。ミクロには自我の問題にさじを投げることで終止符を打ち、アイドルとしてはあまりに身もふたもないような形で自らが消費されることを「永遠」という名のもとに肯定する。もちろん、それらはすべて冬優子がこうありたいと望んで得た結論のはずだ。しかし、その冬優子の決定は、19歳の年端もゆかない少女が得る結論としてはあまりに老成しすぎている。私たちがだんだんと世界に何も求めなくなっていくように、冬優子の中でアイドルもストレイライトも世界そのものも、いつかやってくる終わりに備えるだけの「消化試合」が始まっていくのだろうか。
いや、それでもやはり、私たちはこの世界と黛冬優子を愛さずにはいられないのだ。どんなにバカバカしい世界でも、どんなに不条理でも、日々を耐え忍んでやってくる奇蹟や美や倫理を信じられるから私たちは生きていられるのではないのか。冬優子が私たちに教えるもの、それは適切に世界に絶望する方法である。自己憐憫にもペシミズムにも陥らず、希望と絶望を両手に抱えてこの世界をサヴァイブする技法を私たちはここまでの冬優子の分析から勝ち得ている。ならば、最後に私たちが自身に問うとしたら以下のようなテーゼが導き出されるだろう。黛冬優子を愛するようにして世界を愛することは可能か?あるいは、「担当」について書くということは世界を記述することと同義なのか?
終章:世界から光が消えるとき――それでも「あなただけ」と言い続けるには
本論で言いたいことはたった一つである。言葉をどんなに尽くしたところで、どんな華麗な修辞を用いたところで、私たちが黛冬優子を愛する理由のいくらかさえ伝えたことにはならないということを、改めて私たちの前に開示すること。序章で述べた「書けなさ」とは、対象との距離を見誤っているが故に起きるエラーであると単純に言い切ってしまうのは語弊がある。私たちが対象との距離を見失っているということを客観的に述べられなくなったとき、私たちはその対象に呑まれている。そして呑まれてしまったら、どんな言葉を費やしたところで無力感に苛まれるだけで、あらゆる言語活動は徒労であると大した文章も書いていないのに疲弊してしまうのがオチである。
私たちは黛冬優子に関して――繰り返しになるが、書き手が黛冬優子担当であるという困難をなお排して――できる限り正確に彼女によって表象されているもの、あるいは彼女の眼に映っているものを描写しようと試みた。しかし、こんなことははっきり言ってそれこそ「どうでもいい」のである。私たちが冬優子のWINGで全身が震えるほど泣いたり、はたまた【三文ノワール】で言葉を失ったりする経験をいかに自分の中で消化できるか、こういったシャニマスのゲームに関わる根本的な問いをシャニソンのリリース以降私たちは考えることを迫られている。
黛冬優子を愛するようにして世界を愛することは可能か。「担当」について書くことは世界について書くことなのか。世界は冬優子ほどチャーミングではないし、邪悪だし、不条理に満ち溢れている。そして、「担当」について書けば書くほど、世界は砂のようになって指の隙間から零れ落ちていく。しかし。それでも、私たちはもう少しだけ冬優子を信じるようにして世界を信じてみたいと思う。その信じた先が絶望と破滅しかなかったとしても、私たちが世界を信じることは、つまり愛を信じることだからだ。ジル・ドゥルーズが映画を論じた『シネマ』の一節にはからずも一致してしまったが、ドゥルーズが半ば横暴な形で映画と世界を結びつけたのよりは、私たちは冬優子と世界の双方を信じることができる可能性についてクリティカルに述べることができたと思う。あるいは、自分の欲望の対象について、いくらか正直になって書いてみることは、書くという営みがあらかじめ不可能な営みであることを越えて書き手自身が世界とつながっていることを実感できる数少ない営為である。冬優子について書くことは、すなわち複数形ではない「私」について書くことに他ならなかった。これは、浅倉透だろうと、樋口円香だろうと、緋田美琴だろうと、田中摩美々だろうと、可能にはならなかった。冬優子について書くということが、すなわち「私」を書くことであり、世界を書くことに他ならなかった。そして世界を書くことから、担当も世界も信じられるのである。
さしあたって、この決して短くはない文章を閉じるにふさわしい痛快な一文は出力できそうにないが、この極めて個人的な黛冬優子についてのエッセイを締めくくろうと思う。「だれとでもセックスできる」このヴァーチャル・パラノイアの世紀に、あなただけしかいないのだ、と、黛冬優子さんに愛をこめて。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
