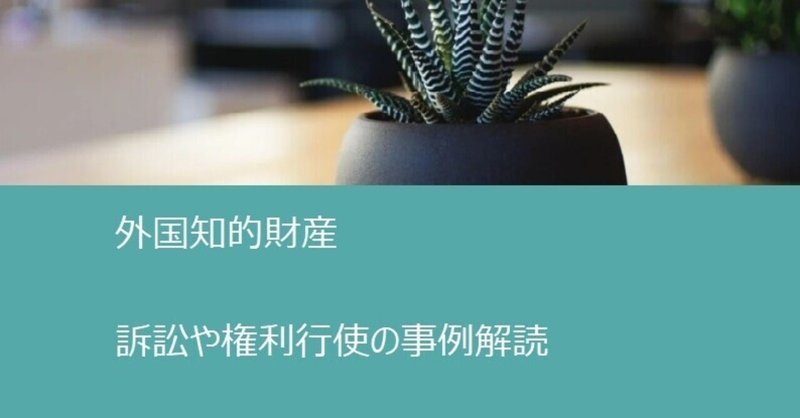
中国 懲罰的賠償の司法解釈について
中国では、3月3日付、最高人民法院が知的財産権侵害の懲罰的賠償の査定方法について解釈を公示し、悪質な侵害行為に対するしっかりした処罰の方向性を明確にしました。これは、アメリカのトランプ政権時に二国間協定の対象項目であり、国内大手企業による侵害得に対する強い不満の表明も強い後押しになり実現したといえます。これまで中国政府は中国には事情があるのだと言って、国内の貧富の差、特に地域的な差が大きいが、による共産党の施策が国内の様々な変化と経済状況に押し切られ大きく舵をとった感じともいえる。いずれにしても、韓国も懲罰的賠償を昨年から実質的に入れており、司法による恣意的な判断が導入されることになりました。
中国での懲罰的賠償については、悪質な行為が目立っていた商標分野で、まず2014年と2019年の商標法改正(第63条)で導入され、2015年の種子法改正(第73条3項)でも導入された。その後、2019年の不正競争防止法(反不正当競争法第17条3項)、2020年の特許法(第71条)と著作権法(第54条)の改正でも懲罰的賠償条項が追加された。こうした流れを加速したのは、2019年に立法化された民法典の第1185条に「他人の知的財産権を故意に侵害し、情状が重大である場合、被侵害者は相応の懲罰的賠償を請求する権利を有する。」と規定され、今年2021年1月から施行されたことから、知的財産権関連の法律法規はすべてこの規定に対応して改正されていくことになります。
知的財産権侵害に対する賠償は損失の補償という建付になっているため、中国では逸失利益を実損の算定、ライセンスレートによる算定などに基づきますが、独自の算定として、法律で上限を決めた法定賠償額が導入されています。前者は原告が一定の逸失利益額を証拠とともに立証する義務があります。後者は初歩的な証拠に基づき裁判官が裁量により決定します。裁量と言っても裁判官が決めた内規があり、それを参考にしています。もちろん、難しい案件は裁判所内で検討会を開いて決めているわけです。こうした中で、懲罰的賠償を導入することになりました。中国での法律規定の制定は、まずやってみるとの経験則に基づき、その後それを見ながら意見募集のような特定関係者からの意見や調整成案を受けて決定していますので、懲罰的賠償の判決は既に複数出されていますし、最初に判断基準を出したのは2019年の江蘇省高級人民法院の指導意見によるものです。ここでは、こうした状況を踏まえて、懲罰的賠償について、いくつかのポイントを挙げで考えてみます。
1. 故意と悪意について
日本などでは法律の建付けとして「悪意」はありません。中国の民法典も「故意」としており、日本の法曹界では「知りながら」になります。故意については、直接的故意と間接的故意(発生意図がない)の場合ありますが、悪意については明確な共通の認識や定義がないと思います。商標法上は故意による侵害の規定はありますが、悪意は出願においてのみ使用されており、基本的に違いはないように考えられますが、おそらく過失が含まれない前提から、故意の場合でも、その程度が更に強く、悪いものを指して悪意と言っていると考えられます。例えば、知りうる、知りうべき、知りながら、知っていて…で悪意のような感じでしょうか。つまり、悪意には道徳的な意味合いもあり、心が悪く、たちの悪い意図があるさまをいうため、悪意は故意に基づくかなければならず、明確に行う行為の結果を知っていて自発的に行う動機がなければならないということになると考えるのでしょう。なお、商標法と不正当競争防止法は悪意と条文上規定しているため、司法解釈の発表記者会見では、故意も悪意も同じと考えると説明しています。
今回の司法解釈では、第3条に故意を認定する事例を6項目挙げています。
①警告してもやめない、②当事者間に利害関係者による支配関係がある、③被告が労務関係などから知的財産権に接触したことがある、④被告が業務関係から知的財産権に接触したことがある、⑤被告が海賊版や登録商標を偽造したことがある、⑥その他の故意。
その他とは何と考えますが、2019年の江蘇省高級人民法院の指導意見は以下の通り、やや具体例になっています。
①警告書後も侵害行為を継続した場合、②使用許諾関係の終了後も継続実施した場合、③仮差止の裁定後も継続実施した場合、④裁判所或いは行政機関の処罰決定後も継続実施した場合、⑤侵害者が名称変更や別法人になり侵害を実施した場合、⑥著名商標のフリーライドなどの商標権侵害行為などの状況を実施した場合。
いずれにしても、こうした状況があったと判断される場合は、証拠とともに懲罰的賠償を申立てるべきということです。
2. 情状が重大について
情状が重大(深刻)な状況について、司法解釈の第4条は、権利侵害の手段、回数、権利侵害行為の持続期間、地域範囲、規模、結果、権利侵害者の訴訟中の行為などの要素を総合的に考慮するとし、その認定事例を7項目挙げています。
①再犯、②事業としての知財侵害、③証拠の偽造・毀損・隠匿、④保全措置拒否、⑤巨額の利益や損害、⑥社会的影響、⑦その他
こうした事情からすると悪意の道徳的で質の悪い場合が対象となっているように判断されますが、中国ではよくある事情で、判決を数多く読んでいるとこうしたことがしばしば起きていることがよく分かります。
3. 賠償額と懲罰的倍数について
賠償額に侵害を差止めるために支出した費用、言わる合理的な支出は含まれません。この認定はいろいろありますが、ここでは考えません。ご参考までに、通常、原告の証拠収集や提訴までの弁護士費用などは少なくとも800万~1000万円はかかります。
賠償額の認定方法は特許法第41条、商標法第63条、著作権法第54条、不正競争防止法第17条、種子法第73条に規定がありますが、最近は証拠保全による会計資料やデータの取得による算定、裁判所による関係資料の提出命令による算定を頑張る方法もあり、積極的に高額賠償を狙う事件も多くなっていますが、初歩的な証拠に基づき、販売数量や利益率に基づき一定の逸失利益を主張することになります。裁判所は原告の実際の損失額、被告の違法所得額或いは権利侵害により獲得した利益を算定根拠に判断しなければならないですが、その算定方法が正しいかどうかを判定することになります。通常は、被告に立証の転換することになるため、反証がなければ原告の主張を認めるとの建付けになっています。
そこで、3倍から5倍の倍数ですが、主観的過失の程度、権利侵害行為の情状の重大な程度などの要素を総合的に考慮するとし、裁判所の裁量に任せる建付けです。これまでの判決では3倍からで、5倍は社会的影響がある場合や強い司法の意思表示の場合などになるのではないかと考えています。
4.その他の注意点
今回の司法解釈だけではないですが、原告の主張は後出しはできませんので、損害賠償金を目的とした訴訟であれば、先ずは提訴時点で懲罰的賠償も請求に入れることが必要です。なお、司法解釈では第一審の口頭弁論終了時までにその増額の申立をすることができるとしています。
損害賠償額の査定では、特に特許侵害の場合、自社の利益率やライセンスレートを参酌するとの規定があるなど自社の営業秘密が出ることになるため、十分な対応をしなければならない。比較的想定損害賠償額が大きい場合や事業に対する影響の大きな侵害の場合は、証拠保全で算定のための証拠収集をすることが好ましいと考えます。
最後の注意点は、せっかく懲罰的賠償が認定されたのに被告が賠償額を支払えない場合です。中国での訴訟では被告の経済状況の変化に提訴前から注意深く確認し、必要に応じて財産差押えの保全措置を早めにとることは肝要です。
以上、これまでの訴訟経験などからの思考を巡らせましたが、ご参考になったでしょうか。
■著作権表示 Copyright (2021) Y.Aizawa 禁転載・使用、要許諾
上記は仮訳であり何ら保証や責任を負うものではありませんので、原文を必ずご確認ください。転用する場合は事前にご連絡ください。なお、ご購入頂いた方でPDF版や改正履歴をご希望の場合はお気軽にご連絡ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
