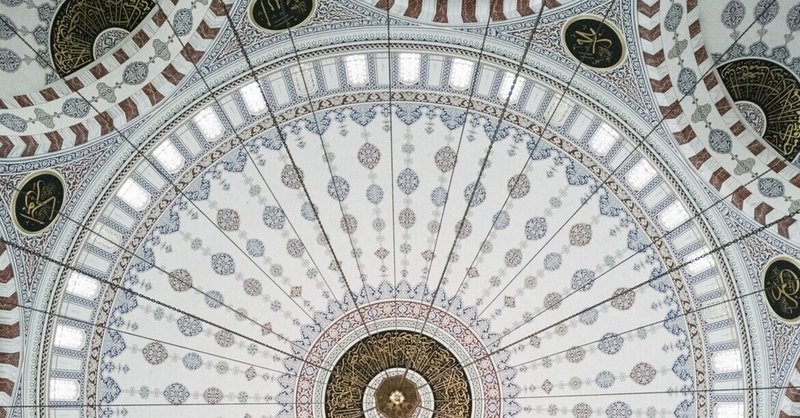
ポスト・モダンの音楽論
はじめに:録楽化社会論を超えて
2022年5月、私は社会学者、小川博司の「音楽化社会」という社会評論を批判的に読み解き、現代を「録楽化社会」だと指摘した。
現代は、自分にとって不愉快なノイズである他者を簡単に排除してしまう社会である。
現代の録楽化社会では不確実性が嫌われることが多いです。「わからない」ということや「わかりにくい」ということは好まれない。複雑なものが嫌われる。それはウイルスであれ、人間であれ、制度であれ、未知のものは嫌われる。そして、未知のもの、理解しがたいもの(不愉快なノイズ)が簡単に排除される不寛容な社会が構築される。
不愉快な他者をノイズとして排除せず、共生してゆくにはどうすれば良いのか、ジョン・ケージを手がかりに評論したのが『「録楽化社会の現在」という話』になる。
だが、私は改めて『「録楽化社会の現在」という話』で評論したことを超えて、録楽化社会論を発展させ、ノイズ(他者)との共生について本稿では論じてみようと思う。
本稿は、前近代(プレモダン)から近代(モダン)、そして現代(ポスト・モダン)までの音楽史を俯瞰し、音楽と人間の関わりを現代思想から読み解くことで、改めて人間が音楽的に生きるとはどういうことなのかを論じていこうと思う。
第Ⅰ章:モダンの音楽
近代(モダン)とは、まず大きな物語に向けて全人類がともに進歩してゆくという、進歩史観が支配的な時代であったと言える。より具体的に言えば、資本主義が発展し、科学技術の進歩や、民主主義の定着が、我々人類の生活を豊かにしてゆくと考えられたのだ。
こうした進歩史観は、ベートーヴェンの音楽にも読み取れる。まずは《第九》を聴いてみよう。
このベートーヴェンの音楽について、音楽学者の岡田暁生は次のように評論している。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
