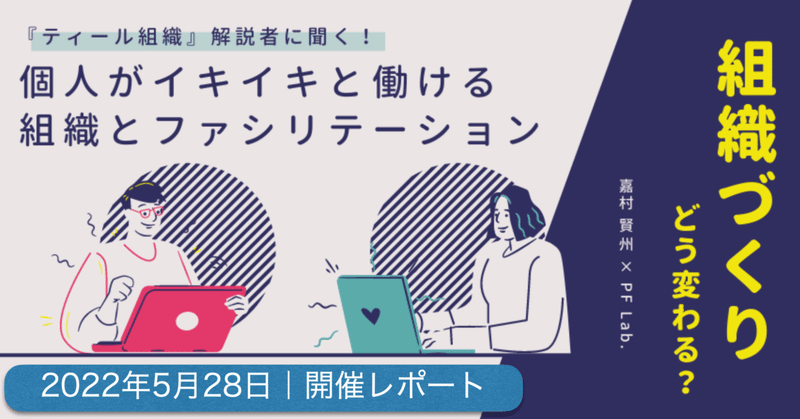
【イベントレポート】個人がイキイキと働ける組織とファシリテーション〜『ティール組織』解説者に聞く!
こんにちは。
今回もPFLabの木戸としてイベント開催レポートのnoteを書いてみました。
前回同様、そうとう荒い文字起こしです。はじめに謝っておきます。すみません。
前回、4/17に開催したファシリテーターに関するオンラインイベント。
その続編のイベントが5/28に実施しました。
今回も、緩やかに開催レポートっぽく文字起こしをしてみたので、みなさんの現場でのファシリテーションの参考にしていただけたら幸いです。
以下は、前回の開催レポート。
これから学び始めたい方や学びなおしたい方向け。
そして今回は、「個人がイキイキと働ける組織とファシリテーション」について。
ティール組織の話も少し?入ってきます。知らない方にも伝わるようにイベント時に質問してみたので、ティール組織の知識がなくても読めるかと思います。
●賢州さん、個人がイキイキと働く組織ってなんですか?

◯オープン・スペース・テクノロジーとの出会い
・元々は「京都のまちを良くしたい!」まちづくりからスタートした
・初めて大きなまちづくりの場づくりをさせてもらう時に色んな世界の手法を勉強しはじめた
・一番の出会いはオープン・スペース・テクノロジー(OST)
・それまでは調整型ファシリテーターが主流だった。イメージは指揮者。
・気をつけないといけないのは、きれいにまとまることもあるが、いざ動いてみると誰も動かないことがある(注:決して調整型が悪いわけではない)
・生成的なファシリテーターは、場からいなくなると「本当は私たちは何がしたかったんだっけ?」と考え始める。きれいじゃなくても動き出すことがある。そんな生成型に魅せられた
◯「学習する組織」をベースとして組織変革ファシリテーター時代
・だんだん「学習する組織」に魅せられていく
・個々人の学習能力を高めて足し合わせた、組織の能力を高める学習能力を高める組織が生き残るんだよ。ということを知った。
・学習する組織は5つの要素がある
(1)自己マスタリー
(2)メンタルモデル
(3)共有ビジョン
(4)チーム学習
(5)システム思考

◯ホールシステムアプローチという大人数でも対話ができる手法群
・その後「ホールシステムアプローチ」という対話手法群に出会う
・今までの対話手法だと5人、10人ならいけるが、20人、50人になると話し合えない
・企業は経営層だけ、まちづくりは有識者だけの話し合うしかない。となっていた。
・5人でも1000人でも話し合える手法があるなら、みんなで話し合えて、みんなで方向性を探って、みんなで進める学習する組織みたいなことができるじゃないか、と思った。
◯ティール組織とファシリテーション
・すごくパワフルなファシリテーションができるけど、組織構造がヒエラルキー(階層組織)だと難しいんじゃないかと思い始めたとき、「ティール組織」に出会った
・色んな会社と出会ってきた。哲学は持っているけど、会議のやり方は一緒(変わらないまま)
・2時間のうち8割はリーダーが喋ってますよね。という会議が多い
・プロジェクトもリーダーがだいたい仕切っている。
・昔のやってきた会議やプロジェクトの叡智とティール組織がつながっていないなと思った
・プロジェクトも3つのやり方がある。統率型、参画型、自己組織化型

●ティール組織をもう少し詳しく教えてください!
・組織づくりって2つの方向性がある。一つがトップダウン(スティーブ・ジョブズなど)。もう一つがボトムアップや分散型組織。分散型組織は仲はいいけど、小粒になりがち。
・ティール組織はボトムアップや分散型組織に分類されがちだけど、そうではない。トップダウンとボトムアップを統合したもの。
・なぜ統合出来たか?3つの視点がある
・1つ目は、組織の運営を管理マネジメントではなく、生命的な存在として扱うということ
・2つ目は、パーパス。「うちの組織は同業他社と同じようなサービスだけど、ティール組織にしたら勝てるんでしょ」という組織があるが、それは絶対に無理。自分たちがやっていることに誇りを持つとか、感動を与えるとかがあるから、ビッグアイデアが実現できる。
・3つ目は、人間愛。同じ人と人として仕事をしたいと思えるか。
●なぜティール組織のような転換が社会に起きている?
・SNSなどで情報が集まってきているなかで、誰もが自己選択をするようになってきている
・会社に一生の居場所を求めることがなくなってきているかもしれないし、会社にいても自己実現していけるようになってきているのかもしれません
・何より時代の変化が激しい中で、トップも読めない。現場の一人ひとりが利用者やお客さんとの接点の中で、「これが必要かもしてない!」というセンサーが必要になってきている。
・現場視点からも、経営視点からも、いよいよ変化のうねりが来ている
●自立分散組織やフラットな組織と「ティール組織」の違いは?
・ティール組織には3つの特徴があると言われている。自主経営、全体性、存在目的の3つ
・自主経営の部分は、自立分散やフラットな組織とも共通しているところが多い。
・全体性は、働いている一人ひとりが職場で出せているのか?不安や弱さや悩みを出せて、それを力に変えていけているか?
・存在目的は、なんのためにこの100人が集まっているのか?私たちだからできることを問うていることがティール組織。
・個人事業主の集まりとも毛色が違うし、ネットフリックスみたいな優秀で成果を出せるから自由ということも違う。優秀さを失ったらいられなくなるという緊張があることはティール組織とは毛色が違う感じがある。
●何を考えているか?ではなく、何を感じているか?を話す「会議の前のチェックイン」
・旧来の組織は「同調性」が力。一致団結するんだ、というところで異端児を生み出しにくい。どう振る舞えばいいんだろうという仮面をかぶらせる
・同時に、今までの組織は生産性を追い求めるので、組織内で交わされる会話は仕事の話。それに対して考えをみんなが語る。
・チェックインという方法がある。企業で会議の前に今感じていることを一言話しましょうというもの。
・問いは「みなさん、今感じていること、気になっていることを話しましょう」
・みんなシンキングを語る。
・だんだんフィーリングを語り始める。そうすると、モヤモヤや違和感が感じさせていたことが見えてくる。
●会議のテクニックは他に何かありますか?
・色々あるが、今日は単純なところを2つ
・1つは、結構な組織で会議室に未だにホワイトボードがない。空中戦で話したり、手元メモだけだったりする。
・話し合っているけど、みんなそれぞれが好きなように解釈して、好きな結論を持って帰っていく
・ホワイトボードをみながら語るとか、テーブルの真ん中に模造紙をおいて話すだけで、堂々巡り問題を防げる。
・ホワイトボードはすごい費用対効果が高い投資だと思う。机に模造紙を置くでもいい
・2つ目は、グループサイズ。
・「うちのメンバーは消極的で、受け身で、何も考えが出てこないから自分が喋らないといけないんだよ」とよく言われる
・シンプルに、10分ずつ2人で話してから持ち寄ろうとするだけで絶対みんな意見やアイデアは持っている。
・常にリーダーが、1対多数で会議をしている
・なぜ始めから最後まで全員が同じ形で、同じメンバーで話をしないといけないのか。
・もっと丁寧にするには、一人の時間、少グループの時間、全体の時間に分ける。
・言われてすぐにポンとアイデアが出る人と、問いをもらってじっくり考えて意見が出てくることこともある。それは個性。じっくり考えるタイプの人の方が本質だったりもする。
・せっかく考えても「私の意見は見当違いかもしれない」と思うと言えなかったりもするから、2〜3人の小グループでの時間で分かち合うと「いいじゃん!」なると勇気が湧いてくる。
・学校のクラス運営で、どうすれば手が挙がるようになるか?ということで使える。多様性のあるアイデアも笑われないんだ、ということが分かると変わってくる
●「決めない会議」というものを聞くが、どう思いますか?
・2つの観点がある
・1つはファシリテーター的な観点。本当にいい対話をしていたら勝手に決まる。
・発散(アイデアを出す)と収束(アイデアを決める)
・収束のときに、この5つのうちどれにする?と話している時点で、深い対話になっていないかもしれない
・どの参加者も「これだよね!」「これしかないよね!」というものが見つかっている収束いらずの会議もある
・ただ、リーダーが「これだよね!」と言っていて、本当は違うのに言い出せていない収束いらずモドキもある
・2つ目の観点はティール組織的な発想。
・ティール組織では助言プロセスという、担当者がみんなからアイデアはもらうんだけど、最後は目的と照らし合わせて自分で決める。
・その観点で見ると、会議で決めるというのは逃げ道になっていることもある。自分で決めるのが怖いからみんなで決めたよね、となる。
・みんなで決めたじゃんと思えるので、考え抜いていないこともある。
・ティール組織の事例のなかでも、会議では決めるという行為はしないという事例もある
・会議はそのあと自分で決めていくための智慧を集める場であるというとこともある。今までの会議の固定観念と真逆なので目からうろこ。
●チームの当事者として自組織でしていけることは?あるいは支援者としてやれることは?
・当事者の観点では「安心・安全な場をつくる」こと
・チェックインやグループサイズの話も安心や安全に話すということ
・他にもやれるとしたときに、リーダーや影響力を持ってる人が弱さを出せることや変わっている一面を出せることで、同調から多様性になることもある。
・あとは新規プロジェクトの時にいきなり生産性の話をしてませんか?まず仲間になるためのチームビルディングをすること。
・あとはチームメンテナンスの観点もある。だんだん溝が生まれていったり、フラストレーションがたまることもあるので取り除いていくことも大事。
・支援者として、まずは「見立て」
・参加者のシグナルをいかに見つけるか?
・モチベーション下がってるなとか、観察すれば分かることでもある
・観察力を高める、エネルギーやシグナルを見る。
●参加者のみなさんからも質問を頂きました

◯ティール組織をつくる上での従業員や経営者の能力は?
・経営者の大変容が必要
・人の個性が引き出せてない等の状況があったときに、まず問うべきものは「自分のあり方や呼びかけ方が生み出していることはないだろうか?」
・本当は発言する力があるのに、自分がしゃべることでどんどん話さなくなることが山程ある
・そういうメッセージを出せたら、究極変容は始めるのでまずは経営者の方が大事かなと思います
◯どんな組織を作りたいか?を話す機会が少ないです
・仕事のことをするために集まっているので、そもそも何で組織のことを話さないといけないんですか?という対立がある
・ティール組織的にいうと、理屈ではなく、なぜそういうことを話せる組織にしたいのか?をいかに語れるか?
・私はしたいんです!という主観で話すこと
・ストーリーテリングとインビテーション
◯振り返りでの学びが少ないです。どのようなフレームワークがありますか?
・KPTLは私はよく使います
・YWTもありますよね。やったこと(Y)、分かったこと(W)、次やること(T)
・あとはやったことの巻き戻し。グラフィックに書いたりする。巻き戻し作業と、考察作業を分ける
◯ファシリテーターを全て外部に任せるのは難しいです。内部でファシリテーションをする時に気をつけるべきことはありますか?
・ファシリテーターの内製化することが大事
・2つある。
・1つは、社内ファシリテーターをつくるが他部署の手伝いをする場合、自分も当事者としてファシリテーターをする場合。
・他部署の応援は割と簡単。
・自分のチームでファシリテーションするときは、自分の意見とファシリテーターとしての意見を分けること。
・そうしないと、この人はファシリテーターの力を使って自分のやりたいように持っていってるんでしょと思われると、誰もついてこなくなる。
◯リーダーの変容を促すために同じチームメンバーとして出来ることは?
・リーダーは鏡となる存在を置くことが大事とフレデリック・ラルーは言っている
・変容は大事だと分かっているけども、「ぶっちゃけカッとしちゃうし、コントロールしようとしてしまうから、それは指摘して」と言う。
・その時に絶対に怒ったり、処遇を悪くしたりしないと約束する
・そうやって「鏡」となる人を任命する
・リーダーも古いやり方が出た時に「ごめんね」と言えるようになることができるとだいぶラクになる。
・周りのメンバーも、リーダーの見ている世界に好奇心を持ってあげる。周りが一番の理解者になってあげることも大事
◯多数決やリーダーが決める以外で早く意思決定をする方法はありますか?
・意思決定には6〜7種類ある
・多数決やリーダーが決めるが一番早いが、納得感を多少増やして意思決定する方法がある
・「テンシード」という決め方がある
・全員が小豆の種みたいものを10個持つ
・そこから重み付け投票をする
・Aに10個でもいいし、Aに5個とBに5個でもいいし、Aに5個・Bに3個・Cに1個・Dに1個みたいに分散させてもいい
・これが第一投票。
・今、どういう切り口で投票したのか?その「なぜ?(WHY)」を意見交換しませんか?
・そうすると、意見だけではなく背景を共有するとメンバーの視座がぐっと上がる
・そのあと小豆を回収して、第二投票をするとかなり集合知を使いながら意思決定できる
●「場づくりカレッジ2022」やるよ!
もう5年くらい?実施できていなかったファシリテーションや場づくりを学ぶ機会が復活します!

第1講は、僕の師匠的な存在である賢州さんとの2日間。
ファシリテーターを引退しているので、ファシリテーションをテーマにした2日間を過ごせるこの機会は実はめちゃ貴重だと思っています。迷ったら飛び込んできてください。
第2講は、同世代のファシリテーターでもあり、尊敬しているはるくんとファシグラについて。
僕みたいに「絵がうまくないからな〜」という方も多いかもいれませんが、実は可視化をするというのはファシリテーターの必須スキルだと思っています。話し合いのような目に見えないものやストーリーを可視化することで、場に関わることは第2講にふさわしいテーマだなと思います。
第3講は、システム思考・学習する組織の福谷さん。人や組織や地域など、なにかに関わるというファシリテーションではシステム思考も欠かせません。僕も5年前くらいに2日間のシステム思考を学ぶプログラムに参加しましたが、そこから「パターンや構造を捉えて根本にアプローチするメガネ」を得たように思います。しかも、ピーター・センゲ氏から10年以上学んでいる福谷さんから直接学べる機会を関西でつくれたのは大きいなと思います。
第4講は、ファシリテーターを引退した賢州さんの後を継いでhome's viのファシリテーションの中核にいる篠原さんと。
実際に場をつくったり、プロジェクトだったり、組織だったりでファシリテーションをする上で欠かせない「やり方(doing)」と「あり方(being)」を学びます。
▼場づくりカレッジ2022のWEBサイト
https://www.homes-vi.org/facilitator-college2022/
▼1講から4講までの詳細&申込みページ
第1講:https://facilitator-college2022-01.peatix.com
第2講:https://facilitator-college2022-02.peatix.com
第3講:https://facilitator-college2022-03.peatix.com
第4講:https://facilitator-college2022-04.peatix.com
noteを書いた人:木戸(きどっち)
講座レポートや今後の展開などもTwitterを中心に発信していきます!
よければフォローしてください。
Twitter:https://twitter.com/hello_kidotti
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
