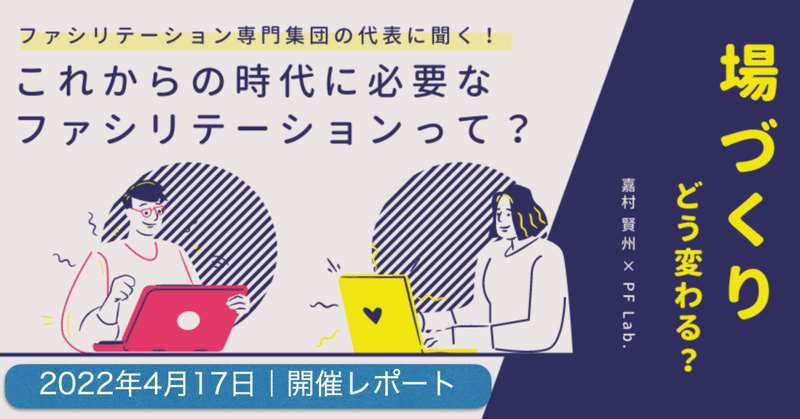
【イベントレポート】これからの時代に必要なファシリテーションって?〜ファシリテーションの専門集団の代表に聞く
こんにちは。PFLabの木戸(https://twitter.com/hello_kidotti)です。
2022年4月17日に開催した、場づくりやファシリテーションについての90分のオンラインイベント。
最初は20人くらいで出来たらと思っていたのですが、増枠に次ぐ増枠で100名ほどで開催することになりました!(感謝!)
そんなイベントの内容を、ほんの少しだけですがレポートっぽくしてみました。何かのきっかけやヒントになれば幸いです。
●開催の背景
僕たちPFLabは、2015年5月に開催された「賢州さんのファシリテーションを学ぶ2日間の合宿」をきっかけに出会い、そこからファシリテーションを学ぶことと実践することを繰り返してきました。
そんな中、昨今のコロナによる社会や組織の変化も相まってか「本格的にファシリテーションを学びたいのですが、何から学べばいいですか?」という質問が増えたように思います。
以下、賢州さんのFacebookの投稿です。
こちらが開催背景を物語っているのではないでしょうか。

●最初の質問|賢州さんはファシリテーションをどうやって学んできたのか?

以下、箇条書きにします!横着してすみません!
▼昔の賢州さん
・最初はファシリテーションを学ぼうとも思っていなかった
・元々コミュニケーションが苦手だった経験がある
・学生時代にいろんな学生団体に関わってきた
・その時の経験で名札があると声をかけやすいといった経験をしてきた
・コミュニケーションが得意な人は意識せずにファシリテーションしているかもしれない
・そういう意味では、苦手から得意に転化した典型的な例だと思う
▼転機となった学生時代のプロジェクト
・学生時代に100くらいのプロジェクトにたくさん参加してきた
・プロジェクトによって運営の仕方が全然違う(ファシリテーター役がいる団体もあれば、飲み会ばかりしている団体もある)
・意外とファシリテーターがいない方が盛り上がったりして、イベント当日に向けて成功したりもしていた
・あるプロジェクトの代表が中野民夫さんの本『ワークショップ』を持ってきて、「うちはこのやり方でやっていく」と言い出した
・だんだんと団体の代表をするようになったり、「賢州は場づくりやファシリテーションが上手だね」と言われ始めた
▼社会人になってファシリテーションを深めていく
・社会人になったときに、ある1000人が集まる場をファシリテーションすることになった
・ハリソン・オーエンさんの本に「5人から1000人まで」と書いてあり、これだ!となった
・ハリソンさんは「いなくなるファシリテーション」と言っている
・多くの場合は指揮者のようなファシリテーション(調整型ファシリテーションという)
・生成型の場を信じるファシリテーションってあるんだと知ることで、そこから学ぶ価値のある理論が山のようにあるんだ!と知り、学び深めだした
・OST(オープン・スペース・テクノロジー)を学んでまちづくりから始まった
・そうすると紛争解決も学び始めた
・まちづくりから組織やイノベーション系のファシリテーションに移っていった。組織も紛争だらけだったり。
・ワークショップのファシリテーションと、パネルディスカッションのファシリテーションは全然違うけど、依頼があると引く受けて学んでやっていく中でファシリテーションの専門家になっていった
●ファシリテーションの分類
ファシリテーションの領域もアート分野もあれば、まちづくり分野もあれば、紛争解決もあれば、カウンセリングもあればさまざま。
さらに、一回完結の場づくりもあるし、継続していく場づくりもある。共通する理論もあるけども、どれを軸に活躍していきたいかによっても違うところはある。

●これからの時代は、ファシリテーションでどうなるの?
オンラインが普及して、世界カンファレンスにも参加しやすくなった。
潮流としては生産性を高めるためのものが多かったが、身体感覚も含めて分断を統合するようなファシリテーションになっていくと思う。社会との分断、他者との分断、そして自分との分断。自分の心と身体が分断しているようなところ。メンタルモデルやNVCなどがある。
今までもそうだけど意見交換の表面的なすり合わせはできる。これまではそれを「やれ!」で動いたけども、本当は心が納得していなかったりもした。これからはもっと「心が何を感じているのか?」も扱っていくようなファシリテーションが活躍していくのかもしれない。
会議やイノベーション系のファシリテーションも、いいアイデアが出ても「誰が本気でやるの?」となる。組織の中でイノベーティブなアイデアが出てもうまくやれなかったりもする。U理論でいうところのUの谷をしっかり下っていく必要がある。そのときに関係性も大事。
内省や関係性を大事にする人は、イノベーションを大事にしていなかったりもする。逆にイノベーションを大事にしている人は関係性をあんまり大事にしてしまったりすることもある。
なので、その両方(アイデア発想やイノベーション系、自己内省や関係性系)を学ぶことは役立つと思う。
●「これから学んだらいいよ」というところはある?
ファシリテーションの基本の基本はどの時代も変わらないと思う。
世の中にある全部のバリエーションを学ぶのは難しいと思うので、いわゆるT字型で得意分野を持ちつつも広く学ぶことが大事だと思う。
「どんな分野があるのか?」というところでこちらを参考にしてもらえたらと思います。

「コクリ!桃色絵巻」はこちら
https://cocree.org/emaki/
●ファシリテーターを一言で説明したら?
難しいけども、、、「助産師」
生み出しうる理想的なものを顕在化するのがファシリテーター。
その人の力を引き出して、生まれるべくして生まれるものをちゃんと世の中に出すことがファシリテーターかな。それが助産師的ということが近い感じがする。
●ファシリテーターがうまくやってもらえるだろうと期待されている時に、どう落とし所をつくる?
あらかじめ結論が出る系もあれば、出ない系もある。
僕はよくやる組織変革系は、生まれるかもしれない、生まれないかもしれないこともある。あらかじめ説明して分かってもらうこともある。
あとは、「現状じゃダメなんですよね。生成的にこのプロセスでやるなら、落とし所を決めない方がいいですよね」ということを分かってもらってから始めることもある。
●導入でいいファシリテーションは?(急にファシリテーションをはじめた時にどう受け入れてもらえるか?)
僕は「ファシリテーターしますよ!」とクライアントのところに行くことはない。いきなりファシリテーターと名乗る人が来ても全然受け入れられない感じがあるから(笑)
最初は板書することが効果的。
話し合いが堂々巡りになってる気がするので、ちょっとポイントだけメモしていきますね。という感じで関わりは始める。その時に大事なのは、誰の意見でも対等に書く。そこで信頼をしてもらっていく感じ。
いきなりファシリテーターで来たら「何様だ!」と思われるけど、板書は喜ばれる。そうするとだんだんみんなが板書を見ながら話し合ってくれる。そのあとなら、「もうちょっとしっかり捉えたいので、Aさんの意見をもう少し聞かせてもらえませんか?」その人を理解しようとして聞くと、この人はちゃんと聞いてくれるんだと安心してもらえる。
次に起こるのが、だんだん信頼されると話し合いをまとめるようになってくる。「今までの30分をまとめると、Aさんのこの意見とBさんのこの意見がぶつかってるみたいですね。」そうするとだんだん問いかけができるようになってくる。「そもそも何でこのやり方をやってるんですか?」
そうするとファシリテーターとして進行してよ、となってくる。
●「場づくりカレッジ2022」やるよ!
もう5年くらい?実施できていなかったファシリテーションや場づくりを学ぶ機会が復活します!

第1講は、僕の師匠的な存在である賢州さんとの2日間。
ファシリテーターを引退しているので、ファシリテーションをテーマにした2日間を過ごせるこの機会は実はめちゃ貴重だと思っています。迷ったら飛び込んできてください。
第2講は、同世代のファシリテーターでもあり、尊敬しているはるくんとファシグラについて。
僕みたいに「絵がうまくないからな〜」という方も多いかもいれませんが、実は可視化をするというのはファシリテーターの必須スキルだと思っています。話し合いのような目に見えないものやストーリーを可視化することで、場に関わることは第2講にふさわしいテーマだなと思います。
第3講は、システム思考・学習する組織の福谷さん。人や組織や地域など、なにかに関わるというファシリテーションではシステム思考も欠かせません。僕も5年前くらいに2日間のシステム思考を学ぶプログラムに参加しましたが、そこから「パターンや構造を捉えて根本にアプローチするメガネ」を得たように思います。しかも、ピーター・センゲ氏から10年以上学んでいる福谷さんから直接学べる機会を関西でつくれたのは大きいなと思います。
第4講は、ファシリテーターを引退した賢州さんの後を継いでhome's viのファシリテーションの中核にいる篠原さんと。
実際に場をつくったり、プロジェクトだったり、組織だったりでファシリテーションをする上で欠かせない「やり方(doing)」と「あり方(being)」を学びます。
▼場づくりカレッジ2022のWEBサイト
https://www.homes-vi.org/facilitator-college2022/
▼1講から4講までの詳細&申込みページ
第1講:https://facilitator-college2022-01.peatix.com
第2講:https://facilitator-college2022-02.peatix.com
第3講:https://facilitator-college2022-03.peatix.com
第4講:https://facilitator-college2022-04.peatix.com
こうやってファシリテーションを学ぶ機会をコーディネイトする立場になり、多くの方と叡智を共有し、多くの現場が変わっていくことにつながればと僕自身願っています。
noteを書いた人:木戸(きどっち)
講座レポートや今後の展開などもTwitterを中心に発信していきます!
よければフォローしてください。
Twitter:https://twitter.com/hello_kidotti
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
