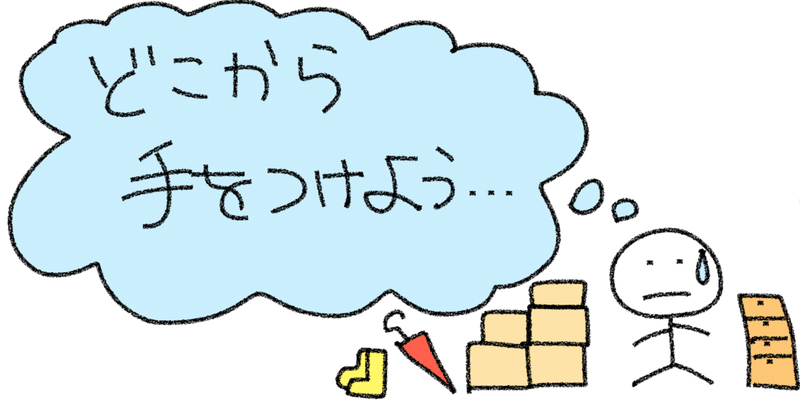
大掃除に思う
大掃除
2022年も年末、なんとなく年末には不要なモノを処分したり、埃のたまった場所をきれいにしたりしたくなる。
普段なら少しぐらい雑然としていてもそのままなのに、年を越すとなるとなんとなく気になったりするのはなぜだろうか?
どこかで誰かから、年始はスッキリと、とか、気持ちを改めて新年を迎えるなどと言われていた(すり込まれた!?)のかもしれない。
この時期、私たちの寺子屋でも恒例となった大掃除が行われる。
少し皆さんと違うかもしれないのは、スタッフと生徒が集まり、みんなで掃除をする、というところだろうか。
学校でも塾でも生徒をかり出して大掃除をするところ、というのはあまり聞かない。
半日掃除をしてみんなでお昼を食べて解散する、というまあ半分は年末のイベントのようなものである。
生徒が掃除に来てくれるのか?とも思う。もちろん婉曲に断る生徒もいれば、ハッキリ断る生徒もいる。
でもなんだかんだと毎年10-15人人程度が集まりがやがやと大掃除をする。
まあ半分くらい遊んでいるのである。
20年以上、これを毎年各教室でやっているのだが、ここ何年かこの掃除に向かう生徒の様子が変わってきたような気がして今回は記事にしてみようと思った次第。
そもそも掃除とは?
さて、少し考えてみる。そもそも掃除って何なのだろうか?
自分の過ごす場をきれいにする。
きれいにする?
雑然と出しっぱなしになっている机の上のモノを整理する
床の埃や小さなゴミなんかを捨てる
ふき取ることで埃や汚れを取る
エアコンなどはフィルタの埃をとったりする
水回りなんかは消毒という意味合いもありそう。
たまには窓なんかも拭く
本棚や戸棚なんかのものを出して不要なモノを捨てたり再配置したりする
まあ自分(自分たち)が過ごしやすいように整理したりゴミを捨てたりすることなんだろう。
ここに求められるのは、少し先を見る力なんだと思う
いまやっている掃除、整理によってこれからの生活がどう変わるのかを想像できるのか?
ここのモノをどけておけば導線が邪魔されない。
これをここに入れておけば使いやすい。
etc
少し先、自分がやることの影響を見極める力なのではないか??
ちょっと大げさだろうか。
大掃除20年の変化
私は子どもと向き合うことを仕事にさせていただいている。
そんなことを20年以上もやっていると、周りの人たちから、またインタビューなんかを受けるとよく聞かれるのが「この20年で子どもは変わりましたか?」という質問。
私はいつも、「いや、基本的には変わりませんよ、でも少し変わったといえば、自分はお客さんである、という時間が長くなっていることでしょうね。」と答える。
「自分はお客さんである」とはどういうことか?
例えば家庭で、勉強して習い事をすれば、家での役割を持たされているケースは少なくなっている。
例えば学校で、勉強だって、とてもよく準備された教材を使って、あとはやればいいだけ。野外活動だってすごくよく準備されている。
準備の不十分な親や先生は評価されない。
これが私の思うお客さん。
私は子どもたちをお客さんにしたくない。
そんなこともあり、普段から、授業あとには自分で机をふいてもらう。
自分の使ったところ、きれいにして帰ろう。次に使う人が気持ちよいようにね。と伝えている。
白い机だから、鉛筆のあとや消しゴムカスが目立つ。みんな毎回机をふいて帰るので自慢じゃないがいつも机は白い。
当然生徒は面倒くさいから、隙をついて掃除せずに帰ろうとする。スタッフはそれを見逃してはいけない。ゲームみたいなもんだ。
さりげなく、台布巾を絞らずに拭いたりする生徒もいる。これは気づかないこともある・・・。
でも消しゴムカスが残ったリするとすぐわかってしまうのでそこまではほぼ必ず全員がやる。
でも、なかなか目が届かず、残念なのが、使い終わった後の台布巾の処理である。
簡単に洗い、絞って広げて干しておいてもらうことになっているのだが、これがかなり適当。
ヒドイのは、洗わず丸めてポイ。
洗ったけれどあまり絞らずポイ。ってのもいる。
ちゃんと洗って絞って広げてくれる生徒は、スタッフが声をかけなければ1割か・・・。
ついつい、昔はこうじゃなかった、と言いたくなる。(多分実際はそうでもない・・・。)
年末の大掃除には、この大前提がある。
でも、掃除について、わかりやすい変化が起きている。
今年(2022年)も12月28日、10名の生徒の参加を得て大掃除をした。
今年だけではないのかもしれない、でも今回、痛感したことは・・・
「徹底的にやりっぱなし!」「自分の作業の結果がどう影響するのか?見えていない」
今年、中高生と小学生をコンビにして、各所の掃除が行われた。
見ていると・・・。
それぞれに掃除をする、下を見ない中高生続出・・・。
(自分はそこそこしっかり丁寧にやる、でも相方には最初に指示を出したものの、何をしているのか見ていない。相方は飽きて遊んでしまう・・・)
一緒に遊ぶ
(なんとなく掃除をし、なんとなく遊ぶ。使った道具は・・・?)
とりあえずやる、黙々と
(それぞれが分担を守ってしっかりやる、でも後先はあまり考えられず、とにかく「やった」となる。中高生の側にそれを確認することはできず)
多くに共通・・・
分担された範囲は終わった!となりでほかのコンビがやっていても手伝うことは・・・ない。
使った道具は置きっぱなし・・・。
もちろん、しっかりと目の前のことを進め、周りに目を配る者もいる。
でも・・・
共通するのは、どうしても「自分自身のやりっぱなし」になってしまうこと。
自分のやったことがこの後どう影響するのか、考える習慣が徹底的にないことだろう。
これも、「子どものお客さん化」の弊害なのだと思う。
これはこの20年少しずつ減退してきている力なのかもしれない。
実は勉強でも一緒・・・
何かを学ぶ時、問題を解くとき、目の前のことだけをやるだけでうまくいくのだろうか?
なぜ学ぶのか?どういう経緯でどこに至るのか? を考えることなく問題を解くと、目の前の問題は解けても、少し複雑になればできない。
数学の問題などを想像するとわかりやすいだろう。
計算が解けても、段階を踏んで解答にいたる文章題はできない。
これに必要なのは、なんども練習すること、だけではない。
ゴールを設定し、道筋を考える習慣なのではないか。
この話は「お客さん」扱いされる子どもがなかなか育たないことと通じている。
数学の文章題を想像してみる。
途中の流れがすべてあり、部分的に穴埋めするような問題を先生が準備してくれる、そうすると大半は各部分を考えれば解けてしまう。
1から解答を作る場合、そうはいかない。自分で道筋を組み立てなければならない。
Aを導くために何をするのか?を考えなければならないのだ。
これをするためにどんな準備があるのかを想像する力を育てることは、学ぶ力をつけるにおいては1つ、大切なポイントである。
そんなことを感じる大掃除だった。
ぜひ子供部屋の掃除は、どこまで何をやるかを決めてから、お子さん自身にやってもらってみてはどうか?
(あ!これも余計な手引きか!? 手引きをしなくても、毎年やってもらっていれば身につくのかもしれないが・・・)
どうぞよいお年を・・・。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
