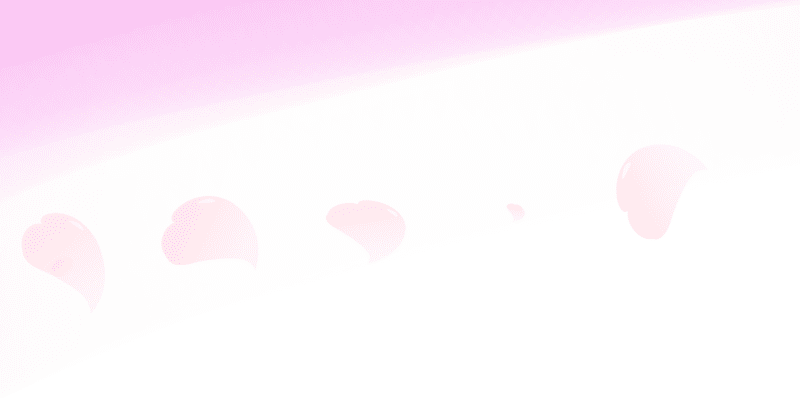
失恋オムニバス【0310】
大人までの距離に
「ハンナね。大人になったら、春樹お兄さんと結婚する!」
なんてベタな台詞も、小さなころは恥ずかしげもなく言えた。
花巻春樹お兄さん。
親戚の、とっても優しいお兄さん。
年齢はわたしの22個上。
当時7歳のときのわたしからしたら、十分以上に立派な大人で。
それから10年たった今でも、お兄さんは大人で。
お兄さんが大人で居続けるように、わたしも好きで居続ける。
だって、あのときお兄さん言ってくれたもん。
「ハンナが大きくなったらな」
って。
花巻ハンナという名前は、あまり好きではなかった。
日本人とドイツ人のハーフであるわたしは、ただでさえ目立つ容姿だというのに、名前までもが西洋かぶれでは、悪目立ちもいいとこである。
目立ちたくないのだ。
出来ることなら、わたしは生涯をひっそりと暮らしたい。
小学校、中学校での経験は、わたしのそういった性分を一層と強固なものしてくれた。
それが一体、どんな経験かは、あまり筆舌したい内容ではないので割愛させていただきたい。
「仲間外れ」とか「陰口」とか。そういうワードから連想される経験とだけ、お伝えしておくことにする。
「……えっと、あなたの気持ちはとても嬉しいです。でも、ごめんなさい。他に好きな人がいるの」
「あ……。そう、なんだ」
「ほんと、ごめんなさい」
「う、ううん。こっちこそ、急に呼び出したりしてゴメン」
放課後に、隣のクラスの男子から呼び出され、想いを告げられた。
ろくに会話もしたこともない隣のクラスの男子だったけれど、直接に愛の告白とは好感が持てる。
昨今はメッセージアプリやらでの愛の告白も多いと聞くが、やはりそういったものは直に言ってもらったほうが嬉しいものではある。
ただ好感が持てるとはいえ、彼の気持ちに応じることは出来なかった。
「なにハンナー。あんた、また告られたのー? やっぱモテる女は違うなー」
同級生で仲の良い実祈が、そのことを囃したてる。
最近、髪をバッサリ切ってボーイッシュな風貌となったが、恋バナと甘い物には鼻が利く女生徒だ。
「告白とか、あまりしないでほしい。目立つし」
「うわ、ドライだな」
あははと、実祈は笑う。
「ハンナ、そんなにモテるのに、なんで誰とも付き合わないかなー? もったいないよー。ゆっちょんみたいに男子が苦手ってわけじゃないんでしょ?」
「結久保さん? でも、あの人カレシいるでしょ?」
「あ、うん。最近できたみたいだよ」
じゃあ、男苦手じゃないじゃん。
まあ、わたしは実尽と違い、他人の恋愛事情に踏み込む趣味はないので、それ以上は言及しなかった。
「ゆっちょん亡きいま! ハンナには我がクラスの代表として、ぜひとも頑張っていただきたいものですなっ! 恋活!」
「いや、あんた何者なのよ」
「ラブマスター」
「ダサさ極まれりね」
昭和でも、そんなネーミングセンスの人は珍しいだろう。
いつも元気そうで何よりである。
「でも、わたしは誰とも付き合う気ないから。好きな人、いるし」
そう言って。
わたしは話を切り上げにかかる。
実尽は一瞬だけ目を丸くし、
「え、それって。例のお兄さん?」
「うん。すっごく優しくて、格好いいんだよ」
「……その人、何歳なんだっけ?」
「39歳」
お、おう。
と、呻き声に近いなにかをあげ、実祈は気まづそうな顔をする。
「なに? なにか言いたいことでも?」
「いや、ハンナのそれって真剣なの?」
「失敬な。愛に歳の差は関係ないわ」
「うん。そうだよね。応援してる」
今度は乾いた笑いで対応される。
コロコロと表情の忙しい娘である。
「もったいないなー」とブツブツ呟く彼女。
もったいなくても良い。
わたしは大人になるまで、お兄さんを好きでい続けるって決めているのだ。
「おー、ハンナ。おかえり」
なんとびっくり。
家に帰ると、春樹お兄さんがリビングでくつろいでいるではないか!
「お兄さん!! どうしたの!? 東京から帰ってきたの!? うちに住むの!?」
「住みはしないな」
恥ずかしくなるくらいに、はしゃぐ姿をみせる。
尻尾が付いていたらブンブンと振って見せただろう。
「少し長めの休暇もらったから、戻ってきたんだよ。そんで寄らせてもらった」
痩せた眼鏡で、髭は綺麗に剃られていて。
だけど髪は少しボサボサで。
彼女とか全然出来なさそうな雰囲気。
春樹お兄さんは変わらずだ。
変わらず、大人の男の人って感じがした。
「まあ、すぐに帰るさ」
「えー、ずっといてよ。いいじゃん、一生ぐらい」
「一生ってのは『ぐらい』で掛けていいほど軽いものじゃないんだぞ」
お兄さんの笑いは、いつもシニカルだ。
そこがまたそそる。
「じゃあ結婚しましょう!?」
「話聞いてた? なんでそうなるの?」
「重い想いならいいんでしょう? わたし真剣だよ」
ピンっと、お兄さんはわたしの額をつつく。
「そういうのが軽いって言うんだよ」
「…………むう」
軽くなんてない。
ずっとずっと想い続けてきたから。
「……約束、したじゃん」
そう言うと、お兄さんは困ったように笑う。
こんなやり取りを、もう何年も続けている。
やっぱり、お兄さんにとってわたしは、どこまでいっても子供のままなのだろうか。
例えば高校を卒業しても、変わらず子供のままなのだろうか。
22年の距離が縮まることはないのだろうか。
「あんたさ。技島くんのことフったんだって?」
体育の時間。
隣のクラスの派手目な女子に話しかけられた。
うちの学校では体育の時間のみ、2クラス合同で行われる。
だけど基本つるむのは同じクラスの子どうし。
わたしに他クラスの友達はいない。
彼女と話したことも、いままで一度もなかった。
『技島くん』とは、先日わたしに告白をした彼のことだ。
「なんか言えよ」
ああ、なるほど。
彼女は、『技島くん』に気があるのだろう。
彼をフった、わたしが気にいらない、と。
「…………別に。わたし他に好きな人いたから」
わたしは、そう答える。
しかし彼女はジロリと睨みつけるような目を背けることはしなかった。
「ちょっと顔が良いからって。あまり調子乗るなよ」
そう言い残し、彼女はバレーボールのコートに入っていった。
――――これだから、目立つのは嫌いだ。
誰かの好きな人が、わたしのことを好きで。
それで勝手に嫌われて。
本当に、めんどくさい。
小学生のころから、こういうことは何度もあった。
でも決して、慣れたりはしないけど。
「ねえ。お兄さん」
「んー? どうした、ハンナ」
「今日、学校で嫌なことあったからさ。わたしを抱きしめてほしい。そんで、そのまま一緒に寝てほしい」
「ははは。そりゃ無理だ。お前の親父に殴られる」
あ、そ。
いくら強く想い続けていても。
報われないものだって当然ある。
そんなことは分かってるんだけどさ。
でもやっぱり、辛い気持ちになってしまうのも事実だ。
わたしは愛されたい。
それだけなのに、なんでこうも上手くいかないんだろう。
「嘘つき」
授業中に、ふと呟いてみた。
すると前の席の子が「呼んだ?」と振り向いてきたのがおかしくて、わたしは笑ってしまった。
そんな、ほのぼのとした思い出だけで満たされた高校生活が理想だったけど。
体育の授業のときのような事も、たくさんある。
たくさんあった。
その度に傷ついて。傷ついて。傷ついて。
そうやって大人になっていくというのなら。
わたしはもう、充分に大人なのではなかろうか。
「卒業おめでとう」
「……ありがとう」
卒業式の日。
学校で友人との別れに慟哭し終えた、わたしを、学校まで迎えに来てくれたのは、お兄さんだった。
「お父さんが迎えに来てくれるもんだと思ってた」
「俺が頼んで来させて貰った」
「……ふーん」
わたしは、お兄さんの車——とはいえ、お兄さんは東京住まいで地元に車を持っていないため、わたしの父から借りたものだった——に乗り込む。
もちろん助手席。
「道、違うよ」
お兄さんの運転は案外こなれたものであったが、帰路とは明らかに違う方向へと車を進めていた。
「こんな日くらい、ゆっくりドライブと洒落こんでもいいだろう?」
お兄さんは笑った。
そして、
「なあ。そろそろ良いんじゃねぇのか?」
と、優しい口調でそう言った。
「…………」
わたしは俯き、唇を噛みしめる。
お兄さんは、鈍感ではない。
ましてや唐変木でもない。
とても優しい人だから、告白のチャンスを設けてくれたのだ。
それは彼が迎えに来てくれた時に察しがついた。
わたしの心からの言葉を、本気の気持ちを、お兄さんに伝えるときが来たのだと。
「……わたし。お兄さんに、話したいこと、ある」
「うん」
お兄さんは、ゆっくりと頷く。
その優しい仕草が、逆にわたしの決意を鈍らせる。
「あのね。今日は、わたしの話。ちゃんと聞いてほしい」
「そのつもりだよ」
わたしの震える声にも、しっかりと耳を傾けてくれる。
「わたし、ね。お兄さんのことが好き」
「…………」
「小さなころから、ずっと好き。何度でも言う。大好き」
「…………」
「でも、お兄さんは、いつも曖昧に笑うだけ。なんで、ずっと応えてくれないの? こんなに何度も好きって言ってるのに……! なんで、わたしの気持ち、わかってくれないの!?」
ポロポロと涙が零れてくる。
あーあ、なんてダサイんだろう。
こんなこと言うつもりじゃなかったではないか。
みっともないにも程がある。
最後まで、逃げてばっかだ。
嫌な役目は。気持ちは。全部お兄さんに押し付けてばっかり。
だって、お兄さんが優しいから――
「わかってるよ。それが嘘ってことくらい」
――ほらね。
卒業式で枯らしたと思っていた涙の何倍もの量が溢れだす。
「ごめん……なさい。……ごめんなさい」
拭いきれない雫を必死に抑えながら、かろうじて謝罪の言葉を口にする。
「なんでハンナが謝る必要あるんだよ」
「だって……、わたしずっと。……お兄ちゃんのこと利用してた。わたし、いつも、自分のことばっか……」
お兄さんは静かに「そっか」とだけ言う。
花巻ハンナは嘘つきだ。
自分のことしか考えてなくて、逃げてばっかりで――
――目立つことが嫌いだ。
わたしがお兄ちゃんを好きでいれば。
わたしは誰とも交際する必要がなくなるし、そもそも交際を迫られることも少なくなる。
そうすれば、誰と付き合っている、とか噂が立つこともない。
わたしが20歳以上も年上のおじさんを好きという変わった嗜好の女であれば。
女子どうしの恋バナで『気取っている』などと言われることもなくなる。
それが理由でハブかれたりもしなくなる。
ただ、まあ――――いくらそういうスタンスで居続けていたとしても、報われないことだって当然あった。
陰口を叩かれることだって当然あった。
わたしは、みんなに愛されたい。
それだけなのに、なんでこうも上手くいかないんだと、思う日もあった。
「でも、そんなとき。今度は『わたしとってお兄ちゃんが全てだから、別にいいんだ』って、自分に嘘を付くの」
そうすれば少しだけ、自分の心が楽になるから。
わたしはずっと、自分の都合のためだけに、お兄ちゃんを好きで居続けた。
周りにも、自分にも、そう言って欺き続けてきた。
「……ごめんなさい」
「だから、謝ることじゃないって。人が誰を好きと言うかなんて……それは、自由だ」
お兄さんは、ずっと私の心中など見透かしていたのだろう。
それでいて、わたしとの戯れに付き合ってくれていたのだろう。
とても優しいから。
「でもな。自分に嘘つくのだけは、もうそろそろ、いいんじゃねぇのか。もうハンナも大人だ。まわりに冷やかされたり、妬まれたりもなくなるさ」
持ってきたかのような台詞を、わたしの上に置く。
ああ、こういうのを大人と言うんだろうな、と思った。
「だからもう、本気で誰かを好きになってもいいんだ」
最後に、「まあ若い子に好き好き言われるのは、悪い気分じゃなかったわな」と笑った。
わたしも、なんだか肩の荷が降りた気分になり笑う。
「あのね。お兄さん」
「うん?」
「わたしね。実はもう、気になる人いるんだよ」
わたしは言う。
「別のクラスの子で、何回フっても、好きだって言ってくれて。顔だけでわたしを選んだわけじゃないってのが伝わってきてて」
嘘でもなんでもない言葉を。
「進路が別々だから。今日、連絡先だけ交換したんだけど……。あの、さ。こーいうのって。最初なんて送ったらいいのかな?」
なんでもない、普通の恋の話を。
「うーん。そうだなあ……」
お兄さんは――
――わたしの初恋は、困ったように笑った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
