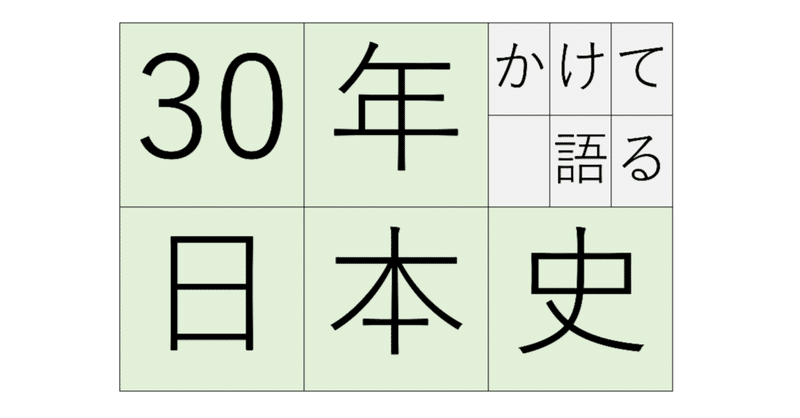
30年日本史00858【建武期】延元改元
京を奪還して建武3(1336)年2月2日に都に戻っていた後醍醐天皇は、内裏が焼けてしまったので花山院(京都市上京区)に住むこととなりました。花山院に入った天皇は、新田義貞を左近衛中将に、脇屋義助を右衛門佐(うえもんのすけ)に任命することで、二人の功績に報いました。
この頃、朝廷では
「これほど戦乱が続くのは『建武』という元号が悪いからではないか」
との噂が広まっていました。
元々「建武」とは、王莽(おうもう:B.C.45~23)を倒して漢王朝を復興した後漢の光武帝(こうぶてい:B.C.6~57)が用いた元号です。後醍醐天皇としては、天皇から統治権を奪った北条氏を倒し、再び天皇家が政務のトップに立ったわけですから、後漢の光武帝にあやかって「建武」という元号を使いたかったのでしょう。
しかし「建武」の「武」という文字が、せっかく幕府を滅ぼしたのに再び戦乱の世となるような不吉な文字にも思えます。公卿たちの評判が悪かったこともあって、2月中旬、天皇は文章博士の平惟継(たいらのこれつぐ:1266~1343)に対し、新たな元号を選定するよう命じました。
このときの後醍醐天皇と平惟継のやり取りが、中院通冬(なかのいんみちふゆ:1315~1363)の日記「中院一品記」に残っています。
惟継「建武という元号は不吉ゆえ改元せよとのお話がありましたが、私は不吉とは思いません。なぜいま改元せねばならないのでしょうか」
天皇「その改元反対の意見を会議の席で述べよ」
惟継「それは困難です。新たな元号を選定せよとのご命令を拝受した私が、それを評議する席上で改元そのものに反対を唱えるわけにはいきません」
天皇「構わぬから述べよ」
このやり取りを見ますと、どうやら改元の命令は天皇の本心ではなかったようです。公卿らにしつこく言われたためにやむなく改元を決定したものの、その会議で「改元反対の意見を述べてほしい」などと文章博士に依頼するあたり、どうもぐらついているように見えます。
結局2月29日付けで、後醍醐天皇は元号を「延元」に改めました。
天皇自身が選んだ「建武」という元号を捨てねばならなかったことは、後醍醐政権が力を失っていることを象徴しているようにも思えます。改革意欲旺盛な天皇が矢継ぎ早に指示を出しつつも、かえって社会を混乱させて公卿らの反発を招き、徐々に公卿らに譲歩せざるを得なくなっているというわけです。
ちなみに、後醍醐政権を認めない足利方はこの改元を拒絶し、引き続き「建武」を使い続けます。世は再び、二つの元号が入り乱れる時代となるのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
