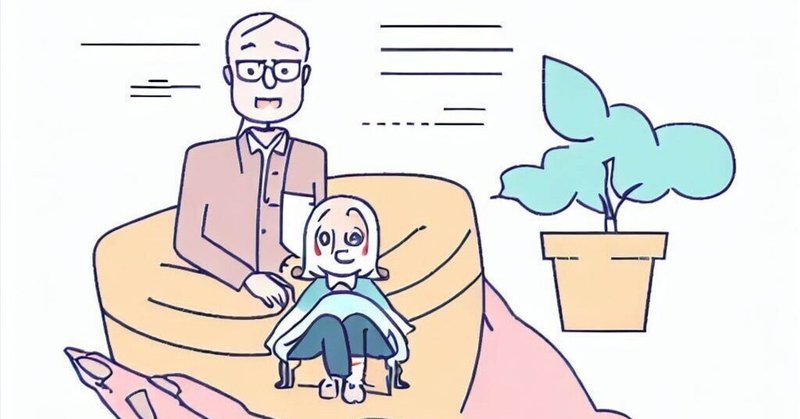
亡くなった親の家に同居していた場合、相続税・贈与税はどうなる?
親が亡くなったとき、遺産を相続する場合には相続税がかかることがあります。しかし、相続税は(3000万+法定相続人の数x600万円)までは非課税で、相続した財産の額や相続人の数、親との同居の有無などによって変わります。
特に、親が住んでいた家(実家)を相続する場合には、同居していたかどうかが重要なポイントになります。同居していた場合には、その住宅の敷地の課税価格が最大80%減額される特例があります。
しかし、この特例を受けるためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。また、同居していた住宅を売却する場合や生前贈与を受けていた場合などには、相続税の計算方法や注意点が異なります。
この記事では、亡くなった親の家に同居していた場合の相続税や贈与税について、詳しく解説していきます。また、認知になった場合の対応、相続税の特例や寄与分の主張、節税対策などを知っておくことで、親から受け継いだ財産を無駄にしないようにしましょう。
相続税・贈与税の基礎知識
相続税と贈与税は財産の移転に対して課される税金です。相続税は人が亡くなった時に財産を受け取った場合にかかります。贈与税は生きている人から財産をもらった場合にかかります。
相続税は、亡くなった人名義の財産から借金を引いて、さらに基礎控除や非課税枠を引いた後の金額に対してかかります。
相続税と贈与税は基礎控除や非課税枠があります。
相続税の基礎控除・・・3000万+法定相続人の数x600万円(例えば相続人が一人であれば、3600万までの相続財産は非課税で受け取れる)
贈与税の基礎控除・・・年間110万円までの贈与は非課税。それ以上は金額が上がるごとに贈与税も増える
相続税の非課税枠・・・生命保険、死亡退職金はそれぞれ500万円まで非課税
贈与税の非課税枠・・・教育資金贈与、住宅取得費、結婚に関しては一括贈与の非課税枠があります
同居していた住宅に引き続き住む場合の相続税の特例とは?
同居していた住宅に引き続き住む場合、相続税の計算において、その住宅の敷地の価格(土地の価格)が最大80%減額される特例があります。
なぜなら、相続税の負担を軽減させ、相続人が住宅を売却せずにその家に住み続けられるようにするためです。
ちなみに、土地の価格は最大80%減額ですが、建物はというと減額はありません。固定資産税評価額と同等の金額が建物の価値と理解していただいて大丈夫です。
相続税の特例(小規模宅地等の減額)の要件は?
相続人が同居していたこと(住民票などで確認)
相続人が引き続き住むこと(3年以内に売却、賃貸すると無効)
主たる居住用であること(自分名義の住宅を所有していないか?)
敷地面積が330平米(100坪)以下であること
が要件になります。
例えば、上記要件に合致して親と同居していた土地の価値が3000万円だったとすると、評価額は8割減の600万円で済むことになります。
同居していた住宅を売却する場合の相続税の計算方法と注意点
同居していた住宅を売却する場合、相続から3年以内に売却すると相続税の特例を受けた分が無効になり、追徴されます。
また、売却すると所得税(譲渡所得という)がかかる場合があります。
所得税がかかるケースは、
売却金額ー取得費(親が購入した金額)ー必要経費(支払った相続税など)>0
また、ここから最高3000万円まで控除できる特例があります。
この3000万円引いて+であれば、所有期間によって5年超の場合は20%、5年未満の場合は20%の所得税がかかります。所有期間というのは親が取得した時から売却までの期間です。
一般的には、取得時よりも売却価格が安くなっているケースが多いです。つまり所得税はかからないケースが多いです。土地の値段が上がった人だけ気を付ければいいでしょう。
同居していた親から生前贈与を受けた場合
同居していた親から贈与を受けた場合、相続分は変わる可能性があります。
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に財産を贈与したことをいいます。生前贈与された財産は、被相続人の死亡時にその時価額で評価されて、相続財産に加算されます。これを「贈与分の相続財産への加算」といいます。この加算は、遺産分割の際に公平性を保つために行われます。
例えば、同居していた期間に家賃相当分を支払っていなかった場合は、特別受益として評価される可能性があります。特別受益とは、被相続人から不当に利益を得た場合のことで、相続分から差し引かれます。特別受益にあたるかどうかは、事情によって異なりますが、一般的には以下のような要件があります。
被相続人から生前贈与や遺贈を受けたこと
被相続人から不当な対価を支払わずに利益を得たこと
被相続人から利益を得る意思があったこと
被相続人から利益を得ることが公正ではないこと
贈与を受けた場合、相続税との兼ね合いなどは?
贈与は基礎控除があり、110万円までは非課税です。ただ、相続前に駆け込みで贈与するのを防ぐため、相続から遡って7年間は持ち戻しといって、非課税で相続財産に加算されます。
例えば、相続税を減らそうと年間110万円贈与していた場合は、770万円が相続税の財産として加算されます。(贈与税を後から払ったりする必要はなく、相続税として課税されます)
相続時精算課税制度などもありますが、ちょっとややこしいですし、一般の人には関係ないので割愛します。
家族に住宅取得費用を贈与した場合の税金関係は?
子供に住宅取得費用として贈与する場合、また親名義の土地を子供に贈与する場合の税金関係はどうなるかを確認しましょう。
住宅取得費用を贈与した場合
令和4年4月1日から令和5年12月31日までの間に、親や祖父母からの贈与により、住宅取得費用を取得した場合は下記の金額が非課税になります。
省エネ等住宅の場合・・・1000万円
それ以外・・・・500万円
期限が決まっていますが、毎回更新されますので、非課税枠が無くなる可能性は少ないでしょう。また、非課税枠は変更されますが、いつ贈与してもらうのが得か損かは住宅ローン控除も合わせて考える必要があります。
親名義の土地や建物を子供に贈与した場合
結論から言うと、富裕層でないかぎり、一般的な人は贈与せずに、貸す方が税金がかかりません。
名義変更をすると贈与になりますが、名義変更は相続時にすればかなり節税できます。
つまり、子供に貸して相続時に名義変更するのが得策です。
非課税財産を受け取った場合の相続税や遺留分の影響と注意点
生命保険などは非課税で受け取れる相続財産です。
例えば、土地や建物を長男が相続で受け取り、次男が生命保険を受け取った場合はどうなるかというと・・・
生命保険は受取人固有の財産という定義があり、次男は相続財産をもっともらえる場合があります。
また、遺留分といって、例えば長男に全財産を相続させるという遺言があったとしても、次男には法定相続分の半分(つまり1/4)は受け取れる権利があります。
同居親族と別居親族の間で相続問題が起きる場合と回避する方法
同居親族と別居親族の間で相続問題が起きる場合は、以下のような原因が考えられます。
同居親族が親の財産を独り占めしようとする
同居親族が介護や生活費を負担したことを理由に、別居親族の相続分を減らすように要求する
遺言や相続分に対して不信感や不満を持つ
このような問題を避けるためには、以下のような方法があります。
生前に遺言を作成し、子供たちに内容を説明する
生前に財産分与を考え、子供たちの相続分を調整する
相続問題が起きた場合の解決方法と専門家への相談方法
実は、相続問題でもめる家庭の約半数は相続税がかからない家庭です。つまり一般家庭でも争うことがあるということを覚えておいてください。
解決方法には、遺産分割協議、調停、裁判などがあります。 まずは遺産分割協議で話し合いを試みるのが望ましいですが、合意に至らない場合は、調停や裁判を申し立てることができます。²調停は裁判よりも手続きが簡素で費用も安く済みますが、調停委員の提案に従わなければならないという制約があります。 裁判は自分の主張を裁判官に判断してもらえますが、手続きが複雑で費用も高くかかります。
専門家への相談方法には、税務署、市役所、司法書士、行政書士、弁護士、税理士などがあります。それぞれに得意分野や対応できる業務が異なりますので、相談する前に確認しておくとよいでしょう。例えば、税務署では相続税に関する相談ができますが、遺産分割や遺留分に関する相談はできません。弁護士は法律手続き全般に対応できますが、費用が高くなる可能性があります。
親が認知になった場合、相続や贈与や遺言は?
結論から言うと、親が認知になってしまったら遺言は無効になってしまいます。なぜなら判断能力が衰えているので有効な契約とはみなされないからです。
また、贈与の場合も不公平な贈与なども考慮しておかないと、相続の際にもめることがあります。
認知になったら医師や弁護士などの専門家に相談して進めましょう。
できれば、認知前に家族信託や話し合いで家族の相続分などを決めておきましょう。
Q&A
Q、同居中の家計分担や相続、贈与に備えるためにすべきことは?
同居している親族は親の世話や家計分担などで負担が重い場合があります。別居親族とよく話し合って、相続や贈与で不公平感がなくなるように話し合いましょう。
よろしければサポートよろしくお願いいたします。いいものを作れるよう活動の糧にします。
