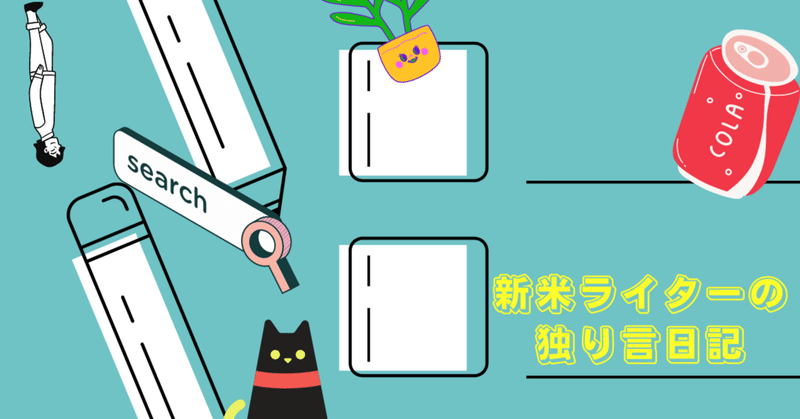
〔道をひらく〕にて。
最近、松下幸之助さんの「道をひらく」を毎日読んでいます。
1日読みすぎず、一篇、もしくは二篇だけにして噛み締めるように読んでいます。
なんてったって、一篇の重みがすごいので、たった見開き2ページで大きく成長させてもらえます。
その中でも、今日読んだ内容が少し尖っていたのであまり好きじゃない表現があったので紹介させていただきます。
・世間知らず
忍耐づよく、根気よく、知識を身につけよう・校長と先生の命令に絶対したがうべし・校長や先生が教室にはいるとき、教室を出る時、起立して送迎すべし・先生に答えるときは起立、先生の許可あって着席すべし・校長と先生には敬意をはらい、校長や先生に道で出会ったときは礼儀正しいおじぎをせよ・年上のものを尊敬せよ・老人、幼児、弱いものに親切に丁寧であれ、道や席をゆずり、あらゆる援助をせよ・親の言うことをきき、手助けをし、弟妹の面倒をみよ・・・・。
これはソ連の小学校、中学校で省令として公布されている“生徒守則”の一部で、この規則を破った生徒は退学の罰を負うということである。中共においても同じような規則がつくられていたし、欧米諸国においてもこれに似たことが説かれている。
どこの国においても、たとえ主義主張がちがっても、人間として大事なことは万国共通、人みな共通である。だからやはりどこでもだれでも大事にする。礼儀とか道徳とかいうと、何となくうとましいもののように思うわが国の昨今、おたがいに世間知らずであてはならないような気がする。
全体的にはとても好きなのですが、主に「校長と先生の命令に絶対したがうべし・校長や先生が教室にはいるとき、教室を出る時、起立して送迎すべし・先生に答えるときは起立、先生の許可あって着席すべし」の表現がやはり時代なのもありますが、絶対服従の四文字が垣間見えて好きじゃないですね。
目上の人を敬い尊敬することはとても大切なことだとわかっていますが、少し行き過ぎた表現だと思います。ただ、これは松下幸之助さんの言葉ではなく、ソ連が生徒守則で作った文言なのもわかっているつもりですが、やっぱり気になってしまいますね。
あまり気にしすぎず後半の文章が特に大事だと思いますので、今日はそこをしっかり噛み締めたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
