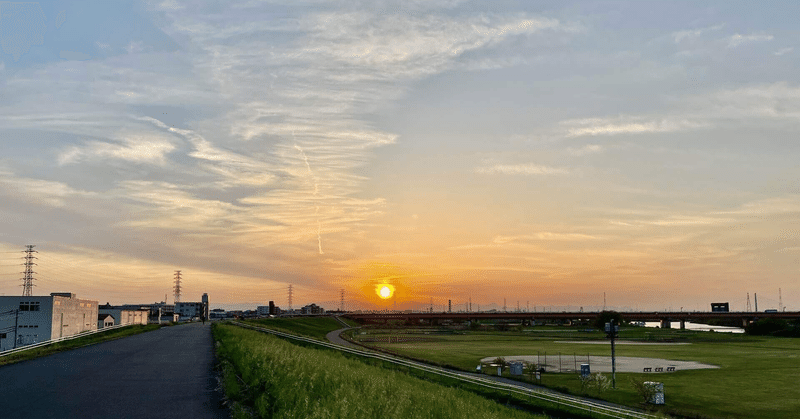
夫婦間での子育ての温度差
前回、発達障害グレーゾーン(?)の息子について書いた。息子は保育園の途中から少し怪しい動きをみせるようになり、年長の時から地域の療育センターなどを使って対策を始めることになった。いま小学校にあがったばかりで、先日、担任の先生と面談があったが、本人は学校でパニックにならないよう大変、頑張っているとのことだった。また担任の先生にも情報がまわっているため、つかず離れずでうまいこと対応していただいているようであった。学校で気を張っている分、自宅では疲れてすぐに横になったり、ちょっとしたことで怒ることも多くなったので、そのような様子を担任の先生とは共有させてもらった。以前は保育園で暴れて、自宅ではいい子にしていることが多かったので、これはこれでいい兆候と捉えている。ただ親は大変である。
先日、知り合いの方(女性)と話している時にその方のお子さんの話になった。年長後半くらいから集団行動がとれなくなり、時に保育園で暴れてしまって困っているという話であった。私の経験や療育センターを利用した話などをさせていただいたが、最後にその方がこんなことを言っていた。
「夫に言っても、なかなか理解が得られないんですよね」
よくよく聞くとその方は子供のことを心配して、なんとか介入したいと思っているが、旦那さんは成長の一過程と捉えて、あまり問題と思っていないということであった。共働きだが、奥さんは時短で働いており、子供の面倒はほぼ奥さんがみているということだったので、そういったことも影響しているように感じたが、よく考えると根本的には夫婦間の考え方の違いが問題なのではないかと思った。私自身、そのような経験があったからである。
最初に書いておくが、我が家は共働きで、祖父母の援助は得られない状況で、お迎えなどはほぼ同等で行っている。保育園での問題行動が顕在化する前のある時、妻からこんなことを言われた。「息子のこんなところがおかしい気がする、専門の精神科の先生に見せた方がいいのではないか」
いま思えばある種の予兆だったのだが、私は「そんなことは自分ご子供の時もあったしなぁ」と深くは考えなかった。ただ妻が心配していたので近くの小児精神科を探したものの、タイミングが合わず受診には至らなかった。その後、保育園の先生から、息子が大きな声を出すという話をされたことがあったが、ふざけているだけでしょうと相手にしなかった。これもいま思えばサインだったのだが、当時の私は楽観的に考え、成長の一環だろうと捉えていたのである。
きちんと統計をとったわけではないが、周りの話を聞くと、子供が問題を起こした時に私のようなリアクションをとる男親は多いようである。子育てにほぼ参加していない人は仕方ないが、私は週の半分はお迎えから晩御飯、お風呂、寝かしつけを行い、ほぼ毎日、息子と顔をあわせていたにも関わらず、サインに気づくことができなかったのである。
話は変わるが、私はこの手の失敗を母でもしている。15年ほど前になるが、当時、私は独身で大学病院で医師として働きながら週に一度、実家近くのクリニックにアルバイトに行っていた。そしてバイトの仕事が終わると実家で夕食をとり、大学病院近くの一人暮らしのマンションに帰っていたのである。ある時、一緒に夕食を食べながら母が、「最近、体重がどんどん減っていて、ついに50kg台になった」と言い出した。もともと母は太っていたので、ダイエットでもしているのかと話を流してしまった。また別の時、膝のところに塊のようなものができ、それが数日して動いたという話をしてくれた。その時も、あぁそうと流したが、結果からいうと母は膵がんを発症しており、それがきっかけの糖尿病を発症していたのである。体重が減っていたのは重度の糖尿病のためであった。さらに最終的に母は肺塞栓が原因で他界したのだが、がんがあると血液凝固に異常をきたし、血栓を作りやすくなることが知られており、膝の塊はまさに血栓のことをさしていたのである。診察室で患者の話は真剣に聞いていても、家族の重大な悩みは聞き流していると無力感を感じた出来事であった。
さて話を子供のことに戻す。私自身が息子のことで真剣に介入しなければと思ったのは結局、保育園の先生から保育園での息子の様子を具体的に聞いてからであった。このあたりのことは前回も書いた。では楽観的なお父さんを真剣にさせるにはどうしたらよいか?私は具体的な子供の様子を知らせ、異常性を示すことだと思う。例えば、保育園で子供が他の子に手を挙げてしまったとする。多くのお父さんはこう思うだろう。「あー、俺も小さい時によく喧嘩したなぁ」
しかしこの感想は、異常性については吟味していない。例えば、自分の子供が友達に意地悪をされていて、腹が立ってその友達を殴ってしまったとする。暴力はよくないという議論は置いておいて、この反応に異常性はない。特に保育園くらいだと話すのが下手な男の子は反論できず、友達を叩いてしまったりするとよく聞く。喧嘩した後で先生に殴ったことを咎められ、相手の子に謝ることができればパーフェクトだろう。成長するにつれて、意地悪しないでと言えるようになり、暴力を振るうこともなくなると予想できる。またこういったことがあったら先生から親に報告はあるかもしれないが、医療介入しましょうという話にはならないだろう。
では、みんなで座って絵を描いている時に突然、一人の子が立ち上がって叫び出し、隣にいる子を殴り出したらどうだろうか。異常性を感じるのではないだろうか?これは極端な例だが、発達障害で問題になる子供は理由もなく突発的な行動をとることが多いようである。周りの大人も含め、なぜその子がキレているのかわからない。ただ、おそらくその子なりの理由はあるのだと思う。先ほどの場面でいえば思ったような絵が描けなかったとか、うまくペンケースが開けられなかったとか、そういった理由があるのである。ただそれを表現できない。もちろん年齢を経るにつれてできることが増えたり、周りに助けを求められるようになり、自然に解決していく場合もあるが、そうでない場合もある。したがって適切にトレーニングしてあげ、本人が生きづらくならないようにすることが重要と私は思っている。またそういった場面を見た時に、保育園の先生は両親に子供の問題行動を伝えるので、それをよくあることと流してはいけないと思う。さらに、そういった異常性を伝えられれば、楽観的なお父さんも真剣になると思うのだが、どうだろうか。
最後にタイトルにもした子育てに対する夫婦の温度差について言及したい。療育センターに行くようになってから私たち夫婦と先生で面談を行う機会が多くなった。最近、気づいたのは面談の際に私が話している時間が極端に少ないということである。一見するとワンオペで子供の面倒をみているお母さんと仕事ばかりで子供の様子がわからないお父さんの構図に見えると思う。しかし実際はそうではない。私の方が保育園の先生とはよく話をしていたし、療育センターなども私の方が多く付き添っている。ではなぜ私が黙っているのか。勤務時間の関係で妻の方が普段、先生と話す時間が少ないため面談では多く話してもらいたいということもあるが、それより同じ出来事をみていても夫婦で捉え方が異なり、そのため意見の相違が生じることが多々あったことの方が大きい。もちろん妻が話していて全く違うなと思った時は口を挟むし、どうしても自分の意見を言いたい時は口を開く。しかし基本的には妻の考えに沿うようにしている。これは我が家のというより、マイルールだと思う。
話はずれるが、爆笑問題の太田さんが普段はテレビで大暴れしているのに、奥さんが出てくると黙っておとなしくなることをいじられる番組を見たことがある。その時に太田さんが言っていたのは、「夫婦で捉え方、考え方が違うからこっちがあんまり言うとあとで怒られるんだ」ということであった。我が家の場合、怒られはしないが、同じ場面について話していてもそれは違うよと言われることは多々あるし、逆のこともある。したがって家庭の方針を一本化する目的で私は黙ることにしている。妻が子供にしっかり向き合い、方針を決める一方で、私が少し引いて客観的な判断をするというのが理想的ではないかと思っている。例えば教育虐待につながりそうなど、方針がおかしくなりそうなら私が軌道修正を試みるのである。
ちなみに逆のパターンはよく聞く気がする。つまり子供の面倒をみていないお父さんがペラペラ話し、ワンオペの奥さんは押し黙っているというケースである。もちろん話すのが得意とか、苦手とかはあるが、これはこれで健康的でない気がする。
いずれにせよ、私自身はあまり迷惑をかけない形で家庭に貢献できればよいなと切に願っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
