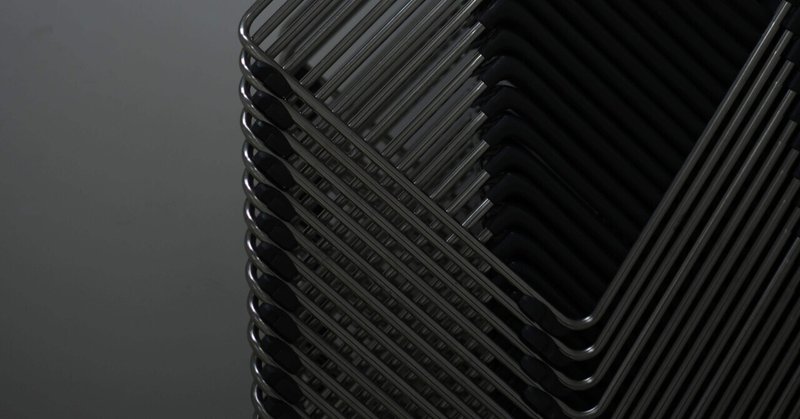
「私」が不在する写真。「私」を物語る写真。「私」が語る写真。
トモコスガさんの動画を見ていて、目から鱗が落ちるような感覚を得た。
ここで語られていることは、考えれば当たり前のことなんだけれど、写真表現は自分の抱えている問題を浮き彫りにして表現する手段としても有効なんだよな、と。
そんなことをすっかり忘れていた。
僕はもともと文章を書くことを学んだ、というか好んだ人間である。(で、その程度かい、というツッコミはご容赦願います…汗)
なんならトモコスガさんと学科は違えど同じ大学、学部に通っていた。年齢的には、トモコスガさんが多浪していない限りはキャンパスを同時期に歩いていたことになる。
かたや見事な解説、解釈をされる(そしてとても声が好きだ)方、かたやカメラゲットしたぜ、げへげへなどど言って喜ぶだけの飛べない豚である。飛ばないではない、飛べない、だ。どうしてこうなった?(間違いなく部活で酒を飲みまくり真冬の江古田コンパの階段を転げ落ちて道端で寝入ってしまうようなことを繰り返していたからだ。だが、そのうだうだな4年間を否定はしない。得たものも大きいからだ)
文章は、絵も描けない、集団で活動もできない自分にとって、最適な表現手段だった。16歳のころにそこそこの長さの物語を完成させた。A5版のノート一冊くらいかと記憶する。ベタなストーリーだったが、その分純粋だった。それからもう一本、こちらは当時山本直樹(?!)の「ありがとう」にかなり影響を受けていて、それでうまく消化できていればいいのだけれど、まあ、つまり、今の自分からしてもそんなに上手い文章ではない。ただ、僕が書きたい映像があって、それをなんとか言葉で表そうと四苦八苦したのは、いい練習になっていたと思う。子供の頃から誰しも、少なくとも教科書できれいな文を読んではいても、いざ書いてみるとここはどう表すべきか、わからなくなる。それを知っただけでも得たものはあった。
ここで言いたいのは、そんな物語のなかに、僕は確かに「私」を描いていた、ということだ。厨二病よろしく、僕の自己陶酔的内面を反映した登場人物がそこにいた。なんとなればヒロイン的立場の女の子を出せば、それはステレオタイプな女性か、僕が夢想するワンピースと麦わら帽子の女の子、みたいな。つまりどこかの心理学者が言うところの恋愛とはつまり自己愛である、を、言葉の中に再現していたのだ。
まあ、十代なら多かれ少なかれある話だ。
ただ、そんなことを長くやり続けていたのは残念な話である。
社会人になり、ブログを始めてみた。最初は書き溜めてきた小説なりを載せるためのものだったが、カメラを手に入れたこともあり、ブログを移行して言葉とともに写真を載せる体裁を取るようになった。
そうしてそんな自己顕示欲満載のブログをけっこうな期間続けてきた。それはそれでいいと思う。そんな時期は必要だ。
今見返すと……「うん、恥ずかしい」となってしまうけれど。

ただ、そうやって益体もない言葉を綴っていくと、自分には語るべきものがないなあ、ということにぶつかった。夏目漱石がイギリスに留学してノイローゼになったように、島崎藤村が自らの出自を問題としたように、あるいは佐田稲子が自らの体験を書いてプロレタリア文学を体現したように、そしてトモコスガさんが紹介した方のような、自身のアイデンティティの不確かさを写真で表現したように。自分には世に問うようなテーゼを見出せなかったのだ。
そう言うものがない人間が何を語るべきなのか、そんなことを考えていた。
そんなものなくても書くべきことは山ほどあるぞ、とゼミの教授に言われたのを思い出す。
そうして書いていったのは、結局益体もない自分だったわけだが。
今写真を撮ることに夢中になって、そうして撮り続けているわけだが、僕のそれらがどうもつまらないのは、写真の巧拙だけにあるのではないような気がしてきた。
あれだけ自分がー!自分はー!と書き殴ってきたその自分が、そんな自分すら、その写真に込められていないのだ。厄介なのは、だからといって、ただの記録にもなっていないと言うこと。書くことも撮ることも、そこにはどうしても「私」が介在する。そしてその「私」というのが、安易なテンプレートで写真を撮ろうとしていることに気付かされる瞬間があるのだ。こう撮った方が「らしい」とか「っぽい」とか。

見る側に立って、写真を語るとき、断然面白いのは組写真だったり、写真集だったりする。一枚で完成されたそれに激しく感動することは少ない。すごいっ上手い!とはなるけども。
なぜ組写真や写真集が面白いのか、それはやはり一貫したテーマがあるからだ。
たとえば今回拝見した動画であれば、韓国人の両親のもとに生まれ、日本で育ち、アメリカで学び、そして国籍を手に入れる、その間に自身のアイデンティティとは、ルーツとは?という問題に向き合うことになる。自身の直面した問題を題材にしている。
これを、「『私』を物語る写真」と名付けてみよう。
私の言いたいこと、表現したいことは何かを明確にし、そのためにどんな写真が必要か、撮るべきかを「創り出す」 だから、それらを観ると、一本の映画だったり、私小説を読んだ気分にさせられる。作者という「私」を介在して届けられた主題を、我々が受け取る形になる。その主題と自分とがあまり関係がないところにいたとしても、そういう問題を抱えた人がいる、ということを知り、ひとつの社会問題として考えるきっかけを与えてくれる。

あるいは、同じく韓国繋がりで権徹氏が撮った「歌舞伎町のこころちゃん」4歳のホームレスの女の子を撮った写真集。こちらは「『私』が語る写真」と名付けてみる。
この作品は2009年ごろだと記憶するが、不景気のなか、日本では考えられなかった子どものホームレスという社会の問題を帰納法的に切り取っている(私が語る写真は常に帰納法的である。当たり前の話だが)。こうした自分の外にあるものに問題意識を持ち、そこにまなざしを向けて撮っていく。写真表現の手段としてはこちらの方がオーソドックスかもしれない。ただ、その社会で起きている問題を問題として認識し、それをどう切り取っていくかは、「私」というフィルターを必ず通すことになる。「写真」とは言え、何を見るか、どこでシャッターを切るかは、結局、何を見せるか、という「私」を介在した表現になっていくのだ。
内側のものを外に出すか、外にあるものを浮き彫りにするのか、つまり「私」を語る写真か「私」が語る写真か、その違いはあれ、ともにきちんとしたテーマを持って撮られた写真たち。それは巧拙やテーマ性がどうあれ、れっきとした作品だと言える。
今の自分には、表現したい何かを持っていないことに気付かされる。時々写真展にお呼ばれされて掲示するけれど、それは何枚もただ撮り続けたなかから、一つのテーマを見出して並べたものに過ぎない。だからどうしても作品とは言い難い。
なんだか、そこに「私」の主張があるような顔をして飾られている写真たちが、その実、どこかのだれかの真似ごとにすぎず、本当の意味での「私」が存在していないのだ。
さて、僕は何を撮るべきなのか。
趣味だからいいじゃないか、なんだって、とは思うけれど、心のどこかで何かを表現したい、という想いはある。だけれど、若いころのような自己陶酔も、社会に対する憤りも、世界の悲惨な状況にも、僕の忙しく、そして愛おしい日常の前にかすんでしまっている。
だから結局毎日、私の半径500メートルを撮り歩くことしかできないし、そのなかでなにか面白いものを見つけて、面白く撮ってみるか、というようなことしか術がない。

かなり以前、写真を真剣にやっている知人が「テーマが見つかったんだ」と電話をしてきたことがあった。その内容は、ああ、なるほどね、と思うものではあったけれど、今考えてみると「それってTwitter(X)で人々が晒す『こんなひどい親がいるんだぜ』と何が違うんだろう」と思うものでもあった。「それを作品として耐えうる表現にするのが写真家なんだよ」とも思うけれど、いや、これ、相当難しい。何より正直に言えば、写真家として名をあげるために、何か社会の問題を取り扱おうという意図が目に見えて、あまり気持ちの良いものではなかった。いや、名を上げるために社会問題を利用することは何も悪いことではないとは思うけれども。
一方で、数年前にCanon新世紀で賞をとられた方がいる。その作家さんは地元の方だけれど、彼の写真にはそういう「云いたいこと」が不在であった。不在からくる不安がそこに写し出されているように思った。
写真は、というより全ての芸術と呼ばれる作品は、私が仕事をすることによって、どうしても「私」を不在にすることはできない。くだんの地元出身の方の写真は、すごく空っぽで、故に吸引力があって、ちょっと長いこと観ていることができないような写真たちだった。白昼堂々と行われる、冷淡な殺人事件のような陰を含んだ明るさがあった。ここまで何を言いたいのか、伝えたいのか分からない写真は見たことがなかった。
だが、それだって、そこに「私」が介在しているのだ。そうしてその写真に介在する「私」は見事なものだと思った。むしろ、こんなのが好きなんでしょう?とか、こんなのが写真っぽいよね、と定型や陶酔に陥った写真の方が、つまり自分の写真は、ということになるわけだが、本当の意味で、「私」が不在となってしまっていることを、強く感じさせた。

SNSで見かける美しい写真。それだけでも僕にはけっこう難しい。たくさんのイイネをもらっている写真はやはりきれいだ。けれども、それらはなかなか記憶に残らない写真でもある。Instagramの特性で、画面をスクロールしてあ、と思ったら、いいねをタップする。そのような条件反射で見たつもりになっている写真たちは、いわゆる単なる消費と成り果ててしまっている。それでもいい。とは思う。楽しめればそれでいいし、いいねをもらえたらそれで十分写真趣味としては機能している。何よりやっぱり上手いし、きれいだ。
だが、それでも。私は私の写真に、何を介在させたいのだろう。何を語らせたいのだろう。そんな気持ちが、ふつふつとわいてくる。機材を購入して、ぐふぐふとほくそ笑んでいるのも楽しいが、一方で、あの益体もない自意識と戦っていた青年期の、何かを伝えねばっという気持ちの表現を、写真というメディアでやってみたいな、と思う。言葉でそれをやっていたとき、それは若さもあって、そして言葉を使っていたこともあって、饒舌で語りすぎていて、それゆえに押し付けがましいものだった。今ならもう少し抑えを効かせてやれるような気もする。
だが、抑制というスキルを身につけた今、今度は私の中の語るべきものが枯渇しているということは認めねばなるまい。忙しく愛おしい日常によって感性は衰えるのだ。だったらどうするか。「私」を語ることが要らないのであれば「私」が語る写真を撮ることしか残されていない。「私」が生きるこの社会を、「私」が語るために、「私」を介在させるのだ。そのために必要なのは、外向きの視線である。それを知性という。感性は衰える。だが知性は成熟する。「私」が間違いを犯さずに語るために、私は学ばなければならない。「私」を語ることは、はたから見れば、気持ちが悪いとすら思う。でも、それをうまくやってのけた写真群はすごいと思う。それはきちんと自身を客観視しているからだ。勝手に介在する私に色をつけずに見つめたからこそしっかりと乾いた自分がそこに浮き上がってくる。そうすることもできぬまま、じっとりと濡れた自分を描こうとしているうちに、言いたいことも無くなってしまった初老の男に、果たして私が物語る写真すら撮れるかどうかあやしいが、それでもいつか、問題意識をしっかり持った写真表現というものをやってみたいと思っている。そのためには結局、半径500メートルしか撮ることのない日々を送りながらも、自身の外を見て知らねばならないし、学ばねばならないし、撮り続けていかねばならない、それは確かなようだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
