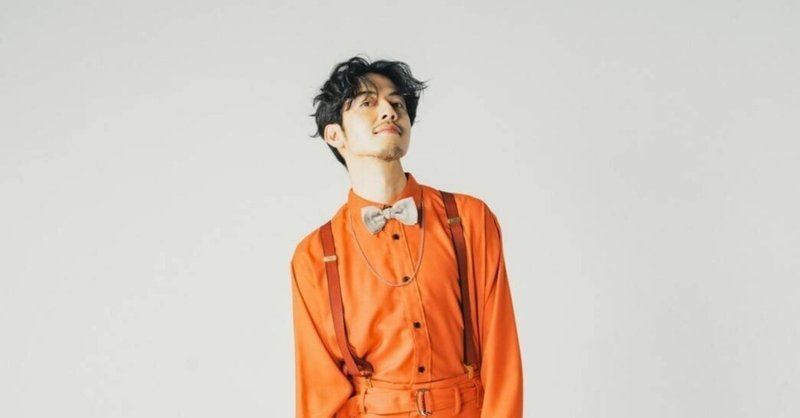
『ギフト文化』という選択肢【キンコン西野】
このnoteは2024年5月18日のvoicyの音源、『CHIMNEY TOWN 公式BLOG』の内容をもとに作成したものです。
一旦、素直に聞いてください
本当に「同じ過ちを何回繰り返すんだよ」という話なのですが…
当時、クラウドファンディングのことを「詐欺だー!詐欺だー!」と批判していた人が、震災で家が壊れたり、お店が壊れたり…あるいはコロナでお店がまわらなくなって、ついにクラウドファンディングという選択肢にすがったものの、「その昔、自分が大声で批判してしまっていたせいで、自分のまわりにはクラウドファンディングに理解がある人がいなくて、支援が全然集まらずにお店が潰れました」みたいなケースが少なくありません。
他にも、当時、オンラインサロンを「宗教だー!宗教だー!」と批判していた人達が、最近、ひっそりとオンラインサロンを立ち上げたものの、当時、自分がオンラインサロンを率先して批判してしまったせいで、自分のまわりにはオンラインサロンに理解がある人が少なくて、自分のオンラインサロンには全然人が集まらない…というケースがあったり…
「無料公開」という打ち手に対して、「ダンピングだー!」と批判してしまったクリエイターさんが無料公開という(今となっては当たり前の)マーケティングが打てなかったり…
あとは、プペル歌舞伎の時に仕掛けた「VIP戦略」に対して、ブーブー言っていた日本の演劇関係者が、最近になって西野に見つからないようにコッソリとVIP戦略(VIP席)を始めてみたものの、当時、ファンと一緒になってブーブー言っていたもんだから、自分達のファンの間で「VIP席=悪」が出来あがっていて、そのせいで自分のファンから猛バッシングを浴びる…という、なかなか味わい深いブーメラン芸を展開されております。
「理解できないものを批判する」は、自分の将来の選択肢を減らすだけなので、理解できない時は「理解できるまで静観する」が正解なのですが、皆、どうにもこうにも条件反射的に感情が出てしまうみたいです。
今日のこの話は、どちらかというと舞台関係者に向けてお話ししているのですが、もう本当に悪いことは言わないので、これから僕がお話しする提案に対しては「今すぐ自分も試す」かどうかはさておき、一旦、素直に聞いていただきたいです。
その提案というのは、昨日のVoicyで熱弁させていただいた『ギフトチケット』のことです。
「利用者に販売する」か「寄贈者に販売する」か?
「2025年8月におこなうミュージカル『えんとつ町のプペル』(日本公演)に、2500人の子供達を無料招待しよう!」と立ち上がったクラウドファンディングは、現在、730名の子供達を無料招待できるだけの支援が集まっております。
たくさんのご支援に心から感謝します。
そして、引き続き宜しくお願いします。
※クラウドファンディングはこちら
さて。
ウチのオンラインサロンメンバーさんなら、もう千回ぐらい聞かされている話だと思うのですが、自分の作品・商品・サービスを販売する際、「利用者に販売するか、寄贈者に販売するか?」というチェック項目は設けておいた方がいいと思っています。
たとえば、「ランドセル」は利用者(小学生)には販売せずに、寄贈者(おじいちゃん)に販売しています。
ランドセルの例を出すと「言われてみれば、ランドセルって利用者に売ってねーな」と皆さん納得していただけるのですが、あのビジネスモデルを他に置き換えようする人は、あまりいらっしゃいません。
「自分の商品が寄贈品になりうるか?」と考え始める人が、あまりいない。
CHIMNEY TOWNでは、ここは結構マメにチェックを入れていて、それこそ絵本『えんとつ町のプペル』にいたっては、『えんとつ町のプペル こどもギフト』という国内外の子供達に毎月1冊の絵本をプレゼントできるサブスクがあったりします。
「絵本を読みたい人」に買っていただいているわけではなくて、「絵本を読ませたい人」に買っていただいている感じです。
※えんとつ町のプペルこどもギフト
「何が寄贈品になるか?」は試してみないと分からなくて、絵本『えんとつ町のプペル』も試してみた結果、そこに「ギフト」としてのニーズがあることが確認されました。
「支援の文化が弱い」とお金がある人にチャンスが集中してしまう
日本人のマインド的に「義援金」までの距離は近いけれど、「支援」までの距離は遠くて、日本人はすぐに「自分の金でやれ」という言葉が出てきます。
「クラウドファンディングで被災地を助けたい」というプロジェクトには理解を示す人も、「クラウドファンディングでお金を集めてニューヨークで個展をしたい!」というプロジェクトには「自分の金でやれ!」と言っちゃう…みたいな。
「支援の文化が弱い」や「他人の夢を素直に応援できない」が当たり前になってしまっている世界では、お金がある人にチャンスが集中してしまうので(生まれた場所で勝負が決まってしまうので)、皆にとって、あまり喜ばしいことじゃないと思っています。
話を演劇に戻すと、今、演劇やミュージカルは「利用者」にしか売っていなくて、その結果、買う力がない人(特に若い子達)がターゲットから外れてしまっています。
演劇やミュージカルの客席で子供達の姿を見る機会が本当に少なくて、かつ、キャストの集客力に依存した集客をしている作品が多いので、キャストの年齢に合わせて、「客席の高齢化待ったなし」みたいな状況に陥っています。
なので、おのずと作品の内容も「大人向け」に絞られてしまう。
これだと、演劇やミュージカルの行き着く先は「金持ちの爺さん婆さんのエンタメ」になってしまうので、「VIP戦略」と合わせて、「ギフト」の可能性も視野に入れ、その文化作りをお客さんと一緒に進めておいた方がいいと思います。
▼西野亮廣の最新のエンタメビジネスに関する記事(1記事=2000~3000文字)が毎朝読めるオンラインサロン(ほぼメルマガ)はコチラ↓
\メールアドレスのみで利用できるようになりました/
※サロンメンバーさん同士交流される場合は今まで通りFacebookアカウントが必要です
\公式LINEができました/
▼西野亮廣 公式LINEはコチラ↓
https://lstep.app/GEhq1k4
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

