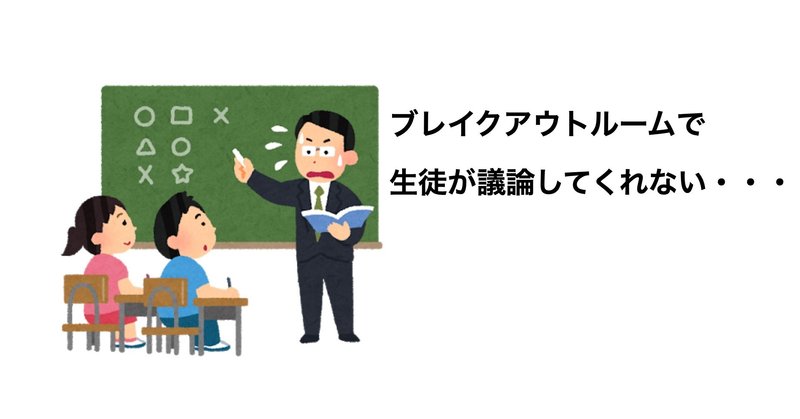
オンライン授業。Zoomのブレイクアウトルームはもう使わない?
A「ついにわが校でもZoomでオンライン授業が始まった!」
B「一方的な講義にならないようにブレイクアウトルームを使ってグループワークをさせるといいらしいよ。」
A「ふむふむ。やってみよう。」
・・・・
B「どうやった?」
A「う〜ん、なんかあかんなあ。子どもらが固まってしまったわ。結局何も話し合ってくれへんかった。」
B「そうなん?やっぱオンラインじゃ授業は無理か・・・」
A「もうブレイクアウトルームは使わんとくわ。」
・・・・
ちょっと待って。
これはブレイクアウトルームの問題なのでしょうか。
確かにオンラインならではの難しさはあります。子どもたちの仕草・体の微妙な動きを察知するなどのスキルが使えないとか、何もしていない子どもに即座に声かけができないとか、各グループを回っていきながら実は他のグループの会話にも耳を傾けているとか、そういう教師スキルは使えません。子どもたちも、例えば相手の発言を最後まで聞いてから返事をする、顔の表情をいつもより豊かにして相手に伝えわるようにするとか、そういうオンライン会話スキルが身につけていないのでグループワークをオンラインでしろと言われても戸惑うのはわかります。
けど、ブレイクアウトルームで子どもたちが固まるのはそれ以外の根本的な原因が考えられませんか?
例えば、ブレイクアウトルームで話し合う目的がはっきりしていない。誰から話し始めるか指示がない。誰に司会を、記録を取らせるかなど役割分担がない。時間設定がない。ミュートのままブレイクアウトルームに移動させてしまっている。人の話は最後まで聞く、途中で反論したり質問しない、大きくうなずくなどのオンラインコミュニケーションの基本を教えていない。普段の授業は一方的な講義ばかりでグループワークをしたことがない。そもそも子どもたちがその授業を学ぶ必要性を感じていない。学習内容の導入が面白くない。など。
普段から上手にグループワークをさせている先生ならきっとブレイクアウトルームを使っても同様の成果は上げられると思います。
先ほど言ったようにオンラインの難しさは確かにありますが、動画授業ではできない双方向でアクティブなオンライン授業を模索していただきたいと思います。
Inspire Children at Home. Stay Home.
追記
小中学生が「9月入学」について当事者目線で議論したそうです。子どもたちの生活に関連していることで、子どもたちが議論したいと思えばオンラインでもオフラインでも関係ない!
世界一わかりやすいZoomの書籍。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
