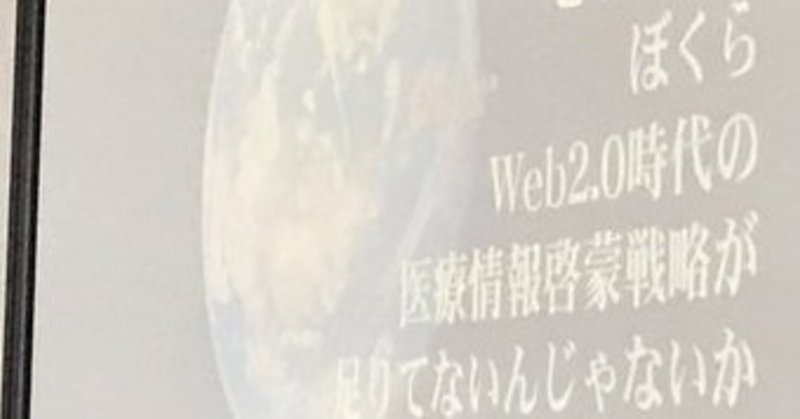
腹を割るための条件。
情報伝達においてはさまざまなエラーが生じるけれど。
腹を割ってゆっくり話し合えば、たいていのことはそこそこわかりあえるものだ。
ではこの「腹を割って話す」というのは、どういうやり方を指すのか?
このnoteでは話題を無駄に引き延ばすつもりがないので、一気にぼくが考えていることを書いてしまう。「腹を割って話すためのカギ」は、お互いのリアクションを信用できる環境にあるんじゃないかな、と思っている。
こちらが何かを言ったときに、相手の表情がかすかに曇る。あるいは、語尾が濁る。さらにはもっと直接的に、「ごめん今のわかりづらかった」という言葉が相手から出る。
そうしたらすかさず、「あっ、わかりにくかった?」と声をかけて、仕切り直すことができる。これができるかできないかに、コミュニケーションの真髄があるんじゃないかと思っている。
もちろん、逆のパターンもある。たとえばこちらが何かを言ったときに、相手の表情がぱっと晴れる。あいづちが入る。「今のわかりやすかったなあ」と言われる。そのときは、「なるほど、このしゃべり方だと相手にやさしいんだな」と、自分の言葉に効力を感じることができる。
自分の説明の何にひっかかっているのか。共有している前提に何か違いがあるのか。
自分が何を題材にしてどのように話したときにガンガン食いついてくるのか。どのような情報を相手は「もっと聞きたい」と感じ、どのような伝達手段だと「なんか飽きてきたな」と感じるのか。
「伝わるはずだ、伝わったはずだ」ばかりでフィードバックが働かないまま一方的に「講演」すると、なかなか情報は伝わらない気がする。
「ちょっと待って、もう一度」と言える関係。
「いいね、それもっと聞きたい」と言える関係。
これこそが「腹を割って話す」ということであり、コミュニケーションのエラーを防ぐ優れた方法だと思う。
対話の間に、お互いのリアクションがきちんと相手に届くこと。
***
さきほど、
このnoteでは話題を無駄に引き延ばすつもりがないので、一気にぼくが考えていることを書いてしまう。
と書いたが、「ぼくが考えていること」自体が終わらなさそうなので、引き延ばすつもりは毛頭ないのだけれどまだ続く。
文章の細かな技術、ブログの体裁、プレゼンの見せ方、喋り口調……。こういった「伝える技術」というのはどれもこれも当たり前のように有用である。うまくなりたい。
しかし、たとえ語り手の「伝える技術」が一流でなくても、聞き手のリアクションに敏感に反応できていれば、リアルタイムでお互いの理解度を確認できるならば、十分に、いやそれ以上にコミュニケーションは成立するものだ。
……ここでぼくは、「伝える技術」よりも「リアクションを伝え合う関係」のほうが大事だと言っているわけではなくて、その両者が大事なんじゃないかな、ということだ。そこはわかってほしい。
その上であえて言う。
どうも、医療情報を伝えようとがんばっている人たち、医療者や医療系メディアのみなさまは、「伝える技術ばかり上手になっていく」気がする。
多くの医療系記事を読んでいると実感するのだが、臨床的に名の知れた医療者たちの書く文章はどんどん読みやすくなっている。華やかでうねるような展開。匂い立つ語彙。フフッと思わせるウィット……。
すばらしいことだ。
でもその一方で、「これでもまだわかりにくい」と感じる非医療者たちの素直なリアクションをすくい取る場所が増えていないなあと思う。
「伝える技術」を向上させることに成功したなら、「リアクション環境」のほうも平行して整えていったほうがよい。……これは理想論だろうか? ぼくは極めて現実的な改善案だと考えている。
ぼくを含めた医療者は、インターネットで情報を伝えた相手の「顔色」を探ることについて、正直、どうしていいかわかっていないと思う。診察室でひとりひとりと向き合うならまだしも、インターネット上で不特定多数の人間がどういう受け取り方をしているかを読むというのは難しい。
ときに、読む人・聴く人のリアクションを受け取る方法を勘違いしているケースもある。その最たるものが「PV」や「RT数」だ。
PVやRT数は、コミュニケーションが行われた回数と比例する。けれどもそこでエラーが生じているかどうかにはあまり関係がない。「やさしい医療情報」が1回伝わっても、「あからさまに誤解をうむ医療情報」が1回伝わっても、カウントは1増える。
「私たちは適切な内容をより多くの人に届けるために日夜がんばっています」と宣言することはまっとうだ。しかし、受け手のリアクションをはかる手段がPVやRT数だけというのはいかにもお粗末である。
細かいニュアンスで引っかかっている瞬間の受け手の気持ちを、どうすくい取っていく?
そこをきちんと解決しないと、ぼくらはいつまでも、「あの先生はすごく熱心にいろいろ説明してくれるんだけど、おうちに帰ったらなんか半分も覚えてなかったわw」と言われる医者のままだ。
結局、ときおり双方向でやりとりをしていくしかないという結論に落ち着く。情報を発信する際に、毎回双方向型でとりくむというのは現実的ではないけれど、
「たまには非医療者と腹を割って話し合う」
という姿勢をとることならできるだろう。
そこで必要なのは「ほめあうこと」でも「けなしあうこと」でもなくて、瞬時のリアクションをやりとりすることだ。「あっ今のはよくわからなかったなあ」という表情を、語り手の目の前で、リアルタイムで聞き手が表出する瞬間を見逃さない。すかさず感じ取ってプレゼンをリアルタイムで修正する。これをくり返すのだ。積み重ねるのだ。
***
在宅、リモートが全盛となって、さまざまな「伝える方法」が現れた。ZoomやYouTubeをもちいたオンライン対談やオンライン講義などはその最たるものだ。
伝える技術に長けた「プロ顔負けの発信者」を目にする。あたかも「リアルの講演会のような臨場感」が手軽に得られる。「会場のスクリーンで見るよりも、視聴者自身のPCモニタやスマホのほうがプレゼンが見やすい」などという思わぬ副産物もある。
一方で、オンラインで医療情報を伝える際に、視聴者がリアルタイムでリアクションしているところを無視する講演者が多いことが気になっている。
正確には「リアクションを得ようと思ってもどうやっていいかわからない」のだろうな。講演後に、「必死でしゃべったけどみんなどうだったかなあ」みたいなことをつぶやいている医療者をあちこちで見かける。
オンラインでは聴衆の顔色がうかがいづらいという事実について、みんな、もう少し真剣に問題視したほうがいい。
「モニタの前で、コメントも入力せず、無言で眉をひそめた人」の顔を見ることは本質的に不可能である。ここに強い「制限」がかかっているのだということを、オンラインで医療情報を伝えようと思った人は、ほんとうに心の底から意識したほうがいいんじゃないかと思う。ぼくらはこのままオンラインになれていくと、自己満足のプレゼンを「現場で微調整するチャンス」がないのだ。だんだん、ずれていくと思うのだ。
