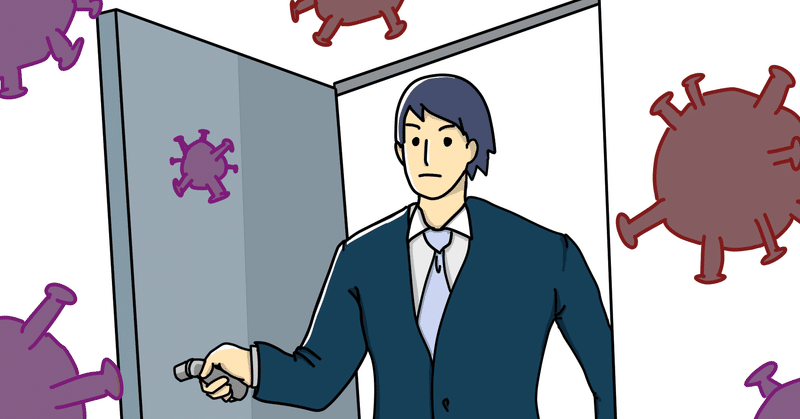
新型コロナウイルスは、空気感染するのか?(5月13日こびナビTwitterspacesまとめ)

☝Twitterspaces参加方法はこちらのツイートを参考にしてください。
2021年5月13日(木)
こびナビの医師が解説する世界の最新医療ニュース
本日のモデレーター:峰宗太郎
木下喬弘
おはようございます。
峰先生、おはようございます。
峰宗太郎
あ、聞こえます? 聞こえますか?
ちょっとこれテストしていいですか?
(木下先生の音声に若干の乱れが発生)
峰宗太郎
あれ? 木下先生が不安定なのかなぁ?
木下喬弘
あれ? 僕がアカンのかなぁ?
峰宗太郎
Hey Siri、Taka先生を呼んできて!👶
Hey Siri、Taka先生を呼んできて!👶
Taka先生だよ!!!👶👶(笑)
安川康介
あの……ありがとうございました。
ちょっとこれで……去りたいと思います🥦(笑)
木下喬弘
(笑)
じゃあ今日皆さんどうもありがとうございました🔥
日本の皆様よい1日をお過ごし下さ……
前田陽平先生
こらこら、こらこら!
峰宗太郎
今、まだ雑談の時間なんですけど、今は……あ、もう658人ですね!
あ、黑川先生が来ましたね。
黑川先生、聞こえますか?
(黑川先生、音声トラブルで無音)
前田陽平先生
黑川先生側の問題があるのかもしれないですね。
なんかミュートマークも出ていないし。
峰宗太郎
うーん。
ま、いいですかね。
では雑談がてら始めていきたいと思います。
今日は僕がモデレーターって言うことでいいんですよね?
木下喬弘
Yes!
峰宗太郎
今日は安川先生とダブルヘッダーで行きたいと思います。
僕が基本はリードします。
オッケーですか、安川先生?
安川康介
よろしくお願いします。
実は僕、昨日モデレーターやったんですが、みんなに「最初のトピック何がいいかな?」って相談した時に、木下先生が「今いろいろ議論があるところなので、空気感染は避けてくれ」と言ったんですね。
僕は「空気を読んで」空気感染の話題を避けたわけですが、次の日に峰先生が空気感染を話すことになって、個人的には面白いです。
峰宗太郎
はい。まぁ、空気感染の話題ですね。
この話題はすごい激しい「議論」といいますか、いろいろなことが起こっている話題です。
ただこれ、ベースは科学と医学と医療の話なんですよね。
だから冷静にお話しすれば皆さんわかってくださると私は思っています。
別に戦闘的な意図は全くないです。
時に私も武闘派なんですが、そんなことは気にせず、淡々といきたいと思います。
安川先生、今日は僕がナビゲートして一緒に進めていきますので、よろしくお願いします。
【新型コロナウイルスの基本の予防策は大事】
峰宗太郎
では今日の「こびナビの医師が解説する世界の最新医療ニュース」です。
今回は、最新でも医療のニュースでも……まぁ、医療ニュースなんですかね。
最新というわけでもないですが、最新の知見を交えながらお話していきます。
今回のテーマは「感情的に」いろんな方が聞いていらっしゃると思います。
「空気感染が新型コロナウイルスの感染モードの中で主たる感染経路だ」と思っている、簡単にいうと新型コロナウイルスは「空気感染がメインルートなんだ」と思い込んでいらっしゃる方は、聞いているだけでイライラして、机をドンドン叩きながら聞くようなことになってしまうかもしれないのですが、そういうことにならずに、どういうことを問題視しているのか、どういうことが大事なのかを、しっかりと順序だてて話していきます。
これから軽く安川先生を含めて皆さんと議論したいと思いますが、その前に、1番大事なことを、最初と最後に2回いいます。
新型コロナウイルス対策、基本予防策の徹底、大事です。
これをあらかじめ強調しておきたいと思います。
今流行が再拡大しています。
日本中が大変なことになっています。
世界中でも、インドなんてとても大変な状況になっています。
ですが、大切な事は、
・日本から提唱された3密の回避
・マスクをする
・換気をする
・距離を取る
・手をよく洗う
・体調が悪ければ外出しない
・栄養と睡眠を取る
そういったことをしっかり徹底していただいて、とにかく人と人との「接触」を減らすことでしょう。
とにかく病原体がやってくるルートを断つことをしっかりやって、感染リスクを下げていきましょうということが大事なんです。
これを最初に強調しておきます。
これは空気感染が絶対メインの感染ルートだと言いたい方も世の中にはいらっしゃると思いますが、そういう方でも気をつけていることです。
例えば3密を否定するとか、手を洗わなくていいとか、コロナは嘘であるとか、そういう主張まで行ってしまっている人でなければ、理解していただけると思います。
木下喬弘
では、アレクサ、空気感染て何?🔥
峰宗太郎
ハーイ アレクサ ダヨー!👶
……ていうことではなくてですね(笑)
アレクサがどういう声をしているのか知らないんですけど(笑)
去年からですね、定義を大事にしないこと、概念をいい加減にする、また「自分の知らない知識は初めから存在しないもの」と目をつぶったり、「いい加減に適当に自分勝手に扱っていいよ」という人たちがワラワラとわいてきました。
例えば、最近で言うと某「手を洗う救急医 Taka」という先生の Twitterタイムラインで、PCR検査にベイズ推定を使ってはいけないとか、ベイズの推定なんて使うものじゃないとか、「そんなものはない」と主張するすごい人が出てくるんですね。
これは純粋にベイズというものが理解できなくて、否認しちゃっているという、結構強いステート(主張)の方ですね。
変異ウイルスの名称にしても、学問的な概念を理解せずに変異種と簡単に読んでしまった人もいました。
やはり言葉を、つまり概念を、結構ないがしろに使っちゃうとか、いい加減に使ってる人っているんですよね。
でも、そういうことってよくないんですよね。
言葉の概念・定義(つまり何を意味しているのか)からしっかりすり合わせて、そして有益な議論をすることはとても大事です。
こうしたことを常々私は申し上げておりまして、ここにも今日は私のタイムラインをよく見てる方もいると思うんですけれども、そこは理解していただける方が多いのかなと思っています。
一方で今回の空気感染の話題に入って行く前に、非常に煽る人たち、アラーミストという人たちが増えているということも事実ですね。
特に「変異ウイルスの感染力は15倍!」といった、びっくりする数字を突然出すなどして、とにかく騒ぎたい人がいます(致死率だったかな)。
海外の某有名大学の研究者や医師の方なども「ブレイキングニュース(速報)!!!」と「!」をいっぱいつけて毎日やっています。今回の空気感染も、アラーミストの人たちは、とにかく空気感染!空気感染!と言いたいだけです。
「では具体的に何が対策なんですか?」と聞くと、「もっと注意するんだ!」とか、「怖いんだ!」とか、「騒がなきゃいけないんだ!」とかで、うーん、よく分からないことを言い出すんです。
また、反逆のレトリックといって「こんなのは単に言葉の捉え方、定義の問題なんだよ」とか「安全マージンの取り方なんだよ」とか「喧嘩両成敗みたいなもんだよ」と言って足を引っ張る、両論併記と同じでバランスを取ろうとする「相対論者」というか説の評価のできないような日和見的な方も必ず出てきてしまうのですが、そういった方も、実は非常に不誠実な態度で、結局は「デマサポーター」のようなものだと私は思っています。
「PCR はいくらでも無限にやっていい」と主張するような人と大して変わらないです。
正しく議論するには、正しい知識、正しい定義、正しい理論(考えていく道筋)、そういうことが大事です。
現時点では不明な点もまだまだたくさんあります。
新型コロナウイルス感染症についてもそうでしょう。
多くの科学とか医療については完全なものではなくて、まだまだ知識が開拓中のものであり、考え方が大きく劇的に変わっていく可能性がある部分もあります。
ですが、その時点その時点でのベストなエビデンスや知見をもとに、今どういうことが言えるかを考えていくということが大事です。
実際はただの言葉遊びや定義論争ではなくて、実際非常に重要な、リテラシーの根幹でもあることを今日は安川先生とお示ししたいと思います。
……という長口上が、前段でございます。
実は、空気感染は、「空気感染対策」という実際の対策とも結びついていますので、1番最初に強調した基本予防策の徹底がとにかく大事だよ、ここは全然変わらずはっきり何度も強調します。
では、なぜプロが「空気感染がメインである」という言い方をしていないかをお話しします。
【空気感染とは何か?】
ここからは、安川先生のショートレクチャーという形で話を進めていきます。
安川先生聞こえますか?
安川康介
聞こえます。
峰宗太郎
じゃあ、今日は安川先生はアレクサとお呼びしてもよろしいでしょうか?👶
安川康介
是非「ブロッコリー🥦アレクサ」でお願いします🥦
峰宗太郎
はい、ブロッコリー🥦アレクサ!👶
空気感染の1番古典的かつ伝統的な定義って何?
安川康介
(笑)
これはしっかりした定義が決まっていて、どの教科書でも大体「飛沫核、5μm 以下の粒子によって起こる感染」という定義がされています。
峰宗太郎
ありがとうございます。
非常に端的なショートアンサーでありがたいです。
5μm より小さい粒々が飛んできた時に、その粒々から感染する場合は空気感染ということですよね。
飛沫核感染(airborne infection、droplet nuclei transmission)ということですね?
では、それより大きな粒々が飛んできたときに感染するものは、何感染と言うんですか?
安川康介
古典的な定義では、飛沫感染(droplet transmission)と呼ばれています。
峰宗太郎
ではその飛沫感染(古典的には飛沫(しぶき)による感染)は伝統的にはどのぐらいの距離、どういう状況で感染すると思われているのか、安川先生教えていただけますか?
安川康介
飛沫感染と空気感染はもう何十年も前、近距離の粒子の大きさをあまりしっかりと測れなかった時代に確立された概念です。
その時は、5μm 以上の粒ならば、大体 1〜2m 以内に落ちていくだろうという考え方があったので、くしゃみとか咳をしたときに、その飛沫が大体 5μm 以上あって 2m 以内に落ち、それで感染が起こるんじゃないかと考えられました。
空気感染に対して飛沫感染という、二項対立のような感染の定義がもともとあって、これに基づいて感染予防がされてきたという経緯があります。
峰宗太郎
ありがとうございます。
飛沫感染と空気感染を掘り下げる前に簡単に別の感染ルートも考えておきます。
安川先生、接触感染はどういう状況だかお教えいただいてよろしいですか?
安川康介
接触感染は実際に触って感染が起こるということです。
病原体が入っている粒子を触ったりして、それが直接目とか鼻とか口とかの粘膜に触ったときに接触感染(間接接触感染、formite transmission)ということになります。
峰宗太郎
つまり環境が汚染されていて、手か何かがそれを触っていて、その手で目などを触ってしまった時が接触感染ということですね。
では、例えば私が感染していて、安川先生にチュッチュをしてうつしてしまったときにはどうなるんでしょう?👶
安川康介
まぁ……それは、確実に……というかうつる可能性が高いですね🥦💦
※編集注:
人と人の接触による感染が起こるものを「直接接触感染」と言います。
峰宗太郎
はい、モードとしては接触感染ですね(笑)
安川康介
はい(笑)そうですね。
峰宗太郎
その他にも、モードとしての感染経路はいくつかあるんですね。
例えば
ベクター感染:蚊やマダニなどに刺されるとか、ネズミが運ぶなどの感染(ベクターは運び屋と言う意味)
血液感染:輸血、血液暴露、針刺し事故などで起こる感染
性交渉による感染:体液感染の一種
糞口感染:これも接触感染の一種。よく胃腸炎何かで汚染された便を触った手とか、飛沫が飛び散って起こる感染
このように色々な感染形態があるわけです。
さて、その中の2つ、
飛沫感染:5μm 以上の飛沫が飛んで感染する
空気感染:5μm 以下/未満の飛沫核で感染する
と安川先生から教えていただきましたが、具体的に見ていきます。
空気感染する病原体として今まで知られているものは何があるんでしょうか?
安川康介
これは医師国家試験にもよく出題されるので、医師ならば全員が知っているものです。医学生が必ず覚えている病原体が3つあります。
1)水痘:水ぼうそう、帯状疱疹を起こします。
2)麻疹:はしか。麻しんとも呼ばれます。
3)結核:世界的にとても大事な病気です。
この3つが、古典的に空気感染を起こす病原体としてとても有名です。
峰宗太郎
はい、ありがとうございます。
結核、水ぼうそう、はしかの3つということです。
池田早希
医学生用の語呂合わせとして「麻の帯を結ぶ」と覚えると良いです。
峰宗太郎
なるほど。
水痘=帯状疱疹が「帯」で、「麻」が麻疹、結核で「結ぶ」ということですね。
はい麻の帯、しまりました!👶
ということで、安川先生と池田先生からも教えていただきましたが、この「麻の帯を結ぶ」(水痘、麻疹、結核)これらは、伝統的に空気感染を起こすことが確実と言っていいんですね。
安川康介
そうですね。
峰宗太郎
そうすると、これらの病原体の特徴は 5μm 未満の飛沫核から、例えば培養されるとか感染が成立するということが証明されていると思っていいんですよね?
安川康介
そうですね。
特に麻疹と結核ですね。
結核は 5μm 以下の粒子が感染性を保ったままいるということがはっきり分かっています。
※参考:
Particle sizes of infectious aerosols: implications for infection control
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30323-4/fulltext
出典:The Lancet 2020/7/24
Variability of Infectious Aerosols Produced during Coughing by Patients with Pulmonary Tuberculosis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3443801/pdf/AJRCCM1865450.pdf
峰宗太郎
そうすると、この空気感染、すごく長い時間とか長距離を飛んで広がっていくことが想定されるわけですよね。
そうすると、1人の人が1人の次の人にうつす可能性もすごく高いと思えます。
R0(基本再生産数)は、こういった病原体では特に高いでしょうか?
安川康介
そうですね。
特に麻疹は、R0 がめちゃくちゃ高いです。
大体1人の人が12から18人ぐらいに感染させるということがわかっています。
特に有名な事象としてディズニーランド……カリフォルニアのディズニーランドである人が麻疹に感染していて、その人が元になっていろんな人に感染していって、結局100人以上が感染した事例があります。
麻疹の非常に高い感染性を物語る1つのエピソードです。
水痘も R0 自体は8から10人ぐらいと言われていますので、かなり高いです。
結核に関しては国によって違うのではっきりとした数字は分からないですが、大体2〜4位と言われています。
※参考:
Measles Outbreak — California, December 2014–February 2015
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6406a5.htm
出典:CDC 2015/2/20
峰宗太郎
結核については感染はしても発症をする人が少ないっていうのもあって正確な R0 が求められないんですよね。
いま安川先生に述べていただいたようなことがもし新型コロナウイルスで起こったら、メガクラスターとかスーパースプレッダーとか言われるような事象です。
時に新型コロナウイルスの R0 はいくつ位なんでしたっけ?
安川康介
大体2〜3ですね。
峰宗太郎
ということは、かなり違うということは分かるんですね。
安川康介
そうですね。
麻疹や水痘などの空気感染する病原体よりもはるかに低い数値ではあるといえますね。
峰宗太郎
ありがとうございます。
それでは、ここから飛沫感染との差を見ていきたいと思います。
飛沫感染の「飛沫は 5μm 以上」ということでした。
そして先程の安川先生のお話では、飛沫は 2m 以内に落下していくと昔は考えられていたということでした。
では、実際それは本当なんでしょうか?
安川先生、5μm よりは大きい粒子が、もっと長い時間空間にいる(長い間空間を漂う)ことで感染する現象は、インフルエンザを含めてこれまで知られていなかったのでしょうか?
安川康介
すみません、質問が聞こえませんでした……もう一回お願いします。
峰宗太郎
つまり、5μm よりも大きい粒子、これは確実に2m 以内に落っこちてしまうものなんですか?
安川康介
いえいえ。
最近は粒子の研究によって、実は1〜2m 以内に落ちるものは、大体 60μm〜100μm 位とわかっていて、それ以下(100μm 以下)の粒子は空気を漂うことが分かってきています。
※参考:
How far droplets can move in indoor environments – revisiting the Wells evaporation–falling curve
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-0668.2007.00469.x
出典:Wiley Online Library 2007/5/29
峰宗太郎
ということは、5μm よりは大きいけれども100μm より小さいようなものは、空気中を漂うこともあるということですよね?
そうであれば、従来から考えられている飛沫感染のイメージよりは、もうちょっと長い距離を漂って感染すると言えそうですよね?
安川康介
そうなんですよ。
峰宗太郎
そういうところを何とか名付けようとして開発された言葉が「エアロゾル吸入感染」(aerosol inhalation transmission)と理解しているんですが、その理解でよろしいでしょうか?
安川康介
そうですね。
比較的最近、論文でエアロゾル(吸入)感染が出てきました。
空気感染と飛沫感染の2つは、粒子のサイズを 5μm で分けて、かつ距離も大体 2m に限るという定義は、限界がある感染のモデルです。
その限界を克服するために、エアロゾル吸入感染という新しい概念を作り出そうと提起されたわけですね。
※参考:
Aerosol transmission of infectious disease
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25816216/
出典:pubmed
峰宗太郎
はい。
では、その新しい定義ってしっかりとコンセンサスを得られてるんですか?
安川康介
おそらくマイクを持っていろんな医師に「エアロゾル感染ってなんですか?」って聞いていくと、かなり違う答えが返ってくると思います。
峰先生も後から触れようと考えていると思うんですが、WHO(世界保健機関)の最近の発表を見ると「droplet nuclei (飛沫核)= エアロゾル」と書いている文章もあります。
※参考:
Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
出典:WHO 2020/7/9
確かにエアロゾルは空気(気体)の中を漂う固体とか液体のことを、そのサイズにかかわらず指す言葉ですが、WHO が飛沫核とエアロゾルを同義に扱う文章が出たために、最近では「空気感染 = エアロゾル感染」みたいに捉えている人もいます。
峰宗太郎
はい、ちょっと議論が難しくなってきました。
簡単に言うと 5μm よりも小さい粒子を飛沫核と言い、これは空気感染を起こすものです。
5μm より大きいものによる感染は、飛沫感染と純粋に呼ばれているわけです。
昔は飛沫感染は 2m 以内に落ちるものだと考えられていましたが、最近は 5〜100μm の間のものは空間を漂うこともあるから、この間にあるものをエアロゾルと呼んでみようよと提唱した人がいたのですが、WHO が何故か 5μm 未満をエアロゾルと言ってしまったために大混乱になっているということでよろしいですか?
安川康介
そうですね。
これで混乱が生じて、メディアのニュースや論文によってエアロゾルの定義が違ってきています。
メディアだけではなく、科学者とか医師の中でもかなり混乱が生じていると思います。
【空気感染対策と新型コロナウイルス対策の相違点】
峰宗太郎
はい、ではここで矛先を変えてみたいと思います。
古典的に空気感染すると言われる3つの病原体について、「空気感染対策」は実務上何か異なるものなんですか?
安川康介
そうですね。
水痘、麻疹、結核ですね。
僕がよく見るのは結核です。
途上国に行ったりすると結核はすごくありふれている病気なんです。
実際に病院で診る場合、医療者はN95マスクをつけて患者さんは陰圧個室に入れるという感染症対策が取られることが一般的です。
1)かなり長い距離をふわふわ飛んでいって離れたところで感染を起こしてしまう可能性があることが分かっていますので、患者さんがいる部屋は陰圧に(空気が外に漏れないような工夫を)することが大切になります。
2)マスクは普通のサージカルマスクではなく、かなり網目の細かい N95マスクを使うことになります。(N95マスクは大体0.3μm 位の小さな粒子を95%ぐらい補足するマスクです。N は Not resistant to oil で油性の粒子にはあまり効果がないという意味です)
峰宗太郎
今回の新型コロナウイルスがもし空気感染するとしたら、そういった対策が取られると思うんです。
CDC(アメリカ疾病予防管理センター)は医師に N95マスクをつけるようにと推奨してはいますが、実際に陰圧管理とか(安川先生はおっしゃっていませんでしたが)HEPAフィルターを通した独立空調室で管理するといった対策、つまり空気感染対策をとることが推奨になってるんでしょうか?
※参考:
結核院内(施設内)感染対策の手引き 平成26年版
https://jata.or.jp/dl/pdf/law/2014/3_2.pdf
出典:厚生労働省インフルエンザ等新興再興感染症研究事業 「結核の革新的な診断・治療及び対策の強化に関する研究」2014/3
※参考:
Transmission-Based Precautions
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html
出典:CDC
安川康介
そうですね。
アメリカではかなり感染者の数が増えて、僕の病院でも200人とかいる状況になりました。
全ての患者を陰圧室で管理するということがどこの病院でも難しい状況だったので、必ずしもそうではありませんでした。(補足:CDCはエアロゾル発生手技を行う患者に優先的に空気感染隔離室を使うことを推奨しています)
※参考:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
出典:CDC 2021/2/23
峰宗太郎
実際には、空気感染対策を完全に取れなかった現場も普通にあるということですね?
それで院内感染が結構広がるものですか?
安川康介
明らかに空気感染によって感染が広がっているということはないですね。
峰宗太郎
それは、新型コロナウイルスは独立空調じゃなくても感染がひろがらないと言えそうだということですね?
安川康介
そうですね。
峰宗太郎
空気感染と飛沫感染の定義の違いも、感染対策という意味で確認したいんです。
3密を避ける、と日本は早くから言っていますよね。
これは飛沫感染と空気感染のどちらを避ける意味合いがあると考えられますか?
もしくは、両方避けられるものなんでしょうか?
安川康介
これは、両方になると思います。
特に換気、つまり密閉空間にいないことは、日本が世界的に見ても最初に言い出した新型コロナウイルスの感染対策です。
日本は昨年、かなり早い段階でクラスター対策をしていて、密閉空間で感染が広がっていることをいち早く見つけて、いわゆる小さな滞留する粒子によって感染することがある、と密閉を避けて換気するという対策を打ち出しました。
僕はこれはすごく面白いなぁって思っていました。
当時アメリカでは、全くそういうことが言われていなかったんです。
とりあえず距離を6フィート(1.8m)とって、マスクをしよう、対策はただそれだけだったんです。
峰宗太郎
思いましたよね。
アメリカは、基本的に「マスクをつけなさい」と言い出したのも遅かったです。
「手を洗え、距離を取れ」という対策ばかりで、「マスクをつけなさい」が出始めたのが去年でした。
今年になって初めて「人混みを避けなさい」が申し訳程度に出てきて、ようやく最近、換気が出てきましたよね。
日本は結構進んだ対策をしていたのか!って今でも思うんです。
そう考えたときに、やはりひろがり具合とか、現在のコロナの防護の CDC の推奨があったわけですが、CDC が新たな Scientific Brief を出しました。
この Scientific Brief、安川先生ももちろんお読みになりましたよね?
※参考:
Scientific Brief: SARS-CoV-2 Transmission
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html
出典:CDC 2021/5/7
※参考:
新型コロナの感染経路 いま分かっていること、いまできること
https://news.yahoo.co.jp/byline/sakamotofumie/20210508-00236853/
出典:Yahoo!ニュース 2021/5/8
安川康介
そうですね、はい。
峰宗太郎
あれには Airborne infection(空気感染)という用語は書かれていましたか?
安川康介
これはすごく面白くて、空気感染(Airborne transmission)に対して新しい推奨が出た、と言っている人がいるんですが、この記事の本文自体には Airborne という言葉は一言も出てきていないです。
引用文献にはあるんですが、本文には出てきていないです。
今日ここで議論してきたことに注意して作文された内容だと思います。
峰宗太郎
はい。すごく丁寧に書かれていますよね。
皆さんにも実は読んでいただきたくてツイートにもぶら下げました。
言葉選びを慎重にされていて、「非常に細かい粒子は空間を漂ってそれを吸い込むと感染する」とは言っているんですが、この粒子が 5μm 未満であるかどうかという点は、確定していないということで、触れていないですよね。
そして、先ほど安川先生にもご説明いただいたように、いわゆるエアロゾル吸入感染(日本でいうマイクロ飛沫感染)、空間を滞留する粒子によって感染することがあるから注意なさいな、と書かれています。
CDC が日本の3密を追いかけた形になっているんですが、安川先生はどう捉えていますか?
安川康介
そうですね、そういう感じだと思います。
峰宗太郎
では安川先生、もう一点だけ科学的なことをお伺いして、締めに入っていきます。
新型コロナウイルスは 5μm 未満の粒子になったときにも RNA が検出されるという論文を結構読んだんですが、培養可能とか伝染を確実にしているという文献報告を安川先生ご覧になりましたか?
安川康介
まだプレプリント(査読前の論文)段階だと思うんですが、最近 WHO を中心としたグループが本当にそういう粒子の中に新型コロナウイルスが入るのかを発表しています。
論文の中にはできたという報告もあるんですが、ほとんどないですね。
実験室でのデータでは、5μm 以下の小さな粒子に感染性を保ったままウイルスがいるというデータは2つくらいあると思います。
※参考:
https://f1000research.com/articles/10-232
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2004973
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/9/20-1806_article#r6
峰宗太郎
それは結核に関してだとどうですか?
結構論文があるんですよね?
安川康介
そうですね。
結核はかなり調べられていて、すごい面白い……面白いと言ったら変なんですが、歴史的にも1950年くらいから空気感染が調べられてきた病気です。
※参考:
Infectiousness of air from a tuberculosis ward. Ultraviolet irradiation of infected air: comparative infectiousness of different patients
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14492300/
出典:pubmed
峰宗太郎
では最後に聞いておきたいんですが、安川先生、この新型コロナウイルスって飛沫感染するんですよね?
安川康介
古典的な 5μm のサイズだけで切った場合は、飛沫感染であると言えます。
ただ、飛沫感染を 2m 以下のもので区切った場合は違うのです。
新型コロナウイルスは空気感染だと言われている現象がいくつか起こっています。
・2時間半合唱の練習をした時にそこにいた方の8割くらいが感染してしまった事例が去年ワシントン州であり、残念ながら2人が亡くなってしまった
・ジムなどの密室の空間で感染がちょっと離れた距離で起こった
・中国のレストランで 4.6m 離れた人に感染が起きたと言う事例(これはまた有名な論文です)
このような、いわゆる「これは空気感染だ」と言っている事例も、僕たち感染症をやってる医師から見ると、大体比較的近距離なんですね。
空気感染と言うと、例えば、
・水痘で病院内感染が起きたことがあり、30m 離れている人にも感染した
・結核とか麻疹でもかなり遠いところの感染が起きている
・麻疹ではある小児科の外来にある患者さんがいてその患者さんが去って1時間後に診察に来た子に麻疹が感染してしまった
というようなことが報告されています。
新型コロナウイルスに関しては、そういういわゆる昔から知られている空気感染のような形で感染した事例はあまり見ていないですね。
※参考:
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132321001955
https://pediatrics.aappublications.org/content/75/4/676.long
https://pediatrics.aappublications.org/content/70/4/550
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM198002213020807
峰宗太郎
ありがとうございます。
私も麻疹には痛い思い出がありまして。
麻疹を発症したお子さんが電車に乗ってしまって(これは小児科医の指導不足だったんですが)、車両1両全員保健所の追跡を受けて大変なことになった事例もありました。
空気感染って、とても大変ですよね。
安川康介
いや、そうですよね。
峰宗太郎
ここまで延々と話してきましたが、これらを受けてどう考えたらいいのかをまとめたいと思います。
空間中をふわふわ漂っている粒子を吸うことによる感染、これは新型コロナウイルスであっても良いようですね。
5m とか 10m 未満とかですね。
安川康介
そうですね。これは実際に報告されています。
峰宗太郎
これ、古典的には飛沫感染と言われていたものの部類に入れざるを得ないんですが、言葉も不適切だし今後はエアロゾル(吸引)感染とかマイクロ飛沫感染とか何か適切な言葉で統一されていくと非常にいいですね。
安川康介
そうですね。
これは実際にそう提唱する方もいて、峰先生触れる予定でしたかね?
飛沫感染と空気感染という区別に限界が来ているので、spray transmission とか inhalation transmission とかそういう新しい言葉を使おうと言っている研究者もいます。
峰宗太郎
そうですよね。
そういう議論があるとはいえ、結局対策としては今日本で新型コロナウイルス対策として言われている3密の回避、距離を取る、マスクをする、接触感染もあるので手を洗うなどの対策、今まで言われていたことをしっかり徹底していくことで、感染はある程度防げるものですよね。
安川康介
そう思います。
峰宗太郎
ということは、新型コロナウイルス対策としては、今まで言ってきたようないわゆる「空気感染のための厳重な対策」までは普通は必要ないと考えていても問題ないですよね?
安川康介
そうですね。
そういった厳格な空気感染対策をしなさいとは、CDC なども言ってないです。
峰宗太郎
そうですね。
AIIR の話などを今スピーカーに入ってくださった Hanako先生にも教えていただいたんですが、伝統的に空気感染と知られている他の3つの病原体と扱いが違うということですよね。
安川康介
はい、そうですね。
峰宗太郎
空気感染は、空間を滞留している定義されたサイズ未満の粒子を吸い込むことによって起こる現象に名前をつけた、技術用語(テクニカルターム)です。
新型コロナウイルスに対して空気感染という用語を使いたい方は結構多いと思うんですが、この用語を、空間を漂う粒子一般からの感染に、安易に無批判に流用してしまうのは間違いだと言わざるを得ないですよね。
今まで使ってきた定義された「空気感染」という言葉は主に水痘、麻疹、結核という3つの特殊な病原体に使う用語です。
一方で、新型コロナウイルスをのせた飛沫も空間内にある程度滞留するところもある、ということで、概念を整理してエアロゾル(吸引)感染などのところでうまく整理できたら、齟齬がなくなるかもしれないですよね。
安川康介
今回新型コロナウイルス流行が始まって色々と混乱が生じていますから、変えなければいけないと思います。
【エンディング】
峰宗太郎
安川先生は米国感染症内科医で、プロフェッショナルで感染管理についても大変詳しいので、今回聞いてまいりました。
空気感染という言葉は、しっかりと定義があって、それはいろんな慣習的なものやいろんな成果が積み上げられてできた技術用語なんですね。
皆さんがイメージする「ふわふわ漂ったら空気感染」ということではないです。
そういうことを考慮せずに、空気感染という用語を使いたいだけで「空気感染!」「空気感染!」と騒がれても、それは困っちゃうよということです。
これが今日一番伝えたかったことです。
やはりアラーミストという方は弊害があります。
丁寧に言葉を提示したり概念を整理したりしないで、現象を正しく捉えられない状況のまま、とにかく危険を煽りたい、不安を呼び起こし、自分たちが感情で捉えてきたようなことをとにかく広めたいと、怖いことをどんどん言う人はいます。
例外的ではありますが、時にそれが安全マージンを広く取ることに繋がって、良い方向に向かうこともあります。
しかし、空気感染はよく知っている方にとっては非常に強い感染伝播力を指す言葉で、空気感染対策という対策の違いにもつながっていくものです。
日本で既に推奨されている新型コロナウイルス予防策である、3密を避ける、距離を取る、マスクをつける、換気をするといったことを実施すれば、対策はできます。
大きく「新型コロナウイルスは空気感染をする病原体だ!」と言って、3つの伝統的な病原体(水痘、麻疹、結核)と同じように扱うのではなく、しっかり対策を続けることで安全が取れるということです。安全マージンを考えても、空気感染という単語を使う必要ないだろうと考えている次第です。
まぁ煽ったり感情的になったり、なんとなく党派性?を帯びてきて空気感染を騒いでる人たちが、私に対して「変異ウイルスは病原性が上がってきてるから対策も変わるんだぞ!」と突っ込んできているんですが、「具体的に何が変わるんだ、どういう対策をしたらいいんだ」と聞くと、「対策をもうちょっと頑張る」と。
言ってることが分からないことが多く、戸惑っていたところでした。
今日は安川先生と概念から丁寧に話をしてみました。
あまりまとまりがないですが、他の皆さんから何かございますでしょうか?
木下喬弘
まぁこれは要するに、5μm より大きいけど、飛沫が直接かかる2mぐらいの距離より、もう少し遠い距離まで届く滞留粒子のことをエアロゾル(吸引)感染って呼んだら済む話ですよね。
峰宗太郎
OK Google 👶すぐにまとまった!
たったの10秒でまとまったよ!!👶
木下喬弘
(笑)
あの……Google には質問して、お願いだから😂
峰宗太郎
そうなんですね。
僕、さっきまで AbemaNews を見ていたんですが、もう木下先生の理解力の素晴らしさは誰もが知っているところです。
とにかく今おっしゃっていただいた、5μm より小さいというのは、かなり特殊なんですよね。
5μm より大きいけれども100μm よりちっちゃい大きさで空間を漂うものがあって、厄介だよね、そこは多くの人が気付いているので、3密対策をちゃんとしようねという話に落ち着いてきます。
ただ、学術的にはしっかりした用語を使う必要がありますね、ということを安川先生と話してきた次第です。
池田先生、いかがですか?
池田早希
特にないでーす。
木下喬弘
特にないって(笑)
めちゃくちゃ冷たいですよ(笑)
池田早希
えーと、これ木下先生の口癖を真似しただけです。
木下喬弘
(笑)伝わったかな?これ…
峰宗太郎
結論、木下先生が冷たかったということになりました👶
じゃあ、そういうことで今日は締めたいと思います。
では今日は安川先生、長い間半分以上、全てを教えていただいてありがとうございました。
安川康介
こんなにたくさん質問が来るとは思いませんでした🥦
峰宗太郎
いやいやいや。
次回安川先生のモデレーター回では僕が答えますから、よろしくお願いします。
今回1,447人!ということで、多くの皆さんに聞いていただきました。
それではアメリカの皆さん、良い夜をお過ごしください。
日本の皆様、よい1日をお過ごしください。
ありがとうございました。
安川康介
ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
