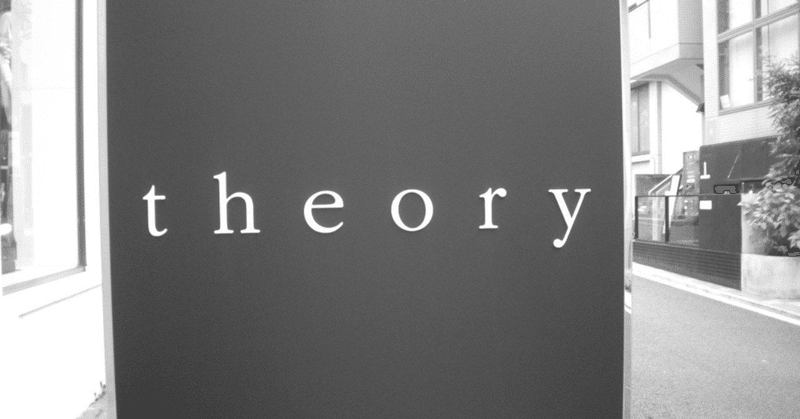
「理論」ってなんだ? -理論の定義と4つの機能-
「大学院に通って、一番学びになったことはなんですか?」
先日、ある人事の方に質問をいただきました。
2021年、立教大学大学院 経営学専攻リーダーシップ開発コース(LDC)に入学しました。そして、卒業をしてから1年が経ちます。Before LDCとAfter LDCではまったく見える景色が違う。それくらいこの大学院から得たものは大きいものでした。
なので、冒頭の質問を頂いた時に、”一番は学びになった”と言われると、果なんだろう?と迷ってしまいました。ただ、それらのものを総括して言葉にすると「理論を武器にする力」を手に入れたことは、大きなものの一つかもしれません。
一方、「理論」といってもそもそも何だかよくわからない、、、ということもある可と思いましたので、本日は「理論とはそもそも何なのか?」「理論の機能とはなにか?」について、先人の著書から引用させていただきつつ、ご紹介したいと思います。
「理論」とは何か
「◯◯理論」と銘打たれたものは、なんだか説得力がありますね。
ただ、”理論”と言っていても、その理論は誰か特定の人が言っている「ん?それ本当に理論??」という眉唾なものもあれば、多くの人に支持される骨太の理論のようなものもあります。
では、口に出して「理論です」といえば理論になるのか?
この話については、後述しますが多くの人に認められる必要があります。
一方、まずはそもそもこの「理論」なるものを考えてみたいと思います。この理論の説明について、國分康孝先生が著書『カウンセリング理論』において、大変わかりやすい説明をされていました。
以下、少し長文になりますが引用いたします。
まず理論とは何か、理論の機能は何か、ということから話をすすめたい。
カウンセリングのカの字も知らない素人でもわかることが一つある。それは人間世界のさまざまな現象(Phenomena)である。自殺、家庭内暴力、離婚、暴走族、麻薬常習などがそうである。(中略)
研究者はアンケートや面接や心理テストを用いて、たとえば離婚した人とそうでない人とは生育歴や性格に相違があるかどうかを調査する。その結果明らかになったことを事実(fact)という。研究者の仕事の第一は、現象の中からいくつもの事実を発見することである。
事実が発見されたあと、どうするか。研究者は、いくつかの事実に共通する原理を読み取ろうとする。たとえば、十代の結婚は離婚率が高いという事実がある場合、多分これは「役割葛藤」(例:母に対する息子という役割と、妻に対する夫としての役割を同時にこなせなくて、板挟みになる)があるからではないか、と読み取るのがその例である。事実の中から、一つの概念(この例では役割葛藤)を生み出すのである。
さて、概念がいくつか抽出された場合、それらの概念を相互に連携して一つのゲシュタルトにまとめあげたもの、これが理論である。すなわち理論(theory)とは概念の束である。
要約するとこうなる。「現象→事実→概念→理論」
なるほど、、、。
理論に至るまでには、現象→事実→概念→理論とまとまりが大きくなっていくようですね。
たとえば、コーチングやカウンセリングに当てはめて考えてみます。
(以下、私なりの解釈なのであっているかはわかりません。悪しからず)
たとえば、「人の話を聞いている」という”現象”があります。
相手の話に対して頷いたり、相槌を打ったり、相手の話しやすいペースにリズムをあわせるなどの”事実”がある。そして、それらを合わせると「傾聴」という”概念”になる。
さらには「質問」という”概念”もあります。これはオープンクエッション、クローズドクエッションなどの聞き方(事実)の集まりである。そして、その他にも「観察」をしたり「挑戦的な行動のリクエスト」をしたり、「矛盾を指摘する」などいくつもの関わり方があるようだ。
そうやってコーチングの技法がより大きな概念としてできあがり、それらの概念を更に学術的なものと紐づけていくことで「コーチングの理論」と言えるようになる、、、そんなことなのかなと思われます。
(コーチングの理論は、技法・スキルに近い気もしますが、、、)
「理論」の機能とは
では、「理論」はどのように役に立つのでしょうか?
こちらも國分先生の『カウンセリング理論』から、理論の機能としては、以下述べられていました。
<理論の4つの機能とは>
(1)結果の予測ができる
理論があれば、経験がなくとも、こうすればどうなるかという予測が可能である。予測できるから、ある行動を起こすこともできる。カウンセリング理論は、カウンセラーの一挙手一投足の根拠となる。
(たとえば、欲求不満攻撃説を知っているから、経験がなくとも、人に限度以上の我慢を強いてはいけないとわかる)
(2)ある事実を説明・解釈する手がかりになる
ある事実を説明、解釈(読み取り)ができるから、安心して行動がとれる。
人生最初の新事実にぶつかった場合でも、理論を知っていれば説明がつくので不安に陥らないですむ。(たとえば、登校拒否児に出会った場合、性格形成論をしっているから、これは親定着ではないか、反抗の現れではないかと色々の解釈が成り立つ)
(3)ある現象を整理することができる
たとえば、学生が教室の後ろ半分に席を取る、前方はがら空きであるという”現象”が見えたとする。この現象に対し「空間的距離は心理的距離を意味する」というボディ・ランゲージの理論を適用すれば、前席の学生は講師に親近感があると読み取れる。
(4)仮説を生み出す母体になる
理論をしっておけば、理論上こうなるはずだという一つの仮説を立てることができる。
とのこと。
こちらについては、石川淳先生の『リーダーシップの理論』の著書にも、更に絞った形で理論が実務に役立つ点として「事象を説明できる」「結果を予測できる」「結果をコントロールできる」の3点が紹介されていました。

ここでも、「リーダーシップの”理論”も知っておくと実務に役立つ」と述べられています。特にリーダーシップ理論は、文化や時代、多くの研究者の検証という風雪にさらされて来たため、説明力、予測力、コントロール力は高い理論とされています。
その中で、たとえば「フィードラー理論」なるものがあります。
これはリーダーとフォロワーの人間関係がとても良好な場合、あるいは険悪な場合はタスク志向のリーダーシップがうまく機能し、両者の関係が良好でも険悪でもない中間くらいのときは、人間関係志向のリーダーシップがうまく機能することが指摘される理論です。
もしこの理論を知っておけば、自分があるチームの状況において、どのようなリーダーシップスタイルを取ると機能しやすいのか「結果をコントロールする」ための補助線になり得るわけです。
理論として認められる条件
さて、冒頭の話に少し戻りますが、”口に出して「理論です」といえば理論になるのか?”問題について考えてみたいと思います。
石川先生の著書によると、理論として認められるための条件として、”提示された概念間の因果関係を多くの人に適切であると認識される必要がある”と述べています。つまり、そう思っているのはおまえだけだよ、と思われていたら理論として認識はされない、となるようです。
そして、”多くの人”が何人となるのかも、その学術分野によって異なるようです。たとえば、自然科学系であればほぼ人類全てからの同意が求められるかもしれない。あるいは社会科学であれば特定の国・地域に限定されてもよいかもしれない。ただし、”ある程度の時間・空有間を超える必要があること”、”再現性をもって因果関係を証明できること”は、理論として認められる一つの条件になるようです。
まとめ
こうして言葉で整理をすることで、改めて「現象」「事実」「概念」「理論」という繋がりを理解することができたような気がします。
また、「理論」といっても、その信頼度も様々なであることも理解しました。「リーダーシップ理論」のように多くの研究者に検証されてきた骨太の理論もあれば、一部の人が言っているだけ、という「ほげほげ理論」というのもあることも理解しました。
そして、人類が発見してきた先人の知恵の結晶が「理論」であり、組織行動にまつわる様々な「理論」という武器があることを理解し、それを(まだまだ道半ばではあるものの)取得してきた旅路、そしてそれを実務に活かすという選択肢を大学院で手に入れた大きなことだったな、、、そんなことを感じています。
理論とは奥深い。そして実に面白いのです。
最後までお読み頂き、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
