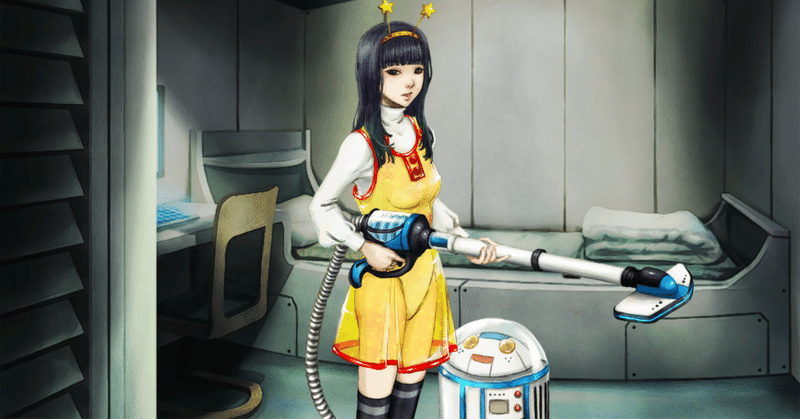
メタいゲームっていいよね
みなさんは「メタい」という言葉をご存じだろうか。おもにフィクション作品において登場人物が「自分たちが作品の登場人物である」ということを認識した発言や行動をとる時、その特殊な状況を指して「メタい」という。難しく考えると自己言及的とか高次の認識とかややこしい話になりそうだが、要は「画面のこちら側に我々がいる」ことを認識した要素があればメタいのである。
そんな「メタい」要素は使い方によってはゲームをさらに面白くしてくれる。メタけりゃいいってもんじゃないが、効果的なメタ要素はゲームの中のキャラクターが画面を越えてこちら側に手を伸ばしてくるような、変化球じみた体験をさせてくれる。私はそのメタ要素がとても好きなので、代表的なものをいくつか紹介してみようと思う。
(UNDERTALEだけSwitch版でやったのでスクショないです)
(ネタバレが大量にあるので注意)
OFF

OFFは後述のUndertaleや各種ホラー系RPGに影響を与えたといわれる名作で、主要キャラクターのほとんどがナチュラルにプレイヤーを認識してくる。主人公のバッターははじめにこちらを向いて「じゃあ、WASDキーで俺を動かしてくれ。」というし、ショップNPCのザッカリーは「マジになんなよ、たかがゲームなんだから」と茶化してくる。本編最後までこの調子である。
ゲーム自体は時々パズル要素のあるRPGだが、そのパズル要素にも所々メタ要素が含まれている。例えば攻略に必要なパスワードが見つからないのでショップNPCに聞くと「そうだな、READ MEはもう読んだのか?」と返される。あわててファイルを開いて読んでみると、ゲームをダウンロードした時に一緒についてくる文書「READ ME(ゲームの説明書みたいなもの)」の中にパスワードがはっきりと書かれているのである。ゲーム外にヒントが隠されているのはPCゲーならではの体験だといえるだろう。
UNDERTALE
Undertaleは「メタいゲーム」の代表格といっても過言ではない名作だ。地底の「モンスターの国」に迷い込んでしまった子供が地上へ戻るのを目指して冒険する中で、個性的なモンスターたちとふれあいつつ王国の秘密に触れる…というストーリーで、敵を倒さずとも進めるシステムと個性的なキャラクター、各シーンのBGMなど様々な要素が人気の心温まるRPGだ。
このゲームではいくつかのキャラクターが第四の壁を無視し、プレイヤーを認識している。そのうちの一人目であるおしゃべりな花、フラウィーはその能力をゲーム序盤からナチュラルに使用して殺しにかかってくるし、二週目以降では別のセーブデータでのプレイ内容を指摘してくる。Undertaleは「誰も死ななくていいやさしいRPG」をスローガンに掲げているのだが、一週目で何人か殺してクリアしてしまい二週目は不殺を貫いてみようかな…と意気込んだプレイヤーはここで一度「たかがゲームだしやり直しがきくって思ってないか?やり直してもお前は殺人者だよ」と煽られてしまうのだ。
もう一人、このゲームの超人気キャラクターであるスケルトンのサンズは、フラウィーのような超能力ではなく独自の物理学的な研究によって世界のループ(=セーブ&ロード)に気が付いており、モンスターの殺害数によっては主人公…というよりプレイヤーの前に立ちはだかる。そしてこれまでの敵とは格が違う圧倒的な攻撃に加えて戦闘コマンド選択画面への攻撃、死亡回数をカウントして煽る、挙句のはてには自分のターンを限界まで引き延ばすことによる敗北回避といった、いちNPCの能力を超えた反則に近い手段を用いて殺しにかかってくる。ほかのキャラクターの敵対理由が「主人公の確保」や「主人公の殺害」であるのに対し、サンズは明確に「プレイヤーの心を折ること」を目的として行動するため、勝利しても敗北しても他のキャラクターとは一線を画した印象を残してくれるのだ。
Oneshot

Oneshotは「チャンスは一度きり」をキャッチコピーに掲げる、太陽が消えた世界に再び光を取り戻すための冒険だ。プレイヤーは別世界からの救世主ニコを操作して、街の住人やロボットたち、それに画面のこちら側へ話しかけてくる謎のウィンドウと交流しながら世界の中心を目指すことになる。

Oneshotの大きな特長はPCの機能を最大限に利用した謎解きにある。パスワードが見つからないな…と思っていると、突然ウィンドウがポップアップし「ドキュメントを探してみるといい。」と言われたり、「パズルのヒントを君が一番見やすい箇所に置いておいた。」というメッセージとともに壁紙が更新されたりする。このヒントも秀逸で、直接的な言い方ではないがPCの各所を探せばそれとわかるような、楽しい手掛かり探しになっている。

黒塗り部分はPC内に登録されているプレイヤーの本名 ビビる
Oneshotのメタ要素は単なるびっくり要素・おしゃれ演出にとどまらず、ストーリーにも大きく絡んでくる。一週目の終盤、崩壊を続ける世界を修復するには太陽を戻すだけでは不十分で、世界の外部からの干渉が必要だということがわかる。普通のゲームならここで詰みだが、別世界からの救世主と神たる視点を持つプレイヤーのタッグならそんなルールには縛られない。
プレイヤーはゲームファイルをいじくったり、別のウィンドウを出して重ねたりあらゆる手を尽くして今度こそ世界を救おうと奮闘する。「チャンスは一度きり」のルールをゲームの外から覆すのだ。
Lobotomy Corporation

Lobotomy Corporation(以降ロボトミ)は怪しいエネルギー会社の管理人となり、多種多様な怪物たちを管理するゲームだ。毎日増えていくエネルギーノルマを達成し、職員を育成し装備をかき集め、必要とあらば最初の日に戻るのを繰り返しながら50日間を勤め上げるのだ。

このゲームは特に設定、それも世界観設定だけでなく各種UIやゲームシステムそのものに付随する意味までもが良く練られており、ゲーム自体の理不尽な難易度も相まって遊んでいるとどんどん主人公へ感情移入できるようになている。怪物がどこか愛嬌のあるデザインなのは管理人の恐怖を軽減するためのフィルターが機能しているからだし、「一日をやり直す」機能は提携企業の時空操作技術によって実装されている。
そして、もちろんその設定はストーリーの説得力にも大きく影響している。このゲームはたいていの場合クリアするまで何度も時間を巻き戻し、場合によっては最初からやり直させられる苦行仕様なのだが、このゲームシステムは「主人公が抱える罪を乗り越えるために反復し続ける」というストーリーとリンクしている。そして練り込まれた設定を味わいストーリーとリンクした苦痛を乗り越えた最後には、プレイヤーこそが本当の意味で主人公であったのだと信じられるのだ。
グノーシア

グノーシアは一人で遊べる人狼ゲームだ。自分と、そのほか14名の個性的なキャラクターとともに、誰が人類に害をなそうとしている「グノーシア」なのかを話し合って考え、一人ずつコールドスリープさせていく。対人での人狼における言葉巧みな騙しあいは起きないが、それぞれがキャラクターの性格に忠実な行動をとるため、そこから主張の信ぴょう性や陣営内での庇いあいなどを見抜いて考えることができる。
主人公と、その信頼できる仲間であるセツは世界のループに閉じ込められており、条件を変えて様々な並行世界を探索することでループ脱出の手掛かりを探す…というのが大まかなストーリーである。

目立ちすぎてコールドスリープさせられたり恨みを買って襲われたりしやすい
グノーシアのメタ要素はそこまで多くないが、その演出には特筆すべきものがある。このゲームはグノーシアの人数や自分の配役を最初に設定して遊べるのだが、ストーリーを進めていくと「グノーシアが発生していない世界はどんな状況だったか」を確かめる必要が出てくる。もちろん通常グノーシアは0人にはならない(グノーシアがいないとゲームが成立しない)ため設定項目をそんな極端な値にしようとは考えないものなのだが、なんとその裏を突いて「グノーシアをゼロ人に設定してゲームを始める」ことがストーリー進行の鍵となっているのだ。
もう一つ、このゲームでは「ループ」がストーリーの重要なキーワードとなっている。通常のプレイの範疇では二人分のループを止める方法が見つからず、主人公のみがループから解放されセツは並行世界のループにとらわれ続けてしまうかなしいエンディングしか迎えることができない。ではどうすれば二人分のループを破壊できるのか?
答えはセーブスロットにある。新しくゲームを始めるとセツとの会話の選択肢に「二人で遊んだことを覚えているか」という内容の項目が追加され、それを選択することで真のエンディングへとストーリーが分岐する仕組みになっている。「既存の世界に解決策がないのなら、新しく世界を作ってしまえばいい」というわけである。

物語の最後に、セツは世界の理を破壊してまで自分を助けに来てくれたプレイヤーに感謝を述べる。ここでいう「君」とはプレイヤーが操作していたキャラクターではなく、我々、新しい世界を創造してまで戻ってきてくれた画面のこちらの私たちなのだ。並行世界をループするストーリーと、私たちが何気なく使っているセーブファイルを秀逸に活用した素晴らしい仕掛けだと思う。
最後に
ここで紹介した5つのゲームの他にも、メタ要素のあるゲームはたくさん存在する。ゲームのナレーターと喧嘩できるThe Stanley Parableとか、あんまり詳しくないけど超有名なドキドキ文芸部とか。メタ要素の定義を「こちらを認識する」から「ゲームシステムを活用する」にまで広げると、声が武器の敵はゲーム内ボイス音量を調節して無力化できるパノラマサイトとか、ニューゲームがニューゲームじゃない7 Days to End with Youとか、ステージを選択する前のワールドマップ自体もパズルになっているBaba is Youとか、キリがないくらいに面白いゲームがたくさんある。
メタ要素はただの「遊ぶ人」だったプレイヤーをゲーム内の登場人物へと引っ張り込んだり、ストーリーをどこか他人事のようにとらえていた我々の喉元にいきなりナイフを突きつけたり、あるいはゲームそのものに対する疑いを抱かせてくれたりと、普通のゲームとは切り口の違うやり方で特別な体験をさせてくれる。ときには「ゲーム」というジャンル自体を一層好きになれるような驚きを提供してくれる。私はメタいゲームが大好きだ。
(記事のヘッダー?画像は使いどころのなかった夕里子様です)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

