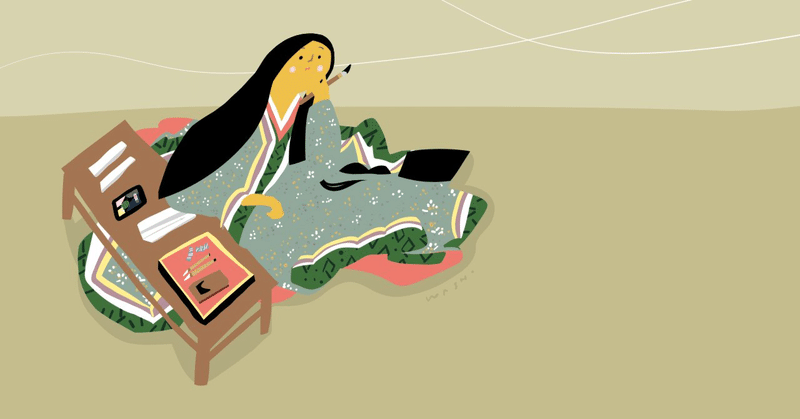
1000年経っても変わらない「人の思い」
先日、千世さんがこんな記事を書かれていた。
内容に関してもいろいろと考えさせられたが、この記事の中で「私がずっと思っていたことと同じだ」と思う一文があった。
時代は変わっても、根底にある「人の思い」だけは変わらない。
千世さんはその想いから、「歴史」の面白さや深みに気づき、どんどんのめり込んでいかれる。
そして、今は歴史をいろいろな角度・視点から深掘りし、文献にあたることはもちろん、時には自分の足で歩いてその場所へ行き、考察された記事を書かれている。
うわべしか知らなかった歴史を知ることができるので、とても面白い。特に大河ドラマの解説は、毎回楽しみで仕方がない。なんとなく見てわかった気分になっていたことが明確になったり、「え~?実際はそうじゃなかったんだ~」と驚かされたり、とにかく大河ドラマを2倍楽しめるのだ。
私も10代の頃から「1000年も前から人間って考えていることは変わらないんだ」と気づき、そこにあるドラマをもっと知りたいと思っていたところまでは同じなのだが、私の場合は「歴史」ではなく「文学」へと興味が向いた。
大学はいくつか受けたが、すべて文学部。そして、受かった大学の文学部で国語国文学科を選び(2回生から選んで学科に分かれるようになっていた)その中でも国語国文学を専攻した。
勉強したかったのは、平安時代の貴族文学だ。「○○日記」や「和歌」を深掘りしたかった。あの世界がたまらなく好きだったからだ。
菅原孝標女が書いた「更級日記」で、彼女が自分がどんなに「源氏物語」を好きかを書いている場面がある。
「この源氏の物語、一の巻よりしてみな見せ給へ」と心のうちに祈る。すると、祈りは叶い、おばさんから源氏物語50巻をもらうことになる。
はしるはしる、わづかに見つつ、心も得ず心もとなく思ふ源氏を、一の巻よりして、人もまじらず、几帳の内に臥してひき出でつつ見る心地、后の位も何にかはせむ。
この一文を読んだとき、なんてかわいらしい人なんだ!と思った。もらった源氏物語を手にしてワクワクが止まらず、家に帰ると1巻から取り出して、几帳の内でくつろぎながら、誰にも邪魔されずに順番に読んでいく。その時の気持ちといったら「后の位も何にかはせむ」、つまり「后の位にも代えられない、何にも代えられない喜びだ」と言っているのである。
その後、あまりに毎日「源氏物語」に没頭しすぎた罪悪感で、夢に僧が出てきて「法華経の5巻をちゃんと習いなさい」と言うのでちょっとびびるのだけど、やっぱり頭の中は「源氏物語」でいっぱいで、習おうとも思わない。それどころかどんどん「源氏物語」の登場人物に想いを寄せていくのである。
ほとんどの人がこの気持ちに共感できると思う。「源氏物語」ではなくて、本でも漫画でもYouTubeでもいいけれど、誰にも邪魔されずに好きなものに没頭する時の気持ち。隣近所にいそうな女の子の姿だ。
こういう時代が変わっても変わらない人間の想いや行動に惹かれ、もっと追求したいと思ったのだ。
大学に入り、ようやく好きなことを思い切り勉強できるんだと張り切っていたが、2回生の4月、国語国文学の講義を自分で選ぶ段階になって、恐ろしいことに気づいた。
ない!!
どこにも平安時代の貴族文学を学べる講義がない!!
愕然とした。まさかと思った。だって、国文学の中で平安時代の貴族文学って花形じゃないか。これが1つもないなんて信じられなかった。
私の大学はとても規模が小さく、国語国文学科は私の学年は確か26人だった。それでも多いほうで、先輩や後輩の学年はもっと少なかったと記憶する。(ちなみに哲学科は2名だった)
そんな規模なので、教授の数も少ない。教授の専門はそれぞれ
・万葉集
・中古中世(平安~鎌倉)の仏教説話
・近世(近松門左衛門とか)
・近代(明治~昭和)
・国語学(文学ではなく言語としての国語)
というものだった。
2回生は必修でこの5人の教授の講義は絶対1コマずつは受けなければならなかったので、とりあえず上に書いたものは一通り勉強した。
やってみると万葉集は意外に面白かったし(万葉仮名を読むのが大変だったが)、近世もくずし文字を読むのがまだ簡単だったし、それなりに楽しんだ。国語学はもう何をやったのか覚えていないほどつまらなかった。
そして、近代の教授の講義がとにかく面白く、文学とはストーリーを追うだけのものではないことを知った。
堀辰雄の「菜穂子」を1年かけて1文ずつ皆で解読していったこともあったが、この時ほど「国文学って世の中で一番役に立たない学問なんじゃないだろうか」と思ったことはない。やっていることはまるで平安貴族たちのお遊びだ。自分の教養を深め、互いに披露し合って、時には競い合う。なんて贅沢で、なんて自己満足な学問なんだろうかと思った。でも、そう思いながらも、それが楽しくて仕方なかった。
3回生になると4回生で書く卒論のために、より専攻をしぼらなければならない。簡単にいえば、先に挙げた5人の教授の誰につくか、ということだ。
花形の平安貴族文学が学べない私は、最後までどこの教室に入るか迷っていた。近代文学は教授がいいし、面白い。でも、私は「1000年も前から人間って考えていることは変わらないんだ」という気づきから古典文学を学びたくて国語国文学科に入ったのだ。やっぱり平安・鎌倉時代の文学を深掘りしたい、と思った。
そう。一応、平安・鎌倉時代の専門の教授はいたのだ。しかし、その専門が仏教説話。きらびやかな平安貴族の文学とは真逆の庶民の文学だ。あまりの違いに迷いがあったが、この教授の講義を受けているうちに仏教説話の面白さを知ってしまった。また、運命の鴨長明の「発心集」にも出会う。
結果的に私は中古中世の仏教説話を専攻し、4回生になるとその分野で卒論を書いた。(卒論についてはいずれ別の機会に書いてみたい)
仏教説話はやればやるほど面白かったし、今ではこれでよかったと思っている。ただ、今の大河ドラマ「光る君へ」を見ていると、やはり若い頃抱いていた想いがふつふつと湧き上がるのを感じる。
「お前は○○を読んだことがあるのか」と聞かれ、さらさらと漢文をそらんじてみせる。そういう教養のひけらかし合いみたいなのが、私はたまらなく好きなのだ。気持ちをすぐ歌にしたためるところも。
あー、やっぱりこの時代の貴族文学を学んでおきたかったなぁ、そうしたらもっと面白いだろうなぁと思ったが、いやいや「学ぶ」のは今からでも遅くはない。久しぶりにあの時代のことを深掘りできるような本を買ってきて読んでみようかなと思う。
そういう経緯もあり、私は今の大河ドラマが楽しみなのだが、夫は歴史好きといっても戦国時代と明治維新の頃しか興味がない人。
「次の大河、紫式部の話やで」と最初に伝えた時も「ふーん、なんか惹かれへんわ。見るのやめよかな」と言っていた。
それが、とりあえず第一回は見てみるかと、私の横で見出したら「めっちゃ恋愛ものやん!」と私より興奮している。夫には何をやっているのかわからない行事やしきたり、会話なども多いようだが、夢中になって見ている。まひろと道長が別れたりするシーンなど、大声で「きゅーん!」とうなっていた。「はぁ~、なんかきゅんきゅんするわ~」と。
まさにこれだ。
1000年経っても変わらない人の想い。根底にあるもの。
それがあるから、歴史や文化の知識などなくても夫はきゅんきゅんできるのだ。現代と変わらぬ人間ドラマにドキドキしたりハラハラしたりできるのだ。
うん、そうだ。やっぱりそうなんだよなぁ……と、横できゅんきゅん悶えている夫を見ながら独りごちた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
