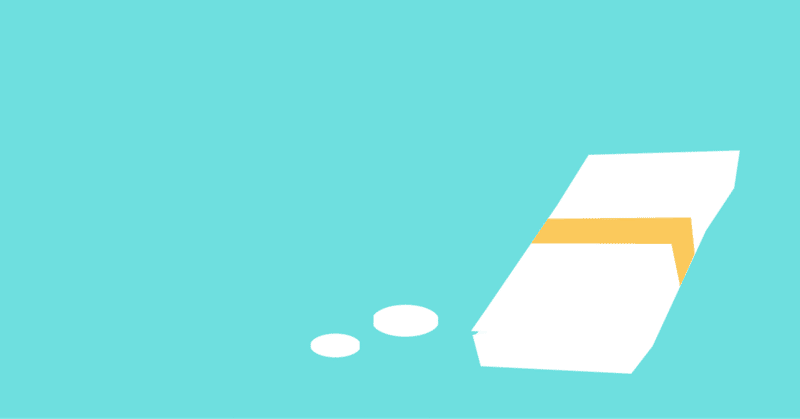
しっかり売価を上げて報酬に還元する
日経ビジネスの記事より。味の素の藤江社長の言葉「値上げは波乗りのようなもの。真っ先に上げるべし」に納得。

趣旨
・現場は値上げを嫌がる。「シェアが減るのではないか、お客様に見放されるのではないか?」
・しかし、値段を上げるのは波乗りのようなもの。先端に乗れないとうまく乗れない。波が過ぎた後では値上げできない。真っ先にあげるべし。
・価値あるものには消費者はお金を払う。商品の価値を適正に反映する「バリュープライシング」があるべき姿
つまり、適切な物価上昇と、それに見合う賃金上昇がなければ幸せ感がなくなるということかなと思います。
少し深掘り
言葉をもう少し足すと「値上げは波乗りのようなもの。適切に顧客価値を提供しているなら真っ先に上げるべし」が適切です。
仕入れ値、原材料の高騰・・・この中で、本当に売価を上げるべきか?という悩みがあったとして、現場は値上げに反対します。

このとき、経営判断には2種類あります。
A)十分な価値を提供しているので説明とともに値上げをする
B)価格を変えずに我慢

しかし、価値を提供できているのなら「真っ先に値上げすべき」です。
なぜなら、スタート地点ではA社とB社の売価は同じでも、真っ先に値上げに踏み出したA社と、後で追従したB社では、以下の図のように、時間が経つごとに利益の差が大きくなっていくからです。
具体的には、A社は利益が出るがB社は厳しくなっていきます。

前提として、「顧客価値を提供していること」「値上げの説明をきちんとすること」が必要ですが、その上で値上げは他に先駆けて実施することが重要、ということですね。
後追いがなぜだめなのか
B店が後追いで「原材料費が上がったから値上げするね」と説明するとなぜよくないのか。A店と同じ結果になるのでは?という疑問が浮かびます。
主なポイントは、価格設定におけるタイミングの重要性です。ここで言う「値上げの波に乗り遅れると上げにくくなる」というのは、市場の動向や消費者の意識において先行する企業が値上げを行うと、後から値上げをする企業は消費者から敏感に捉えられ、批判されやすくなるということです。
例えば、ある地域でアイスクリームの原材料費が上がったとします。最初に原材料費の上昇に対応して値上げを行ったアイスクリームA社は、顧客に「原材料費が上がったから値上げするね」と説明しました。顧客は、他の店より少し高くなっても、その理由を理解し、受け入れました。
一方で、後から値上げを決断したアイスクリームB社は、A社が既に値上げをしている状況で値上げを行います。この時、顧客は「他の店は前から高いけど、なんで今更この店も値上げするの?」と感じ、値上げに対して敏感になります。このため、B社は顧客の不満をより多く受けることになります。
ポイントは3点です。
1.市場先行者に利点がある
A社が最初に値上げを行ったとき、消費者はこの変化を新しい市場の状況として受け入れます。その後、B社が値上げを行ったとき、消費者はこれを「他の店が既に行った後追い」と見なす可能性があります。これは、市場における先行者が新しい価格設定に対する消費者の反応を形成し、後続する企業はこの既成の認識に対抗しなければならないという点で不利になります。
2.消費者の慣れ
A社が値上げをした後、消費者は新しい価格に慣れ、それを市場の標準と見なし始めます。B社が後から値上げをすると、この新しい標準からの逸脱と見なされ、消費者の反応はより敏感かつ否定的になりがちです。
3.リーダシップポジショニング
最初に値上げを行ったA社は、市場の変化に迅速に対応していると見なされる可能性が高いです。市場のリーダとしての地位を確立することができます。これは、消費者に対する透明性と信頼の構築に寄与します。一方で、B社が後から値上げを行うと、消費者はこの遅れを「反応が遅い」「他の店に追随しているだけ」と捉えるかもしれません。
経営判断として、価値を作り込み、売価をしっかり上げて、報酬に還元させることで、みんなを幸せにしたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
