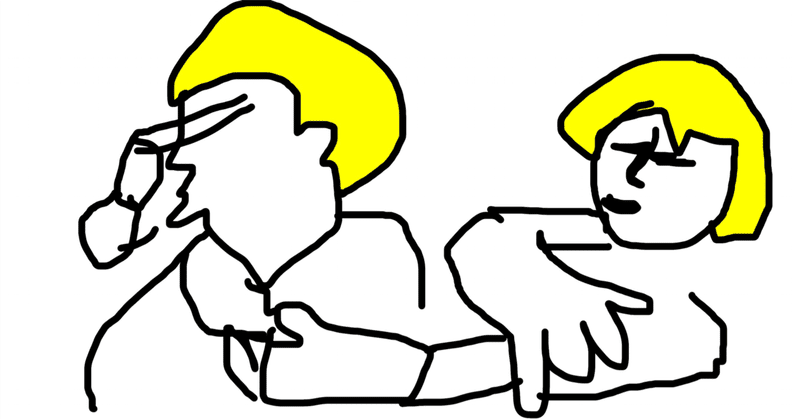
考えの異なる人との相互理解方法
1.お互いの考えはみな違う
人生で一番長い間過ごす人は親でも子どもでもなく配偶者という話がある。
ところで、自分の考えと異なる価値観、考えを持っているのも配偶者だったりする。
離婚の一番大きな理由は「性格の不一致」らしい。(Presidentオンライン)
記事では、離婚の理由は「性格の不一致」から金銭的なものに変化していっているという内容。
ただ、お金の使い方も一つの「価値観」だとすれば、「価値観の不一致」が大きな原因と言えそう。
男性と女性というだけで、身体的、精神的な違いも大きいのに、働く職場、生活リズムやスケジュールも変わってくれば違う考えや価値観になることも仕方あるまい。
問題はその課題の捉え方や向き合い方なのかもしれない。
2.異なる価値観の中でも共有する時間を作る
最近、夫婦で取り組んでいるものが同じ書籍の読書とその所感の共有。
同じ本を読むことで、内容を共有しつつも、異なる感性や考え方が比較することではっきりしてくる。
自分が心に残った箇所と妻の心に残った箇所が違っている。
どちらが正しく間違っている…ということではなく、単に「違う」。
お互いで共有する時間を持ちつつ「異なる」ところを告白し、相手に伝えることでそれをお互いに受け入れ受容するプロセスに信頼感が造成される感覚。
「えっ?そんなところに引っかかったんだ?」というとろに気がついたり、その話を聞いたことで内容の理解が深まることもある。
まずは、共通する関心事を洗い出すところが難しいという話もあるけれど。
それは本でなくとも、映画でもいいし、漫画でもいいのかも。
3.読書を通じて「ファクト」に根ざした関係性づくり

ちなみに、今回一緒に読み進めているのは「ファクトフルネス」という書籍。
ベストセラーになっているのは知っていたけれど、気になりながら、なかなか手にとって読めなかったので、最近マイブームの図書館で借りてみた。
夫婦関係でも起きた事実に根ざさず、知らず知らずのうちに、感情や自分の主観で相手に迫っていることが多かったかもなと反省。
人間のハマりやすい10個の「本能」という表現でその対策と合わせて整理されている本で、9月に読み進めた本で一番良かった。
人間は「恐怖」を感じるとそれを避けようとする「本能」があるし、複雑な事象を全て一つ一つ考えていられないので、「単純化」することで効率的に生きようとする「本能」がある。
それ自体が悪いわけではないけれど、そういう「本能」によって実際に起きている「ファクト」「事実」とそこから得られる自分の感情や考えがねじれてしまったり、思わない勘違いをしたりする。
朝起きて洗い物で山積みになったシンクを見ると、夫は自分のことを女中とでも考えているのではないだろうか…?というのは「事実」ではなく、現象を単純化して評価しているということに気がついていない状態なのかもしれない。
一つ一つの「ファクト」の背後にある「理由」や「原因」は事実を土台にお互いに胸の内を語り合う以外には歩み寄る方法がないのかも。
人間が生きていくためには役に立つ「本能」もそれに自覚なく生きていると気づかないうちに他の人を傷つけ、逆に傷つけられる。
その本能によって自分が効率よく生きていけるということも含めて「自覚的」であることが理性的な生き方ができる第一歩なのかなと。
自分自身の考え方、夫婦としての在り方も含めて俯瞰して、メタの視点で見直すことができたのはとてもラッキー。
こういう体験ができるのが読書の味だよなと改めて感じました。
知らず知らずに妻を傷つけていないか考えてみようかなと思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
