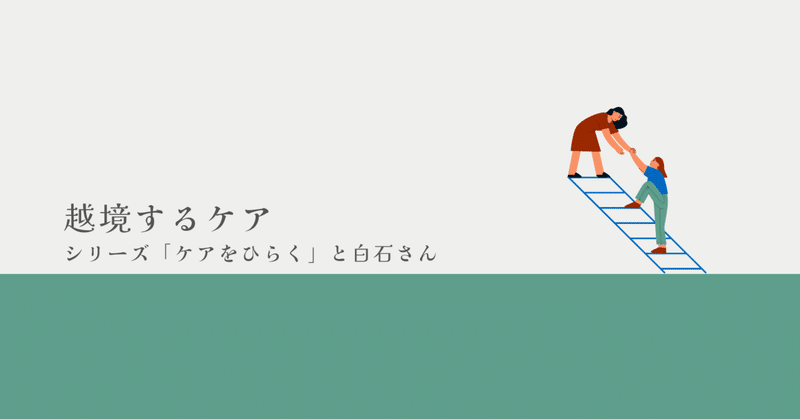
越境するケア-シリーズ「ケアをひらく」と白石さん-
いきなりですが、「白石さん」と言われたら、誰が思い浮かぶでしょうか?
身近に白石さんという名前のお知り合いがいれば、その方が思い浮かぶかな。いなかったらどうだろう。
私が真っ先に思い浮かぶのは、編集者の白石正明さんです。
ちょっと前までは、「生協の白石さん」でしたけど。。。って、世代がばれるwww
ここで取り上げる白石さんは、医学書院という出版社の編集者さんで、2024年3月に定年退職されるときに『精神看護』という雑誌で、「白石正明さんが主観で解説するシリーズ「ケアをひらく」全43冊」という特集が組まれたという方です。看護とも介護とも無縁の私ですが、はじめて『精神看護』を買いました。たぶん、最初で最後だと思います。
そして実は、2年前に、ほぼ日の特集でもインタビューされていたようです。昔、校正のお仕事も長くされていたということで、妙に共感する部分もありました。
で、なぜ白石さんに興味を持ったのかというと、きっかけは、『超人ナイチンゲール(栗原康)』という本を読んだことでした。
ちょうど、ブレイディみかこさんのアナーキック・エンパシーという考え方の影響でアナーキズムに興味を持っており、「鬼才文人アナキストが、かつてないナイチンゲールを語り出した。」というコピーに、ビビット来て、即ポチリ。独特の小気味いい文体がおもしろく、想像を超えたナイチンゲール像に魅了されました。で、この本が、「ケアをひらく」シリーズの当時の最新刊だったんですね。ちなみに、「ケアをひらく」は株式会社医学書院の登録商標だそうです。
もともと、2022年末に『ケアの倫理とエンパワメント(小川公代)』、続いて『ケアする惑星(小川公代)』を読んだあたりから、「ケア」に対する興味関心が徐々に積み重なっていたというのもあり、「ケアをひらく」シリーズが気にならないわけがなく、そうこうするうちに、白石さんの特集が雑誌で組まれるという情報をゲットしたのだから、まあ、ポチりますよね。
でね、届いてすぐに読んでみたんですが、やっぱり、魅力的なんです。白石さん。
柔軟で、ある意味かろやかさがあって、「おもしろそう」から出発する、自分のワンダーが原動力になっている方、という感じ。そして、ケアする人への尊敬のまなざしがある。
しかも、このシリーズがはじまったのが2000年で、なんと24年も前なんですね。最初の一冊目が『ケア学 越境するケアへ(広井良典)』という作品です。
『精神看護3月号』では、白石さんがこの本について
「この本は、「君たちの小さな望遠鏡ではケアの大きさが見えていないだけなんだよ」と言っている。それだけの潜在力と広さと豊穣さがあるケアというものを、「わからないからといって、つまらない評価をしないでくれ」と言っているのがこの本です。」
と語っている。そして、
「広井さんは、ケアが一対一を前提にしていることもおかしいと言っていました。医療でもカウンセリングでも、一対一で深めるんだ、それが正しいんだと多くの人が思っています。でも広井さんは、「もっとコミュニティとかグループみたいな前提で考えないと、ブレイクスルーはない」と言っていた。」
とも。まさに「ケアをひらく」シリーズのスタートを飾るのにぴったりの本。この記事読んで、読まないわけにはいかないでしょう。
帯のコピー「ケアの多様性を一望する」のことばどおり、ケアに関わるさまざまな専門分野を「越境」する本でした。著者の広井さんは、公共政策や科学哲学の専門家。お名前に見覚えがあるなと思っていたら『人口減少社会のデザイン』って本が積読になっていました。読まないと。
実は、私は、専門家でも研究者でもない一般市民ですが、いつも自分なりの探究テーマを持っています。昨年からの探究テーマは「ケアとタテ社会」なんですね。
タテをカタカナにしているのは『タテ社会の人間関係(中根千枝)』へのオマージュです。
ちなみに、探究テーマとかって大袈裟な感じですが、自分が楽しいから探究しているだけなので、何か結果を残したいとか、深めて誰かの何かの役に立ちたいとか、キャリア形成に有効だからとかといった目的はありません。おもしろいことや楽しいことは自分でつくる、というだけです。
いちおう、ちょっと意識高いことをいうと、明らかに目に見える形でゴロゴロしている、日本社会独自の構造(タテ社会)から生じる社会問題や社会課題が、どうすれば少しでも改善するか、という問いに対して、最適解をさがして探究し続けているという面もありはするんですけどね。
白石さんの言葉を借りれば、潜在力と広さと豊穣さがあるケアを、コミュニティとかグループみたいな前提で考えると、なんらかのブレイクスルーが起こるかもしれない、と思っています。
だから、私は「ケア」にひかれるのです。
これまでも、哲学、対話、教育、仏教、子育て、心理学、社会学、生物学、コーチング、ファシリテーションなどさまざまに興味関心を持つ分野を、好奇心の赴くままに学んできましたが、「ケア」はそれらすべて包み込む、包容力を持つ概念だと感じています。
封鎖性の高い小集団が弱いネットワークで、数珠つなぎになっている日本社会。
エモーショナルな結びつ付きがその閉鎖性を強くするがゆえに、小集団内部でも、小集団同士の関わりにおいても、さまざまな問題が生じてしまう。
その封鎖性を切りひらく力が「ケア」にはあるのではないか。
そんな期待を持って、しばらく探究を続けたいと思います。
研究者でも専門家でもない普通の人だからこそ、越境できる。
そして、ケアはすべての人にひらかれているから。

追記となりますが、先日、朝日新聞デジタルに白石さんのインタビュー記事が掲載されていました。その記事の中で、「ケアをひらく」の「ひらく」という表現について、
「ケアとはこういうもの、と定義し狭めていくやり方の逆です。面白い本――僕の言葉でいえば、読者を驚かせ、世界の見え方を少し変える本にできればと思った。」
と回答されてました。このnoteの全体テーマが、自分なりの世界の見え方なので、なんかちょっとシンパシーを感じたのでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
