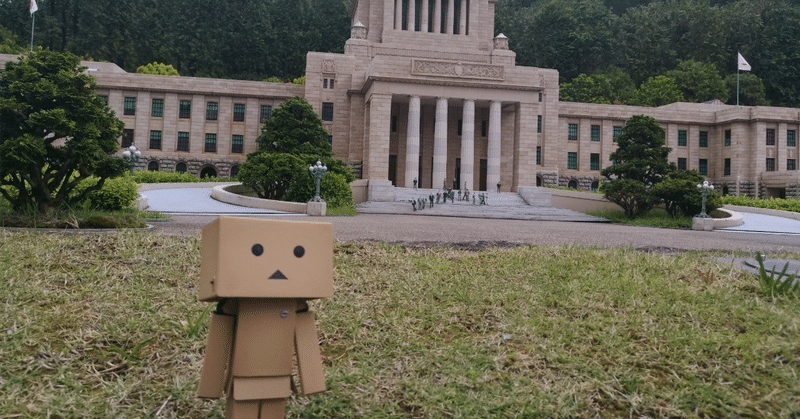
衆議院法務委員会・やまのい和則議員(立憲)2024年4月5日質疑
>委員外でありますが、30分間質問をさせていただきます。誠にありがとうございます。
最初に申し上げますが、まだ私も最終的には、我が党も私も、法案の賛否は決めておりませんし、是非とも今日は前向きな答弁をいただければと思います。また失礼ながら、今日は小泉法務大臣のみに質問通告をさせていただいておりますが、22問通告を、あのいやいや基本的なことしか質問してませんので、そういう意味ではそれに基づいて、質問をさせていただきたいと思いますし、通告通りさせていただきたいと思います。
それで、私がなぜ今日質問に、あの委員外であるにも関わらず、立たしていただいたかということは、私はこの政治家になる原点が、このDV被害と極めて密接に関係しておりますので、誠に失礼ながらですね、ちょっとその私が学生時代に経験したことにも触れながら、法案に直接関係することですので、お話をさせていただきながら質問に入らしていただきたいと思います。
私は、大学院まで酵母菌、バイオの研究を理系でやっておりました。研究者でした。 ところが、たまたまというか同時に母子生活支援施設、簡単に言いますとDV被害のお母さんとお子さんが逃げ込んでくる、駆け込んでくる30人規模の京都の駆け込み寺で、水曜日と土曜日2~3時間ずつ、子供達とドッジボールしたり勉強教えたり折り紙したりですね、小学生中学生、高校生もおられましたけれど、遊ぶボランティア活動を6年間やっておりました。
そしてやっぱりその中で非常に考えさせられたのが、例えばその施設には20世帯ぐらいですかね、表札があるわけですけどね、入り口のところに。ほとんど偽名なんですね。本名じゃないんです。それ、やっぱり逃げてきてるからなんですね。だから、言っちゃ悪いけど、ちょっと頭が混乱するんですよね。井上さんって言ったけれど、お子さんは本当は井上じゃなかったりしたりですね。
なんかそういうことで、なんで名前が隠してるのかなって言ったら、これDV夫から逃げてきてるという理由で、でした。
ある時、いや大変やと、こういう3階建ての建物でしたけれど、DV夫が来て石をバーンとね、「うちの嫁さんおるやろ、出せ」って言って石を放って、それで母子家庭支援施設の窓ガラスが割れそうになったりして。これはちょっと大変やな、とね。それは押しかけてきたら、みんなでそれ守らなあかんなと、お母さんと子供。という風なことで私たちもですね、ただ単に子供と遊ぼうと思ってたわけですけど、これなかなか大変だなと思ったと。
それとやっぱり多くのお子さんが非常にこうメンタルで傷ついておられて、ちょっと不登校になったり、一言で言うと対人恐怖症で。なんでかなと思ったら、要は自分は直接殴られてないんですけれど、目の前で夫が妻を殴ったり暴言してるのを見て育つ中で、結局メンタルがやられちゃって。
私、議員になって24年ですけれど、1つ取り組んだのは、児童虐待防止法の中に面前DVというのを入れるということをやりました。なんでかというと、手出しをされなくてもDVを目の前で小さい時ずっと見せられると、子供のやっぱり精神状態が崩れてしまうんですね。ですから、両親が一緒にいた方が幸せなケースもあれば、今言った様に下手にDVを見せられちゃうと、もう非常に大変なことになっちゃうと。だから例えば、大人の男性が声をかけるともうビビっちゃう子供たちがいて、なんでなのって言ったら、いやもうお父さんがお母さんを怒鳴ったり殴ったりしてるのを見て育ったから大人の男性は怖いの、とか言われてですね。
その中で、私が実は忘れられない出来事がありまして、数年間やってそろそろ私も就職を決めないとだめだなとか思っているときに、ある事件が起こったんですね、その施設で。というのは、何とDV夫が突破して、門を突破して、施設の中に乱入してきてしまったんですよ。包丁を持って。そのとき私はおりませんでしたが。乱入してきてしまった。それで、大変だということになって、女性の60代の小柄な職員さんが、「お母さん大変や、お父ちゃんがナイフ持ってきた。絶対、出たらあかんで」と言って、電話をしたわけですね。そうしたら、そこに乱入した男がブスッと職員さんを刺してしまったという事件が、残念ながら起こってしまった。私はその場にいなかったんですけれども、私も大変ショックを受けて、その職員さんに「大丈夫でしたか」と聞いたら、もちろん病院に行かれたんですけれども、その職員さんが「いやいや山井さん。刺されたのがお母さんや子どもじゃなくて、私でよかった」とおっしゃったんです。私はその話を聞いて非常にショックを受けましてね。60代の小柄な女性職員さんでした。私は本当に本当に頭が下がって、それまで数年間ボランティア活動で遊び相手していたけれども、やっぱりこの職員さんは命掛けで人生かけて子どもやお母さんを守ろうとされている。遊び相手に専念していた自分はちょっと取組みが甘かったなと、非常に考えさせられまして。僭越ながら、微力ながら、自分もそういう困っている子どもやお母さんの盾となれるような生き方がしたいなと思って、理系をやめて、実は政治を志したんです。
だから、そういう姿を見ていますから、まさかと思いますが、今回の法案で同じようにDV夫から刺されたりするお子さんたち、そういう弱い立場のお子さんやお母さんの命や生活を守るために、法律があるわけですから、間違ってもこの法改正でそういう、(共同親権になって、ハッピーになる方も私は十分おられると思いますよ、もちろん。全否定はしません。)ただ運悪く審判とかでDVが認定されなくて、結局、会ってしまったら。実は過去にも起こっていますけれども、そういう命を失うとかそういう被害を受けられる方が、今回の法改正によって出ませんか?増えませんか?まずその基本認識。小泉法務大臣お願いします。
小泉法務大臣>まずこれまでの親権制度、これは家族というのは夫婦関係と親子関係が合成されて縦糸横糸ででき上がっていると思うんですね。これまでの親権制度というのは、夫婦関係が破綻すると、親権者は一人ですから、やはり片親と子どもの関係は自動的に切れてしまう、というところに少し疑問があって。そしてその次に、子どもの幸せということを考えなきゃいけないな、という判断が入ってきて。そしてでも子どもの幸せというのは、子どもが置かれた状況に千差万別さまざまな状況によって、子どもの幸せの在り方は、形が変わってくると思うんです。したがってこの制度を柔軟なものにしていこう、という考慮が働いていると思うんです。先生がおっしゃるように、本来子どもの利益のための法改正でありますので、いろいろな事情があるにせよ、結果として、法改正した結果、不幸な子どもが増えたんじゃ、それは全く本末転倒であります。それは間違いのない事実であり、そう判断しなければいけないわけです。ただ全体は柔軟性を持って、さまざまな状況に置かれた子どもの幸せというものを、この夫婦関係及び夫婦関係の破綻に従属させるのではなくて、子どもの幸せという観点から再構成していこう。状況がさまざまでありますので、柔軟に選べる形にしていこう。でも本末転倒になってはいけない、それは本当にそのとおりだと思います。そして、ですからこういう国会の審議において、さまざまな御経験をされた、さまざまな御経験を代弁できる委員の方々からさまざまな御議論をいただく。それは非常に重要なことだと思います。
先生も、学生時代からボランティアとして児童福祉施設で働かれ、そこでまたそういうショッキングなことがあり、またそこから国政を目指してこられたというふうに今伺いました。そういう中からいただいたお話は大変貴重なものだと思いますので、共有をさせていただきたいと思います。まずは私の所感でございます。
>先日の参考人質疑、もちろん賛成派反対派両方おられまして、例えば犬伏参考人はこの法案については前向きですということで。ただ「家庭裁判所の人的充実、裁判官の増員とともに、家事事件についての専門性を高めていただく必要があります、調査官の増員も必要です」ということを前向きに捉えながらも提案をされています。おそらくこの法案に賛成されている方々も、このことに関しては、増員必要だよね、という共通認識を持ってられるんじゃないかと思います。
そして慎重派である斉藤参考人、もちろん皆さんもお聞きになったと思いますが、DV被害者の方でありますけれども、もう繰り返すのは釈迦に説法かと思いますが、あえて重要なことなので申し上げたいと思います。議事録を読み上げます。
「この知人は元夫から突き飛ばされたり壁を殴られたりするDVを受けており、子どもも怯えていましたが、証拠が十分でなかったのか、家裁はそうした事情を汲み取ってくれず、面会交流をされたのです。ほかには同居中に乳児が骨折するまで暴行を受けたのに面会を命じられた子どももいます。面会交流中に父親から性的な虐待を繰り返し受けている子どももいます。伊丹市では2017年、面会交流中4歳の女の子が父親に殺される事件が起きました。調停でDV被害があったことを訴えましたが、調停委員から面会交流を勧められました。元夫につきまとわれる恐怖にさらされながらも面会交流に送り出された日に、娘さんは殺害されました。『DVの証拠の写真を提出したんだから、ちゃんと判断してほしかった。』それで面会交流中に子どもたちが命を落とすケースは、既に共同親権を導入している国ではこれまでに985件報道されています。」と。こうなっているんですね。もちろん、面会交流はよくない、というわけではありません。ただ現時点でも家裁や調停の中で、やはりDVだと主張しても認められずに、面会交流した結果、お子さんが亡くなられたという痛ましい事件が起こっていて、現時点でも起こっているけれども、今回この法改正によって、そういう痛ましい被害が増えないか、ということなんですが。改めてですけれども、小泉大臣。理論上はDVの人が除外されます。それはそうなんですよ。問題は、それは調査員の方も人数に限りあるし、時間にも限りがあるから、それが見落とされて今回みたいな命が失われるとか、そういうことにならないか、ということなんですけれども、そのことついても御答弁をお願いします
法務大臣>確かにおっしゃるように、その仕組みとして、DVあるいはDVの恐れがあるときは、単独親権あるいは単独行使、そういう道筋があるわけでありますが、その判断が甘くなれば、それはおっしゃるようなことにつながってしまうリスクというのはあるわけですよ。ですからこの法改正を一つの契機として、DVに対して裁判所がどうあるべきか。こういった観点からの、我々がそういう議論をすることによって、立法府と、こうやって立法府で御議論をいただくことによって、それは司法権も注視をしております。どういう議論があるのか。どういう事実があるのか。またそれを行政としては司法と共有する考えでございます。ですから、こういう議論を通じて、その実効性を高めていかなければいけないと思うんですね。DVから子供を守るということを、より、より、より丁寧に着実に進める、その努力を、この法案というものを、一つの大きな契機として、我々は立法も行政も司法も一体となって議論し、進めなきゃいけないと思うんですね。それが私の考えです。
>これですね、今おっしゃったことは、私はそのとおりだと思うんです。けれども問題はスピードだと思うんですね。例えば、法改正が実現したと。主旨は、みんな想いは一緒だと。子供に幸せになってほしいと。でも、いざやってみたら調査員の方が足りなくて十分にチェックできなくて被害者が出ちゃったよね、ということでは、これははっきり言いまして賛成した議員も反対した議員も含めて、(これは賛成しているのが悪いとかという話で私は済まないと思うんですよ。)これはもう国会で審議している以上は、やはりここにいる国会議員全員が、やはり反省せねばならなくなるし、そういう被害が出て、数年後にやっぱり法改正をもう一回しましょうとなったら、(繰り返し言いますけれども、これは賛成反対は私は関係ないと思うんですよ。)やはり審議に参加した議員みんなの連帯責任になってしまう、というふうに私は自戒も込めて申し上げたいと思います。
そういう中で、例えば私もボランティアする中で小学生の女の子とかから言われたことがあるんですよね。お父さんに会いたいと。お父さんに会いたい、と。でも、お母さんを殴ったり、怒鳴っているお母さんは嫌いや、と。この子供の揺れ動く思いとか、やはりそういうことを聞いたことがあります。
それで先ほどの斉藤参考人の話の中でも、妻の発言はさておき、お子さんが、やはり怖いと。会いたくないと。例えば、今まで虐待を受けたりして、もう怖いから会いたくないと言っているという気持ちは、非常に尊重すべきだと思うんですが。
私たち今後、米山理事・道下理事を中心に修正案を提示して、修正協議もお願いすることになるんじゃないかと思うんですけれど、もちろん それを充分に飲んでいただいたら賛成しやすくなるし、全く飲んでいただけなかったら賛成しにくくなるし、そういうことだと思うんですけれども、私も個人的な意見を申し上げるわけではないですけれども、今言ったような子供の意見を尊重してほしいという意味で、通告の17になりますが、離婚等の場合の親権者の定めに関し、意見聴取等により把握した父母及び子それぞれの意思の考慮の明記の修正、やはり子供の意見を尊重するというふうに修正をしていただけないか。ここで「はい」とか言いにくいのはわかるんですけれども、要望として、やはり子の人格の尊重だけでは、817条の12のその子の人格を尊重する、だけではやはりちょっと弱いと私は思いますが、その子供の意見を尊重、というふうな形に修正をしていただくというのはいかがでしょうか。
小泉法務大臣> 子供の人格の尊重の中には、子の意見・意向を適正な形で考慮する、尊重をする、そういう意味は間違いなく含まれています。
そしてもう一点申し上げれば、親権者の変更について、子供は申し立てをすることができます。自分が言い出すことができます。この自分の父親を親権者に、母親を親権者に、そういう意見がもし子供から出てくれば、それは当然尊重されることになっていくと思います。
ですから両方の規定から、この法律は子供の発言というものを非常に重く見ている。このことは司法においても理解をしていただけるものだというふうに思っておりまして、法案修正までは必要ないかなというふうに思います。
>また前向きにご検討いただければと思いますが、次の論点です。
私もボランティア活動をする中で、やはり非常にメンタル傷ついて不登校になってしまうお子さんたちも残念ながら多いんですね。つまり両親のいざこざに子供が、やはり幼いながら巻き込まれちゃうわけですよね。例えば、今回この通告7ですけれども、保育園幼稚園小学校中学校で、例えば公立に進学するか私学に進学するかも、別居している親の同意が必要なのか。つまり大学まで言わなくても、もう保育園幼稚園小学校中学のときにも公立と私学がありますから、このときにもやはり別居している親、別にこれは妻であっても夫であっても、別居している側の同意は、やはり必要になるんでしょうか。
小泉法務大臣>これは厳密には、その子が置かれている具体的な状況によると思いますが、教育理念の特色や学費等もさまざまであって、その中でどの学校を選ぶかどの保育園を選ぶか。これはやはり進学先進路、子どもの進路に影響するような事象である、というふうに考えられます。
基本的に父母が共同して決定すべき事項ではないかと。基本的にはそのように思っております。
>いやだから私も、ある離婚された家庭のお子さんの声を聞いたことがあるんですけれども、何年も同居していない別居している親から、急に進路について了解してほしいとか言われるのはやはり困ると。子ども困りますよね。それで仲良かったらいいんですよ、それがもう何から何まで大喧嘩してすれ違うように決まっているというのに、 幼稚園保育園から相談しないとだめになっちゃうと。
繰り返し言いますけれども、夫婦間で戦うのはしょうがないじゃないですか。離婚ですから。
子どもが巻き込まれるのがかわいそうだと思うんですけれども、そこで残念ながら別居している親が反対したとしますよね、そうしたら、例えばわかりやすく大学入試にしましょうか。子どもは高校生で、進学したいと思っている。それで同居している親は一緒に頑張って勉強しようねと言っているけれども、何年間か別居している親が共同親権になって、いきなり、金がかかるから進学はだめだと言い出してしまったと。
そうなったときには、だいたい審判をすると、何ヶ月ぐらいで結論が出ますか。進学できるかできないか、別居している親の答えが。これはもう質問通告を入れておりますので、何ヶ月ぐらいか、何年ぐらいか。
小泉法務大臣>それはちょっと個別具体的な事例によりますので、また司法の問題でありますから申し上げられませんが、今の事例であれば、何年もケアしていない、子の養育費も払っていない、コミュニケーションもとっていない、だけれども共同親権になったとたんに介入をしてくる、あるいは妨害的なことをしてくるということになれば、それはそもそも共同親権者としてふさわしくない、あるいは共同親権を行使する上にふさわしくないという判断が、充分裁判所において成り立ちますので。そこに判断を預ければ、いやあなたは何もお金も出さずに口だけ出しているんですよね、という形で排除することはできる仕組みになっていると思います。
共同親権者だから、じゃ何でもできるんだ、いやそうはいかない、ちゃんとやることをやっていなければ、裁判所は共同親権者としてふさわしい人として認めてくれないわけでありますから、それが基本的な歯止めになっているわけですよね。そういうふうに御理解をいただきたいと思っています。
>おっしゃる主旨はよくわかるんです。ただ小泉大臣も具体的明確には答えられないとおっしゃっているぐらいだから、お父さんお母さんや子どもさんからすると、より予見が不可能なんですよね。もしかして、進学の、かかっちゃうんじゃないかしらと思ったりして子どもは不安になりますよね。それでそのことに関連して、私もボランティアしていて、子どもたちを見てつらいなと思ったのは、一番つらいのは、もう不登校になってしまうお子さんとか非行に走って事件を起こしちゃうお子さんって、残念ながらおられるんですよ。僕らからすると、あんないい子どもが何でこんな事件を起こしてしまったんだと、大ショックを受けるんですよね。いつもドッジボール一緒にしていたのにとかね。そんなときに、いやいや実は家庭が今お父さんお母さんで大揉めに揉めていて、その両親の争い不安が子どもに出て、やはり子どもが不登校になっちゃった、あるいは事件を起こし起こるかと言ったら、もうそんなんだったらもう進学をやめるわと。もうそれでまたお父さんお母さんが喧嘩するのでは、もうやめるわ、となっちゃって。要は命を失うとかということじゃなかったとしても、その共同親権騒動に巻き込まれて、もう進学を断念する子どもが出てきてしまうんじゃないかと思うんです。
例えば2ヵ月ぐらい以内に結論が出るとか、高2の夏休みまでには決定するんですとかというのがないと。そのあたり。例えば大学受験だったら、高3の4月、高2の夏、やはり勉強必要ですから。これは。直前に進学していいですよと言われたってもう間に合わないから。例えば急迫の事情というのはありますけれども、大学進学だったら、いつぐらいまでに、さすがに決定を、この本会の共同親権の場合にしていただけるんでしょうか。
小泉法務大臣>これは法案審議の過程で、こういう切実な御議論があり、また私としても、それは適切な期間の間に処分審判が下されることが、当然望ましい。そういうふうに思い、そういう答弁をする、御議論いただき答弁をする。これ議事録に残り、法案が通していただけた暁には、司法も共有することになります。彼らが、司法が、適切に対応してくれると私は期待するし、望みたいと思います。それが一点でございます。
二点目は、離婚のとき子どもが傷つく、で別れたんだけれどもまた共同親権で接点を持つから、またそこでこういがみ合い、もう一回子どもが傷つく、という御議論だったと思うんですね。
二回目に子どもが傷つくような、場面が続くような、そのお二人を共同親権に私はできないと思います。ならないと思います。その手前のところで、それが単独親権に収まっている話だと思うんです。
共同親権まで行くには、さまざまなありとあらゆる事情を考慮して、この二人ならば、二人は撚りは戻らないけれども、子どものためには協力できる余地ありと。さすがに万全な100%の機械的な答えは出せませんけれども、蓋然性において うまくコミュニケーションがとれるだろうという方々を共同親権にしよう、希望があれば。という制度でありますので、その点を二点目として申し上げたいと思います。
>私、大臣のおっしゃる趣旨はよくわかるんですよね。それはそんなにトラブルになるようなケースは、そもそも共同親権になりません。私もその答弁を信じたいんですけれど、大臣も真心でその答弁をしてくださると思うんですけれども、ここの7ページにもありますように、家裁の体制増員も必要ではと。裁判所は今まで以上に難しい判断を迫られるようになり、今の裁判官や調査員の人数では足らず、増員も必要になるのではないか。主旨はわかりましたよ、主旨は共有しますけれども、いくらやりたいというのも、現場が調査員が足りないということで、ワークしないリスクというのがあると思うんですけれども。あとの質問通告にも入れていますが、家庭裁判所の人的体制の整備等についての規定を修正により法文に盛り込むべきではないか。いかがですか。
小泉法務大臣>裁判所との間では、日常的に法務行政あるいは司法に関する情報交換と意思疎通をしております。今回のこの法案の策定に当たっても、最高裁と、マンパワーが足りるかどうか。数だけではなくて、機能として十分応えられるかどうか。そういうことをぜひ考えていただきたい、そういう要望、我々の考え方は最高裁にお伝えし、最高裁もそこは真摯に受けとめていただいております。御指摘の点は、非常に大事なところだと思いますので、法律をつくったけれども実際動いていないということになれば、それは大変なことですから、そこはしっかりと責任を持って私は対応していきたいと思います。法案に書くところまでは必要はないと思います。【ここなぜか笑い】
>今後引き続き検討していただきたいんですけれども、言っちゃうんですけれども、私、大臣の発言を疑っているわけではないんですでも、やはり担保というか歯止めというか、何かをやはり欲しいわけですから。それともう一点、それに関連して質問20。一応施行までの期間は2年となっているんですけれども、今の答弁をお聞きして、信じたい気持ちは山々なんだけれども、万が一、都道府県によっては調査員が足りなくて、十分な調査ができなくて、子どもが亡くなっちゃったとか、進学断念をみんなしちゃったとかだったら大変なことになって、子どもの不利益になりかねませんから。この法案を修正して、施行までの期間を5年とする修正を行うべきではないか。いかがですか。
小泉法務大臣>まずはこの委員会において議論を尽くさせていただきたいと思います。今の時点で、我々は施行まで2年の法案を出していますが、3年延ばすという、そこまでの必要性を判断するには至っておりません。
>時間が来ましたので終わらせていただきますが、ここはもちろん法務省さん、政府の判断、大臣の判断もあると思いますけれども、やはり今後我が党としても修正案を提示しますし、やはり与党や他の野党の方とも議論をしながら、とにかく最後に申し上げますが、この法改正によってハッピーになる方も私はもちろんおられるとは思いますが、万が一この法改正の結果、お亡くなりになるお子さんとか、そのせいでもう進学断念したのという子どもが出たら、これはもう賛成の方も反対の方も誰も望むことではありませんので、そうならないように修正協議をぜひがんばっていただきたいと思います。ありがとうございました。
(書き起こしは以上です。)
途中、小泉法務大臣が吹き出すように笑う場面がありました。「法案に書くところまでは必要ない」という答弁でした。似たような内容を繰り返し答弁する事になって笑ってしまったのではないかと思いますが、筆者は「特に理由はないけど修正には応じないぞ」という態度がつい表れたものだと感じました。憤りしか感じませんね。。。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
