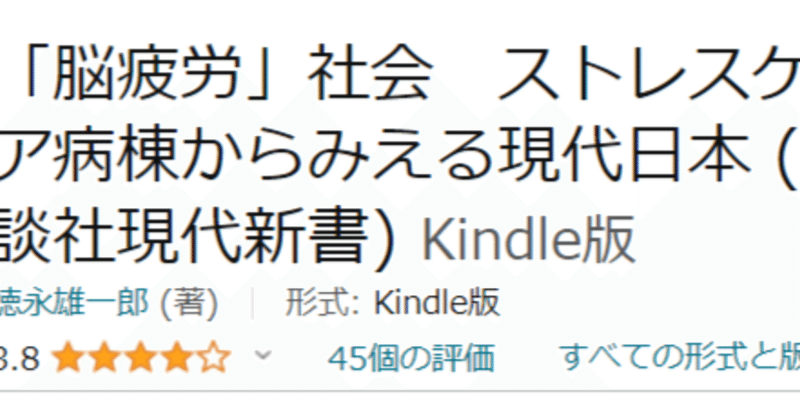
うつの原因を調べたメモ【「脳疲労」社会 ストレスケア病棟からみえる現代日本】
最近読んだ「『脳疲労』社会 ストレスケア病棟からみえる現代日本」という本が良かったので、参考になった所をまとめました。
ストレスと脳の関係
ストレスと脳機能には、脳の視床下部、下垂体、副腎皮質系の内分泌活動が大きく関わっています。ストレスが高くなると副腎皮質刺激ホルモンの過剰分泌が起こり、体内のコルチゾールが増加する結果、脳内の海馬の神経細胞の新生が阻害され情動などの不調をきたしやすくなる、とされています。
高ストレス状態が持続し、うつ病になった人では、海馬の容積が低下しているという報告が多く認められており、これには、うつ病だと減少する脳由来神経栄養因子が関与していると考えられています。
さらに副腎皮質刺激ホルモンが過剰分泌されると、セロトニン神経系の働きが抑制され、この現象がうつ病などで見られる前頭葉機能の低下と関連すると言われています。
これらのように高ストレスの持続が、脳内の披露からホルモンや種々の脳内神経の変化を起こし、うつ病に至ると考えられ、研究が進んでいます。
化学物質の中でも、ノルアドレナリン、ドーパミン、セロトニンは精神疾患と密接な関係がある事が示唆され、気分障害、不安障害、統合失調症に関する仮説が提案されています。
一方で、人間の遺伝子=ゲノムは解析が進んでいますが、鬱になりやすい人の遺伝子は今のところ見つかっておらず、鬱の原因に関わるとは言えないそうです。
また、精神神経科医の黒川駿哉先生によると、意欲や情動をつかさどるセロトニンやドーパミンは九割が腸内で生産されているそうです。
成人の腸内には100兆個の細菌が存在する事に対して、成人の細胞数が37兆個といわれており、腸内細菌とストレスの関連でも研究が広がっています。
うつ病の症状
うつ状態は、気分の落ち込みと抑うつ気分、やる気が出ず何をしても億劫、能率や判断力の低下、すぐ疲れる、悲観的になる、自信が無くなるといった状態を指します。
このような脳疲労と脳不調の状態、抑うつ状態は一時的には誰にでも起こりうる症状です。
今の日本で「うつ病」と診断されるには「ICD-10」や「DSM-V」という診断基準があり、PET,SPECT,MRIなどの画像検査を受けると前頭葉の機能低下が分かります。
うつになりやすい性格傾向
遺伝子的な原因は見つかっていないため、誰でもうつ病になると考えられていますが、うつ病になりやすい一定の性格傾向はあるそうです。
それは一般的に執着気質と言われるような性格であり、「物事に取りかかったら自分ではなかなか止められない」「失敗したら考えなくていいことまで先に考えてしまう」といった人が当てはまります。
仕事に真剣に取り組むために周囲の信頼は高い人が多いそうです。
このように考え過ぎて疲れることを「思考疲労」と著者は呼んでいます。思考疲労になりがちだったり、そういった行動に思い当たりがある人もいるため、自分の性格を把握しておくことも重用かもしれないそうです。
うつ病の患者に多いのは教員や看護師、SEなど長時間多くの仕事をこなすような職種だそうです。他にも主婦や議員もうつ病の患者にいます。夫の定年まで耐えて自由になりたいと考えている主婦の方も多いようです。
うつ病に掛かった後に休職してすぐ治る患者もいる一方で、休職後もうつが治らず、退職してしまったため再び安定した職に就けなくなってしまった人もいました。
また、多くの仕事で頭脳労働が中心になると共に、趣味でも運動よりも脳を使うようなアクティビティが増えた事も、脳の疲労に関係があるかもしれないと言われています。
近所への気兼ねと家族への申し訳無さ
うつ病と診断されてから、休職後に自宅での療養を選ぶ場合には注意が必要です。
自宅周辺に顔見知りが多い場合、気分転換に散歩へ外へ出かけにくくなり、引きこもるようになってしまう事があります。
また、自宅で仕事が出来ない、家事が出来ない姿を家族に見せるのは、責任感の強いうつ病の人にとっては辛い体験になります。休職のため実家に帰省した場合も、親や周囲への気兼ねが強く働きます。
このように、自宅療養が症状を悪化させる事もあるので入院による治療が大事だと言います。
治癒像の視覚化
入院生活中に、悪化時期を乗り越え回復段階に達した患者の方は、他の患者と交流する集団療法が設けられたり、四人部屋で生活して仲間と会話する時間もあります。
これらのように、スタッフや医師が在中して患者のケアや相談相手になるだけではなく、入院生活を通し病棟で他の患者と交流する事で、病状が治った状態の自分をイメージ出来るといいます。
上記の「周囲への気兼ね」のように、自宅療法では回復しにくい場合でも入院によって生活を一変させる事が出来ます。
感想とまとめ
本の内容は以上で、ここからは感想です。
「うつになりやすい性格傾向」としては、自分から何かを辞めたり、「できない」「やらない」と言い出す事が難しい人、ドクターストップが無いと止まらない人などが当てはまると思います。主体性の無い人物とは異なる、責任感の強さが原因で自分を追い込むような人が、このような性格に当てはまると思います。
「近所への気兼ねと家族への申し訳無さ」は、実家に居る時にうつが悪化した自分にも理解できます。自分も実家に居た時に親から「近所から良くない眼で見られてる」と言われてから気にするようになり、外に出るのが怖くなった事がありました。
うつ、新型うつ、といったワードはネットでよく見るものの、実際の原因を知るのは初めてでした。常に不安かつギリギリ生きている状態だが、自分が苦しんでいる物の正体が少しでも分かると多少は希望が持てるので、この本を読んで良かったです。
うつ病になる原因も、労働環境や生活形態に依る物が多く、症例や悪化する仕組みにも心当たりがあったため、自分の状況と照らし合わせつつ原因を取り除いたり、自分のうつ状態を軽減するセルフケアに活かすつもりです。
また、この本の一部ではネット上の「脳科学辞典」を引用していました。
「病症についてネットで調べてはいけない」という事は良く言われていますが、出典が明らかになっていて、尚且つその出典が信頼できる人物である事を、書籍など別のソースから確認できる場合は、Webサイトを信用して良いと思います。
例えば、YoutubeのTedEDなど教育目的の機関が、科学者や心理学者の協力を元に作った動画は、英語ですが数多く見られます。
周囲のストレスは直接脳や体に影響せず、ストレスに対する心理的な反応が自分の体や脳に影響を与えている。全てが勝ち目のない恐怖であると思い込むよりも、制御し克服できる状況だと思うことが出来れば、短期的にも成果を出す事ができ、長期的に見ても自分の健康を損なわずに済む。
昨今の多様な職業や環境が原因で、うつ病になる人は増えているようなので、心身共に健康であることが一つの重要な資産になる時代が、今後来るのではないかと思いました。
看護師や教員は、社会的に必要な職業であり、ある程度責任感のある人が務めるべきですが、少なくとも今の労働環境では肉体的にも精神的にも続ける事が難しい人が増えてしまうのが現状かもしれません。
感謝します
