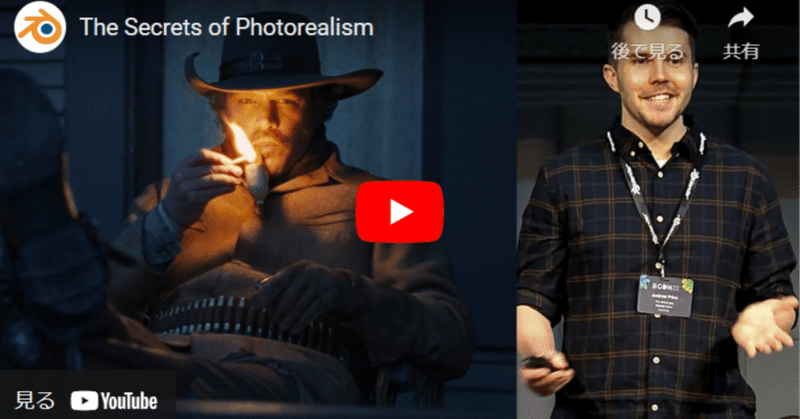
3D作品のリアルさとは【The Secrets of Photorealism】(Blender,3D)
最近はゲームもアニメも、昔に比べてリアルかつ画面の情報量もリッチになってきていると思いますが、3D作品の中で「リアルだ」と感じさせるポイントは、どの要素でしょうか。
「3Dを使った作品の中で、リアルさを感じる部分とは何か?」というテーマについて、The Secrets of PhotorealismというBlender公式の講演動画が、非常に参考になったので役に立ちそうな部分をまとめました。
導入
動画で講演しているAndrew Priceさんは、フォトリアリズムの原則を正しく理解して作られている作品として「トイ・ストーリー4」を挙げています。
そして、このフォトリアリズムを表現している要素としてライト、マテリアル、オプティクス(主にカメラの特性等)の三つに分けて動画で解説しています。
ライト
光の特性について最も簡単に学べる要素は光の色であり、現実世界のほとんどの光は、この色温度=ケルビンスケール内に収まります。

トイ・ストーリー4では温かいトーンの色は太陽光等に、冷たいトーンの色は月光や空のライティングに使われて、ピンク等の鮮やかな色は人工の建物等に使われています。
また、デビット・フィンチャーが短編映画の撮影中に、オイルランタンと月光の明るさに1800Kと4000Kを正確に指定した例も挙げています。このように色温度での指定を行えば、光源同士の距離が正確な時にライティングも必ず正確になるからです。
光の減衰(フォールオフ)
光は光源からの距離によって減衰しますが、その減衰する量が軽視されがちです。
人物の頭頂部から光で照らした場合、頭頂部の明るさを100%とすると足元には1.2%程度しか光が届きません。

光が発生源からの距離の2乗に反比例して減衰する現象は、逆2乗の法則に基づいた物です。この光の量の計算自体は、大体の3Dソフトが自動で計算してくれるので覚えておく必要はありません。
逆に、上の図の通り発生源から届く光の量が、100%→25%→11%→…となっている様に、一定の距離であるにも関わらず、光の発生点から急激に光量が低下するという事と、発生点から遠ざかるほど減少する量も少なくなるという事は意識するべきです。
動画のサムネイルとなっているカウボーイの画像を見ると、タバコの火から発生している光が指の第一関節の付近で既に大きく減衰している点、太ももやすねに当たる光の量は減少量が少ないため同じぐらいの明るさになっている事が分かります。
また、日光は地表からかなり離れた位置の光源であるため、建物の屋上から地面まで、だいたい同じ量の光を受けるようになります。
マテリアル
物体に光が当たると、その一部が反射(Reflection)され、残りは吸収された後に、物体の内部でいくつかの粒子に当たり、それから屈折(Refraction)して表面から出ます。
科学者が屈折と呼ぶものを3Dではディフューズと呼びますが、それらは同じものを指しています。

マテリアルは、表面で光を反射して光沢を持っている物体と、反射しない物体の二種類に分類出来るように見えますが、実際には殆どのオブジェクトが同じ量の光を反射します。
物体表面のツヤやザラザラした質感は、物体表面に当たった光を反射する方向が均一でないため起きる現象です。

例えば、レンガのように一見光沢感のないような物体でも、当たった光を反射しています。
下の画像内の、左側のレンガは現実世界で撮影した物で、画像中央のレンガは交差偏光撮影(cross polarized lighting setup)で物体の反射光を除いた物です。
通常の物体と反射光を除いた物体とでは色合いが大きく異なり、反射光の影響を受けている事が分かります。

このように、現実世界に存在する表面が滑らかでない物体も、光沢のある物体と同様に、同じぐらいの量の光を表面で反射しています。
この特性に従い、3Dソフト上で光を反射しない物体を再現する場合は、スペキュラーの値を下げず、そのままラフネスの値のみを上げるようにすると良いです。
フレネル
物体の色については上記の反射と屈折で大体説明出来ますが、反射が常に均一に起こるという事は無く、そのような事例の一つとしてフレネルが存在します。
「フレネル」自体に色々な意味がありますが、この場合はオブジェクトの表面が輪郭部分=エッジに近づくほど光の反射が強くなり、オブジェクトのキワ=エッジ部分では常に100%光を反射するという特性を指します。

トイ・ストーリーに出てくるガラス製の鉢や、ジョージ・クルーニーが被っている宇宙飛行士のヘルメットなどのように、光沢のある球体のエッジ付近に近づくにつれて、光の反射も強まっていきます。
本当は物体表面のラフネス等に応じてフレネルも変化するのですが、色々いじるのも難しいので、その辺の調節は3Dソフトにある出来合いのシェーダーに任せると良いと解説しています。
金属の反射
金属は物体の内部で光が屈折せず、表面から光が出てくる事はないため、反射された際の光の色のみが物体の色として見えます。


Blenderであれば、Principled (プリンシプル) BSDFノードを使い、ラフネスを0に近づけてメタリックの値を最大にすると、フレネルの効果を含めて確実に金属のマテリアルを再現出来ます。
露出とシャッタースピード
写真を撮影する際に調節するのが露出とシャッタースピードです。
屋外での撮影でよく起こるような、画面全体が白飛びしてしまう露出オーバーや露出アンダーを避けるため、露出とシャッタースピードを調節するのは重用です。
例えば、暗い部屋に一つだけある窓から日光が差し込む場合、窓と反対側の直接日光が当たる部分が明るくなり、対して窓側から差し込む光は露出の関係でカットされます。現実世界で同じような部屋をカメラで撮影した場合も、このようになります。

露出の関係で窓側から差し込む光はカットされる
トイ・ストーリー4では、このような特性が全編を通して上手く調節されているため、非常にリアルに見えると解説しています。
例えば、全体が暗い環境で通過する車のヘッドライトが顔を照らすシーンや、屋根裏部屋の天井から日光が差し込むシーンなどで、このように光源側の明るさがカットされている事が確認できます。
露出
絞りを広げる(Fストップを小さくする)と光をより多く取り込み、更にいわゆる被写界深度(DOF)も増加するので、前景背景をぼかす事もできます。
このため、ポートレート撮影では低いFストップで人物に焦点を当て、風景写真では高いFストップで絞りを狭めて多くの物に焦点を当てられるようにします。
シャッタースピード
シャッタースピードが長くなるほど、より多くの光がレンズに当たる事になり、結果としてモーションブラーの効果が大きくなります。
Blenderにはモーションブラー設定からシャッタースピードを設定できるようなパラメーターがありますが、これは実際のシャッタースピードによる効果を再現するような物では無いので、どのぐらいのブラー効果をかけるかはクリエイター次第となっています。
このように手動でブラー効果を設定しなければならない場合、実際のカメラについての理解が役に立ちます。例えば、一般的に昼間の撮影では、夜間よりもモーションブラーが少なくなります。
これは、夜間のショットでは光を多く取り込むためにシャッタースピードが遅くなり、昼間の撮影では周囲が明るいのでシャッタースピードは早くなるためです。
小ネタ
他にも「映画らしく」見せるためのテクニックがいくつかあります。
アナモルフィックレンズの再現
アナモルフィックレンズは映画撮影用のレンズの一種で、撮影した映像を後処理で引き伸ばすため、DOFの効果受けたボケている部分も引き伸ばされるのが特徴です。
(Bokeh Imageは和製英語で講演内でも「ボケ」と呼称されている)
blenderではApertureのRatioを2にするだけで、このアナモルフィックレンズのボケが再現できます。

レンズの歪み=歪曲収差
歪曲収差(barrel distortion)によって画面の外側に近づくほどレンズの歪みの影響を受けます(下画像の黄色の破線部分)

blenderのLens Distortionコンポジットノードを使うと再現出来ます。
まとめ
光学的な物理現象と、それを撮影するカメラやレンズの特性について知る事でフォトリアリスティックな表現ができる、という内容に興味を持ってまとめましました。
色々と原理についてまとめた記事になっているように見えますが、この動画全体を通して、Principled (プリンシプル) BSDFを使う理由、パラメーターを不必要にいじらない理由など、物理現象などを参考に3DCGの制作において「なぜそうするのか」を解説するものになっています。
露出とモーションブラーの関係性などが分かりやすく、夜間は周囲が暗いので光を多く取り込むためにシャッタースピードを遅くする→シャッタースピードが遅いのでモーションブラーの効果が少ない、という例は実際の現象に基づいた納得できるリアルさの一つでした。
どこを光らせるか、光らせないかというのは非常に重用で、光源からの距離と照り返し等の設定が7年前のゲームの方が正確なため、古いゲームの方が高クオリティに見えてしまうような事も起きています(下動画参照)
2Dアニメ
2Dアニメで画面全体が明るすぎたり暗すぎたりすると、少し気になる事がありました。露出とシャッタースピードの項目で触れた露出オーバー、露出アンダーに近い状態です。
そういったシーン内の明度バランスの崩れが無く、画面の光や影のバランスが良く出来ている作品として、自分は村瀬修功監督の作品、「閃光のハサウェイ」「虐殺器官」などが挙げられると思っています。
そういったライティングの作品が他の監督でも見られないかと調べた所、渡辺信一郎監督の「ブレードランナー ブラックアウト 2022」が村上監督と同じようなライティングの具合でした。
でもクレジットをよく見たら作画監督が村瀬修功さんでした。
という訳で、村瀬修功さんの関わってる作品が、フォールオフの項目で触れた光の減衰や、暗い部屋での露出などをアニメ表現に落とし込んでいると自分は思います。
Key Animation: Shukou Murase (村瀬 修功)
— randomsakuga (@randomsakuga) November 29, 2021
Anime: Blade Runner: Black Out 2022 (ブレードランナー ブラックアウト 2022) (2017)https://t.co/nDrXKRI66z pic.twitter.com/GsV3NyayXW
しかし、暗い室内の場面のシーンばかりというアニメは少なく、むしろ屋外で画面めちゃくちゃ光らせる表現が主流だったりするので(青春SF夏アニメ映画が大体そう)、そういうリアルさがある事が一概に良いわけではないと思います。
従って、今回紹介したような物理現象や光学特性は作品の用途によって採用したり無視したりするべきです。
補足等
「レンズ」と「物理現象」を重視しているという点では、以前に解説したUnityのHDRPの動画と通ずる所がありました。この二つがリアルな画作りのポイントだと考える人は多いようです。
また、映画DUNEのVFX解説動画で「物理的なカメラで撮影するのが難しそうなカットが無い」という点が指摘されていました。
これは、キャラクターの周りを360°物凄い勢いで回ったりせず、高速で飛ぶ飛行機のアクションシーンでも、空撮のようなカメラワークを使っているような点がリアルさを演出しているという話です。
ライティングや光学機器の特性以外にも、映像のリアルさを出す方法はあります。
以上、自分が「なるほど」と思ったポイントは抑えましたが、この動画や同チャンネルの他の動画を見てみると、より詳しく3Dについて学ぶことが出来ると思います。
なんとなくサジェストで出てきた動画よりは、blenderやゲームエンジン公式チャンネルの、カンファレンスの講演をまとめたような動画の方が、ソースがしっかりしていたり、変な広告が途中で挟まったりしてないので役に立ちます。
感謝します
